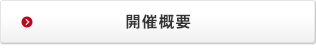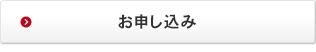Executive Business Seminar
新しい価値創造へ向けた挑戦
〜 新たな発想、アイディアを実現する環境・仕掛けづくり 〜
![]()
10月27日(月)9:50~17:00
![]()

9:50~ ゲスト講演Ⅰ(60分間)【斬新なアイディアを生み出す組織環境づくり】
新市場を生み出す経営術
- 「モノマネはしない」 キングジムの商品開発
- ヒット商品「テプラ」が生まれた舞台裏
- 縮小市場で勝ち残る!目指すは“打率1割のホームランバッター”

株式会社キングジム
代表取締役社長
宮本 彰 氏
1954年生まれ。77年3月、慶応義塾大学法学部卒業後、キングジムに入社。84年、常務取締役総合企画室長に就任。同社初の電子文具開発プロジェクトを発足させ、「テプラ」の開発指揮を執る。92年4月、代表取締役社長に就任し、現在に至る。近年ではデジタルメモ「ポメラ」や、「ショットノート」等の市場開拓型の商品を次々と世に送り出している。
【本講演からの考察ポイント】
今やオフィスの定番となっている「キングファイル」や「テプラ」などユニークな商品を生み出した企業、それがキングジムです。近年では、テキスト入力に特化した電子機器「ポメラ」や手書きのメモをスマートフォンに保存できる「ショットノート」など、社内で生まれるアイディアからユニークな文具を次々と発売しています。 本講演では「テプラ」の開発指揮も執られた宮本社長より、キングジムの商品開発にみる、独創的な商品が生まれるうえでの考え方を考察いたします。
10:50~ ゲスト講演Ⅱ(80分間)【イノベーションを育む環境づくり】
イノベーションを育む環境を設計する
マネジメントは何を変化させ、何を変化させてはいけないのか
- 暗黙の了解に基づく形式化されたルール
- 自由という知覚を生み出す規律
- 感情を動かす論理的なアプローチ

スリーエム ジャパン株式会社
チーフ・プロセス・オフィサー(CPO)
コーポレート・プロセス・イノベーション及び
品質保証本部担当
大久保 孝俊 氏
1980年九州大学大学院工学研究科応用化学専攻 修士課程修了。83年3月住友スリーエム(株)入社 磁気製品事業部開発部。87年3M社 メモリーテクノロジーグループ研究員。90年磁気製品AV技術部主任。96年技術本部ビジョン2000プロジェクト次長。99年山形スリーエム(株)デコラティブ・グラフィックス技術部長。2002年 シックスシグマ マスターブラックベルト。03年3M社 アジア・太平洋地域担当シックスシグマ ダイレクター。05年3M社 コーポレートリサーチ研究所上級技術部長。07年技術本部統轄部長。07年執行役員 技術及び環境マネジメント担当 カスタマー テクニカルセンター長 兼任。09年執行役員 技術担当。09年チーフ・プロセス・オフィサー(CPO):コーポレート・プロセス・イノベーション本部担当。2013年チーフ・プロセス・オフィサー(CPO):コーポレート・プロセス・イノベーション&品質保証本部担当。 社外活動として2013年~東京工業大学イノベーション人材養成機構非常勤講師。
雑誌への寄稿では「感動でイノベーションを引き出すグローバルリーダー」一橋ビジネスレビュー(2009AUT57巻2号)など。
【本講演からの考察ポイント】
マネジメント層がイノベーションを起こすためにすべきことは何か?
その第一歩が、組織にイノベーションを育むことができる環境(基盤)を作ることです。では、その環境を設計する上で、マネジメントの皆様はどのような考えのもと行動していけば良いのか。スリーエムジャパンで今まさに全社視点のイノベーション創出マネジメントを手がけていらっしゃる大久保様より、ご自身の体験や失敗から培われた経験に裏打ちされた、効果的で実践的なイノベーションマネジメントの本質を考察いたします。
12:10~ 休憩(60分間)
13:10~ 協賛社講演Ⅰ(50分間)【潜在力を活用した新たな価値創造型組織のつくり方】
企業のイノベーション課題と潜在力を活用した解決策
新事業創造型企業のつくり方
- 企業が内包するイノベーションへの克服課題
- 価値創造型組織の行動モデルとは
- イノベーションに求められる人材と能力
- 企業内イノベーションの矛盾を克服するための仕掛けづくり

株式会社ICMG
取締役 コンサルティング事業部代表
大庭 史裕 氏
マッキンゼー日本支社においてエレクトロニクス・通信・ヘルスケア業界等での成長戦略・企業変革・新規事業の立案と実行支援に従事。2005年にアクセル(現ICMG)に参画。日本の大手企業を中心に成長戦略策定・企業変革・事業開発・企業再生等のコンサルティング活動を主導。企業の内部資源分析と事業分析を融合した知的資本戦略デザインが専門。
【本講演からの考察ポイント】
企業には、創造の種となる極めて専門性の高い知・技術 ・ノウハウが潜在しています。 しかしこれらは、新たなビジネス・価値を生み出すイノベーションに十分に活用されていないという欠点があります。これまでの単線型で閉じた技術応用、商品開発やソリューション作りを越えて、組織内外の周辺知・暗黙知を広く集め、顧客や社内人材を巻き込みながら、新しいコンセプトを生み出していく動きを企業の体質として定着させることが、継続イノベーションの鍵となります。企業の潜在力をフル活用し、イノベーションを生み出す動きを人の能力とプロセス両面で創り上げるイノベーションエコシステム構築へのヒントをお届けします。
14:00~ ゲスト講演Ⅲ(60分間)【事例:グローバルレベルで実現するイノベーション戦略とは】
シスコシステムズの
ビジネスイノベーションへの取組み
- シスコシステムズのイノベーション戦略
- イノベーションを加速するための組織風土、プロセス、テクノロジー
- 今後、日本企業が取り組むべき方向性について

シスコシステムズ合同会社
専務執行役員
鈴木 和洋 氏
1983年 慶應義塾大学 経済学部卒。日本アイ・ビー・エム株式会社に入社、通信事業者向けの営業部長、ビジネス開発部長を担当した後、日本チボリシステムズに出向し代表取締役社長に就任、その後、ダブルクリック株式会社で代表取締役社長 兼 CEOを務めるなど、企業経営者としての経験を積む。その後、日本マイクロソフト株式会社の執行役として、サーバープラットフォーム製品部門、金融、流通・サービス、製造を中心としたエンタープライズ営業部門、グローバル企業向け営業部門の責任者などを歴任。シスコジャパンに入社後は3年半に渡りエンタープライズセールス事業をリードし、現在は、専務執行役員としてお客様向けのビジネス戦略コンサルティングビジネスを担当。また、経済同友会の経済懇談会の委員として経済、経営に関わる提言活動に関わる一方、オープンイノベーション推進にも積極的に活動しておりCreww株式会社の顧問を務めている。
【本講演からの考察ポイント】
グローバル化する大企業において、プロセスや組織をグローバルで標準化していくというガバナンスモデルの強化とイノベーションを継続的に起こしていくことは、ある意味二律背反する大きな課題になっています。本講演ではシスコシステムズのそうした課題への取組みについてご紹介いたします。また、新しいテクノロジー、ビジネスモデルをどう生み出すかという部分にフォーカスされがちな議論に加えて、それを育てるための組織風土、プロセスの重要性についても言及いたします。
15:00~ Coffee Break(10分間)
15:10~ 協賛社講演Ⅱ(50分間)【アイディアをビジネスへと昇華させるプロセス】
新たな事業には新たな事業化プロセスが必要である
~アイディア出しから新事業の立ち上げまでにやらなければならないこと~
- 魅力的な事業アイディアを発想するための6つの視点
- アイディアの事業化プロセスに欠けている要素
- 初期段階からのアイディアの見える化

株式会社フィンチジャパン
代表取締役社長 パートナー
髙橋 広嗣 氏
早稲田大学大学院を修了。1999年野村総合研究所経営コンサルティング部入社。一貫して経営戦略・事業戦略立案に関するコンサルティングを行ってきた。顧客満足を科学的に分析した結果が日経BPに掲載されるなど、対外活動も行ってきた。2006年に当社を設立し、現在に至る。
【本講演からの考察ポイント】
アイディア出しには取り組むが、新事業として社内提案に結びつかない。また事業化しても売り上げ目標に遠く及ばない。こうしたケースの背景には、アイディア出しから新事業の立ち上げまでの「プロセス」に関する問題が見受けられます。 新事業を生み出すプロセスに何が欠けているのか、新事業開発を専門に手掛けるフィンチジャパンの高橋代表より、アイディア出しから新事業の事業化までのプロセスについて徹底解説いたします。
16:00~ ゲスト講演Ⅳ(60分間)【イノベーションへつなげる思考法の考察】
ビジネスのためのシステム×デザイン思考
正解のない問題に直面したとき、何をどう考えたら良いのか?
グローバル・ネットワーク社会において日本の企業・事業体が生き残るために革新的イノベーションの重要性が高まっている。本講演では、講演者らが開発した、枠外思考や協創を重視したシステム×デザイン思考に基づく革新的デザインや問題解決の方法について述べる。また、実例についても述べる。

慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科
研究科委員長・教授
前野 隆司 氏
1984年東工大卒、1986年東工大修士課程修了、1993年博士(工学)学位取得。キヤノン (株)、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、ハーバード大学客員教授、慶應義塾大学理工学部教授等を経て現職。研究テーマは、イノベーション教育からシステムデザイン・マネジメント学、幸福学まで幅広い。
【本講演からの考察ポイント】
今やイノベーションを起こすことで成長することが必然の時代となり、イノベーションの源泉たるアイディアを生み出す"人"と"組織"をどうマネジメントしていくのかが多くの企業で課題になっています。
本講演では、アップルやサムスン電子、P&Gなど名だたるグローバル企業も取り入れてきた「デザイン思考」の考察からイノベーションの考え方を体系化し、実践することの重要性を検証いたします。
17:00~ 終了 ※終了後 17:00~18:00でゲストスピーカーを交えた懇親会を実施