Executive CX Conference 2017
コト(体験)発想で挑むこれからの顧客戦略
~顧客体験価値を最大化するマネジメントと最適な組織体制
2017年11月22日、東京・ザ ストリングス 表参道にて、株式会社ビジネス・フォーラム事務局主催で「Executive CX Conference 2017」を開催いたしました。昨今、消費者の興味が「モノ」の所有欲を満たすことから、人生やライフスタイルを豊かにする経験や体験など目に見えない価値である「コト」消費重視へと推移しています。先進企業では、この変化を勝機と捉えて顧客との関係性をより良いものにするために、優れた顧客体験の提供のチャレンジをはじめています。このような背景を踏まえ、フォーラムでは「コト(体験)発想で挑むこれからの顧客戦略」をテーマに掲げ、顧客体験価値を最大化するマネジメントと最適な組織体制について、実践企業のマネジメントに携わる方々にご講演いただきました。
特別ゲスト講演Ⅰ【ブランドの全体最適と組織力強化】
「走る歓び」マツダのブランド価値経営
~すべての顧客接点を通じた
ブランド体験価値の強化を目指して
マツダ株式会社 常務執行役員 営業領域統括 ブランド推進・グローバルマーケティング・カスタマーサービス担当
青山 裕大 氏

お客様から選ばれるワンアンドオンリーを目指す
2010年以降、新しいデザインテーマと使いやすい技術を統合した新世代の自動車を次々と生み出しているマツダだが、その長い歴史の中では周期的に経営危機に直面し、その都度起死回生を遂げてきた。リーマンショック後は、大量生産によって販売台数を伸ばすのではなく、長く乗ってもらうためのブランドづくりを目指している。その価値観の変革について、常務執行役員の青山氏が語った。
大量生産ではなくワンアンドオンリーで生き残っていく

最近は元気がいいと言われるようになったマツダも、リーマンショックでは大きな打撃を受けました。そこから立ち直るために部門横断型のチームをつくり、開発から製造、営業、人事などの部門長クラスが集まって唯一無二の価値を生み出す議論を続けました。マツダは自動車メーカーの中では小規模であり、だからこそ大規模メーカーにはできない強みがあるという思いで、いろいろな意見を出し合いました。それによって、「規模の大小から存在価値の有無へ」と価値観を変革し、大量生産で生き残っていくのではなく「ワンアンドオンリーの提供価値でお客様に必要とされるマツダブランド」を目指すことにしました。
マツダはもともとエンジンへのこだわりが強いメーカーなので、車づくりに関しては内燃機関を究極まで磨き上げて世界一にすることに力を注いでいきます。これからはEVやハイブリッドEVの時代だと言われている中、エンジンにこだわる理由は2つあります。1つは、量産向けに力を入れていた頃のエンジンの評価があまり高くなかったので、まだまだ改善する余地があるということです。もう1つは、成長著しい新興国を見ると、コストがかかるEVはまだ普及が難しく、それならばエンジンの効率を上げることで環境を改善するほうが地球全体にとってよいのではないかということです。そうした車づくりを目指すために生まれたのが、「スカイアクティブテクノロジー」であり、一目でマツダ車とわかる「魂道デザイン」です。これらによってマツダは、子どもの頃に感じていたわくわく感や心のときめきが実感できる、「走る歓び」を体験する車をお客様に提供します。
マツダは大規模メーカーとは異なる独自のブランドを形成することによってお客様と強い絆で結ばれ、愛され続けることでビジネスを強化します。マツダにとってのブランディングはマーケティングではなく、経営企画に関わることであるというのが社内の共通認識です。
営業領域では「つながり革新」を

車づくりだけでなく、営業領域の戦い方も変革しました。営業領域での一番の阻害要因は規模を大きくしたいという目標でしたので、まずはその価値観を変えることが必要でした。大きくなくてもよい、むしろ小さいことに価値を見出すとはどういうことかを考えました。その結果、「コストダウンを訴求するのではなく、ブランドの商品価値を訴求する」「新車販売台数を上げるのではなく、売り上げ・利益を最大化する」「新車販売時点の利益を追求するのではなく、ライフサイクル利益を追求する」といったことが重要であるという結論に達しました。お客様に一生涯マツダの車に乗っていただくために、顧客愛着度を向上させ、選ばれ続けるメーカーになることを目指します。私たちはこれを「つながり革新」と呼んでいます。「走る歓びに溢れた商品を、お客様にどのようにお届けし、マツダ車との生活をどのように過ごしていただくかを再設計する」活動です。
2013年から3年間は構造改革プランとして、戦略の転換に重点を置きました。その結果、日本、アメリカ、ドイツにおいて販売台数が伸びてきたわけですが、特徴的なのは販売主体がそれまでの低価格車から高価格車に移っていることです。特に、マツダ自慢の独自技術を持った車の売れ行きが好評だったことから、営業部門が自信を持つようになりました。
2016年からは構造改革プランのステージ2が、2018年までを期限として始まりました。そこでは、「カスタマーケア」「販売空間の変革」「人材育成/風土」に重点を置いて取り組んでいます。カスタマーケアでは、お客様を笑顔にするカーライフづくりのお手伝いをします。たとえば、車が故障した時にはすぐに駆け付けるのは当たり前ですが、その前にお客様が置かれている状況をお聞きし、必要であれば代車を用意するなどの気遣いにも重点を置きます。また、モーターショーなどのイベントに販売会社を通じてお客様を招待したり、マツダ車を楽しむファンミーティングを開催し、お客様と開発者が直接交流する場を設けたりします。販売空間の改革では、新世代店舗をグローバルに展開しています。
技術で実現できることはだんだんとコモディティ化していきます。その中でマツダらしさを保っていくには、コーポレートビジョンを達成していくための人と人とのつながりを大切にすることが必要だと思っています。そのためには、「アウトサイドインからインサイドアウトへの変革」として、単に製品の特徴や機能性の訴求を中心とするアピールから、マツダのものづくりの背景にある志やスピリットを伝達することに力を入れたアピールを心がけていきます。
基調講演 【顧客体験価値を最大化する組織戦略】
顧客体験で勝ち抜くための組織とメカニズム
アバナード株式会社 代表取締役
安間 裕 氏

従業員体験が顧客体験を生み出す
2000年にアクセンチュアとマイクロソフトの合弁会社として設立されたアバナード株式会社。デジタル・トランスフォーメーションが注目される以前からデジタルによるイノベーションを提唱してきた。先行する欧米での事例を紹介しながら、デジタルへの投資が顧客体験や従業員体験の向上にどう結びつくのかについて、代表取締役の安間氏が語った。
デジタルへの投資が顧客体験を向上させる

デジタルによるイノベーションは投資です。日本人はこれまでITをコストとして見てきたのですが、アメリカはITを投資として見てきました。ようやく日本でもデジタルと投資のイメージが結びつき、その投資を顧客体験や従業員体験の向上に結びつけようとしています。アバナードの調査では「すでにお客様の期待に応えている」と自負している企業はわずか14%ですが、64%の企業が「競合との差別化」のために顧客満足度に力を入れようとしています。そのために80%の企業が「マーケティングテクノロジー・プラットフォームを更新・変更したい」と述べています。一方で企業のブランド価値を上げるには、従業員が自社のブランドに自信を持ち、顧客満足度を高めるサービスやメカニズムをしっかりと持っていると思うことが重要です。企業はお客様の方を向くことと同じくらい、従業員に信じてもらうことが必要で、そこでは従業員体験の向上が大きな意味を持ちます。
もともと、日本人は改善やおもてなしの文化により、顧客満足度や顧客サービスを重視してきました。そのため、アンケートなどによってお客様からのフィードバックを収集するテクノロジーには投資しているのですが、収集したデータを分析するテクノロジーやその結果を社内でシェアする手段に投資する企業は、われわれの調査では50%以下しかありません。
デジタルの進化を見てみると、最近話題のRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)は、今まで人がやってきた単純なオフィスワークをロボットが代行します。その効果は、コストダウンや生産性の向上だけではありません。ロボットでもできる仕事はロボットに任せてしまえば、人は残りの時間を企画や意思決定に使え、新たな価値を生み出して創造性をもたらすのです。デジタルは人が考える時間を作り出します。日本人は、こういった新しいテクノロジーに対するアレルギーが非常に少ない国民でもあると言われています。
どのようにデジタルを活用すれば顧客満足度が向上できるか

実際にデジタルを活用して顧客体験を向上させている欧米での事例を、少し日本流にアレンジして紹介しましょう。あるアパレルチェーンの店頭では、お客様が欲しい服のサイズがなかったのですが、店員から1サイズ大きくても大丈夫だと言われて買って帰りました。ところが、実際に家で着てみると袖が長すぎることが気になりました。そのお客様が不満をSNSでつぶやくと、日頃から自社に対する意見をWebでチェックしているアパレルチェーンのコールセンターが発見しました。そこで、すぐにお客様に謝罪し、近くにあるリペアショップでのお直しをオンラインで予約してポイントを2倍にするなどの対応をとったことで、お客様の不満は解消されました。デジタルを活用すればこのように迅速な対応ができ、お客様のネガティブな体験をポジティブな体験に変えることができます。他にも、イタリアの生協ではお客様の年齢や性別を認識し、目の前にあるディスプレイにおすすめの商品を表示して購買意欲を高めています。
従業員体験を向上させた例も見てみましょう。あるチェーンに勤務する従業員が休暇をとって地元に帰ったのですが、暇なので地元にある店にシフトで入れないかと自社の人事ボットに聞いてみました。すると、すぐにボットが地元の店でのパートタイムのシフトを紹介してくれました。別の製造業のフィールドサービスの例では、トラブルを起こした製品の画像を従業員が現場から送れば、ボットが型番などを認識してチェックリストを送ってきます。そのチェックリストに応えれば修理のための手順が手元のタブレットに表示され、対応終了後は作業ログが自動的にレポートとして送られます。これによって、従業員の手間が省け、ミスも減ります。その結果、従業員体験の向上が顧客体験の向上に繋がっていくのです。
このように、欧米で先行する事例を日本企業に向けて提供するのが、アバナードの役割です。デジタル・トランスフォーメーションとリーダーシップによって、従業員体験と顧客体験は大きく変化します。日本は部門別のコミュニケーションが中心になっているため、たとえば、営業部門と経理部門ではあまりコミュニケーションがとられていません。それでは従業員体験の共有ができないのです。日本の企業は昔から無駄な会議が多いので、そんなものはいらないと思っている人もいますが、私はすべてが無駄だとは思っていません。そういった機会も使って、従業員同士に組織の壁を超えさせるのもリーダーの役割であり、そのリーダーシップは役職など関係なく、誰がとってもいいのです。
特別ゲスト講演Ⅱ【コト(体験)を創出する組織づくり】
新しいユーザー体験を生み出す
ソニーのモノづくりと組織
ソニー株式会社 TS事業部門 副部門長
斉藤 博 氏

ミッションは新しい体験の創出
ソニーのTS事業部門は今までなかった新しい体験を創出していく事をミッションに社長直轄の新規事業チームとして2013年に発足。 “Life Space UX(ライフスペースユーエックス)”という新たなコンセプトを立ち上げ4年間で4つの商品を生み出した。いずれも各方面から注目され、中には1年半たっても販売が落ちないという家電製品としては異例のヒット商品もある。そのようなものづくりは、どのような組織から生み出されたのか。部門発足からイントラプレナーとして参画してきた副部門長の斉藤氏が語った。
メーカー目線ではなくユーザーが求める体験目線で企画する

私たちTS事業部門が開発に関わっているのは、Life Space UXというコンセプトの商品群です。Life Spaceとは住空間という意味で使っているのですが、家の中で新しい体験を作り出そうというコンセプトの元、4年間で4つの商品を出しました。その中でも、昨年出した超短焦点プロジェクターとスピーカー製品が好評で、1年半たっても販売が落ちないという、家電分野では異例のヒット商品となっています。
住空間に着目したLife Space UXというコンセプトを創り出すきっかけになったのは、家電製品に対する違和感や家電メーカーの考え方に対する違和感があったことです。コンセプトを検討する際には、家や部屋に関する建築系やインテリア系のさまざまな写真を集めたのですが、それらの写真の部屋の中には一つも家電製品が置かれていませんでした。すてきな住空間であればあるほど、家電製品を置くと違和感があるのです。そこで、どのような家電製品であればそこに置いてもらえるのかを考えました。最初は「見た目がなじまないから、デザインを考え直したらいい」という議論になりました。そのうちに、一般の人の価値観と家電メーカーの価値観が乖離していることに気付き始めました。家電メーカーは、家に家電製品が増えると嬉しいだろうと思っています。戦後の時代はたしかにそうでした。家電メーカーは製品にどんどん機能を詰め込んでいくことに価値を見出しました。しかし、今の時代、それでは喜ばれないことに気が付きました。「価値観が多様化し、いかに自分らしい時間を過ごせるか、家電がそこにどうアプローチできるかを考えるかが重要だ」という議論になり、家の在り方や過ごし方を捉え直しました。そして、「家電製品は自分らしく過ごせる空間を作るサポート役になればいい」という考え方にたどり着きました。Life Space UXは家電メーカーによる自己否定プロジェクトであると考えています。もの視点で発想するのではなく、家や空間やそこでの過ごし方から発想し、そこに技術を活用する事でお客さまにとっての理想の体験や新しい体験を生み出すのです。家電を足していく足し算ではなく引き算で考えていくので、家電は目立たたなくていいんです。
既存の体制を否定することから始めた組織づくり
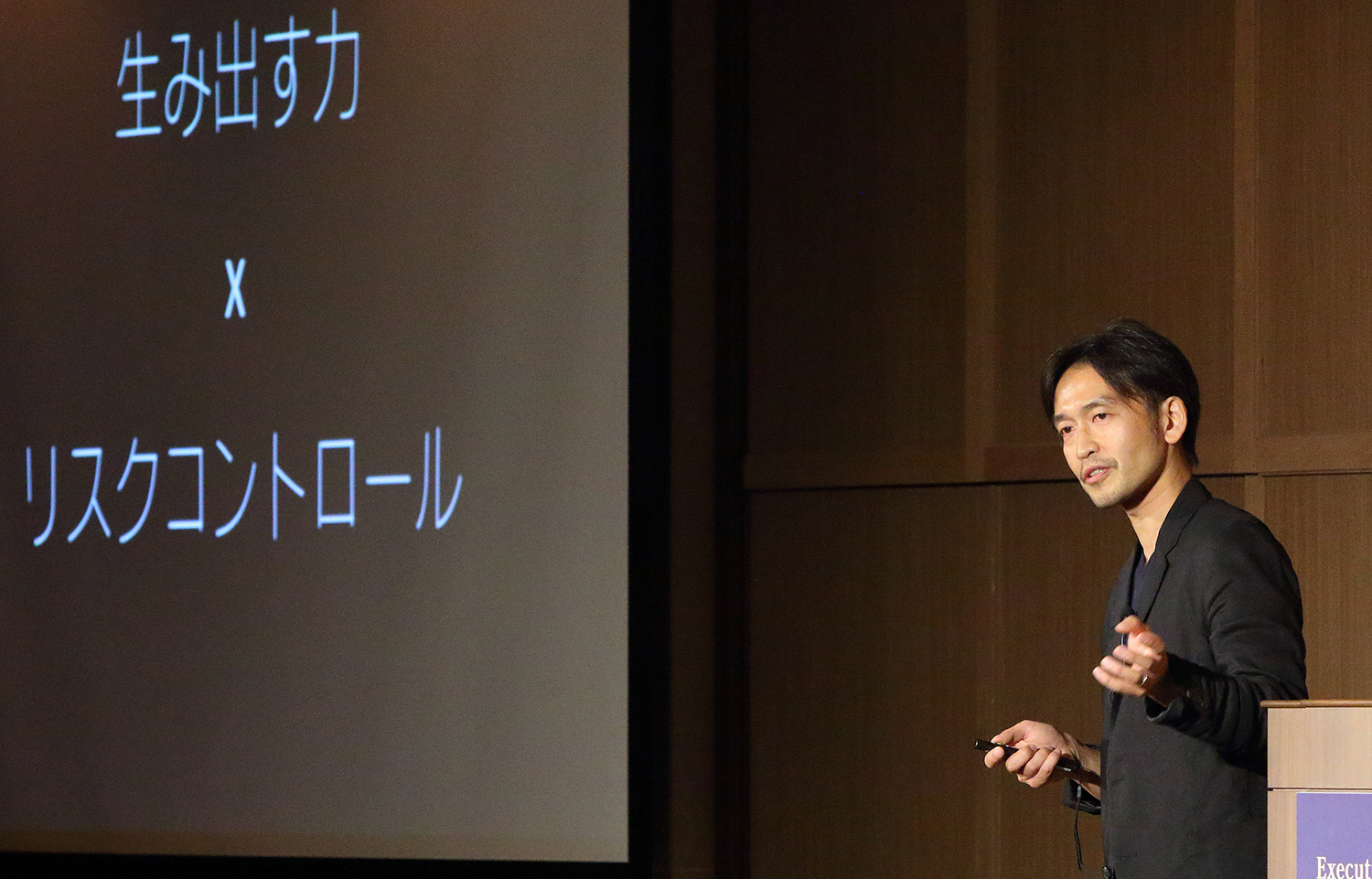
4年前に社長直轄の組織としてTS事業準備室として発足した当初から、社長の平井からは「リスクを取ってでもどんどん商品を出す組織を作れ」という言葉をもらいました。一般的な組織では新規事業を始めるにも、「既存の組織で取り組む」「コンセンサスを求める」「成功を確約させようとする」といったことが求められ、なかなか新しく挑戦することが難しいでしょう。しかし、新しいことを始めるには「今ある常識や前提を疑うこと」が必要です。また、コンセンサスをとるのではなく、「新しいアイデアは賛否両論が出たほうがよい」のです。みんなが賛成するものは既存の軸に沿って提案されているので新規性がありません。そして、何をするにも成功が前提で始めるのではなく「ほとんどが失敗する」前提で、いろいろとアイデアを出して、その中の一つでも当たればいいと考えるべきです。
われわれのチームは、既存の組織から独立したコンパクトな組織になっています。案件ごとに少人数で話し合いをして、やろうと決めたらすぐに動く。通常は家電の場合1つの商品を作るのに1年から1年半はかかるのですが、それを4つを続けて出せたというスピード感があります。
とはいえ、壁にもぶつかりました。実際に製品開発を進めてみると、どういう人がどのタイミングで必要になるのかが分かりませんでした。異なった技術を組み合わせた製品を作るには、その都度さまざまな領域のエンジニアが必要になります。新規事業の鉄則は、最小限、最低限で始めていくことなので、それぞれのプロダクトに適したエンジニアをソニー中からかき集めてプロジェクト化しました。彼らには通常業務と兼務してもらい、プロダクトが完成したら元の組織に戻ってもらいました。また、社外からも人材が必要になった時のために、Hub型のコネクション作りに力を入れています。社外の人材に一人ひとりあたっていくのはたいへんなので、いろいろな方面に繋がりを持っているHub型の人とコネクションを作るのです。
最初の1、2年はコネクションづくりに奔走しました。そうやって、やっと体制が整ってきてから出てきた課題が、左脳と右脳の違いです。通常のメーカーは営業や技術開発に力を入れていて、イノベーション型ではなくオペレーション型の組織になっています。オペレーション型の組織では、今ある既存の事業でいかに効率化・最適化するか、利益を最大にするかが重要で、左脳的な思考ができる人材が主流となります。しかし、新事業はいかにアイデアを生み出すかが重要であるし、出てきたアイデアを商品に落とし込む際にも、お客さまがどう思うのかを想像することが必要になってきます。そのため、われわれは右脳型の思考ができる人材を集めるようにしています。
今後もTS事業部門では独立性の高い組織という環境を活かしながら今までにないユーザー体験を提供する事を目標に、そのための組織や体制の在り方などを模索し続けていきます。だからこそできる新たなチャレンジと体験創出からお客様販売までを一貫して関わっていくことで、新たなユーザー体験を生み出していければと考えています。TS事業部門は体験創出からお客様販売までを行う、全く新しい組織なのです。
特別ゲスト講演Ⅲ【顧客接点のマネジメントと組織連携】
ANAが挑むカスタマー・エクスペリエンス(CX)向上と
顧客起点の新たな価値創造
ANA X 株式会社 代表取締役社長
稲田 剛 氏

カスター・エクスペリエンス向上は会社の利益向上につながる
ANAのマイレージクラブに関わるマーケティング部門の一つが2016年12月に独立し、ANA X 株式会社として業務を開始した。マイレージプログラムの企画運営などの事業領域に加え、今後、ANAグループが航空券のチケット販売以外のビジネスとのシナジーを目的に、カスタマー・エクスペリエンスを如何に向上させるか同社が行う活動や考え方について、代表取締役社長の稲田氏が語った。
ビジネスモデルが変化する航空業界

世界の航空業界は航空券のチケット収入が頼りのビジネスモデルから、付帯事業を含む複数の収入源を確保するビジネスモデルに変わってきました。欧米は特にそのスピードが速くなっていて、今や大手航空会社もLCCも垣根がなくなってきました。
これまで、マイレージサービスのようなFFP(Frequent Flyers Program)は、航空会社の中では搭乗プロモーションの手段、いわゆるコストセンターと位置づけられていました。それをプロフィットセンターとして価値を最大化していくことが、われわれの取り組みです。ANAグループには不動産ビジネスの会社もあれば商社もあります。せっかくグループの中でさまざまな事業のお客様接点があるのなら、それぞれの会社が獲得しているお客様を共有できないかと考えました。ANA Xはマーケティング・プラットフォームの構築を目指します。お客様と多面的かつ長期に繋がり、航空券を買ったらスーツケースはいかがでしょうか、海外に行くには両替も必要ではありませんかと、お客様を囲い込んでいきます。これまでの企業の考え方は、お客様に生涯にわたって財布を開いてもらうことに価値があるというものでした。対してANA Xは、お客様にとって一生涯付き合う価値がある会社になることが大切と考えています。
ANAグループの営業利益の推移を見てみると、航空事業は環境に大きく影響を受けるために、浮沈を繰り返した時期がありました。一方で、航空機材などへの投資は常に続けなければいけません。その投資を支える安定した収入源がどこかにないと、企業として成長できないリスクがあります。私は6年前にANAのマーケティング室に配属された時、それを支えるために航空事業と離れたところでビジネスを立ち上げようと思いました。ANA Xはパートナー会社と多面的かつ長期的につながって周辺事業を展開したいと思っています。
アングルを変えて発想すると真のエクスペリエンス提供も可能

実際にカスタマー・エクスペリエンスの向上は、企業にとってどのような価値を生み出すのか。例えば、新規のお客様を獲得するには、膨大な営業コストがかかります。それに対して、一度サービスをご利用いただいたお客様がその体験価値をご評価いただいてリピーターとしてご利用いただければ、営業コストは抑制できます。一般的にそのコストは5倍近く違うと言われています。そして、リピーターのお客様の離反を5%改善すると、営業利益が25%改善されるとも言われています。したがってカスタマー・エクスペリエンスを向上させ、ロイヤリティマーケティングをワークさせることは結果的に、営業利益の向上につながると考えています。
カスタマー・エクスペリエンスを向上させるには、サービス品質向上やクレーム対応が重要で問題解決のための業務改善や投資が必要という議論がよくされます。ですが私は、それだけではなく、お客様が真に必要としているエクスペリエンスを提供するには、アングルを変えて発想してみることも重要だと思っています。例として「エレベーターの話」があります。話の舞台は、ホテル。「エレベーターの待ち時間が長い」とクレームを受けることが多くなったので解決策が検討されました。1)増設2)機種変更3)制御装置新設。結果、どれも採用しませんでした。エレベーターホールでの待ち時間のストレスを“鏡(ミラー)”を壁面に設置することによって“長く感じさせない仕掛け”としたのです。これは、人は鏡があると身だしなみを整えるなどする行動心理をうまくソリューションに結び付け、設備工事の大きなコストも免れたケースです。また、ディズニーランドでは、長い行列の待ち時間を退屈に感じないように、列を進む途中でプレショーを見せるなどのエクスペリエンスをうまくプロデュースしています。“待ち時間”をエクスペリエンスとして捉えたこれらの事例に考えるべきヒントがあるのではないでしょうか。
われわれはもともとANA社内の部署だったのですが、ANAグループ全体としてカスタマー・エクスペリエンスを向上させるための活動や事業開発を、そのまま社内で進めていくことに限界を感じていたため、社内分社化の道を選びました。そのまま社内でも活動できるのではないかと言われたこともあったのですが、事業を持つ単体企業の中ではプライオリティの付け方に相違が生まれがちとなることは否めませんでした。グループ経営の中で独立したこのような事業形態は、ルフトハンザとカンタス航空が先行しています。この2社が我々にとって参考となりました。インタビューをすると同じ悩みを持って踏み出していたことが分かり、勇気をもらいました。
一般的な起業と社内での起業・分社化は似ているようで異なります。参考までに、社内で実現させるには「トップ、タイミング」「孤独、信念、仲間づくり」「波紋、蟻の一穴」「人材、人財」という4つのキーワード群があると実感した次第です。始動時にまず経営トップの意志があり、そして応援者となる関係役職員たちがタイミングよく存在しました。また、多くのスタッフは、新しいチャレンジにワクワクしていたのですが、本籍の会社から新会社へ出向することに複雑な気持ちを持つスタッフもいました。そのため、新しいチャレンジに共感してもらえるように丁寧な仲間づくりが欠かせませんでした。そして、辛抱強く活動しているとだんだん周囲から理解してもらえるようになり、少しずつ波紋を広げることができました。最後にすべてに共通することですが、人を育てることと獲得していくことが重要になります。これらがそろってこそ事業の成功へと向かって漕ぎ出せる。それが社内起業であり分社化なのではないかと振り返って感じています。この話が特に大きな組織で同じようなスタートをご検討の方にとって少しでもお役に立つ情報となれば幸いです。
協賛講演【顧客接点の最適化とオペレーション変革】
顧客の時代に求められる
カスタマー・エクスペリエンスの改革とAI活用
株式会社セールスフォース・ドットコム マーケティング本部 プロダクトマーケティング シニアマネージャー
大森 浩生 氏

AIの活用で日本独自のカスタマー・エクスペリエンスを
セールスフォース・ドットコムは1999年にサンフランシスコで起業し、CRMを基盤としたサービスをクラウドによって提供している。同社のサービスでは、カスタマー・エクスペリエンスの実現に積極的にAIを活用している。カスタマー・エクスペリエンスの中でどのようにAIを活用すべきかについて、海外の事例を紹介しながら、マーケティング本部 プロダクトマーケティング シニアマネージャーの大森氏が語った。
カスタマー・エクスペリエンスの重要性に企業が気付き始めた

歴史を振り返ってみると、1700年代後半に蒸気機関による第1次産業革命が起きました。1800年代には電機による第2次産業革命が起き、1970年代にはコンピューティングによる第3次産業革命が起きます。そして今、インテリジェンスが主体になる第4次産業革命が起きようとしています。第4次産業革命では、AIをはじめとする次世代のテクノロジーを活用して、お客様と新たな形でつながっていくことが重要になります。
この10年、テクノロジーが私たちの生活をすさまじいスピードで変えてきました。特にスマートフォンの登場によって、欲しい情報を瞬時にパーソナライズされた状態で受け取れるようになりました。第4次産業革命のポイントは、お客様が最新テクノロジーを駆使して情報武装する時代ということです。情報武装したお客様は、さまざまな製品やサービスの質に対して今まで以上に期待し、その期待にどう応えるかが企業にとって重要な課題になります。昨秋、セールスフォース・ドットコムが全世界の2600名の消費者や企業幹部を対象に行ったアンケート調査では、消費者の69%が「パーソナライズされた対応でその企業に対するロイヤリティが高まった」と回答しています。カスタマー・エクスペリエンスの向上が、企業のブランド価値を向上させているのです。さらに、サービス部門担当の経営幹部のうち85%が「カスタマー・エクスペリエンスが競争上、重要な差別化要因である」と回答しています。このように、企業側もすでにカスタマー・エクスペリエンスが今後の戦略として重要と捉えており、この2年間で61%の企業がカスタマー・エクスペリエンスに投資したという結果が出ています。
カスタマー・エクスペリエンスの具体的な内容に対しては「問い合わせのリアルタイムな対応に期待する」という回答が消費者から64%、企業から80%という結果でした。それに対して現在の対応は、「サービスのレベルにばらつきがある」が同73%と78%、「対応する部署によってエクスペリエンスにばらつきがある」が同65%と73%でした。すなわち、お客様は店舗とコンタクトセンターとで回答が異なっていたり、営業とサポートチームの間で認識がずれていたりすると不満を感じます。お客様が求めているのは、迅速かつ一貫性のある高品質な対応です。企業はさまざまなテクノロジーを活用して、お客様からのあらゆるコンタクトポイントに対してシームレスで一貫性のあるサービスを提供する必要があります。
人とデジタルが融合し、
リアルとバーチャルで日本でしかできないおもてなしを

すでに、企業がAIテクノロジーをどのようにカスタマー・エクスペリエンスに応用するのかという検討も始まっています。お客様のことを理解するには、AIに顧客データを学習させることが重要です。セールスフォース・ドットコムはAIと顧客データ、プラットフォームを組み合わせ、誰でもが簡単に利用できる世界でもっともスマートなCRM「Salesforce Einstein」をリリースしました。人材を削減するためのAIではなく、人間を支援するためのAIです。Salesforce Einsteinには、ポータルサイトやコミュニティサイトを簡単に作れる機能があります。これによって、たとえばお客様がWeb上で質問をすると、チャット機能などによってAIが的確なコメントを返します。それでも解決できない場合はエージェントにシームレスに接続され、そこまでのお客様とのやり取りがそのまま引き継がれます。こういった機能を活用することによって、お客様にとっては素早く回答を得ることができ、エージェントにとっては生産性が向上できるでしょう。
ここで、アディダスが進めるAIを活用したカスタマー・エクスペリエンスの最新事例を見てみましょう。もともと、アディダスのコンタクトセンターへの質問は30%以上が出荷状況や返品手続き関する問い合わせだったので、これらについてチャットボットで対応することにしました。その際に重視されたのは、「コンタクトセンターに簡単にアクセスできること」「すべてのチャネルからシームレスなサービスが受けられること」「状況に合わせて適切なエージェントが対応すること」「ボットによるセルフサービスで迅速に解決すること」という4つのポイントです。通常、企業がボットサービスを導入する目的のほとんどがコスト削減です。それに対してアディダスは、あくまでもお客様が迅速に回答を得られるカスタマーサービスの導入が会社の成長に繋がると判断したのです。
アメリカでカスタマー・エクスペリエンスの視察に行った証券会社チャールズシュワブでは、問い合わせの98%は基本的にお客様自身がオンラインで解決できるようにナレッジマネジメントを充実させています。一方で、お客様と会話をする際には通話時間は気にせずに、心を込めて対応するということを重視しています。こういった「おもてなし」は、本来の日本が得意としていたことです。日本人は対面でのサービスは世界一といえるのですが、デジタルでカスタマー・エクスペリエンスを実現しようとするとコストの壁が現れます。今後は人とデジタルが融合することで、日本でしかできないおもてなしをリアルとバーチャルで実現していくことが重要になってくるでしょう。
パネルディスカッション【最高の顧客体験を提供する組織への変革】
顧客体験価値の最大化を狙う
「マネジメントと組織」はどうあるべきか?

<パネリスト>
松田 貴夫 氏 (アクサ生命保険株式会社 取締役 専務執行役 兼 チーフマーケティングオフィサー)
木村 奈津子 氏(KDDI株式会社 コンシューマエクスペリエンス推進部長)
佐々木 丈也 氏(三井住友カード株式会社 統合マーケティング部 部長)
木村 真琴 氏(合同会社 西友 マーケティング本部)
<モデレーター>
小野 譲司 氏(青山学院大学 経営学部 教授)
※ご登壇者のご所属、お役職は2017年11月時点のものです。

組織への浸透がカスタマー・エクスペリエンスの課題に
企業にとって、カスタマー・エクスペリエンスの向上が急務になっている。既存の組織の中に、カスタマー・エクスペリエンスを専門とする部署を設ける企業も増えつつある。今後、組織の中でカスタマー・エクスペリエンスをどうマネジメントするべきか。マーケティング、サービス・マネジメントを専門とする青山学院大学経営学部教授の小野譲司氏をモデレーターとし、先進的な取り組みを行う企業の4人のパネリストが意見を交わした。

カスタマー・エクスペリエンスを専門とする部署の役割とは
小野:最近はお客様と企業とがマルチチャネルで接するようになり、企業として一貫性を持った顧客体験をお客様に提供したいという課題認識が深まっています。一方、カスタマー・エクスペリエンスの向上にデジタルをどう活用すればいいのかという検討も進んでいます。そういった状況に置かれた、カスタマー・エクスペリエンスについての課題に真正面から取り組んでいる専門部署として、どのような役割を担っているかお話をいただけますか。
松田:経営者として考えなければいけないことは、ヒト・モノ・カネをどれだけ投入できるかだと思います。そこでは、売り上げやコスト削減に関する数字は簡単に出すことができるのですが、カスタマー・エクスペリエンスはそうではありません。そもそも、新しい取り組みを始めるには、コントロールタワーになる部門が必要になります。私たちの部署は直接カスタマー・エクスペリエンスの業務に取り組むのではなく、見張り番として各部門がカスタマー・エクスペリエンスをしっかり実行をしているかどうかをモニターしています。
佐々木:私が所属しているのは全社的なコミュニケーションを統括する部門として、「顧客とどのようにコミュニケーションを行うか」についての方針・戦略を策定する部署です。精神論で終わらないように、デジタルマーケティング施策を実現するためのインフラ構築、マーケティングツールの活用、データマネジメントプラットフォームの整備を行う役割も担っております。そして収益を確保していくためには、カード会員様や加盟店様に対してどういうカスタマー・エクスペリエンスを提供すればよいのかを考えます。
木村(KDDI):弊社はお客様とさまざまなチャネルで接していますが、代表的なものがauショップです。店頭での印象はお客様にとって大変重要です。私の部署ができた際にまず取り組んだのは、全国のauショップでどのようにカスタマー・エクスペリエンスを向上させるのかということです。とはいえ、なかなか各ショップのスタッフにまで浸透させるのは難しく、根付いていきません。結局、肝になるのはショップを運営している社長の方針なのです。

カスタマー・エクスペリエンスを業績の評価に入れるには
小野: カスタマー・エクスペリエンスを組織へ浸透させるには、業績の評価に組み込んでいくやり方もあると思います。とはいえ、それは簡単ではありません。
木村(KDDI): カスタマー・エクスペリエンスに対する指標を持つことが大切だと思っています。そのためには、カスタマー・エクスペリエンスを社内で共通言語化する努力も必要ではないでしょうか。「カスタマー・エクスペリエンスをやる」という言葉が標語になるくらいモニュメントとして盛り上げないと難しいでしょう。「営業施策や経営施策として新料金プランを導入しました」ではなく、「お客様の体験を向上するための料金プラン変更です」と、みんながきちんと言えるようになることが大事かなと思っています。
佐々木: 弊社の場合、CX向上させる取組を単純に評価に入れるのは、各事業部の反発があると思われるので、CXがもたらす効果を定量化し、社内に発信しています。お客様との関係性を計測する指標であるNPSとも3年前から追いかけており、NPSのポイント変化と収益の相関を見ています。その結果を経営・社内に報告をして、カスタマー・エクスペリエンス的な取り組みが最終的に利益に結び付くということを一生懸命伝えています。
木村(西友): 弊社では、お客様に近いところにいる店舗運営本部が主流なのですが、カスタマー・エクスペリエンスの効果をはかるのは私たちマーケティング本部です。顧客体験の向上に関しては、全社横断プロジェクトが対応します。そういう組織でプロジェクトを進めていかないと、店舗の力だけでは無理なのです。今我々が目指しているのは「エブリデイ・ローコスト」なので、お客様に過剰なコストがかけられないことを理解してもらうため、どうやって本社が店舗をサポートすればよいかを考えています。
カスタマー・エクスペリエンスにデジタルをどう取り込むか

小野: オーディエンスのみなさんには事前のアンケートで、カスタマー・エクスペリエンスにおいて優先して取り組みたいことは何ですかという質問を事前にお聞きしました。そのアンケート結果を見ると、1番多いのが組織や全社に考え方や戦略を浸透させること。2番目が組織間の連携や横のコミュニケーションを促進すること。そして3番目が、デジタルを活用することとなっています。このデジタルをどうカスタマー・エクスペリエンスに活用するかについて聞かせてください。
佐々木: 世の中の変化は、まさにスマホファーストになっています。お客様が我々のWebページを閲覧する際に利用するのは、2年前はパソコンが7割でスマホが3割くらいだったのですが、最近は全く逆転しています。お客様はデジタルの接点を望んでいるので、そこのカスタマー・エクスペリエンスをいかに上げるかというところに力を入れています。
木村(西友): スーパーマーケットにおけるデジタルの活用については非常に難しく、ウォルマートなどのアメリカ企業の方が進んでいます。彼らはまず実行してから結果を見て、だめならすぐに撤退します。アメリカではECの脅威だけでなく、競合がどんどん倒れていく中で生き残っていくという意識が強いことと、マーケットリーダーとしての模範を見せるというところに相当強い意識があると思います。そこが西友とは違うので、参考にしたり、日本でもできないかと検討したりすることはよくやっています。
松田: アクサ生命の商品を買っていただいても、次にアクサ生命の担当者に会うのは30年後に自分が死んだ時かなと思っている人も多いと思います。そこで、たとえば、ある日アクサ生命からパジャマが届きます。じつはそのパジャマにはセンサーが埋め込まれていて、寝ている間の発汗量や心拍数、心電図などを計測します。そして朝になったら、ベッドサイドに置いてあるスマホが、昨日は睡眠の質が悪かったので日頃の運動量を増やしましょうなどとアドバイスをしてくれる。そういった取り組みが考えられます。
木村(KDDI): 弊社は、コアの通信事業を中心に、Eコマース、電気、保険、また最近は、auホームという家庭内のIoTへの取り組みも始めています。デジタルに関して今難しいと感じているのは、データベースのカスタマイズに関する課題です。各事業部やセクターがデータベースを持っているのですが、そこをどうつないで一貫性のあるサービスや顧客経験を提供するのかを考えています。「データはあるのだけれど…」というところで苦慮しています。

小野:最後に、今日参加されているみなさんにメッセージなどがあればお願いします。
木村(西友):じつは、弊社ではカスタマー・エクスペリエンスという言葉は浸透していません。とはいえ、お客様に関わる文脈であればみんなが話を聞きます。今後いろいろと施策を考えていく際にも、全員でやろうという雰囲気になっています。そんなことから、カスタマー・エクスペリエンスの専門部署を作るという体制にはならない会社です。基本的には店舗ごとに大きな権限があるので、そこをどう「見える化」してマネジメントしていくかが、本社の役割ではないかと思っています。
佐々木:カスタマー・エクスペリエンスについては、大上段に振りかぶらなくても小さいことからスタートすれば良いと思います。我々の中でも、定量的に効果が出ているところとそうではないところがあるのですが、一歩ずつ地道に積み上げて取り組んで行くことが大事だと思います。それと、経営陣にカスタマー・エクスペリエンスの重要性を理解してもらう為に、小さなことでも経営にインプットして効果を理解してもらうことが重要だと思っています。
木村(KDDI):コンシューマエクスペリエンス推進部というかっこいい名前ですが、実際にやっていることを見ると、みんな社内を駆けずり回っています。汗をかいているところを社内に見せることも、我々の重要性を認識してもらう方法の1つかなと思っています。それと、なぜ我々はカスタマー・エクスペリエンスを向上させようとしているのかを、部内で定期的に確認するようにしています。私は「みながハッピーになることだから」と言っています。会社もパートナーもお客様もハッピーになることを、私たちがやっているんだということです。
松田:保険会社は以前からブランド投資を長年行ってきています。今の保険会社は、ブランド投資一辺倒だったのを少しずつカスタマー・エクスペリエンスの投資にシフトさせています。私たちはブランドとカスタマー・エクスペリエンスをバランシングさせながら投資を行うようにしています。カスタマー・エクスペリエンスはやはり長期的な投資だと思います。すぐに結果には結びつかないけれど、長期的に考えたらすべて経営の結果に反映します。システム開発のように、ある程度の予算をそこに割かない企業は多分選ばれなくなると思っています。
小野:今日のディスカッションでは触れませんでしたが、お客様の経験を別の角度から見ると、人間はときに非合理的で、感情を伴っている生き物であり、そうした規則立ててとらえるのが難しい生身の人間を相手にするのがカスタマー・エクスペリエンスであり、だからこそ、企業がエクスペリエンスをマネジメントできるかどうかは難しい課題です。本日のお話では、各社それぞれの立場で取り組みをされていました。しかし、手当たり次第に経験ということで追求し始めると泥沼にはまり、つかみどころのないままに終わってしまいかねません。また、よくあるように、5年後には「カスタマー・エクスペリエンス」というビジネス用語がそれほど言われなくなっているかもしれません。しかしながら、言葉は変わるかもしれませんが、今日、皆さんと議論した課題の本質は、変わらぬまま対処し続けなくてはならないと思います。各社各様で一つの答えを出すことは難しいのですが、結局のところ、自分たちに何ができて、何をやりたいのかを明確にしていくことが重要といえるのではないでしょうか。
