CTO forum 2025
事業創造と研究開発マネジメント
~ 勝機をつかみ市場を生み出すR&Dの在り方 ~
開催日:2025年7月16日(水)
主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局
特別協賛:アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社、株式会社ユーザベース
生成AI、IoTの加速度的な進化、そしてカーボンニュートラルへの挑戦――。
2025年、世界を取り巻く環境は、昨日までの常識が通用しない、まさに「ターニングポイント」とも呼べる変革の時を迎えています。この激流の中で、企業が競争優位性を確立し、持続的な成長を遂げるためには、未来を洞察し、果敢に価値を創造し続ける「攻めの研究開発」と、それを牽引するリーダーシップが不可欠です。本フォーラムは、まさにその最前線で活躍されているリーダーの皆様に向け、選び抜かれた知見と本質的な議論の場を提供することを目指しています。
しかしながら、経済産業省の調査によれば、日本の研究開発投資効率は未だ3割に留まり、7割を超える中国など諸外国との間に大きな隔たりが存在するのも事実です。市場のニーズが複雑化・高度化し、製品ライフサイクルが短縮化する現代において、単に優れた技術を持つだけでは不十分であり、それをいかに迅速に事業へと結びつけ、市場を創造していくか、その「事業構想力」と「実行力」が厳しく問われています。
このような背景のもと、3回の開催を迎える今回の「CTO forum 2025」では、CTO(最高技術責任者)、研究開発、技術開発、新事業創出、新事業企画部門のリーダーの皆様が、近年の競争激化に対応し、最新テクノロジーの積極活用や他社とも連携し、スピード感をもって製品やサービスを市場に投入する戦略について考察。
また、不確実な領域でも、潜在する市場と必要となる技術を見極め、自社の研究開発をマネジメントする重要性や新しい時代を切り拓くための意思決定と強いリーダーシップを発揮するためのヒントについても議論を展開、聴講者の皆様へのヒントやキーファクターを探ります。
過去開催の<CTO forum >のレポートはコチラ
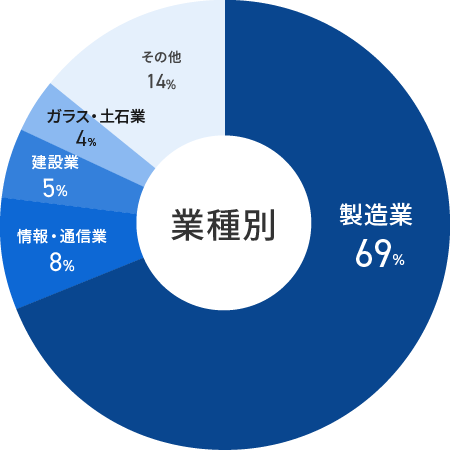
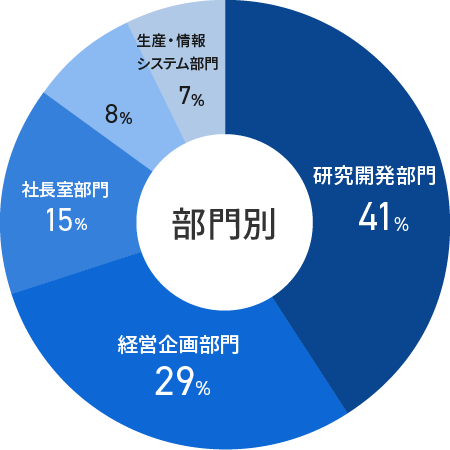
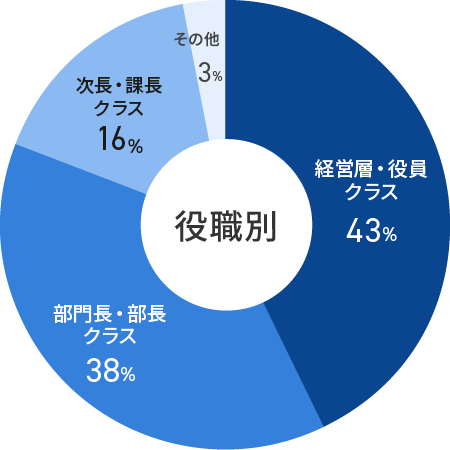
<特別講演1>
SINICを土台としたオムロンの新たな技術経営
オムロン株式会社 代表取締役 執行役員副社長 CTO
宮田 喜一郎 氏
- 先端技術の超加速的進化がビジネスを抜本的に変える時代
- 全社テクノロジーガバナンス導入による持続的な競争優位の確立
- SINICの実践を通じたオムロン流技術経営

参加者の声
- 近未来デザインや社会ドリブン経営への共感
「単なる技術追求ではなく、人や社会の幸せを見据えた視点に強く共感しました。SINIC理論や技術経営2.0の考え方は、自分たちの事業にも生かせそうです。」 - 新規事業創出や組織づくりのヒント
「近未来デザインやトライ&ラーンの実践例がとても参考になりました。IXI設立やポートフォリオマネジメントなど、事業を支える仕組みづくりは自社にも取り入れたい内容です。」 - 人材育成・評価制度の工夫
「人事評価を独立させる仕組みやプロセス評価の重視は、技術者のモチベーション向上に直結すると感じました。横断的な人材育成の考え方も勉強になりました。」
<特別講演2>
村田製作所のイノベーション創出と技術開発
~技術を核とした共創と持続的な価値創造~
株式会社村田製作所 代表取締役副社長
岩坪 浩 氏
- 村田製作所のイノベーションを支える技術戦略
- コア技術×共創による事業のスケール化と仕掛け
- 将来の事業機会を見据えた取り組み

参加者の声
- コア技術とM&Aを活用した事業展開・戦略への評価
「素材というコア技術を伸ばしつつ、デバイスやサービスへ事業展開している戦略に納得しました。積極的なM&Aと組み合わせる成長方針も参考になります。」 - 技術経営(MOT)・共創の考え方からの学び
「MOTやMBAの違い、直感を信じて行動する姿勢、本業や新規ビジネスを“人でつなぐ”考え方がとても共感できました。KUMIHIMO Techなどの挑戦も印象的です。」 - 人材育成と“人”の重要性への共感
「“2分野以上の技術領域を持ちイノベーションを起こす”という人材育成の思想や、経営者が技術現場に熱く語る場面に刺激を受けました。“信用の蓄積”や“知の融合”も心に残りました。」
<特別鼎談>
R&D起点の事業創出
~ 時流を捉え、生成AI時代のCTOに求められる
「革新と不変」のバランス経営 ~
オムロン株式会社 代表取締役 執行役員副社長 CTO
宮田 喜一郎 氏
株式会社村田製作所 代表取締役副社長
岩坪 浩 氏
モデレーター
株式会社ユーザベース 執行役員 スピーダ事業 ソリューション責任者 兼 知財・研究開発領域アカウント統括
伊藤 竜一 氏
- 両社の歴史と思想から紐解く「革新と不変」
- SINIC理論(オムロン様)/社是(村田製作所様)両社の取り組みの振り返りから、革新と不変をどう組み合わせながら成長してきたかを紐解く
- 時流を捉えた技術経営における人財開発・組織づくり
- 社会情勢や技術革新が激しい現代だからこそ求められる人材開発とは?
- 最新技術や市場環境の変化に対し、自社技術の価値を最大化に発揮させる組織づくりとは?
- 経営者として意思決定(判断)するCTOのあり方
- 経営者として技術にどう向き合うべきか、お二人の理論・持論やいかに
- 意思決定時の作法・技法はあるか

参加者の声
- CTOの役割・人材育成・イノベーションの考え方への共感と学び
「CTOのお二人の人材育成や新規・既存事業のバランスの取り方が具体的で、とても参考になりました。『できる人にやらせてみる』『人をつなぎ育てる』という言葉が特に印象的です。」 - 企業戦略・技術経営に関する具体的知見
「技術革新と社会課題の関係、DXと伝統製造業の融合など、幅広い視点が得られました。事業と技術の界面やハードとデジタルの距離感についても学びが多かったです。」
<基調講演>
価値創造3.0時代のイノベーション実装戦略
― PoCで終わらせない事業創出の「仕掛け」論 ―
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 プリンシパル
井上 敦朗 氏
- 価値創出の構造転換 ─
「技術起点・資本集約型」から「価値プロミス起点・共創プロデュース型」へ - PoCの先にある“壁” ─
スケールに必要な事業構造を初期段階から設計に組み込む - 価値創出のリーダーシップ ─
CTO/CIOは「技術部門の統括者」から「価値創造のプロデューサー」へ - 共創の仕掛け論 ─
オープンイノベーションは理念でなく、実装前提で設計すべきメカニズム - 成功の型化と再現性 ─
構想からスケールまでを貫く“営みの型”が成果を左右する

参加者の声
- PoCから事業化への課題と対策に関する学び
「PoCで止まってしまう要因や事業化への溝について体系的に理解できました。共創型イノベーション戦略や、中間撤退の判断、ナラティブの重要性はすぐにでも取り入れたいです。」 - 手法・フレームワークから得られた知見
「事業創出の流れや構造設計、Iteration設計など、フレームワークを動かすための視点が非常に参考になりました。実装に向けたストーリー作りの大切さも実感しました。」 - 自社の課題や業務との共通点を感じ、実務に生かせそうという評価
<ダイアログセッション>
テクノロジーとビジネスを繋ぐリーダーの役割
日本電気株式会社 執行役 Corporate EVP CTO(チーフテクノロジーオフィサー) グローバルイノベーションビジネスユニット長
国際社会経済研究所 代表取締役社長
西原 基夫 氏
キユーピー株式会社 研究開発本部 未来創造研究所 所長
糀本 明浩 氏
DIC株式会社 常務執行役員 技術・R&D担当 技術統括本部長
有賀 利郎 氏
モデレーター
株式会社ユーザベース 執行役員 スピーダ事業 ソリューション責任者 兼 知財・研究開発領域アカウント統括
伊藤 竜一 氏
- 技術をいかに管理し事業化のタイミングを見極めるか
- 死の谷を乗り越えて事業化させる仕掛け
- 組織風土や共感ベースで創るエコシステムの効果 など

参加者の声
- 人材育成・組織づくりに関する学び
「各社の人材育成の考え方や実例が参考になりました。強制ローテーションや専門職に見合った評価制度などの具体例も非常に役立ちそうです。」 - 事業創出と新規プロジェクト推進のヒント
「新事業部門のステージゲートやブーストゲート設計、技術のオープン化による共創促進の取り組みがとても勉強になりました。リーダーシップの重要性も強く感じました。」 - AI活用やオープンイノベーションの視点
「技術開発でのAI活用事例やAIと人材育成の関係に興味を持ちました。オープンイノベーションの話ももっと聞きたかったです。」
<ネットワーキング>


Special Thanks for Sponsors!
特別協賛
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社
株式会社ユーザベース
企画者からの御礼
株式会社ビジネス・フォーラム事務局
プロデューサー 進士 淳一
この度は「CTO forum 2025」へ、多くの方々にご参加を賜りましたこと、心から御礼申し上げます。
そしてこのたびの開催にあたり、多大なるお力添えをいただきましたご講演者の皆様、ご協賛社の皆様に、この場を借りて心からの御礼を申し上げます。
今後も引き続き、ビジネス・フォーラム事務局では、主催セミナー・フォーラムの開催、そしてその感想やご意見を通じて、皆様の課題解決へのヒントや新たな気づきをお届けできるような場を企画し、情報発信を続けて参ります。
今後も、ご関心・ご興味いただけるイベントにて、お会いできることを楽しみにしております。
