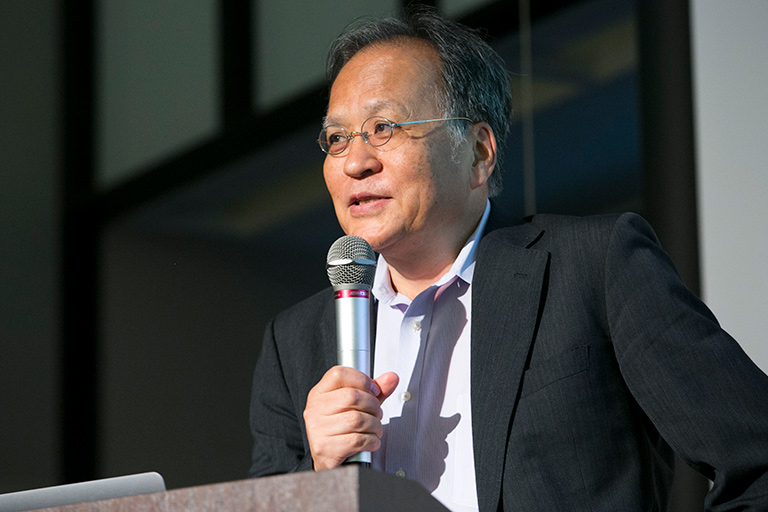製造業におけるデジタル革命とは
サプライチェーンをまたぐエコシステムの創造
岩野氏はまず、ITの社会における役割のI変化について触れました。1990年代には、第1段階として、ビジネスのクリティカルインフラとしてのITに焦点が当たっていました。この段階では銀行、製造業、流通業、物流など産業を支えるクリティカルインフラとしての役割です。2000年代に入ると、社会とITの役割に注目が集まりました。つまり社会のクリティカルインフラとしてのITに期待がおかれたのです。様々な社会システムや社会サービスがクラウドコンピューティングを代表とするITのインフラをベースに設計されてきました。スマートコミュニティーなどが一例です。この第2段階では、ITのコミュニティーは、そのアーキテクチャーや技術の可能性の提示など社会からの預託を受けており、それは社会的責任を伴うものです。そしてこれから起きようとしているのが第3段階で、そこでは「知と森羅万象とIT」がキーワードになってきます。
とくに第2段階としての現在のITの位置付けは、クラウドとサービスの台頭によってビジネスモデルに変化を生み出します。そして、データとアルゴリズムの価値がますます重要になり、サイバーと物理的世界、個人と集団・社会、機械と人間、対象と主体などについての境目がなくなります。そこでは、ITが社会のクリティカルインフラとして機能するかどうかという点において、社会からの預託と科学者・技術者の社会的責任が大切になります。
今後は、モノを作るだけではビジネス的価値は見出せません。モノはサービスにエンベデッドされて初めて価値を生み出し、機能を提供します。そして、機能やサービスは、エコシステムに位置づけられないと、大きく寄与できません。そう考えると、製造業のプロセスインダストリーにおいては、「サプライチェーンをまたぐエコシステムを作ることが、これからの大きなチャレンジになってくるのです」と岩野氏は語ります。
次に岩野氏は、デジタルに取り組むMCHCにおけるCDOのビジョンを、「デジタル技術と思想によって会社、業界、社会に新しい流れを作り、MCHCのビジネスや風土に変革をもたらすこと」と紹介します。MCHCは、新しい価値創造のプラットフォーマーを目指すのです。ただし、自社だけで目指すのではなく、サプライチェーンや新しいエコシステムを作ることにより、新サービスや新ビジネスを行い、様々な組織の連携でこれを実現していきます。そのために、MCHCはデジタル先進風土を持った企業体、集団を目指し、デジタルネイティブな組織になることが大きな課題になるとのこと。