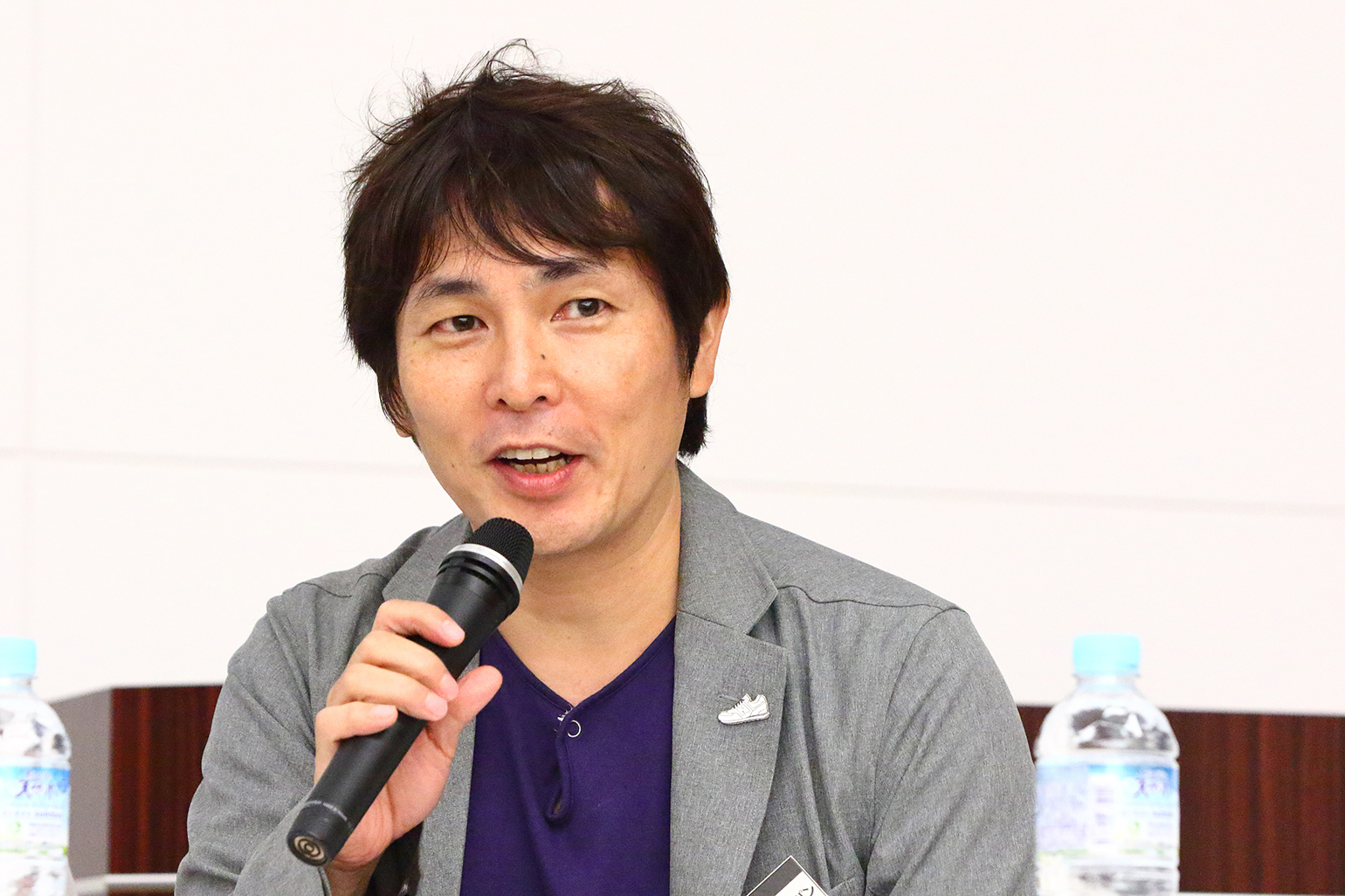顧客接点では人が感情的なつながりをつくる
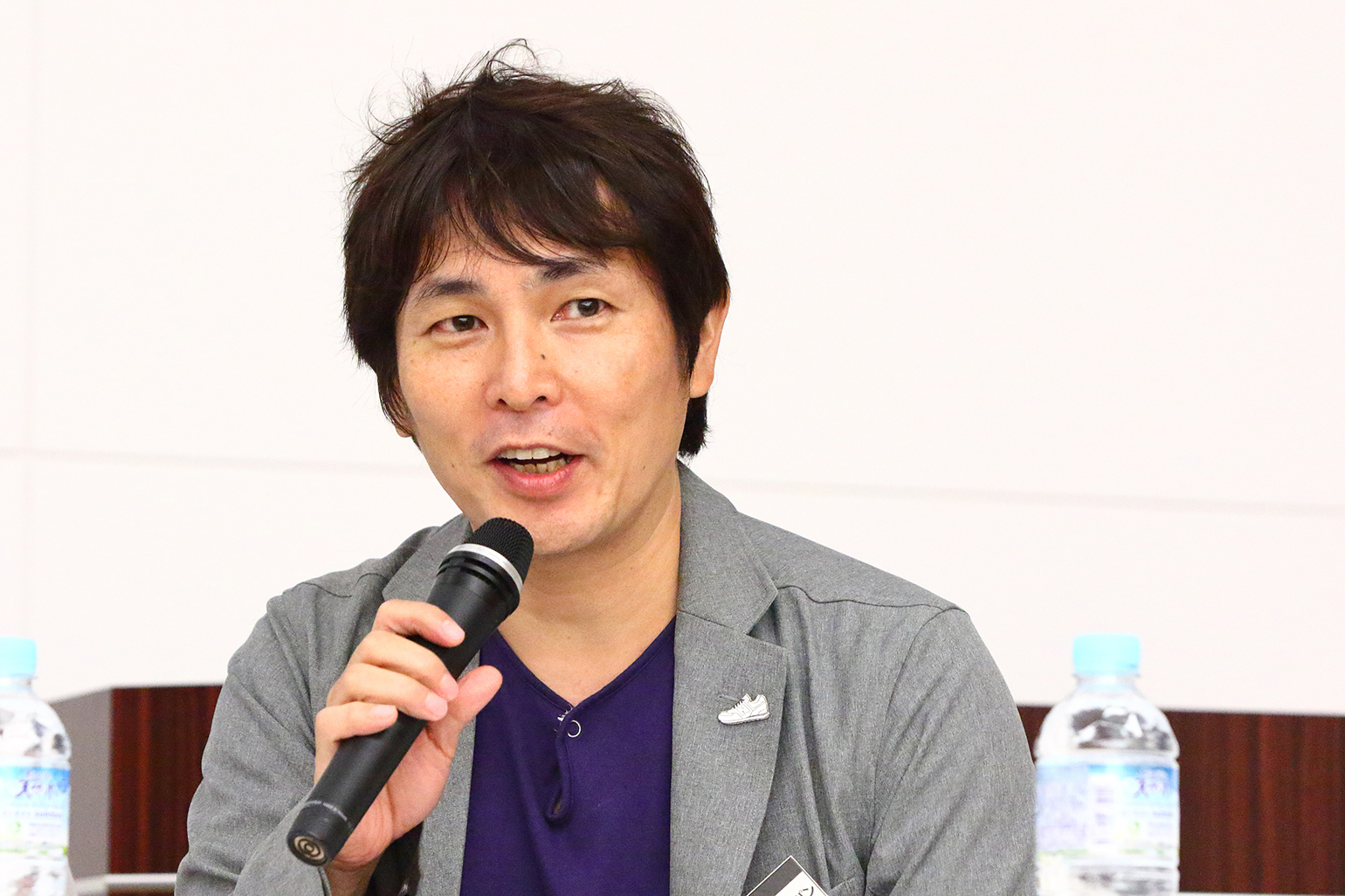
小野: 顧客接点において人が果たす役割は非常に大きいと考えます。人と接点を持つ時というのは良い面も悪い面も感情が生まれやすく記憶に残りやすい、と考えられるからです。そういう意味では東京海上日動コミュニケーションズが設置しているようなコンタクトセンターは、その最前線に立っている重要な存在といえますね。
田口: AIの導入など無人対応化が進み、コンタクトセンターでもお客様と人との接点が少なくなっています。お客様と接する機会をとらえ、どう価値を提供するかが重要です。いろいろ研究してみてわかったのは、社員満足(ES)がお客様満足(CS)に影響しているということです。ESが上がるにつれてCSも上がり、お客様から「本当に助かりました。ありがとう」「次もお世話になりたいから名前を教えて」といった感情のこもったお礼を言われる機会が増えました。また、お客様からの感情のこもったお礼は、社員のモチベーションアップにもつながり、「お客様のためにもっと頑張ろう」となって良いサイクルを生みます。企業は、AIやITへの投資とともに、社員への投資も重要です。

小野: 消費財ブランドも顧客接点における人の役割は大きいと思いますが、いかがでしょうか。
長瀬: 化粧品はブランドエクスペリエンスがすべてといっていい商材です。カスタマーセンターにも非常に力を入れています。AIの導入も始めていますが、プレミアムブランドとして価値を提供しようという時にAIはどうなのかと疑問に感じるところもあります。特に日本人はその辺りの感覚が難しいですから。時代に逆行するかもしれませんが、日本では24時間、人が対応するカスタマーセンターをつくる構想も持っています。
小野: アクティブコアはマーケティングデータやウェブサイトの行動履歴を統合して分析することで企業の経営を支援しています。顧客接点や人について、どんな問題意識を持っていますか。
山田: 以前の企業にとって顧客接点として重要だったのは、営業マンが最初に訪ねる段階でした。そこで資料や動画を使って製品やサービスを一通り説明していました。しかし、今ではお客様は事前にそういう情報は手に入れています。お客様を訪ねる時にはクローザーが登板することが必要です。企業は社員を成長させ、クローザーとしての力を付けさせることが必要になっていると思います。

小野: 今後、顧客接点のリデザインはどういう方向に向いていくのでしょうか。未来の方向性を一言ずつお願いします。
井上: キーワードは「シームレス」だと思っています。バックオフィスもフロントもシームレスにお客様にアプローチできるように注力していきたいと考えています。
鈴木: 今、ブランドが手掛けているコミュニケーション、サービス、ショッピングはひとつの塊のようなものだと思っています。例えばスターバックスはコーヒーを売っていますが、コーヒーを売るだけでは成立しないビジネスです。店舗があって、そこで働く店員がいて、ブランド体験できるのです。ニューバランスでもバラバラになっている接点を垂直統合し、ブランドをマネジメントしていきたいと思います。
長瀬: どれだけマーケティングツールを導入しても、店にモノがそろっていないとか、在庫管理が追いつかないといったことがあればブランドエクスペリエンスは完成しません。デジタルツールを最大限に活用しつつ、社内の業務を最適化した新しいエコシステムを早急につくらなくてはいけないと思っています。
田口: これから重要なのはカスタマー・エンゲージメントです。お客様と感情的なつながりをつくることでLTVは向上します。どのようにそのつながりをつくるかを考えていきたいと思っています。
山田: 顧客接点の1つである顧客サポートについて、昨年からすべての履歴をデジタル化し、時系列でデータベースに入れることを始めています。効率という点では劣るかもしれませんが、ここから新しい知見を得て価値提供につなげられるのではないかと期待しています。うまく活用していきたいと考えています。