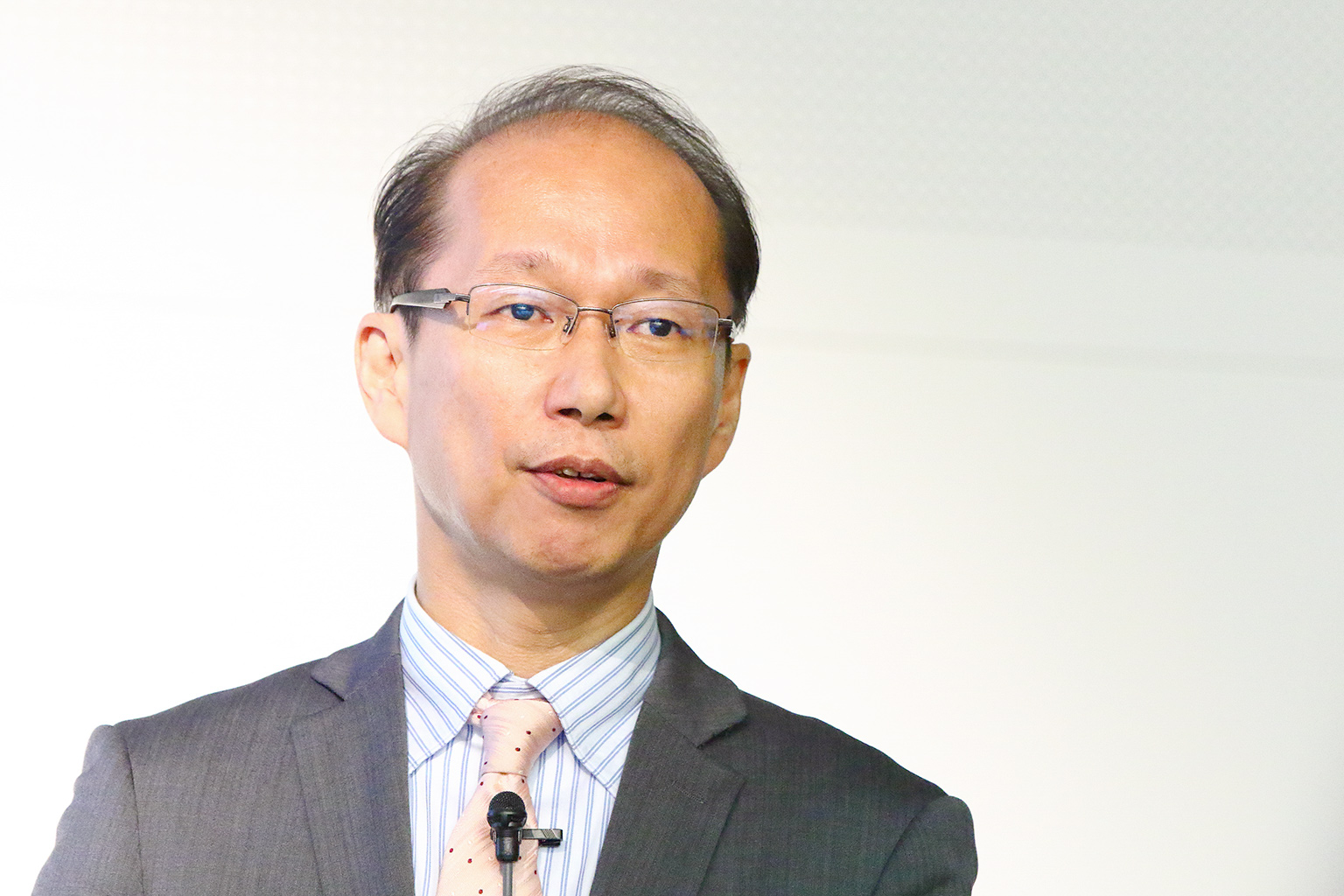コンバージョン(成約)率が1%程度から6.6%に向上

AI(人工知能)が急速に進化しています。先進的な企業では、このAIをマーケティング領域に活用しようという動きが始まっています。機械学習とは確率・統計モデルに基づくパターン認識のことです。与えられたデータからいくつかのパターンを認識・学習し、未知のデータを分類・予測します。機械が予測した結果を正解と比較し、その誤差からモデルを更新していきます。よく使われるアルゴリズムの1つがニューラルネットワークです。AIの多くはニューラルネットワークを使っています。ディープラーニングもAIの手法の1つです。ディープラーニングはニューラルネットワークを幾層も重ね、データを学習して特徴を自動的に抽出します。これがAIにおけるブレークスルーとなり、予測精度は大幅に向上しました。
マーケティング領域で進んでいるのは、企業が構築してきたプライベートDMP(データマネジメントプラットフォーム)に格納している顧客データ、広告データ、Web行動履歴、売り上げデータなどを分析・可視化し、ターゲット顧客を抽出して広告を掲示したり、メールやアプリで情報を配信したりレコメンドするプロセスに、機械学習やディープラーニングを取り入れたりする取組みです。そうすることで顧客の理解を深め、最適な顧客接点を創り出そうという試みが始まっています。
当社が手掛けている事例を幾つかご紹介します。1つは19,000人ほどのデータの中から、購買・コンバージョン(成約)しそうな顧客を予測し自動でセグメントする取組みです。Web行動履歴から資料請求につながる特徴を自動学習して学習モデルを作り上げ、学習を重ねてセグメントの精度を向上します。このモデルをBtoBの販促に活用したところ、送信したメールの開封率は54.7%に達し、コンバージョン率(資料請求)は通常1.0~1.2%のところ6.6%まで向上しました。
メールの配信時間の最適化も図っています。多くの場合、メールは配信後、数時間以内に開封されますが、それ以外の時間で開封する顧客もいます。メールを開封した時間、クリックしてウェブサイトにアクセスした時間、コンバージョンした時間などから顧客を自動分類。機械学習により配信時間を最適化します。従来12時に一斉配信していたものを1時間刻みにして個別配信したところ、開封率は19.1%から29.7%に上がりました。メールの開封率が上がればアクセス率、コンバージョン率も上がります。その結果をまた学習して次回以降の配信をさらに最適化しています。