CDO(Chief Digital/Data Officer)フォーラム 2017
デジタル変革に挑み、
企業競争力に変える
生き残りをかけた
デジタルトランスフォーメーション実現へのリーダーとは
開催日:2017年 7月 14日(金)
主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局
ゴールドスポンサー: PwCコンサルティング合同会社
シルバースポンサー: ドーモ株式会社
ブロンズスポンサー: 株式会社電通国際情報サービス
2017年7月14日、「CDO(Chief Digital/Data Officer)フォーラム 2017」を開催しました。CDO Club、CDO Club Japanにご協力いただき初開催となった今回のフォーラムでは、「デジタルトランスフォーメーションを実現するリーダー像」にフォーカスをあて、これからの企業における変革や経営戦略を牽引する上で、期待が高まるCDO(Chief Digital/Data Officer)の役割やミッションを紹介しました。先進的にCDOを設置している企業の事例とともに、この日の講演やパネルディスカッションから、CDOが持つ可能性とリーダー像をご覧ください。
オープニング
CDOとはなにか
企業や組織の中でどのような役割を持つのか
一橋大学 商学研究科 教授 工学博士 CDO Club Japan 顧問
神岡 太郎 氏
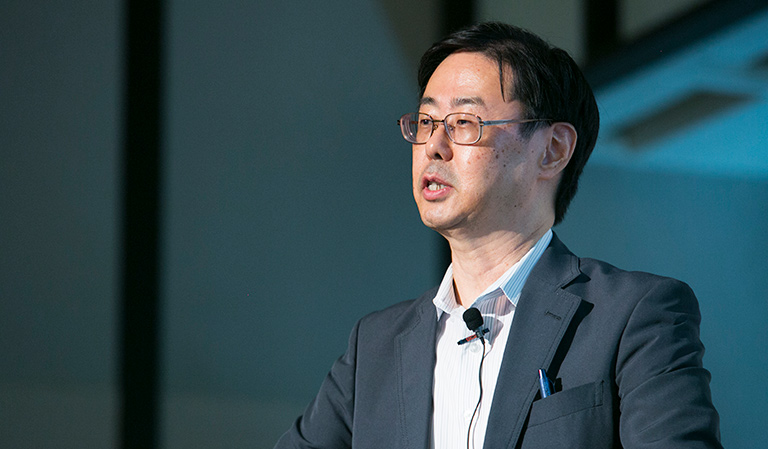
現在、営利非営利問わず、さまざまな組織にとって、デジタルへの対応は避けては通れない道です。デジタル化で組織を活性化したり、顧客やユーザーに最高の体験をもたらすには、これまでのCIOやCMO、CTOではない、デジタル専門のリーダーとしてCDO(Chief Digital Officer)が必要になります。この日のオープニングとして、CDOの定義やその役割などにつき、CDO Club Japanの顧問でもある神岡氏に講演いただきました。
デジタルに対応する組織への転換
組織におけるCDOの必要性

「CDOとは、組織におけるデジタルの最高責任者です。企業あるいは政府・自治体などの組織がデジタルに対応する体質改善のための責任者で、今後非常に重要な役割を果たすことになります」と、神岡氏は説明します。CDOには「Chief Data Officer」という意味もあるといわれますが、本講演ではDigitalの視点から語られました。
ここ数年、意識的にITとデジタルを区別して使う傾向が増えてきましたが、そもそもITとデジタルの違いとはなんでしょうか。その問いに対して神岡氏は、「テクノロジーの視点からは、両者はほとんど同じ意味と捉えていいでしょう。ところが、応用や設計の視点から見ると違いがあります」と答えます。たとえば、ITのシステムは、組織が無駄なく効率的に運営されるように、さまざまなことを管理するために設計されます。そこでは、設計者や管理者の視点でシステムが作られるため、システムの構築途中や構築後に仕様を大きく変更するとなると大変です。一方でデジタルのシステムは、初めから世の中の動きに合わせて変更されることを前提に設計されます。なぜなら、利用するユーザーや顧客の視点でシステムを構築するからです。このようにシステムの設計面から考えると、ITとデジタルでは明らかに必要とされるスキルやノウハウが異なっています。「企業は、まず自社にとってデジタルとは何かを明確にする必要があります」
そして、デジタルをうまく活用して高い成長を遂げたのが、UberやAirbnbなどといったいわゆる「Digital Disrupter」と呼ばれている企業だと神岡氏は紹介します。「これらの企業は顧客の目線に立ち、従来のタクシーやホテルの概念を超えた新しいビジネスモデルを作ることで、顧客に大きな満足を与えることに成功しました」
神岡氏は組織におけるCDOの必要性について、海外の例を挙げ、こう述べました。「もともと企業においては、ITやマーケティングに関わるCIO(Chief Information Officer)やCMO(Chief Marketing Officer)と呼ばれる人たちがデジタルへの対応も担っていました。ところが、組織のあらゆる活動がデジタルに関係することで、たとえばワークスタイルなど働き方にもデジタルへの対応が求められるようになりました。そういったことまでも、CIOやCMOの責任の範疇に含めてしまうことは不可能です。そこで必要になったのが、組織の中でデジタルに関わることを専門に担当するCDOというリーダーです」。企業のみならず、政府や行政に関わるサービスのデジタル化も大きなトピックになっているようで、「すでに世界の政府の24%にCDOがいます」とのこと。
CDOはどういった役割をもつのか
CDOに求められる資質とは

神岡氏は、CDOが組織の中で担う役割には、大きく次の3つがあると紹介しています。1つめは、「デジタルを組織の中にどう取り込んでいくかを考えること」。これまでのビジネスプロセスでは、まずビジネス戦略を決めてからIT戦略を決めていました。しかし、デジタルの場合は、Digital Disrupterの成功例に見られるように、ビジネスと一体で戦略を考えなければいけません。デジタルがあるという前提で、サービスを考えるのです。2つめは、「そもそも今の組織やビジネスは、このままのやり方でいいのか、再定義する必要があるのではないかということをデジタルの視点で考える「Digital Transformation」と呼ばれる取り組み」。3つめに神岡氏が挙げたのが、「デジタルに対応する人材の教育や発掘」です。他にも、「外部企業とパートナーシップを結んでデジタルへの対応を促進したり、新ビジネスに取り組むためのエコシステムを構築するといったことも、CDOに求められる能力になる」と説明を加えます。
神岡氏はCDO Club Japanの必要性として、ノウハウを共有する人材同士が交流する場があることは非常に重要だとし、「そういった人たちがチームCDOとして集まって自分たちの組織を活性化したり、顧客や国民、市民に対して、高いレベルのサービスや価値が提供できるような仕組みができればといいと思っています」と今後の抱負を語りました。
特別ゲスト講演
デジタル化推進により統計を高度化
より実効性の高い政策立案へ
参議院議員 (現:文部科学大臣)
林 芳正 氏

昨今、GDP(国内総生産)などの統計が、社会の急速な変化を把握し切れていないとの指摘があります。デジタル化推進も含めて統計を高度化し、より実効性の高い政策立案に役立てるために何をなすべきか。自由民主党政務調査会の新経済指標検討プロジェクトチームは、こうした問題意識のもとに協議を重ね、今年5月に提言をまとめました。特別ゲスト講演では、提言の内容について同チーム座長の林氏に講演いただきました。
デジタル化で集計作業前倒し
統計精度の向上に民間のビッグデータ活用も

同チームが取りまとめた提言の柱は、「統計手法の改善」「新たな統計基準の整備」「GDPを補完する指標の検討」「統計作成・活用基盤の構築」の4つです。
1つ目の「統計手法の改善」については、経済実態をより的確にとらえるための策を検討しました。林氏は、四半期ごとに出すGDP速報値について「一次速報でプラスだった数値が、二次速報ではマイナスに変わる場合もあります」と指摘。数値に差が出てしまう原因として、GDPに影響を与える財務省の「法人企業統計調査」の集計が一次速報のあとになるためだとして、「デジタル化などにより、一次速報に間に合わせられる可能性はあるのではないでしょうか」と作業を前倒しできるとの考えを示しました。
GDPは、この法人企業統計調査を含むさまざまな調査結果を加工・編集してとりまとめています。林氏は「これら各調査の改善により、GDPの精度はさらに高められる」と主張します。たとえば、家計調査では、国の調査に加えて、民間企業が持つ顧客のビッグデータなど新たなデータ源の活用により、精度の向上が期待できるといいます。
「スポーツや文化、レジャーといったサービス分野の統計に関しては整備が遅れている」と林氏。「たとえば映画館の売上データはあるが、ネット上の動画サイトなどでコンテンツそのものが生み出す収益の統計はない」と述べ、サービス分野に関する基礎的なデータの収集に力を入れて実態を把握する必要があるとしました。
今後求められるのは「コーディネーター」
データ関連人材の育成を強化へ

「新たな統計基準の整備」では、GDPなどを計算する際の国際基準、SNA(System of National Accounts)の改定が行われる際には、国として積極的に参画すべきだと主張します。「我々の知らないところで決められた基準をそのまま受け入れるのではなく、我が国の経済の実像を国際基準に常に反映していこうということです」
SNAの国内版であるJSNAの次回改定時には、欧米と同じく、映画やアニメといった娯楽作品の原本(オリジナル)への支出を、GDPの構成要素である投資に含めるべきだといった内容も、提言に盛り込まれました。林氏は「原本にどれだけのお金を投入したか、細かく把握する統計が整備されていない。基準に入れるだけではなく、数字としてしっかり把握する仕組みが必要」とも指摘しました。
「GDPを補完する指標の検討」の説明で、林氏は「年収が1千万円を超えると、それ以上に年収が増えても幸福感はあまり上がらないとも言われています。GDPの豊かさがイコール幸せとは限らないのかもしれません」と問題を提起。暮らしの11分野(住宅、収入、雇用、共同体、教育、環境、ガバナンス、医療、生活の満足度、安全、ワークライフバランス)で豊かさを比較できるOECD(経済協力開発機構)の指標「Better Life Index(BLI:より良い暮らし指標)」を紹介するとともに、「GDPだけに頼って政策全般を立案するのはリスキーだということで、これの日本版を作ってはどうかと提言しました」と述べました。
最後の「統計作成・活用基盤の構築」では、ここ10年で、農林水産統計職員が85%減少するなど、国の統計関係職員は約6割減少し、統計を支える基盤が脆弱化していると指摘。今後は、CDOを含むデータ関連の専門家を増やす必要があると説くとともに、「データの収集自体はアウトソーシングも可能。これから必要な人材は、集めてきたデータを加工・分析して政策提言につなげるという、いわばコーディネーター的な役割の人」と、求められる人材像を示しました。
林氏によると、現在、統計に関連する大学の学部は、滋賀大学データサイエンス学部のみ。「今後は、各大学でのデータサイエンスを専門とする学部やコースの設置を促進するとともに、工学部など他の理系学部でも統計の基礎的なリテラシーが習得できるような教育を進めるよう提言しました」と述べ、教育の重要性を指摘して講演を締めくくりました。
来日特別講演
CDO Clubの活動と役割
日本企業へのアドバイス
CDO Club CEO David Mathison 氏
CDO Club Japan 代表&創立者 加茂 純 氏


近年、欧米では急速にCDOが注目され、その人数も増加しています。グローバルなビジネス視点からの示唆とともに、CDO Clubの活動と役割、日本企業へのアドバイスについて、CDOフォーラムにご協力いただいている、CDO ClubのCEOであるMathison氏とCDO Club Japanの代表&創立者である加茂氏に講演いただきました。
欧米に遅れることのないようCDO Club Japanを設立し
アジアでの主導を目指す

講演の冒頭では、Mathisonが立ち上げたCDO Clubの経緯などにつき、加茂氏が紹介しました。Mathison氏は2010年頃に世の中でCDOが必要とされていることを認識し、2012年にニューヨークでCDO Clubを設立しました。CDO Clubは現在、世界各地でCDO Summitを開催するなどして、CDOの支援を行っています。
次は、今年5月に設立された、CDO Club Japanの設立の経緯についての紹介です。じつは、日本におけるCDO Clubの設立には、時期尚早という意見もありました。しかし、現在CDO Club Japanの顧問となっている一橋大学商学研究科の神岡太郎教授のアドバイスを受けるなどした加茂氏が、世界に遅れることはできないとの思いでMathison氏の説得などに当たりました。
CDO Club Japanの最初の目標は、CDOの育成、社外パートナーとの協力が必要なCDOがパートナーと出会う場の提供です。2018年1月26日には日本で最初のCDO Summitを開催し、以後年2回のペースで開催するといいます。そして、CDO Club Japanが主導してアジアへの展開を図り、2018年8月にはシンガポール、その後は香港などにおいてCDO Clubを設立することを目指しています。
破壊的な経済からの企業防衛のために
世界で必要とされているCDO

CDO Club の創立者であるMathison氏はCDOについて語る場合、以下の3つのポイントがあると言います。
一つは「今世界中でCDOが増えている」ということです。昨年には、同氏が把握しているだけでも、CDOの人数は2,000人を超えています。次は「CDOからCEOになる人が増えている」ということです。ここ数年で100人以上のCDOがCEOに昇進しました。そして最後は「Chief Digital Officerの重要度がChief Data Officerと同じくらいに増している」ということです。Chief Digital Officerはオンライン経済の主役となっています。この傾向は、企業だけでなく政府や州政府、各自治体でも同様で、さらには、米国だけでなくヨーロッパやアジアなど、どの国や地域においても起こっています。
Mathison氏は、今CDOが必要とされている主な理由として以下を挙げました。
「旧来の経済に破壊を起こしているシェアリングエコノミーにおいては、新しい企業が破壊行為を行っているのではなく、個人の力が破壊行為を行っています」。例えば、TV業界を苦境に陥らせた原因にYouTubeが挙げられますが、そのコンテンツは企業が作っているのではなく、私たち個人が作っています。そして、YouTubeが収益を上げています。これは他のビジネスにおいても同様です。「このような破壊的な経済から企業を防衛するためにCDOの力が必要なのです」

また、2008年に国際金融危機が原因となり、危機管理などのための要員としてChief Data Officerが爆発的に増えました。現在、Chief Digital Officerは約2,000人、Chief Data Officerも約2,000人ですが、Chief Digital Officerは今後2~3倍に増えると見込んでいます。
Mathison氏は、CDOに関連する役職として、デジタルの改革を担当するChief Digital Officer、データの管理を担当するChief Data Officerのほかに、Chief Analytics Officerを挙げます。「Chief Analytics Officerは、データの解析を牽引する役割を担います。この3つの役職が社会を牽引する立場となるのです」。そして、「デジタルは戦略であり、ITに留まるものではない」というマッキンゼーの言葉を紹介しました。
このあとMathison氏は、日本の企業におけるCDOの数がごくわずかであると述べるとともに、米国を中心とした有名企業数十社のCDOの氏名と顔写真を紹介しました。ここで紹介されたCDOの所属企業や氏名などは、CDO Clubのウェブサイトで紹介されています。
スポンサー講演
デジタル変革の潮流と
企業が今後取り組むべき論点
PwCコンサルティング合同会社 パートナー デジタルサービス日本統括
松永エリック 匡史 氏

経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供するPwCコンサルティング合同会社は、世界157カ国、22万人以上を有するPwCグローバルネットワークの幅広い専門性やナレッジを活用することにより、複雑化する経営課題の解決をグローバルレベルで支援する企業です。日本でのデジタルサービスを統括する松永氏は、もともと専門教育を受けたプロの音楽家であり、かつコンサルティング業界でも豊富な経験を持っています。ここでは、デジタル変革に対して企業が取り組むべき論点について講演いただきました。
非連続的な変化が
イノベーションをクリエイトする

CDO Club創立者Mathison氏の講演を受け、信念が確信に変わったと話を切り出しました。Mathison氏によれば、CDOの機能を最初に行使した企業は音楽配信サービスのNapsterであり、最初のCDO採用はMTVであると語った部分です。松永氏によれば、これはCDOの本質的な機能が”イノベーション”にあることを意味していると語りました。Napsterは、音楽コンテンツの権利に対しての革命であり、MTVは音楽の聴き方そのものに対する大革命でした。しかしここで注目すべきは、NapsterもMTVも、最新のテクノロジーを駆使したサービスではなく、本質的なイノベーションを既存の技術で実現した事例であると。つまり、イノベーション=技術ではないという点が重要であると力説しました。
イノベーションを起こすのに重要なのは、非連続的な発想です。アーティストの非連続的な発想として有名アーティストであるデビッド・ボウイが2002年に“近い将来、音楽は水のように消費される時代が来る”と、現在の音楽配信サービスのフリーミアム時代の到来を直感的に予測した事例をあげました。アーティストは事例ベースの連続的な変化を発想するのではなく、非連続的な直感的な発想からイノベーションを起こし続けるのです。この直感的な発想が、CDOに求められる一番重要なケイパビリティーなのです。
イノベーションを起こす
直感を得意とするミレニアル世代

「直感的な発想は、ミレニアル世代が得意としている」と松永氏は見解を述べます。本格的なパーソナルコンピユータの時代をApple IIとすると1977年、そして商用インターネットの開始である1987年を背景とし、幼少期からパーソナルコンピュータでインターネットを使える環境にいる事ができた最初の世代(デジタルネイティブとも呼ばれる)をミレニアル世代と呼んでいます。1年単位で厳密に定義する必要はないと思うのですが参考までに、米国ピュー・リサーチ・センターによればミレニアル世代は1981年から1996年に生まれた人々と定義されていますが、だいたい1980年以降に生まれた世代と定義している方が多いようです。要は、物心がついた時からコンピュータとインターネットが普通にあり恐怖感、違和感なく使いこなす世代というわけです。
ミレニアル世代は、モノにはお金をかけずサービスにお金をかける、バーチャル世界でのインタラクティブなコミュニケーションを好む、バーチャルでの人とのつながりを重視しリアルだけでは満足できなくバーチャル世界でシェアしないと不安でしかたない、などの特徴に加え、直感的に思ったことを重視し、我々がもつ既存の価値観に縛られることを嫌う傾向があると考えられています。その結果としてミレニアル世代は、日本の典型的なよい学校を出てよい会社に入って安定するという従来の帰属意識がなく、自らの価値観でサービスを生み出し起業したりするのです。ミレニアル世代の出現は大きな出来事であり、現にミレニアル世代から生まれたAirbnbやUberが、既存の業界を脅かしています。
松永氏は、「イノベーションは産業全体で起こしていくのではなく、これからは企業が起こしていかなければいかなくなる。そしてイノベーションを牽引する重要な役割を担うのがCDOであり、この役割はCEOにも求められてきている。事実、Mathison氏によれば2017年には100名クラスでCDOがCEOになっていると言います。これはCEOとCDOの役割がイノベーションをキーワードに急接近している予兆と言えるでしょう。今後は企業にも個性があるようにCDOにもイノベーションを起こすための個性が必要になっています。イノベーションを企業でどう起こしていくか組織的な議論も必要となり、CDOを汎用的な定義付けをすることは非常に難しい。」と語ります。そうした中でPwCのデジタルトランスフォーメーションの事例として、PwCデジタル部門がイノベーションのフレームワークとして取り組んでいるBXT(ビジネス、エクスペリエンス、テクノロジー)についての説明がありました。
BXTは、クリエイティブな発想のチームを中心にエクスペリエンスの担当をし、旧来からPwCの強みであるビジネスと最新テクノロジーと融合させることによってイノベーションを牽引するというものです。PwC全体として取り組んでいるデジタルトランスフォーメーションの中核となるフレームワークで、デジタルチームによりアシュアランス、TAX、ディールズといったコンサルティング以外のPwCにも経営層から変革を仕掛け、PwC全体としてイノベーションの中核となっていく取組です。
最後に、今後はイノベーションや企業変革のキーマンとなるべきCDOがさらに注目されてくるであろうという見通しを示し、講演を締めくくりました。
「直感的な発想は、ミレニアル世代が得意としている」と松永氏は見解を述べます。ミレニアル世代は、人とのつながりを重視する、リアルだけでは満足できない、などの特徴に加え、直感的に思ったことを重視し、規定されることを嫌う傾向があると考えられるのです。その結果としてミレニアル世代は、よい学校を出てよい会社に入って安定するという従来の帰属意識がなく、どんどん自分で会社を生み出しています。ミレニアル世代の出現は大きな出来事であり、現にミレニアル世代から生まれたAirbnbやUberが、既存の業界を脅かしています。
松永氏は、「企業に個性があるようにCDOにも個性があり、CDOを見ればその会社のデジタルトランスフォーメーションの方向性がよく分かるし、自分の会社にとってどういうCDOが必要なのかというヒントにもなる」と語ります。一例として、松永氏は自身の会社について紹介しています。PwCでは、これからはビジネスとテクノロジーの観点だけでは、コンサルティングはできないという意識があったそうです。そうした中で打ち出したのが「ビジネス」「エクスペリエンス」「テクノロジー」という3つの言葉の頭文字をとったBXTというキーワードです。音楽家としての経歴を持つ松永氏がエクスペリエンスを担当し、デザイナー出身者がビジネスを担当するなど、クリエイターの直感的な視点もイノベーションに活かそうと考えているそうです。最後に、今後はイノベーションや企業変革のキーマンとして、CDOがどんどん注目されていくという見通しを示し、講演を締めくくりました。
事例紹介講演1
CDO(Chief Digital Officer)の役割と
求められる資質
日本ロレアル株式会社 チーフデジタルオフィサー(CDO)/デジタル統括責任者(デジタルカントリーマネージャー)
長瀬 次英 氏

フランスに本部を置く世界最大の化粧品会社ロレアルは、国や地域別にローカルなCDO本部があります。その下で事業部ごとないしブランドごとにデジタルチームがいるなど、デジタルにたいへん力を入れている企業です。そんなロレアルに30代で経営陣として入った長瀬次英氏に、ロレアルにおけるCDOの役割について講演いただきました。
ロレアルにおけるCDOの役割は
デジタル全般の旗振り役

長瀬氏の仕事は日本での事業においてのCDOとして、世界中から集まった情報を基に、日本の市場においてはどういった戦略で事業を進めるのか、そしてグローバルの方向性にどう合わせていくのかを検討し実施していくことです。日本でのビジネスの仕方を提案し、事業を進めていきます。すなわち、「グローバルの方向性と水準に合わせて組織を動かす」「会社にあったデジタルビジネスの枠組みを提案する」「デジタルビジネスの質を上げ加速させるガイダンスを行う」ことです。また、「CDOがいるだけでデジタルが進みそうな感じがすることも重要」と長瀬氏は語ります。「外部に対するメッセージが強くなり、内部にも明確なディレクションを行うことができるのです」
ロレアルのCDOは、開発からマーケティング、サプライチェーン、カスタマーサービス、教育、人材・採用、IT/ISなど会社全体に関わっていきます。また、ロレアル・ジャパンには22のブランドがあり、それぞれが多くのメディア投資を行っています。新聞や雑誌、テレビなどのトラディショナルメディアもあれば、Webなどのデジタルメディアもあり、それらメディアへの投資を統括するのも、CDOの役割になっています。
デジタルビジネスにおいて不可欠な外部企業とのビジネス連携もCDOの重要な役割の一つです。じつは、自社製品開発が中心にあったロレアルではこれまでに、外部企業とパートナーシップを結ぶことがあまりなかったそうです。もともと開発力が高いので、いいものを作れば売れるというマーケティングを行ってきたのですが、「今は開発力だけでは通用しない時代だという認識を持っています」と長瀬氏は語ります。それを経営層に理解してもらうためにも、デジタルについての教育やトレーニングに力を入れているとのことです。
ロレアルにとってデジタルとは?
デジタルで注意すべきことは?

ロレアルではデジタルの役割は「お客様に近づくこと」と、全社で認識して行くことが大切だと考えています。お客様に近づく手段は、インターネットであろうがスマートフォンであろうがかまいません。「CDOはそういう大きなビジョンの中で、どうやって経営的な数字をあげていくかを考えることが重要」と長瀬氏は語ります。「もう開発力だけでは生き残れない。いいものができたから売るのではなく、できる限りお客様に近づき、お客様の声を拾ってお客様のニーズに答える形で商品開発に活かす必要がある。CDOはそういったデジタルマインドセットやデジタルナレッジによって、会社を強化しなければならないのです」
さらに長瀬氏は、CDOは会社に対してディスラプティブであるべきだと考えています。そのためには、今までいなかった人材を積極的に取り入れることが大切です。長瀬氏自身も、「30代でロレアルの経営陣に入った日本人は珍しく、その期待に応えるのも自身の仕事だ」と語ります。そういった人材がもたらす、新しい組織体制、収益モデル、新ビジネスのエコシシテム、さらに、今あるものに新しいバリューを生み出すことに価値があると考えます。
デジタル人材の採用に関して、注意すべきことがあります。一般的な企業では、WebをやらないといけないからWebマスターを採用する、CRMをやらないといけないからCRMのリーダーを採用するというやり方でデジタルの人材を補充しているのではないでしょうか。それでは、今必要な人材を採用することはできても、その後のキャリア育成については後回しになってしまいます。長瀬氏はデジタルカントリーリーダーでもあり、デジタル人材の育成とそれが活きる組織を構築する事においても責任を持っています。今後外部から採用するデジタルの人材に対して、「経営者まで上がっていけるキャリアパスの道筋を、ロジカルに説明できるようにしておくことも重要だ」と締めくくりました。
事例紹介講演2
三菱ケミカルホールディングスにおける
CDOの役割と展望
株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員CDO(最高デジタル責任者)
岩野 和生 氏
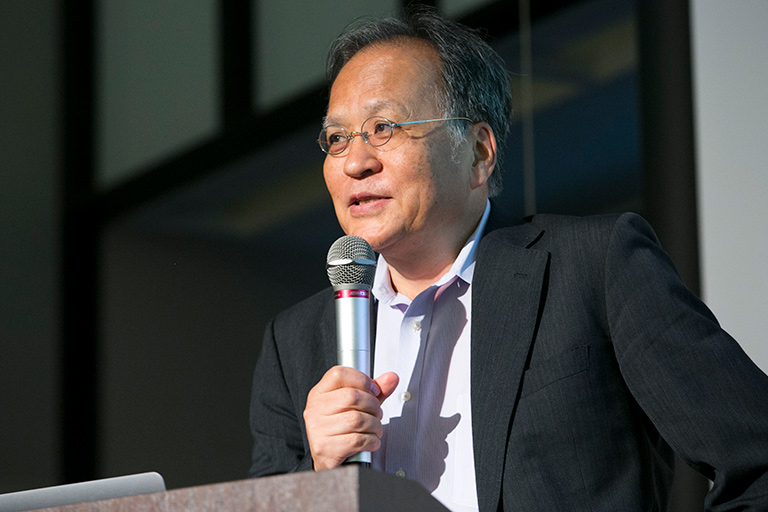
株式会社三菱ケミカルホールディングス(MCHC)は、ケミストリー(化学)を基盤に、機能商品・素材・ヘルスケアの3分野で、人・社会・地球の持続的発展に貢献する製品・サービスをグローバルに提供している企業集団です。今年4月に同グループのCDOに就任した岩野氏に、製造業におけるCDOの役割について講演いただきました。
製造業におけるデジタル革命とは
サプライチェーンをまたぐエコシステムの創造

岩野氏はまず、ITの社会における役割のI変化について触れました。1990年代には、第1段階として、ビジネスのクリティカルインフラとしてのITに焦点が当たっていました。この段階では銀行、製造業、流通業、物流など産業を支えるクリティカルインフラとしての役割です。2000年代に入ると、社会とITの役割に注目が集まりました。つまり社会のクリティカルインフラとしてのITに期待がおかれたのです。様々な社会システムや社会サービスがクラウドコンピューティングを代表とするITのインフラをベースに設計されてきました。スマートコミュニティーなどが一例です。この第2段階では、ITのコミュニティーは、そのアーキテクチャーや技術の可能性の提示など社会からの預託を受けており、それは社会的責任を伴うものです。そしてこれから起きようとしているのが第3段階で、そこでは「知と森羅万象とIT」がキーワードになってきます。
とくに第2段階としての現在のITの位置付けは、クラウドとサービスの台頭によってビジネスモデルに変化を生み出します。そして、データとアルゴリズムの価値がますます重要になり、サイバーと物理的世界、個人と集団・社会、機械と人間、対象と主体などについての境目がなくなります。そこでは、ITが社会のクリティカルインフラとして機能するかどうかという点において、社会からの預託と科学者・技術者の社会的責任が大切になります。
今後は、モノを作るだけではビジネス的価値は見出せません。モノはサービスにエンベデッドされて初めて価値を生み出し、機能を提供します。そして、機能やサービスは、エコシステムに位置づけられないと、大きく寄与できません。そう考えると、製造業のプロセスインダストリーにおいては、「サプライチェーンをまたぐエコシステムを作ることが、これからの大きなチャレンジになってくるのです」と岩野氏は語ります。
次に岩野氏は、デジタルに取り組むMCHCにおけるCDOのビジョンを、「デジタル技術と思想によって会社、業界、社会に新しい流れを作り、MCHCのビジネスや風土に変革をもたらすこと」と紹介します。MCHCは、新しい価値創造のプラットフォーマーを目指すのです。ただし、自社だけで目指すのではなく、サプライチェーンや新しいエコシステムを作ることにより、新サービスや新ビジネスを行い、様々な組織の連携でこれを実現していきます。そのために、MCHCはデジタル先進風土を持った企業体、集団を目指し、デジタルネイティブな組織になることが大きな課題になるとのこと。
データとリアルな現場をもつMCHCのデジタル戦略

ITにおいて、MCHCはユーザー企業ですが、「実は宝の山を持っている」と岩野氏は語ります。製造業として、IT企業にはないデータとリアルな現場を持っているからです。さらに、MCHCには変革への意思があり、さまざまな事業の専門家がいます。「これらの宝を、本質的なビジネスバリューにしていくことが、MCHCにおけるCDOのミッションです」
そのためには、デジタル変革への指針を示す水先案内人が必要になり、その水先案内人が社内にいることがビジネスのオペレーションに本質的な変化を生み出します。ところが、従来の化学業界にはそういった人材が少ないようです。そこで、MCHCでは岩野氏をIT業界から招き入れ、デジタルトランスフォーメーションチームを作りました。チームメンバーの半分以上は岩野氏のように外部から採用されています。現在、そのチームが全社に対してデジタルプロジェクトを進めています。社内に製造のプロフェッショナルがいて、さらにデジタルの水先案内人がいることによって、さまざまな仮説やビジネスモデルが出てくるとのことです。
岩野氏は最後に、2013年にリトアニアで開催された会議において採択された「科学技術イノベーションの実現には、人文・社会科学とのインテグレーションが必要である」と謳ったビルニウス宣言を取り上げ、「MCHCでもデジタルを推進するためにヒューマニティーや哲学、コンピューターサイエンス的思考 (Computational Thinking) を広げていこうとしている」と語り、講演を締めました。
事例紹介講演3
MUFGにおける
デジタルトランスフォーメーション
株式会社三菱東京UFJ銀行 デジタル企画部 プリンシパルアナリスト
柴田 誠 氏

従来、変革に対して後ろ向きだった銀行が、デジタルによる変革に真剣に取り組もうとしています。そのためには、組織のカルチャーまで変えていくことが必要と感じている柴田氏。デジタルの分野で20年近く活躍してきた同氏から、今MUFGの中でどういった変化が起きているのか、そして、金融業界がどういった状況に置かれているのかについて講演いただきました。
金融機関にも求められる
デジタルに対応する組織への転換

冒頭、柴田氏は「私自身はCDOではありません」。ただし、MUFGには、CDOに近い、CDTO(Chief Digital Transformation Officer)というポジションを設置しており、サポートをしていますと自己紹介しました。
柴田氏は最初に、現在ディスラプションが起きようとしている金融業界の変化を紹介します。この数年、日本ではフィンテック投資が大幅に増え、2014年と2016年を比較してみると、投資金額は倍以上になっています。これに伴い、ベンチャー企業が新しい金融サービスを始めたり、アップルやグーグルといったIT企業が決済サービスを始めるなど、金融以外のプレイヤーが続々と金融業界に参入してきました。こういった変化に対応して、既存の金融機関も新しい体制を作るため、さまざまな準備を進めています。
MUFGでも、インターネットバンキングが始まった2000年頃にIT事業部ができ、インターネットを使ったサービスに力を入れ始めています。そして、2015年にはデジタルイノベーション推進部を作り、積極的にイノベーションを取り入れていくことにしました。さらに、2016年にはデジタルイノベーション推進部の中に、イノベーションラボと海外イノベーションオフィスを作りました。「これらの組織はCIOが管轄していたのですが、今年5月にデジタル企画部として統合され、CDTOがみることになりました」と、柴田氏は経緯を語ります。「これから6~7年かけて営業純益を3000億円押し上げていく中で、2000億円はデジタルの取り組みで実現しようとしています」
また、MUFGでは国内外のアライアンスを通じたオープンイノベーションへの取り組みも打ち出しています。AIに特化した外貨預金サポートツールや、企業の決算報告レポートの個人投資家への配信、ブロックチェーンによる企業コインの運用など、これまでになかったさまざまな計画があるといいます。加えて、「サンフランシスコやニューヨーク、シンガポールなど、海外にもイノベーション活動を広げています」と、柴田氏は現状を語ります。
相談に応じるAIや
店頭で接客するロボットに期待

柴田氏は、ビックデータやAI、デジタルマーケティング、ロボティクス、ブロックチェーン、APIなど、新しい技術を取り入れたイノベーションへの挑戦についても紹介しました。たとえば、Webやスマートフォン、LINEなどのインターフェースの裏ではAIが簡単な質問に答えているのですが、今後、MUFGのお客様からの相談にもAIが応じられるようにしていくとのこと。また、インバウンドのお客様向けに人型ロボットを店頭に置いて外国語で接客したり、事務センターやコールセンターなど人手に頼って処理をしていたプロセスも、ロボティクスによる効率化を進めていきます。その他、ブロックチェーンによるMUFG Coinの検討や小切手電子化の実証を進め、外部のベンチャー企業が新しいアプリを作れるよう、法人向けに次いで個人向けにもAPIの公開を準備しています。
「銀行のような保守的な組織も、今やイノベーションを進めていくことが重要だという認識でさまざま取り組みを行っています」と柴田氏。フィンテックが広まり、銀行や金融グループ全体が外からの挑戦を受けている中、メガバンクといえども、新しい挑戦を行っていく必要があるのです。柴田氏は最後に、「MUFGにとってデジタルは大きなテーマであり、これが経営にとっても中心テーマになってきています」と、講演を締めくくりました。
CDO リサーチ レポート
CDOサーベイ
本質的なデジタル化の実現に向けて

日本ではまだまだ注目度が低いCDOですが、海外ではCDOを導入する企業が年々増加しています。では、実際に海外ではCDOの重要性をどのようにみているのでしょうか。また、日本企業がCDOを導入するには、どのような取り組みが必要になってくるのでしょうか。これらのテーマについて唐木氏は、PwCStrategy&が行った国内外でのCDOに関する調査結果を基に見解を述べました。
「テクノロジー系が重要」と考える
グローバルでのCDOに関する認識

PwCStrategy&はCDOを、「会社が目指しているデジタルの姿を具現化する責任をもつ役員」と定義付ける一方で、「デジタルの具現化が完了した後には、必要がなくなる存在である」と捉えています。そして、重要なのは、「デジタルの導入は、コスト削減のためではない」ということです。唐木氏は「デジタルの導入は、自社の今後を再定義する活動と考えています」と語ります。
同社は、全世界の時価総額トップ2,500社(2016年7月1日現在)に対して、CDOの調査分析を行いました。その結果、「2,500社で就任中のCDOの数は475人。就任年では、2012年から加速度的に増えており、大多数のCDOが2015年、2016年に就任していることがわかりました」と唐木氏は報告しました。
そのCDOのバックグランドとしては、やはり「マーケティング、営業」出身者が多いようです。その次は「テクノロジー」で、「コンサルティング、戦略、事業開発」「その他」と続きます。「ここで着目すべきことは、テクノロジーをバックグランドに持つCDOが、2015年から2016年の1年で大幅に増えていることです」と述べた唐木氏は、その理由を「海外では、やはりデジタル化にはテクノロジーが重要であるということに気が付き始めたようです」と分析します。
日本でのCDOに関する認識は 「周りに足並みを揃える」

一方、国内企業はCDOに対して、どのような認識を持っているのでしょうか。PwCStrategy&では、従業員500人以上の日本企業で、部長職以上の2,423人を対象にCDOに関する調査分析を行いました。その結果、日本企業では「デジタル化を推進しているか」という質問に対して、88%が「推進している」と答えています。では、「どういう姿勢でデジタル化を推進しているのか」との質問に対しては、「同業他社に先駆けて」が25%、「同業他社並み」が63%、「同業他社が導入し始めてから」が12%でした。この結果について唐木氏は、「他社と足並みを揃えるというのは、日本企業に多数見られる傾向と思われます。」との見解を述べ、「デジタル化は他社に先んじて新しい時代に乗っていくものであることを考えると、この25%という数字は心もとないと感じています」と、日本企業には不安も感じるとのこと。
次に、日本企業でデジタル化がどれだけ重要と理解されているのかを知る、「デジタル化推進の理解の度合い」の調査結果から、「CEOやCXOが旗を振って推進を進めると、社内でのデジタル化の推進の重要性がかなり理解され、逆に、デジタル化の推進を現場任せにしておくと、その重要性はあまり理解されないようです」と唐木氏は分析します。
最後に唐木氏は、企業におけるデジタル化の準備度合いを知る、6項目のチェックリストを紹介しました。その中で、情報システム部が中心となってシステム構築を進めている場合には、「これまでのシステム構築とは違った取り組み方になっているか」という問いかけが重要になると説明しました。「このチェックシートを、是非デジタルの促進に役立ててください」と参加者に伝え、唐木氏は講演を終えました。
パネルディスカッション
これから日本企業で起きようとしている
デジタルによる改革

パネルディスカッションは、日本ロレアル株式会社の長瀬次英氏、株式会社三菱ケミカルホールディングスの岩野和生氏、株式会社三菱東京UFJ銀行の柴田誠氏、ドーモ株式会社の大山忍氏、一橋大学の神岡太郎氏をパネリストに迎え、CDO Club Japanの加茂純氏がモデレーターとなり、進行していきました。
先駆的にCDOを導入したのは変化に対応するため
まず、モデレーターの加茂氏は、「欧米ではすでに多くのCDOがいて、デジタル改革がかなり進んでいるのに対し、日本ではなぜそこまではデジタル改革が進んでいないのか」と、日本企業が持つ課題を最初のテーマとして提示しました。加茂氏は日本ロレアルの長瀬氏に、いち早くCDOを導入するなど、日本における先行事例を示した日本ロレアルで、なぜそれが可能になったのかを聞きます。
長瀬「このままではいけないという会社の危機意識が一番大きいと思います。我々はプロダクトアウトでビジネスを行ってきました。しかし、例えばの一例ですが、今は何か製品に不具合があったら、すぐにSNSで世界中に情報が広がってしまい、一度悪評がたってしまうと、なかなか回復できません。そこでロレアルでは、お客様セントリックスに方針を変更しました。デジタル世界におけるソーシャルリスニング、これ一つとっても全社員にとってしっくりきたものなのです」
次いで加茂氏は三菱ケミカルホールディングスの岩野氏に、改革が遅れていると言われる製造業の中で、同社がCDOを導入した理由を質問します。
岩野「この4、5年の間に製造業でもビジネス変革が急激に起きています。我々のようなBtoB企業の経営者は、特にデジタルに対して危機意識があります。そのために、新しいデジタルの組織を作りました。レガシーと思われている企業が新しい形に進化していくことは、日本の社会に対するメッセージになると思います」

加茂氏は三菱東京UFJ銀行の柴田氏に、イノベーションが起きにくいイメージがある日本の銀行で、いち早くデジタル担当役員が置かれた理由を問います。
柴田「もともと金融機関は、オンライン化など積極的にデジタルに取り組んできました。しかし、今起きているのは、お客様の側で起きている変化です。スマートフォンの処理能力や通信速度が向上し、いつでもどこでも世界中でネットワークにアクセスできるようになりました。また、最近は独自のインフラを持たない新興企業でも、クラウドを使って簡単に金融サービスに参入できます。こういった変化を、経営レベルでは切実なものとして捉えています。そのため、デジタルに本格的に対応する必要があるのです」
加茂氏は、日本企業でデジタルの導入が進んでいない状況には、さまざまな問題点が考えられるが、それについてどう見ているかをドーモの大山氏に問いました。
大山「日本の場合、企業間で人材の流動性がなく、社内では異動によってせっかく理解したデジタルの知識が生かせなくなるなど、社の内外双方で人材確保に課題があります」
そして大山氏は解決のヒントも示しました。
大山「デジタルの業界を見ると、若い人材が豊富です。社外からそういった人材を入れる場合には、若くてもきちんと権限を持たせることが重要です。また、すでに社内で権限を持っている人が新しい知識を取り込んでいくことも、日本企業におけるデジタル人材確保のアプローチとして重要であると考えています」
加茂氏は一橋大学教授の神岡氏に、海外のCDOサミットに参加してきた経験から見た、日本企業と海外企業のCDO導入への取り組み方の違いを質問します。
神岡「日本でCDOの導入が進まないのは明らかにトップの問題です。もちろん、CEOも危機感を持っています。それなのにアクションに移らないことが大きな問題なのです。今は、昔とは違って不確実性が高い段階で意思決定を行わなければなりません。そういった経営スタイルに日本企業は慣れていないのです。リスクを減らしてからアクションを起こしてももう遅いのです。海外の企業は意思決定してアクションを起こすのが早いのです」
部門を超えて企業を先導することがCDOの役割
次のテーマとして加茂氏は、CDOを導入しても、日本企業にありがちな部門間の兼ね合いによるやりにくさという課題を解決するにはどうすればいいか、パネリストに問いかけます。まず、長瀬氏が答えました。
長瀬「そこは会社の度量の大きさないし本来もっていた個性がポイントになります。ロレアルはもともと開発に力を入れてきた企業であったためにテスト&ラーンを行うことに慣れていて、なにかをやらないとなにも生まれないという考え方を持つ企業風土がありました。その風土がデジタルビジネスの一要素でもあるテスト&ラーン”に馴染みやすくデジタル化を促進させやすい要因だとも思います」
加茂氏は岩野氏に、外部からCDOに採用され、既存の部署に対してさまざま提案することは、巨大な企業の中では大変なことではないかと問います。
岩野「三菱ケミカルホールディングスは技術者が多い会社です。技術者は自分の専門外の専門家を尊敬するのです。私はケミカルについては専門外ですが、工場に行くと、耳を貸して一緒に議論しようという雰囲気が感じられました」
次に加茂氏は柴田氏に対し、コンプライアンスに対して非常に忠実である銀行という組織の中で、イノベーションを起こすための課題を問います。
柴田「新しいことにチャレンジしようとすると、リスクをどう解消していくかが大きな課題になります。必要なのは、挑戦と守りのバランスをとることです。デジタル企画部はプロパーの人材だけではチャレンジが難しいので、3~4割は中途採用の人材です」
加茂氏は、今後、CDOと同じようにCEOもデータをチェックする必要が出てくることにつき、その課題を大山氏に問います。
大山「トップだけではなく、現場の方もデータに基づいたアクションを起こしていくことが重要で、それができるようになることが課題です。トップダウンで意思決定するのではなく、現場にもデータや情報という武器を与えて、その場で意思決定ができるような組織にする必要があると思います」
加茂氏はテーマのまとめとして神岡氏に、これからさまざまな企業がCDOを導入するにあたり、ロレアルのようにCDOをじょうずに使いこなすにはどうすればよいかを聞きます。
神岡「組織を引っ張っていくには、“思想”が必要になってきます。変革を起こす際にも命令を出すだけではだめで、CEOが思想家の側面を持って皆を先導していかなければなりません。CDOに与える役割の一つは、CEOの右腕として、その思想のエバンジェリスト(伝道者)になってもらうことです」
デジタルがあらゆる業界で全社員の共通言語となっていく

最後に加茂氏はパネリストに、「CDOに興味をもって集まってくださった皆さんに、一言ずつお願いします」と来場者へのアドバイスを求めました。
長瀬「本来デジタルは特別なものではないと考えています。今はCDOというポジションが必要ですが、いずれはなくなってもいいと思います。デジタルが当たり前のものになり、全社員にCDOになってもらうためのプログラムを組んでいく事が大切だと思います」
岩野「この先5年くらいが、ITに関わっている人にとって千載一遇のチャンスだと思っています。この波に参加して、新しい流れを作れるという意識を持つと面白いでしょう。私はCDOはいずれなくなるものではなく、新しい職種に変化していくと思っています」
柴田「金融世界でのイノベーションは、一部の人が起こすだけで終わってはいけないと感じています。それは、金融だけではなく、あらゆる業界に当てはまります。そして、いかに組織全体の取り組みにしていくかがそれぞれの現場で問われていくと思っています」
大山「これまでは組織の中で共通言語がないため、事業部間で話がかみ合わずに対立してしまうことがよく見られました。今後データが全社に行きわたるようになると、それを共通言語にすることができます。これが、組織の壁を無くし、企業が一つのゴールに向かっていけるチャンスになると思っています」
神岡「CDO Club CEOのMathison氏は、『今後カスタマーがカンパニーになる』とおっしゃっていました。働くことはどういう意味をもつのかなどを含めて、今はあらゆるものを再定義しなければならない時代です。その変革の中で、デジタルの意味を探すことが重要になってくると思います」
まだ日本では少ないCDOの中からご登壇いただいたパネリストの方々は、それぞれに明確な目的を持ちながらも、これから道を切り開いていこうとさまざまな取り組みを行っています。また、企業におけるデータ活用の重要性についても触れられたことで、Chief Digital Officer、Chief Data Officerの両面からCDO導入の必要性が伝わるパネルディスカッションとなりました。
