CTO forum 2024〈夏〉
事業創造の本質と研究開発
~価値の起点となる R&D の在り方の再考~
開催日:2024年7月31日(水)
主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局
協賛:アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社、株式会社ユーザベース
「技術で勝って事業で負ける」組織からの脱却!
生成AI、IoTの発達、業界を代表する大企業の異業種間連携によるイノベーティブな製品の登場など、製品の市場投下までのスピードが急加速しています。さらに近年はデジタルやカーボンニュートラルといった新たな技術トレンドが登場し、社会的ニーズについても要請が高まるなど、市場環境は急激に変化しています。こうした中、各社は新たな投資・成長の機会をいかに確保するか、存続のために新機軸となる事業をいかに生み出すのか戦略の転換を迫られており、中核を担う研究開発への期待も高まっています。
しかし、研究開発は、投資したものが実る保証のない不確実な領域であり、十分機能していないのではと問題意識を抱く企業は少なくありません。企業においてどんなに新しい技術を生みだしても、収益につながらなければ意味をなしません。これからの研究開発部門は、優れた技術を生みだすだけでなく、技術や製品をいかに自社の事業に結びつけるかという視点を持つことが求められています。
また、研究開発部門が価値を創出し経営に貢献するためには、潜在する市場と必要となる技術を見極め、技術への投資、社内外との連携など、新しい時代を切り拓く仕組みを構築するCTO(最高技術責任者)の強いリーダーシップが鍵となります。今、改めて価値の起点である技術の視点を経営に取り入れ、自社の技術がどのように競争力を高め、ビジネスに貢献するのか、研究開発の在り方と戦略を再定義することが必要なのではないでしょうか。
ビジネス・フォーラム事務局が企画する「CTO forum」第二弾では、CTOの役割とリーダーシップに焦点を当てつつ、今取り組むべき、重要アジェンダを考察いたしました。特別鼎談では「ビジネスに貢献するR&Dの在り方」、後半のダイアログセッションでは「テクノロジーとビジネスを繋ぐCTOの役割」について、最前線で活躍されるリーダーたちをお招きし、新しい時代を切り拓くための課題の突破力を議論いたしました。
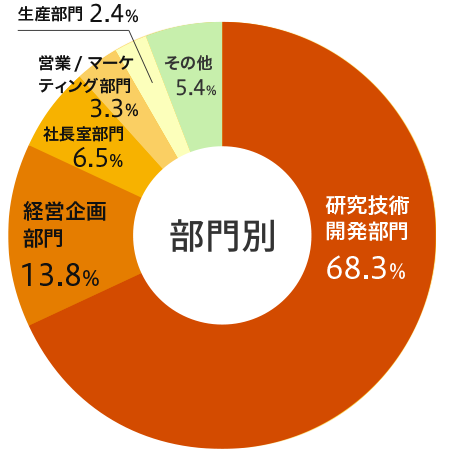
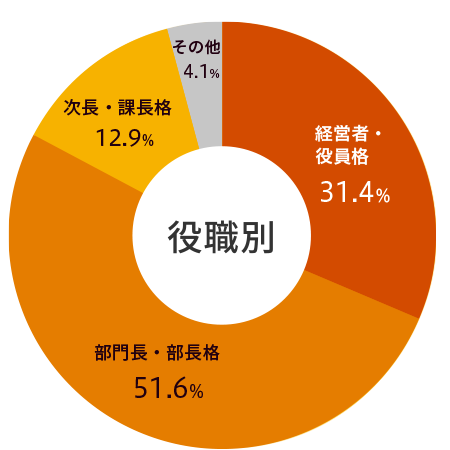
<特別講演1>変革期におけるビジネスモデルイノベーション
味の素のビジネスイノベーション
~事業モデル変革から社会変革への挑戦~
味の素株式会社 取締役 代表執行役副社長、Chief Innovation Officer、研究開発統括
白神 浩 氏
- 中期ASV経営と事業モデル変革(BMX)
- 成長4領域におけるBMXの取り組み
- イノベーションを起こす無形資産の強化
コモディティ化していたアミノサイエンス事業の事業モデル変革を他の事業でも横展開しイノベーションを推進されてきた味の素 白神様。デジタル化によって R&D プロセスも変化する中、研究と事業開発を統括した R&B 組織への変更を指揮されるなど、研究開発組織の在り方についても、様々なお取り組みを推進されています。これまで、全社変革に尽力されてきたご経験をもとに、今後のイノベーション創出の展望などをお伺いしました。

技術と顧客をつなぎイノベーションを生み出す人財資産がASV経営の柱
味の素様は、創業以来パーパス経営(ASV経営)を実践してこられました。独自の強みであるアミノサイエンス®を磨き続けることで事業を拡大。2022年より新経営体制となり、中期ASV経営へのマネジメント変革により、企業変革、ビジネスイノベーションに挑戦されていることを説明いただきました。
バイオ&ファインケミカル事業では、参入障壁の低下するコモディティ事業から、 高付加価値なSpecialty事業へシフトする事業モデル変革(BMX)を実現。中期ASV経営では、事業ポートフォリオを既存の事業群から成長4領域に統合していく全社のBMXを梃に、マットリックスな推進体制を組まれ飛躍的な成長を目指されています。
また、企業変革、イノベーションを実現する鍵は無形資産にあり、特に技術と顧客を繋ぎイノベーションを生み出す人財資産が最も重要と強調、無形資産を豊かにする取り組みをご紹介いただきました。

お客様の声
- 現場感覚のあるキーワードを示唆いただき参考になった
- 無形資産の中で人財を最重視して、4つウェルビーイングの観点から取り組まれている点が参考になった
- 技術・会社のコアとなる『アミノサイエンス』を深め、広げることがR&Dや社員の一体感につながっているように感じた
- コア事業であるアミノサイエンスを活かした事業変革の実現に向けた取り組みが興味深かった
- 技術ロードマップをもとに共創エコシステムへの参画を通じて価値創出されている点が参考になった
- BMXの概念、無形資産の強化に関する考え方が非常に参考になった
- B2B、B2Cを両立される企業のR&Dの考え方がとても勉強になりました
<特別講演2>自社技術の深化と新技術の探索
ありたい姿を目指し続けるAGCの両利きの経営と両利きの開発
AGC株式会社 代表取締役 兼 専務執行役員 CTO/技術本部長
倉田 英之 氏
- AGCの「両利きの経営」:その背景とこれまでの取り組み
- ありたい姿を目指す開発戦略
- 更なる成長へ:コーポレート・トランスフォーメーション 第二章
両利きの経営および両利きの開発をけん引され、コア事業を強化しながら新規事業を創出すべく研究開発におけるDX等を指揮されているAGC 倉田様。社内外との連携においてもAGC横浜テクニカルセンターを設立されるなど他社に先駆けた取り組みを推進されています。技術トップとしての役割はどういったものかといった観点も踏まえつつ、今後の技術戦略の展望や“世界に認められる技術を創出し続ける”ことへのお考えをお伺いしました。

両利きの開発の神髄はチャレンジできる組織カルチャーと戦略をやり抜く力
AGC様は、ディスプレイ事業のコモディティ化をきっかけにポートフォリオを転換、両利きの経営を実践してこられました。2030年をターゲットにした中長期の目標を掲げ、事業ポートフォリオ改革にコミット、既存事業と探索事業を同時に追求しイノベーション創出に挑戦されています。
両利きの開発では、右利きと左利きの開発を組み合わせ繰り返すことで、生産・基盤技術革新や次世代・新商品開発だけなく、新事業創出についても新たな価値を創造されてきました。両利きの開発の推進体制として、CTO直下の事業開拓部を設置するなど、両利きの開発における壁を乗り越える施策をご紹介いただきました。
また、価値創造DXを推進され、競争力の強化だけでなくビジネスモデルの変革にも挑戦すべく、MIやマーケティング、人財育成に力を入れているとのこと。最後に、競争力の源泉である人財を中心とした組織カルチャーの重要性を強調されました。

お客様の声
- 技術の整理のやり方、自社技術の活かし方等参考になった
- 「左利き」の部分に苦心しているため参考になった
- 開発も両利きという形ができている点が大変参考になった
- 特に組織的なアプローチなどをオープンに説明いただけて参考になった
- 両利きの開発について詳細に話を聞くことができ、勉強になった
- 人財の活用に対する工夫、チャレンジする組織醸成の具体的な施策が興味深かった
- 両利きの経営におけるCTOの役割、考え方(開発戦略、知財戦略、DX推進等)が参考になった
<特別鼎談>経営視点から考察する研究開発の在り方
ビジネスに貢献するR&Dの在り方
味の素株式会社 取締役 代表執行役副社長、Chief Innovation Officer、研究開発統括 白神 浩 氏
AGC株式会社 代表取締役 兼 専務執行役員 CTO/技術本部長 倉田 英之 氏
株式会社ユーザベース スピーダ事業 知財・研究開発支援責任者 上級執行役員(SVP) 伊藤 竜一 氏
特別鼎談では、モデレーターに、R&D分析を通じてCTO・R&D組織の中核課題を支援しているユーザベース 伊藤様をお迎えし、味の素 白神氏、AGC 倉田氏とともに、経営視点から「経営とR&D」「イノベーションマネジメント」「人財育成」など深堀してまいりました。

未来の成長領域をつくる、既存事業と新規事業のマネジメント
白神様より、「ポートフォリオとリソースの判断は事業のライフサイクルをみることが重要」であり「R&D投資によって、どれだけ事業利益に貢献しているのかみる」など、指標をおいてマネジメントされていることをご説明いただきました。倉田様からは、「競合の営業利益に対する研究開発費などをベンチマークし議論」されているとしました。白神様からは「アミノ酸のコストダウンの研究に集中していた時期があったが、自分たちの技術をいかに進化させイノベーションにつなげていくか」が重要と付け加え、その見極めが必要であることを語りました。
自社の在りたい姿と実際に顧客が求めているものとのすりあわせ
オープンイノベーション施設「AO」を活用しつつ「技術ロードマップを若手中心に作成しながら議論している」と倉田様は話します。また、B2BとB2C両方の事業を持つ味の素様では、それぞれのよさを融合してシナジーを生む取り組みをされていることを紹介いただきました。
共創とイノベーションについては、白神様は「ASV経営の中でより大きな価値を創出するために、社内技術を社会価値につなげるパートナーとエコシステムをつくっていくことが重要」であり「社会実装される勝ち筋はどこにあるのか、そこにアミノサイエンスが貢献できるのか」考えているとしました。倉田様は「オープンイノベーションが目的になるのではなく、技術ロードマップを見ながら必要なピースをそろえ、問題解決に役立てていく」ことの重要性を強調されました。
R&Dの人財育成
倉田様からは、「新事業の観点では、若手にプロジェクトリーダーを任せるなど育成する機会をつくっている」、「キーパーソンとなる人財がどこにいるか、どこに移動させるかなど把握」し「技術人財はそれぞれの特性に応じて評価軸を設けている」旨をご紹介いただきました。白神様からは、「必ず成功させる新事業テーマについては経営がコミット」しており、アイデアだしから取り組むテーマなどについては、人財育成の意味合いを持って挑戦させるなど、若手に活躍してもらう仕組みを整備していることをご説明いただきました。
お客様の声
- 人財の育成に対する両社トップマネジメントのコミットメントの強さに感銘を受けた
- 人財育成・エンゲージメントの重要性に改めて目を向けるきっかけになった
- フリートーク形式で2つの会社の活動の本音が見えた気がした
- 事業創造にはエンゲージメント向上など人財の活性化が重要だと改めて感じた
- “経営とR&D”をテーマに、CTOの視点、CTOの立ち位置はどうあるべきかの気づきを与えてくれた
<基調講演>R&Dを起点とした企業変革
R&Dビジョンを梃子とした全社トランスフォーメーション
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 プリンシパル
金澤 吉典 氏
- 企業変革の推進に向けたR&Dビジョンの重要性
- R&Dビジョンを梃子とした全社戦略推進事例とその要諦
- ビジョンのグローバル発信と社内エンゲージメント、オープンイノベーション
既存の延長線上に将来の成長を見いだすことが困難な昨今において、多くの企業が「変革」や「新たな成長事業」に取り組んでいる一方、既存の呪縛から抜け出すことにも苦労している様子が見られます。モノづくりを生業とし成長してきた日本企業にとって、その根幹となる「技術」を担う責任者・部門が、技術起点での将来ビジョンを示すことは、変革・成長に向けた社内エンゲージメントや社外とのオープンイノベーションの促進に繋がるのではないでしょうか。本セッションにおいては、CTOやR&D部門が担うべき企業変革における役割とその要諦をご紹介いただきました。

企業変革成功のドライバーとなるR&Dビジョンとは
金澤様より、自社や産業区分を超えた存在価値の革新・再定義が問われる中、多くの企業が変革に着手しているものの、半数以上が成果を感じられていないという結果を説明。その理由として明確なビジョンの発信や実際の活動を落とし込む指針がないといったことを解説しました。加えてR&D部門には、全社ビジョンとのアラインメントおよび将来との接続が見えるビジョンや技術の発信が期待されていることを述べました。
また、R&Dビジョンを梃子とした全社戦略推進事例をご紹介いただきながら、R&Dビジョン作成の要諦やR&Dビジョン活用の重要性を説きました。
最後に、R&Dビジョンは社外に発信され、その企業が保有するケイパビリティとして理解醸成が図られるべきであり、グローバルの展示会等を通じて、広く発信されることで、企業としてのコミットメントを示すとともに、共創促進を促すものであるとしました。
お客様の声
- R&Dビジョンと企業ビジョン(事業戦略)の連携の重要性が理解できた
- コンサル視点でのR&Dの整理、まとめをしていただき新たな発見があった
- 事業ビジョンと連動したR&Dビジョンの策定と発信の重要性を実感できました
- R&Dビジョンの外部発信による社内エンゲージメント向上という発想が大きな気づきでした
- 社会変化を考えて自社テクノロジーのロードマップをつくるという考え方が興味深かった
<ダイアログセッション>最高技術責任者3名と議論!CTOの役割の再考
テクノロジーとビジネスを繋ぐリーダーの役割
株式会社荏原製作所 執行役CTO(技術/研究開発/知的財産担当) 三好 敬久 氏
日揮ホールディングス株式会社 執行役員 Chief Technology Officer(CTO) 水口 能宏 氏
古河電気工業株式会社 執行役員 研究開発本部長 藤崎 晃 氏
株式会社ユーザベース スピーダ事業 知財・研究開発支援責任者 上級執行役員(SVP) 伊藤 竜一 氏
CTOオフィスや研究開発戦略策定委員会を立ち上げるなど、部門間を越えた戦略的なイノベーション創出を推進され、既存事業においても、知的財産部門や事業部門と連携した競争力を高める取り組みをされている荏原製作所 三好様。資源循環社会の実現に向け、積極的な異業種連携や新たなエコシステムの創出など指揮をとられ、サファイアスカイエナジー社の設立や廃プラガス化といた新技術の事業化など推進されている日揮ホールディングス 水口様。IPランドスケープを両利きの手法として推進され、研究所を再編し横のつながりを強化、研究者への教育にも力を入れるなど研究組織の変革に関しても様々なお取り組みがある古河電気工業 藤崎様。3名のCTOをお迎えし、CTOの役割とリーダーシップに焦点を当て、ものづくりの新たなステージに向けた課題の突破力を議論いたしました。

中長期視点で考える新規事業の見出し方
まず、藤崎様より営業統括本部が新事業創出や事業のスケールアップを担っていることをご紹介いただきました。三好様からも「コーポレートにマーケティング統括部」があることを付け加えられ、ベンチャーへの投資等、外からの技術を取り入れながら、新事業開発を目指されていることを発言。水口様からは重要な3つの視点として「コアの技術が生きること」「点ではなく面で攻めること」「スピード」を挙げられました。R&Dの難易度が上がっている中で、どのようなプロセスをとっているのかモデレーターの伊藤氏が問うと、三好様は「デジタルツインの取り組みを進めており、過去の記録から研究に活かしたり、過去の論文をみれるようにするなど、スピード感のある研究開発に取り組んでいる」と話しました。藤崎様からは、「技術をベースに組み立てていき、どう情報を整理していくのか」強化が必要であることに言及されました。ゲート管理の観点では、水口様から「撤退の見極めが大事」であること、藤崎様から「技術はしまっておく」という視点が必要であることなどお考えをご紹介いただきました。
デジタルやAIの活かし方について
三好様からは、3年前からデジタルストラテジックチームを結成し、事業部門と兼務させ価値創出に挑戦されていることをご紹介いただきました。藤崎様からは、「戦略本部デジタルトランスフォーメーション&イノベーションセンター」にてデジタル技術を強化され、合わせて海外拠点の活用についても触れていただきました。水口様は、技術開発する上でデジタルは切り離せないものになっていることを指摘、アカデミア連携を中心に探索を推し進めているとしました。ディスカッションの後半では、生成AIを今後どう活かしていくかについても意見交換が行われました。
事業に貢献できるR&D人財とは
ディスカッションの最後に、事業に貢献できるR&D人財に求めることやお取組みについて意見交換がされました。三好様からは、他社と共創できる「ハブになる人」を育成し、のばしていきたいとお考えを述べられました。藤崎様からは、「プロフェッショナル認定」制度についてご紹介いただきました。水口様は、「技術者は最強のセールスマンであれ。」というメッセージとともに、技術を社外に発信できる能力を育成していきたいと述べられました。最後に来場されている方々に向けて、皆様から力強いメッセージをいただき会を締めくくりました。
お客様の声
- R&Dの組織をどうすべきか考えるヒントとなった
- 各CTOの熱い心を拝聴できたことがよかった
- 研究開発部門の役割を改めて考え直してみることが必要だと感じた
- 組織やプロフェッショナル人財、営業(マーケティング統括部)等どうあるべきか参考になった
- 人財育成や開発のプロセスまで幅広いテーマで各社の取り組みを知ることが出来て大変参考になりました
- 登壇された3社について、CTOを中心とする社内体制・組織を具体的に示しながらディスカッションいただけ興味深かった

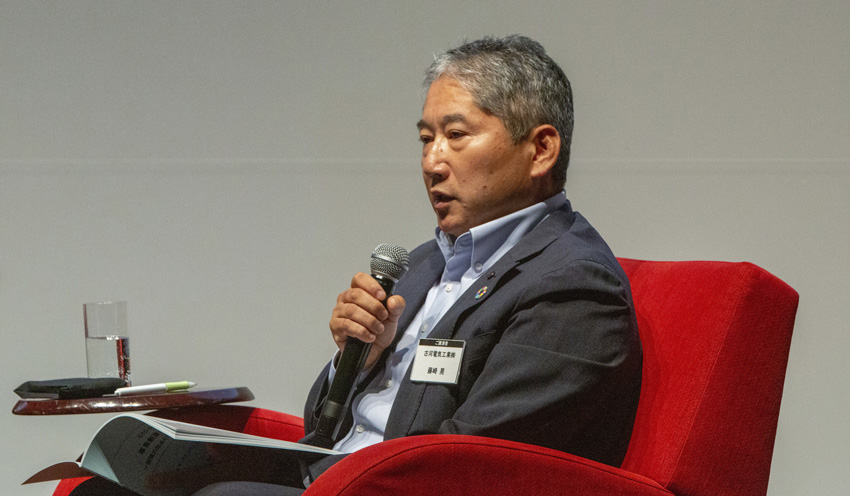
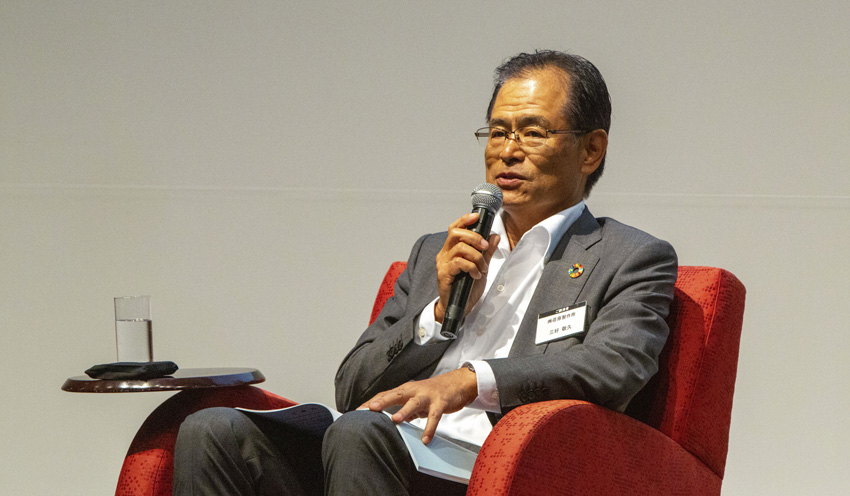




企画者からの御礼
株式会社ビジネス・フォーラム事務局
プロデューサー 江倉 裕美
この度は「CTO forum 2024〈夏〉」へ、多くの方々にご参加を賜り、誠にありがとうございました。
そしてこのたびの開催にあたり、多大なるお力添えをいただきましたご講演者の皆様、ご協賛社の皆様に、この場を借りて心からの御礼を申し上げます。
今後も引き続き、ビジネス・フォーラム事務局では、セミナー・フォーラム等の開催、そしてその感想やご意見を通じて、皆様の課題解決へのヒントや新たな気づきをお届けできるような機会を企画し、情報発信を続けて参ります。
最新のセミナー情報はこちらよりご確認ください。
