持続可能なサプライチェーン・マネジメント2025
サステナブルが求められる時代に企業が目指すべきSCM戦略について
開催日:2025年5月23日(金)
主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局
ゴールド協賛:エコバディス・ジャパン株式会社
シルバー協賛:株式会社Hacobu
近年、グローバルレベルで倫理感のあるサプライチェーン慣行への必要性が迫られています。気候変動や生産・物流の制約、地政学リスク、人権問題など、様々なサプライチェーンに対する課題が山積している中で、企業には、ステークホルダーを中心に、SCM戦略をESG経営の中核の一つとし、ビジネスチャンスの拡大、企業体質を強化し、企業価値を高めていくことが今後、さらに求められると予想されています。
しかしながら大半の企業では、持続可能なサプライチェーンを実行する上での壁があり、現場で起きていることと経営視点での乖離、現場レベルにおいてESG経営を理解できていない、サプライチェーン全体を見える化できていない、物流の人権問題など、大きな障害を数多く抱えています。このような問題を真摯に受け止めて丁寧に解決し、自社の目指すビジョンや戦略を社内・社外を問わず、広く示していく必要が企業にはあるのではないでしょうか。
昨年に続き二回目の開催となる今回の「持続可能なサプライチェーン・マネジメント2025」では、サステナブルが求められる時代に企業が目指すべきSCM戦略について、基調講演では、サプライチェーン管理で実現する持続可能な企業経営について、事例講演では、サプライチェーンの可視化とレジリエンス強化、持続可能な物流課題の解決について紹介いただきます。協賛講演では、ESG時代のサプライチェーン戦略、発注・発送情報のコントロールについて、パネルディスカッションでは、企業が目指すべき最前線の標準化・可視化について議論いただきます。
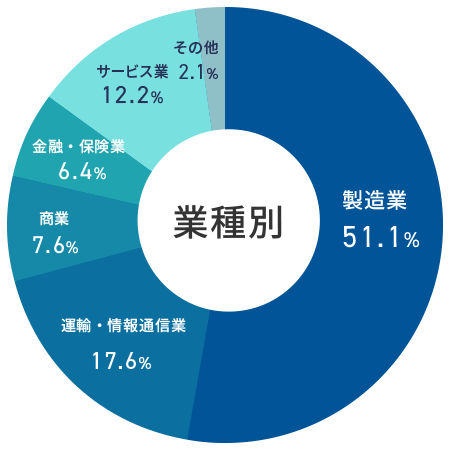
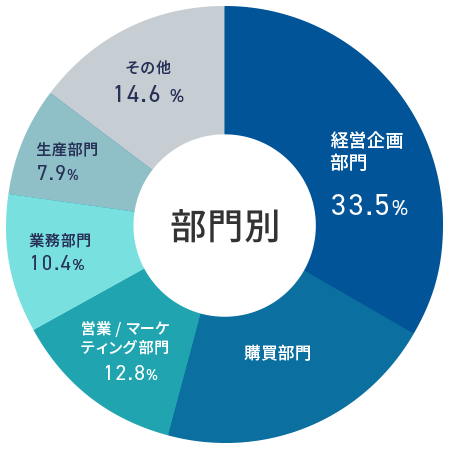
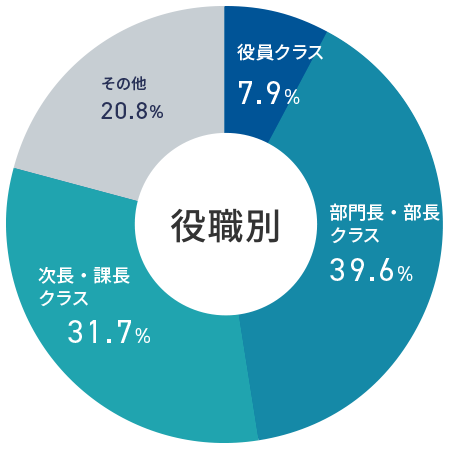
<ゴールド協賛講演>【多角視点でのサプライチェーン戦略】
ESG時代のサプライチェーン戦略~重要トレンド・規制対策・成功の秘訣示
エコバディス・ジャパン株式会社 代表取締役
若月 上 氏
「ESG時代のサプライチェーン戦略~重要トレンド・規制対策・成功の秘訣」
- 持続可能なサプライチェーン管理の最新動向や今後の規制、実践的な事例の紹介
- 企業が直面する課題とその解決策の探求
- 環境負荷の低減、人権・労働問題への対応、透明性の向上
近年、環境・社会・ガバナンス(ESG)への関心が高まる中、企業のサプライチェーンにもサステナビリティが求められています。講演では、持続可能なサプライチェーン管理の最新動向や今後の規制、実践的な事例のご紹介、企業が直面する課題とその解決策を探っていただきました。また、環境負荷の低減、人権・労働問題への対応、透明性の向上など、多角的な視点から持続可能なサプライチェーンの実現方法について考察いただきました。

参加者の声
- AIによる独自評価の仕組みは興味深かった。
- 世界的なサステナブル指標の方向性と実際の測定について必要性を理解。
- 継続的なデューデリジェンス、アセスメントの必要性が認識できた。
- サプライチェーンのグローバルのトレンドがよく理解できました。
- サプライチェーンの責任はバイヤーにある」この考えを前提に仕事する必要があると感じた。
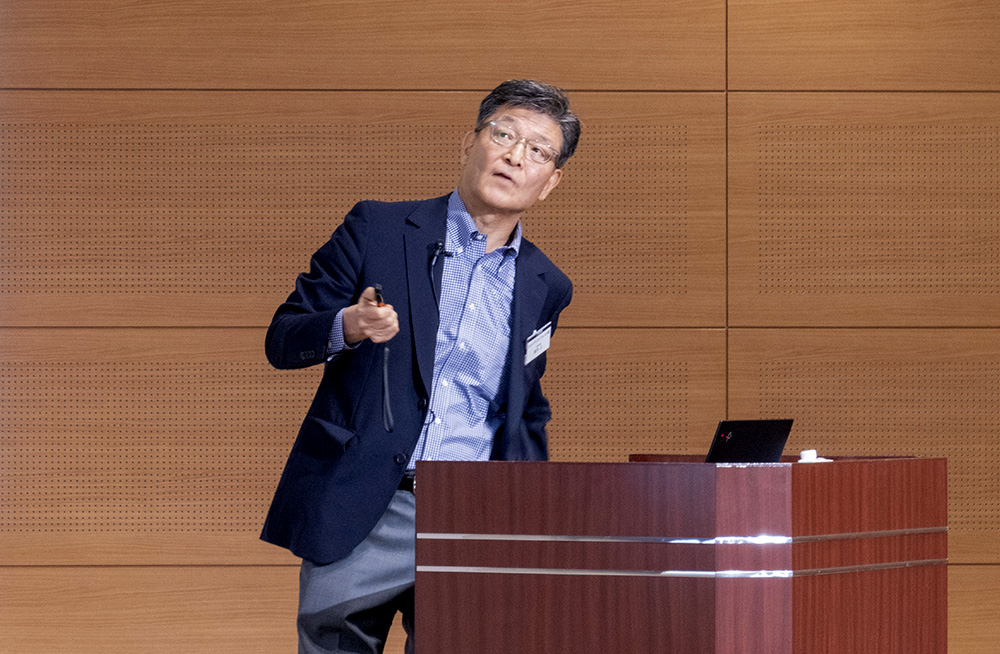
<事例講演1>【持続可能な物流体制の構築】
三菱食品における持続可能な物流の構築について
三菱食品株式会社 執行役員 ロジスティクス本部長
白石 豊 氏
- 中期経営計画 MS Vision 2030の策定
- 物流の標準化に向けた業界での活動
- 社内における物流の可視化、最適化の取組み
三菱食品株式会社は、グループのパーパス(存在意義)として、従来の「食のビジネスを通じて持続可能な社会の実現に貢献する」に、「サステナビリティ重点課題の同時解決」を加え、中期経営計画「MS Vision 2030」を策定しておられます。講演では、物流の標準化に向けた業界での活動や、社内における物流の可視化・最適化の取り組み、物流のオープン化、シェアリングに向けた方向性について、ご紹介をいただきました。
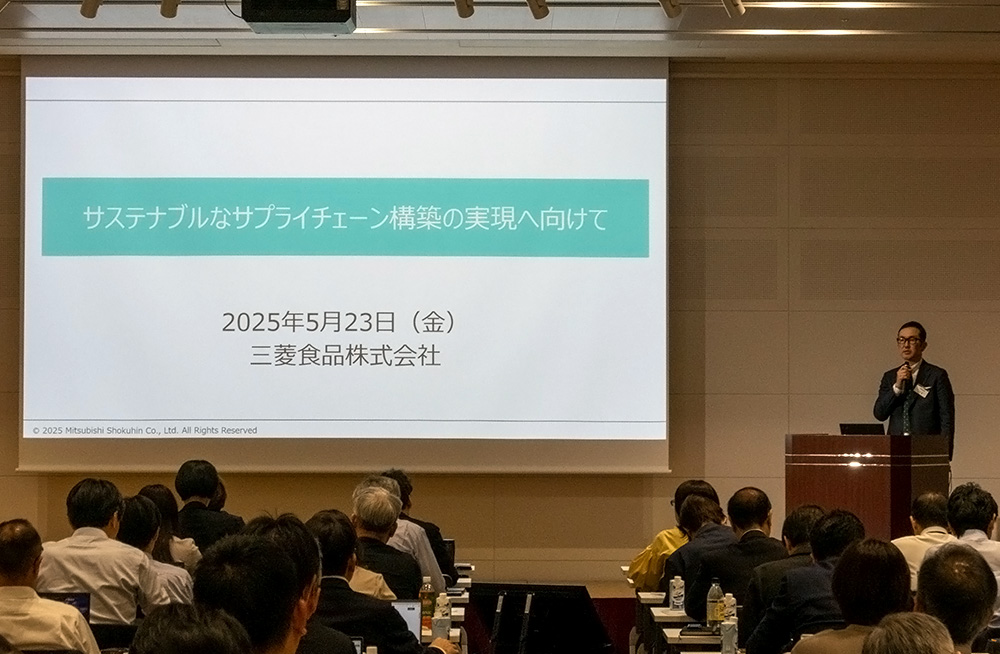
参加者の声
- movoのデータ活用を理解できた。物流=経営最大課題との認識がおもしろい。
- データが見える事で新しいアイデアが出て新しいビジネスが生まれる良い例であり大変参考になった。
- オープン化がどんどん進み業種を越えて三菱食品の波に乗るように頑張っていきたいなと思った。
- 事例内容が興味深かったです。物流業界全体の変革に繋がる可能性を感じ、大いにインスパイアされました。
- 三菱食品様の物流への取組がよくわかった。特にサステナブル投資という考え方は参考にしたい。

<シルバー協賛講演>【サプライチェーンの構造改革】
物流の持続可能性を高めるための、発注・発送情報のコントロール
株式会社Hacobu 執行役員CSO
佐藤 健次 氏
- 顧客サービス重視からのサプライチェーン構造の見直し
- 実物流と発注領域を含めた包括的な議論の重要性
- Hacobuによるサプライチェーン構造改革の推進
これまで、日本では顧客サービスにすべてのエンティティがフォーカスされ、サプライチェーンを構築してきました。しかし、ドライバー不足が社会課題となる中、その構造を見直す時が来ています。構造の見直しは、実行系と言われる実物流の領域だけでは難しく、発注の領域を含めた議論により、その第一歩を踏み出すことができます。講演では、Hacobu社が推進するサプライチェーンの構造改革についてご説明いただきました。

参加者の声
- Walmartとの比較がおもしろかったです。ドライバ、運送業者とのコストメリットを考えるのが難しいと感じた。
- 共同配送、AIの利用は興味深かった。
- 輸出の効率化の上流である発注の最適化に着目しているところが気づきとなった。
- 「企業最適」から「社会最適」という点、確かにその通りと思いました。
- パーパスが伝わり、物流業界を変革する素晴らしい取組みと思います。

株式会社Hacobu
執行役員CSO
佐藤 健次 氏
2008年アクセンチュアにおいて、サプライチェーングループのマネージングディレクター就任。数多くのサプライチェーン改革プロジェクトをリード。2012年よりウォルマートジャパン/⻄友にて、eCommerce SCM、補充事業、物流・輸送事業、BPR(全社構造 改革)の責任者を歴任。ウォルマートジャパン/⻄友の物流責任者として、各国のリーダーおよびパートナーと物流革新を推進。2019年株式会社Hacobuに参画。
<事例講演2>【サプライチェーンレジリエンス】
日立ハイテクにおける持続可能なサプライチェーン共通基盤の構築について
株式会社 日立ハイテク サプライチェーンプラットフォーム統括本部 戦略本部 本部長
田邉 正浩 氏
- サプライチェーンレジリエンスの強化
- さまざまな社会的要請への配慮
- サプライチェーン全体におけるサステナビリティの推進
株式会社 日立ハイテクは、中期経営戦略において、『専門商社として培ってきたグローバル調達機能と、モノづくりにおける調達機能を統合し、サプライチェーン全体でのリスク管理を強靭化することで、「サプライチェーンレジリエンス」を強化して』いくとされています。講演では、自然環境や国際ルールの遵守などさまざまな社会的要請に配慮し、サステナブルなサプライチェーンを実現するための取り組みについて、ご紹介いただきました。
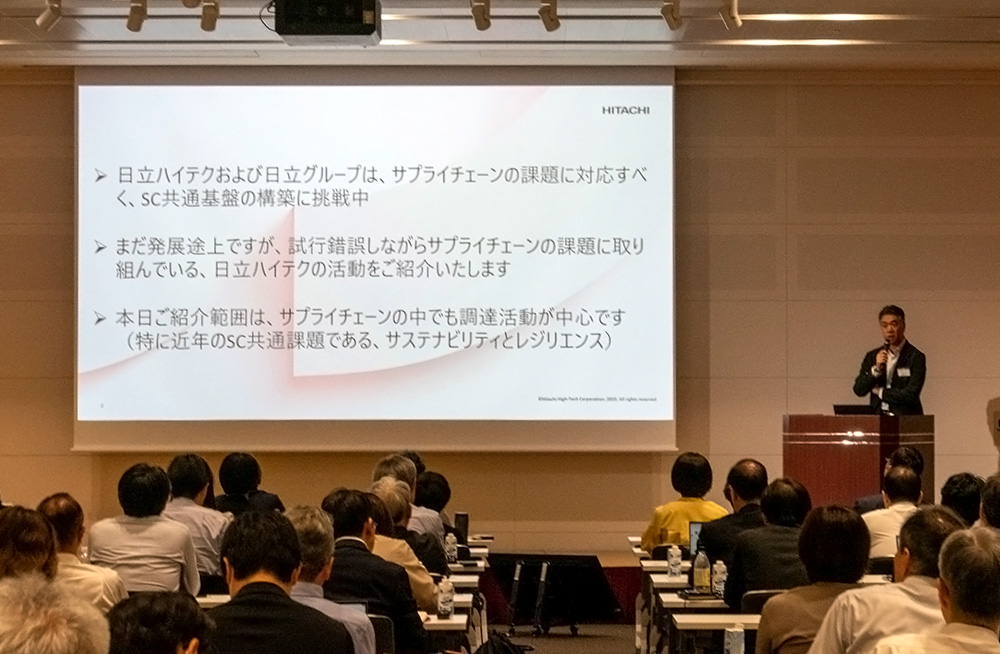
参加者の声
- サプライチェーン全体を把握されて、運用するシステム構築という壮大さを強く感じました。
- メーカーにおけるサプライチェーンに対する課題の幅、深さが構造的にわかった。
- 「アナログでやらないといけないことは人をかけてでもやる」という点、非常に参考になりました。
- リスクシナリオ、レジリエンスをどう高めるか参考になった。
- SCMの各々のポイントを具体的対応、各々の課題と踏み込んだ説明を頂き大変参考になりました。

<基調講演>【SDGsに対応したサプライチェーン管理】
サプライチェーン管理で実現する持続可能な企業経営
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 慶應義塾大学SFC研究所×SDG・ラボ代表 慶應義塾大学Keio STAR副所長
蟹江 憲史 氏
- SDGsは2030年で終わらない。2050年へ向けた対策を考えるとき
- SDGsに対応していないとサプライチェーンから追い出される時代がやってくる
- サステナブルであることを第三者が証明する認証制度の活用を
持続可能な企業経営を実現するにおいて、SDGsに対応したサプライチェーンの管理を行うことは必要不可欠であると言えます。しかしながら多くの企業においては、現実的にそれを実現するには大きな変革が必要であり、中長期的な視点で、SDGsは決して2030年で終わる訳では無く、2050年に向けた対策を考えるべきタイミングにきています。講演では、こういった動きや、サステナブルであることを第三者が証明する認証制度の活用について、お話しいただきました。

参加者の声
- 2030年に向けた達成目標への現状を聞き危機感を感じた。自分事として考え、CSR担当として数字だけでなく、意味合いを考えることを再認識した。
- 学術的な捉え方を含め、サステナブル=SDGsにつながっていることを認識した。
- SDGsの今後について議論が進んでいるというところが興味深く、動向を注視したい。
- サステナブルをデータをもとにご説明いただき面白かったです。
- 一人の人間として、また会社としてサステナビリティについて考えて社会貢献していきたいと思います。中々聞いたことのない内容なので聞けてよかったです。

<パネルディスカッション>【サプライチェーンの標準化・可視化】
持続可能なサプライチェーン実現のために
~企業が目指すべき最前線の標準化・可視化について
パネリスト
日清食品株式会社 常務取締役 事業統括本部長 兼 Well-being推進部長
深井 雅裕 氏
川崎重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニー 航空宇宙生産本部 生産企画部長
酒井 亨 氏
エコバディス・ジャパン株式会社 代表取締役
若月 上 氏
モデレーター
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 慶應義塾大学SFC研究所×SDG・ラボ代表 慶應義塾大学Keio STAR副所長
蟹江 憲史 氏
- サプライチェーンの標準化~埋もれていた新しい価値の創出
- 製配販の壁を乗り越えた、サプライチェーン全体での連携の推進
- サプライチェーン全体としてSDGsへ取り組むことの重要性
パネルディスカッションでは、企業が持続可能なサプライチェーンを実現する上での課題について、標準化による新しい価値の創出や、製配販の壁を乗り越えた、サプライチェーン全体での連携の推進に対する取り組みとテーマを絞り、環境学者かつ、大学教授である蟹江氏から、パネリストに質問を投げかける形で、国際的な食品会社の役員である深井氏、総合エンジニアリングメーカー現場の責任者である酒井氏、評価機関の経営者である若月氏と、それぞれ違う立ち位置より、ディスカッションを行っていただきました。




参加者の声
- アカデミーと企業それぞれの立場での意見ディスカッションは興味深かった。現場とコーポレート部門の連携問題など現実的な話題も出て、どこも同じ状況がわかり良かった。
- 論者の観点がマネジメント・現場・外部評価者と明確で参考になりました。
- サステナブルを達成するためにはリソースもコストもかかる。これを価値につなげるのが大切だと理解した。
- 現場の実情の話もあり、各企業の事例も参考になりました。
- 異なる業種でのサプライチェーンにおける取り組みとサステナブルへの対応についての意見が参考になった。


懇親会の様子



フォーラム全体の感想
- サステナブルサプライチェーンについては、どこも同じような課題があり、打開のために色々と取り組まれている事がわかり良い機会でした。
- SCのサステナブルに関する世の中の動きについて把握することができた。
- サステナブル調達の課題感は各車共通であり、手探りでも進めたところに優位性があると感じました。
- パネルディスカッションは素直な意見も聞け、同じ悩みを抱えているのだと感じた。
- サステナブルサプライチェーンについては、どこも同じような課題があり、打開のために色々と取り組まれている事がわかり良い機会でした。
- 今回の登壇者が全員男性であり、業界の特性があるかとは思いますが、ジェンダーの関係から少し気になりました。
- SDGsの取組み「どこまでやればいいのか」ではなく「やることの価値を見出していく」という考えに改める必要があると感じた。考えを見つめ直す良いきっかけになった。
- SDGsの最新動向が専門家の方から直で聞けたことが本セミナーに参加した価値があった。アレンジ有難うございました。
企画者からの御礼
株式会社ビジネス・フォーラム事務局
企画担当 迫田
この度は「持続可能なサプライチェーン・マネジメント2025」のご参加をいただき、また開催レポート記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。
昨今、多くの場において、「持続可能なサプライチェーン」の重要性が話題にあがる中で、ご講演者の皆様の力をお借りする形で、対外的に弊社としてのメッセージを発したい思いから、弊社主催という形で、企画・開催をさせていただきました。多くの企業において、経営と現場が一体となり、持続的な価値の創出に向けた、強いサプライチェーンの構築していくことは永遠の課題であると認識しております。そのための一助として、当フォーラムの内容が、皆様のビジネスに少しでもお役に立てていただけますと幸いです。
ビジネス・フォーラム事務局では、これからも様々なテーマで皆様に関心いただき、課題解決につながるフォーラムを企画し、情報発信してまいります。お役に立てる機会がありましたら、是非、ご参加いただきますようお願いします。
改めて、この度は「持続可能なサプライチェーン・マネジメント2025」にご参加いただき、また初期の段階から企画に賛同いただき、ご協力をいただいた、ご講演者様、協賛各社の皆様へ心より御礼申し上げます。
どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。
