CMO Forum 2014
マーケティングで挑む経営
~トップマネジメントが創るこれからの価値づくり
2014年2月25日、東京・品川グランドセントラルタワー内「THE GRAND HALL」にて「CMO Forum 2014 マーケティングで挑む経営 ~トップマネジメントが創るこれからの価値づくり」をテーマとしたセミナーを開催しました。(主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局、特別協賛:日本アイ・ビー・エム株式会社、協賛:アライドアーキテクツ株式会社)
このフォーラムでは、会場の中央に巨大なスクリーンと演台を設置し、オーディエンスの円卓が講演者を取り囲むように配置された斬新な講演スタイルを採用。各円卓の参加者が意見を交わしながら手元のアナライザーを使って講演者の質問に答えると集計結果が即座にスクリーン表示されるなど、インタラクティブなやりとりが行われました。
加速度を増すグローバル化とソーシャルメディアの台頭などデジタル環境の一大変化にともない、企業と顧客をつなぐマーケティングの責務と役割は日々拡大し、深化を遂げています。CMO(Chief Marketing Officer:最高マーケティング責任者)の戦略と決断が企業の進むべき道を決すると言っても過言ではありません。このフォーラムでは、経営と一体化したマーケティング戦略によって飛躍を遂げた企業の経営者や改革プロジェクトのリーダー、デジタルマーケティングの側面から改革をサポートする企業の専門家らを招き、豊富な経験から得た知見、提言を披露して頂きました。
特別講演 Ⅰ
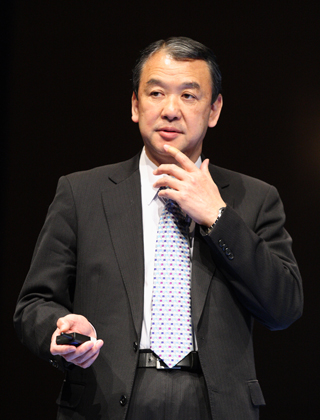
日本の専門店で一度凋落した企業が復活した例はない――。そんな定説を打ち破ったのが「無印良品(MUJI)」ブランドで知られる株式会社良品計画だ。V字回復の陣頭指揮を取った代表取締役会長(兼)執行役員の松井忠三氏は、「マーケティングとは顧客の変化を知ること。変わる顧客と市場を見つめ、自らも大きく変わる決意をしたからこそ成し遂げることができた」と語る。現在、無印良品のファンは世界を舞台に日々拡大を続けている。苦難の時代を振り返りながら、顧客重視の経営から導き出された‘変革の方程式’について詳しく解説した。
奇跡のV字回復を可能にした
顧客第一主義のイノベーション
良品計画は1989年に西友から独立、その後は堅調に業績を拡大し、現在は衣服・食品・生活雑貨などを企画・販売する「無印良品」を中心に、国内に387店舗、海外24ヶ国に257店舗を展開。売上高約2,000億円、経常利益約220億円を誇るグローバル企業だ。しかし、2000年からの数年間は「無印良品はもう終わった」と囁かれた時期があった。同年、創業以来初の減益に転じ、店舗の閉鎖、人員整理、在庫の大量処分といった厳しい施策を余儀なくされたのだ。まさにその最中、2001年に社長に就任したのが松井氏である。「上場を果たすなど拡大を続けるなかで我々に慢心や奢りがあったことは否めない。危機感を喪失していた」と振り返る。とりわけ猛省すべきは、社会や顧客が変化するなかで、かつては光を放っていたブランドが弱体していることに気づかなかったことだと言う。
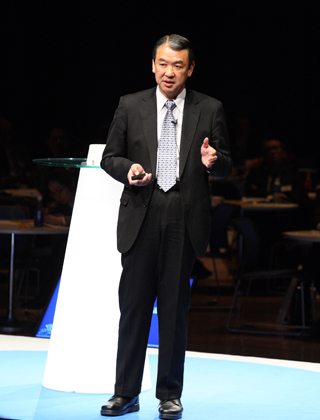
松井氏は大鉈を振るう決意をした。ユニクロなど競合の台頭にも要因はあったが、それよりも内部の要因を全て洗い出して改善することが重要だと考えた。「リストラは辛い現実だが難しいことではない。何より重要なことはマーケットを見直し、顧客の声に耳を傾けることだった」。例えば、改革の重点ポイントの1つに「品質苦情なくす」ことを掲げた。02年には電気洗濯機や食品など複数の商品が回収対象となり、また、問い合わせの約3割が苦情という現実があった。改善の努力によって、クレーム件数は3年後に8割減少した。
最も重要な変革はブランドの立て直しだった。「わけあって、安い」という企業の核となるコンセプトを変えてはいけないが、サブコンセプトは市場と顧客に適合したものでなければならない。そこで、「WORLD MUJI」、「FOUND MUJI」という新たな考え方を打ち出す。これは、「いいものを世界に求め、生活のなかから探して見つけ出す」という意味だ。このコンセプトを全社に浸透させ、商品開発から販売の現場まで徹底したイノベーションを図り、勝つ構造作りに専念した。海外展開については、91年に英国1号店を出店して以来11年間赤字が続いていた。しかし、ブランドの浸透には時間がかかるという認識から出店を止めずにグローバル化を遂げていたことが「WORLD MUJI」の実践につながった。世界規模で実施した改革により、02年からは海外事業も黒字に転じている。
徹底した「Observation」で新商品のシーズを発見する

商品開発の大変革は即座に効果を上げた。衣料品では世界のファッション業界の最先端で活動するヨウジ・ヤマモト社と契約。モノトーンを基調としたデザインは市場に投入するやいなや無印良品の‘顔’となり、新たなファンはもちろん、離れていた顧客も戻ってきたと言う。生活雑貨についても海外デザイナーらを積極的に起用し、シングル仕様が中心だったベッドやソファなどの商品群にカップルやファミリーでもMUJIブランドを楽しめるものを加えていった。顧客のライフスタイルの移行に伴う「卒業現象」を克服していったのだ。こうして、日本はもとより世界での無印良品(MUJI)ファンを確実に増やし、02年を境に海外を含む業績は再び成長を始める。
変革のなかでも、マーケティングと商品開発の仕組みを大きく変えたのが「Observation(観察)」という考え方だ。「顧客のニーズを受けとめるの は常識。我々はその先、生活の細部をつぶさに観察し、必要とされるであろう新商品のシーズ(種)を発見することを目指した。そのため、各家庭に大量のス タッフを送り込んだ」。スクリーンにはバス用品や壁掛け家具など、「Observation」から生まれたヒット商品が次々に映し出されていく。こうした 省スペース商品は、実は住宅事情が厳しいニューヨークなどの海外都市部の顧客にも好評だと言う。
最後に、海外展開の経緯と実情について解説。「海外で通用しないブランドは国内でも勝ち抜けない」という海外初出店当時の経営者の言葉は、今も同社 の根底に息づいている。欧州、米国、東南アジア、中国で33都市101店舗と順調に拡大しているが、松井氏は「グローバルマーケットという言葉に実体はな く、世界にはそれぞれのローカルマーケットしか存在しない。個々に適合できるかが鍵だ」と気を引き締める。日本企業が日本流をそのまま持ち込んでしまう 「ジャパンリスク」で失敗する事例が後を絶たないからだ。そのため、「MUJIGRAM」と呼ばれる13冊、2,000ページに及ぶ店舗業務マニュアルに ついては、日本と同様に海外の店舗でも変更・進化させるよう指示している。基本事項は除き、マニュアルはそれぞれの地域の顧客の声や社員の体験で日々変 わっていくからだ。「2016年には日本と海外の店舗数がほぼ並ぶ。真のグローバル企業としてさらなる発展を遂げたい」と結んだ。
特別講演 Ⅱ

ここ数年でマツダという自動車メーカーに対する印象が大きく変わったという人は多いだろう。根強いファンを獲得しながらも「個性的だがマニアック」、「値引き販売のマツダ」など、ネガティブとまでは言えないが歓迎し難いイメージが存在していたのは事実だ。しかし今、そうしたイメージは払しょくされ、「個々の車種以上にマツダが好き」、「欧州の輸入車と比較したがマツダを正価で購入した」というファンが増えている。世界でも同じ現象が起きており、それは好調な業績にも表れている。大変革プロジェクトの牽引役を果たしたのがマツダ株式会社で常務執行役員 営業領域総括、グローバルマーケティング・カスタマーサービス・販売革新担当を務める毛籠勝弘氏だ。同社が挑んだグローバルマーケティング戦略を基軸とする革新の内容に参加者は聞き入った。
経営とマーケティング戦略は表裏一体
過去と決別する覚悟で変革に挑む
「私は、マーケティング戦略とはビジネス全体をドライブすべきだという考えに立つ。つまり、マーケティングはブランド戦略と直結し、企業の戦い方を設計するも のでなければならない」。組織の一部門であり、宣伝や広報、市場調査といった狭義の理解ではブランド価値経営へのシフトは成し得なかったと言う。マーケ ティングとは顧客を知ること、すなわち企業経営の本質だ。その視座に立った時、マツダが過去に犯していた誤りが明確に見えてきた。巨大自動車メーカーと比 較すれば中堅規模ではあるが、売上高2兆6,000億円、120ヶ国で年間130万台を販売するグローバル企業が、経営の主軸を大胆にシフトするためには 何が必要だったのか。

過去、ヒット車種を次々に送り出しながらも周期的に訪れる危機。為替の変動に翻弄されたのは明らかだが、真因はほかにあるのではないか。そう考えるところから改革はスタートした。マツダには長きに渡り、トヨタや日産、ホンダに追いつき追い越せを目標に規模の拡大を目指すのが当然という考え方が根づいていた。しかし毛籠氏は、欧州を歩いて得た、自社や商品に対する評価を分析した結果、そもそもそうした前提が成長を阻害する真因だったと気づく。同時に、マツダが目指すべきは巨大メーカーとは異なる土俵で戦うこと、つまり顧客にとってのナンバーワンではなく、オンリーワン・ブランドになることだと確信した。自動車製造業界ではタブーともいえる発想だが、顧客を囲い込むのではなく選ばれ続けることこそがマツダらしい戦い方であるという考え方に行きついたのだ。
技術革新の面では、マツダはハイブリッド路線を選ばずエンジン(内燃機関)を究極まで磨き上げたSKYACTIV Technologyの開発に成功していた。勝つための‘武器’はそろった。問題はそれをどう生かすかであり、いかにして顧客とつながる販売やサービスの領域を変えていくかだ。車種ごと、エリアごと、あるいは「販売の現場は売値を含めて販売店任せ」といった分断された仕組みをすべて見直し、「走る歓び」を顧客に提供するマツダブランドを全社的に打ち出していく。戦術や計画レベルの手前にある、唯一無二のブランドを構築するという「考え方」のレベルからの変革、「つながり革新」に着手した。
個別の車種ではなく‘マツダ’を売る
「インサイドアウト」で顧客に選ばれる

そうした考え方をどう戦略に結びつけるか。顧客との絆をテーマにブランドロイヤリティの向上に焦点を当て、販売、マーケティング、サービスの活動全般を再設計した。最も重要な点は、冒頭でも述べたようにマーケティング戦略がブランド価値経営と一体となってビジネス全体をドライブすることだ。それがあってはじめて具体的な戦術や計画が生まれる。「値引きのマツダ」というイメージを払しょくするために、ただ上から「値引きするな」と命じても、多くを売りたい現場は混乱するだけだ。そこで、宣伝広報を含めた様々なチャネルを通じて、顧客にはマツダ車には価格価値だけではなく「意味的価値」があることを訴求した。毛籠氏は「正価は顧客が決める。値引きを抑制する最大の処方箋は、意味的価値を含めた透明性のある価格づけであり、それに顧客が納得することが重要だ。正価販売は残存価格を長く、高く維持することにもつながる」と語る。それがマツダへのブランドロイヤリティを高め、「次もマツダ車を」という好循環を生む。
コミュニケーションの部分では「インサイドアウト」というキーワードを打ち出した。個々の車種の認知度を上げるべく予算を配分していては他社に勝てない。つまり、個々の車種の性能や装備を訴求する「アウトサイドイン」の発想を逆転させ、すべての車種に宿るマツダの技術、スピリット、開発の背景にあるストーリーを内から外に伝播する取り組みを優先した。それに共感するファンを確実に掴むこと、つまり不特定多数ではなく特定多数に照準を合わせた戦略を実践した。テレビCMなどでも頻繫に目にする「Be a driver.」というメッセージはそうした緻密な戦略から生まれたものだ。こうした努力が実り、2011年SKYACTIV Technology投入前と2013年を比較すると、後者では実取引価格の向上と販売台数増加が反比例しない良績が得られた。劇的な変化である。「我々はこれに満足せず、顧客とのさらなる強い絆の構築を目指す。単に満足度を上げるのではなく、顧客エンゲージメントの向上に努めていく」。
また毛籠氏は「モダンマーケティングはクリエイティビティとサイエンスの融合」という考え方に立ち、成果を数字で表し、説明責任を果たすことが重要だと述べる。核心部分は社外秘と注釈を入れつつ、ビジネス面とブランド面両方の現状と成果を測定するパフォーマンス・インジケーターの一例を示した。 グローバル主要10ヶ国で常時モニタリングを続けていると言う。また、こうした考え方と戦略を全社的に共有し、高めていくために、毛籠氏自らがチェアマンを務める「グローバル・ブランド・フォーラム(戦略フォーラム)」を年3回ほど開催している。さらにそれをリージョンごとの「ブランド・フォーラム」に落として実行計画に移す。毛籠氏は日本・北米・欧州・中国・ASEANすべてのリージョン会議に参加し、助言を与えている。
「デジタル時代が訪れ、我々が想定している以上に顧客は企業のことを知っている。過去の経験値は通用しない。デジタルマーケティング戦略が有効に機能する組織への自己改革が急務だろう」と述べ、マツダはこれからも顧客を囲い込むのではなく、選ばれるブランドに成長していくと宣言した。
協賛社ショートセッション
アライドアーキテクツ株式会社は「ソーシャルテクノロジーで、世界中の人と企業をつなぐ」をミッションとし2005年に設立。日本のソーシャルメディアマーケティング分野をリードする企業だ。約3,000社に支援実績があり、13年には東証マザーズ上場を果たすなど堅調に業績を伸ばしている。個人がメディアとなり情報を発信し、個人と企業が自由に、縦横無尽につながりを築いていく時代に、FacebookやTwitterをいかに活用し、デジタル分野でのROI(投資利益率)を高めていくか――。同社のマーケティング部門、セールス部門で担当役員に就く津下本 耕太郎氏が、自社の取り組みと顧客の成功事例などを示しながら解説した。
手段を目的化せずビジネス全体のなかで位置づけよ

まずはデジタルマーケティングの最新動向について説明した。日本のスマートフォン普及率は50%を超え、特に20~30代では8割を上回る。視聴者数においてもPCに迫る勢いだ。これにタブレットやテレビなどが加わって出現した「デバイスの多様化現象」は個人の生活を豊かにする一方で、企業が顧客にリーチする手段を複雑かつ難しいものにしている。ネットの世界ではポータルサイトやメールマガジンの影響力が低下する一方、SNSや無料アプリなどのソーシャルメディアが台頭してきた。しかし、一言でソーシャルメディアといっても運営事業者は多数存在し、SNSや無料アプリが新たに出現するごとにマーケティングもまた生まれては消えている。こうした「入口の多様化や細分化」が企業のマーケティング部門に大きな課題をもたらしていると津下本氏は言う。「マーケッターは技術にキャッチアップするだけで時間を失い、多様化・細分化された入口ごとに担当が違えば知識は断片化する。つまり、経験値が蓄積されないうえに、手段が目的化してしまう」。目下、多くの企業が抱えているリスクを的確に指摘した。
「大切なのは、デジタルのよさを認識することだ。一言で言えば、安価かつ細やかに顧客に再リーチできること。生活者の顔が見え、1対1の関係を築くこともできる。これは従来型の広告が成し得なかった圧倒的な利点だ」。掛け捨て(フロー)型の広告に対し、ソーシャルメディアはストック型のモデルを可能にする。継続して知識やデータを蓄積することで、明らかな効果が見えてくる。同社はFacebookを活用した支援で数多くの実績を築いている。そこから見えるは、インプット(具体的な目標の設定とそれに応じた投資計画)とアウトプット(低コスト・再リーチといった利点をいかに具体的な価値に変えていくか)をしっかり定義した企業ほど成功しやすいという法則だ。
「ソーシャルメディアは『デジタルを用いたブランド顧客育成プラットフォーム』であると位置づけてほしい」。津下本氏は、マーケティング戦略の立案時などに用いられる「認知」から「関心・検討」、「購入」、「リピート」に至る購買ファネルをスクリーンで示し、個々の施策やアイデアを投入する以前に、購買ファネル全体の中での役割と数値目標を明確にすることが重要だと訴えた。
ソーシャルメディアの活用に成功した企業は何が違うのか?

次に、支援する企業の1つである高級ワイングラスのグローバルブランド、Riedel Japanの成功例について解説した。Facebookページを単に商品情報を提供する場ではなく、「ワイングラスの知識がワインライフを豊かにする」という同社の考え方を体現する場と位置づけた。ソムリエからの情報提供を起点とし、ファン同士が活発に発言し合うコミュニティを形成することによって、同社が主催するセミナーや商品の情報は口コミの力によって拡散していく。「ワイン専門誌の広告では決して得られない実売効果を生んだ」と高く評価された。一方、通販限定化粧品ブランドのFacebookについては一度ユーザーとなった顧客を継続的にサポートする場と位置づけ、むしろ商品情報をダイレクトに打ち出している。ソーシャルメディアはこうあるべきだろうと漠然と運用するのではなく、いずれの成功もインプットとアウトプットを戦略的に定めて実行したことが成果につながったと言う。
BtoBの領域でもアライドアーキテクツのサービスは強みを発揮している。自社で運営する「ソーシャルメディアマーケティングラボ(SMMLab)」をもとに、短期間で既存広告のROIを上回った成功事例を示した。また、強みとして知られるキャンペーンのほか、運用コンサルティングや制作、近年では台湾やベトナムなど海外事業の支援にも力を入れていることを紹介し、講演の最後をこう結んだ。「ソーシャルメディア単体ではなく、ビジネス全体のなかで位置づけることが重要だ。手段を目的化せず、ソーシャルメディアを組織の力に変えてほしい」。
基調講演
「デジタル時代をリードする企業のトップは、今や顧客を経営陣の一部だと考えている」。そう話すのは日本アイ・ビー・エム株式会社の理事でありスマーター・コマース営業担当を務める鈴木洋史氏だ。コモディティ化(品質などの違いの不明瞭化、均質化)が進んでいるのは耐久消費財だけではない。あらゆる企業の商品やサービスが、‘進化した消費者’によって時に飽きられ、時に切り捨てられていく。多くの企業にとって、そうした顧客の実像を掌握し、顧客中心の経営モデルを打ち立てることが急務となっている。「そのためにも企業はマーケティングの概念を広げ、ビッグデータなどのテクノロジーを積極的に取り入れる改革に臨まなければならない。CMOを含む経営陣こそがその先頭に立つべきだ」。
自社に最適なテクノロジーを選択し進化した「C世代」をファンに変えよ
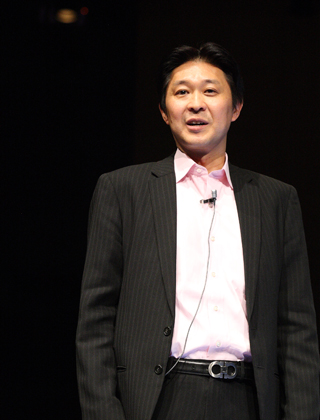
鈴木氏はまず、今回のセミナー会場が自身の提案によって工夫されていることを参加者に伝えた。参加者は講演者を取り囲むように配置された円卓に3名ずつ着席。各テーブルには講演者の質問に応じて操作するアナライザーが用意されている。さっそくこう問いかけた。「みなさんは『C世代』とは何かをご存知ですか?」。結果は即座にスクリーンに映し出される。85%が「No」という回答だ。C世代とは「コンピュータを使いこなし、日常的にネットワークにコネクトしてコミュニティを大切にする。そうして自分らしい価値をクリエイトしていくような進化した消費者」を意味する。それぞれのキーワードがCで始まることからC世代と呼ばれる。主に若者を中心とした層だ。彼らこそが新しい市場の主役だと鈴木氏は言う。日本のEC(電子商取引)市場は昨年の統計で9.5兆円。成長率は12.5%に達する。国内だけでなく国境をまたいだEC扱い高も増加の一途を辿っている。「C世代の90%は友人や家族の口コミを信用するが、企業からの直接情報を信じるのはたった10%」という調査結果もある。彼らを優良顧客としない限り、次代を拓くことはできない。

では、企業はどう対応すべきか。顧客の先を行くテクノロジーを柔軟に取り入れなければならないと言う。その一つがビッグデータだ。参加者に「ビッグデータを説明できますか?」と問うと77%が「No」と回答した。ビッグデータの特性は4つの「V」で表される。膨大な量(Volume)、データが発生する速度(Velocity)、 データの種類・多様性(Variety)、データの正確性(Veracity)だ。上手く活用すれば顧客の平均値ではなく個々の特性をタイムリーに把握できる。しかし、ポイントはデータを手にすることではなく使いこなすことにある。「ビッグデータやソーシャルメディアを導入したいのだが…」という相談が増えているが、明確な目的がなければ投資は無駄になる可能性が高い。「流行っているから、取り残されるのが怖いからという理由からではなく、自社にほんとうに必要かどうかをまず考えてほしい」と鈴木氏は訴えた
新たなテクノロジーを武器に変えた小規模事業者が突如として競合企業になることもある。さらに海外の企業が軽々と国境を越えてライバルとなる時代だ。つまり、自社の商品やサービスが、比較される以前に「顧客の選択肢に入ること」さえ難しくなっているのだ。「ITはこれまで一部の事業で効率化やコスト削減の役割を果たしてきたが、今やマーケティングやアフターサービスの領域への導入が迫られている。進化した消費者と対等に向き合うには、組織体系そのものの変革が必要となるケースもある」。
世界の経営層4,000人の調査から明らかになった3つの課題

「C-suite Study」は、同社が全世界の経営層を対象に対面でインタビューを行い、得られた結果を分析したデータだ。昨年の対象者は4,000人を超える。そこから導き出された1つの結果が「成功している企業は、顧客を積極的に自社の経営に取り入れている」というもの。対象者の60%が「顧客の声を事業戦略の策定に活かす」、50%以上が「顧客は既に経営層に次ぐ影響力を持つ」と回答している。つまり、顧客の声を経営に活かすのは経営陣の役割なのだ。旧来のマーケティングや営業、サービス部門に止まらず、業務プロセスや組織体系そのものを顧客の声で変える――。欧州の銀行の取り組みなど、鈴木氏は複数の成功事例を紹介した。
キーワードは、「デジタルと実世界の融合」だ。それは理想ではあるが、3分の2の対象者が「強化したいがこれからの課題」と答えたと言う。しかし、セブン&アイ・ホールディングスのように、消費者が欲しい商品をいつでもどこでも買えるオムニチャネル事業モデルの確立に約1,000億円を投じて邁進している企業が既に存在している。スーパーからコンビニまでグループ全体で扱う300万アイテムをネットで購入可能にする。現在1,000億円のEC売上高を2020年には1兆円にまで伸ばしたいという。そうした規模でなくても、「デジタルと実世界の融合」を果たした新しい商品やサービス、市場は次々と生まれている。日本アイ・ビー・エム本社内には大型ディスプレイを活用した車のショールーム、バーチャルショールームが設置されており、実寸大の‘車’でリアルな試乗体験ができる。体験者の操作履歴はクラウド上に蓄積され、分析などに活用もできる仕組みだ。住宅などにも応用可能だと言う。さらに必要とされる取り組みは「魅力的な顧客体験の提供」だ。顧客をセグメントするのではなく個としてとらえ、継続的にファンでいたくなるような体験を作り出す。それは企業ごとにまったく異なるべきであると鈴木氏は強調する。なぜならば、その違いこそがコモディティ化を払しょくする競争力となるからだ。これもまた、1つの部門で達成できない課題であり、CMOを含む経営層が率先して取り組むべきだと言う。
鈴木氏は参加者への最後の質問として「必要とされるこれらの取り組みを認識し、克服できていますか?」と問いかけた。結果、ほとんどの回答が「No」を示した。阻害要因の多くは「組織の壁」だ。それを取り除く手立てとして、「顧客体験シナリオ(カスタマー・ジャーニー・マップ)」の作成と活用を提案した。今の顧客像ではなく、今後の目的に合致した顧客像を描いて、彼らが自社の商品やサービスで体験するストーリーをできる限り具体的にマップ化する。それが組織の壁を越えるための‘共通言語’となる。もちろん経営層自らがシナリオ作成の指揮を取らなければならない。最後に鈴木氏はこう呼びかけた。「多くの方がこれらの取り組みを実現できていると回答したら、私がここでしゃべっている意味がない(笑)。それは当然のことで、世界的にもまだ実践できている企業は少ない。本日お会いした皆さんに、ぜひ先駆者となってほしい」。
特別講演 Ⅲ
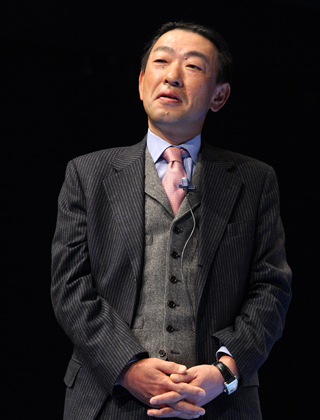
「社長の頭のなかにある時代観、感性が問われる時代が来ている。参考にすべき教科書や参考書は存在しない。私には1つの読みがある。それは、顧客第一主義が叫ばれる時代の次には顧客中心主義の時代が到来するということだ」。営業マンと店舗の廃止、画期的な手数料体系の導入、日本初となる本格的インターネット株取引の実施などによって‘証券業界の革命児’と呼ばれる松井証券株式会社 代表取締役社長の松井道夫氏。マーケティングの究極の目的が市場の変化と顧客の実像を正確に掴むことであれば、松井氏は社長業に就いてから今日までの四半世紀に渡りトップマーケッターであり続けたと言える。人と社会はどう変わり、企業はそれにどう対応すればいいのか、社長の果たすべき役割は何か。成功秘話を交えて雄弁に語った。
「時代とのギャップ」は最大のコスト
顧客中心主義の時代に適応せよ
およそ1世紀続いた大量生産大量消費の時代は終わる。その延長線上で企業経営を考えているようでは生き残れない――。今起きている大変化とは、一度分離した 資本と労働が融合することで、主役が企業から「顧客」に入れ替わる動きだと松井氏は読む。天動説から地動説へ、コペルニクス的転回が起きると言う。これま では企業が中心にあり、その周りを顧客という星が取り巻く状態で社会は成り立っていた。企業は個人を引きつけるための重力を求める。すなわち、規模を拡大 して顧客を抱え込もうとする。しかし、何億という顧客がそれぞれ中心となり、その周りを企業が飛び回るような時代が訪れると言う。顧客の重力に逆らえば企 業は滅びる。企業のトップは常に顧客を見据えてその動きに順応しなければならない。顧客と顧客、企業と顧客の間に張り巡らされた新たなネットワークは、刻 一刻と変化を遂げる。それに見合ったビジネスモデルをどう構築するかが問われていると言う。
松井氏が導き出した1つの策は、組織の規模を徹底的に小さくするということだ。時代の変化に合わせていかようにも自らを変え得る組織が理想だと言う。松井証券の株の扱い額は直近で年間約40兆円、社長に就任した頃と比べると300倍近い。しかし社員数は現在も120人ほどで、スリムな組織を維持している。証券業界にイノベーションを起こし、小さな組織で高収益を生む体制を築いた同社だが、それでも安心できないと言う。
前職である日本郵船時代に海運業界の凄まじい過当競争を目の当たりにしたからだ。1980年代に米国レーガン政権が北米航路で運賃を自由化したことにより、運賃相場はたった2カ月で20分の1まで下落した。しかし、それは受け入れなければならない現実だ。価格を決めるのは顧客であり、顧客は価格の裏側にあるコストを選んでいる。運賃相場を破壊した新興国の海運会社の強みは、圧倒的に安い人件費だ。さらに、コンテナや船が老朽化したものであっても顧客は気にしない。つまり顧客にとって、日本の海運会社が価格に反映させていたコストの大部分が不要だったのである。不要なコストの代金を顧客に要求したら必ず負ける。それは虚業であり、虚業を見切るのも社長の役割だと言う。
新たな価値を創造するのは個人
企業は個人の力を活かす器にすぎない
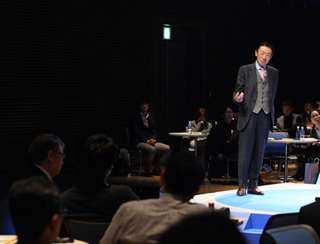
今日の証券業界も手数料を奪い合っているだけでは未来がないと読む。そこで、「過当競争の影響を受けないものとは何か?」と考えた。例えば金利。年利、月利、日歩は存在するが、今日の投資家は1日に何度も売買を繰り返す。ならば時歩、分歩、秒歩という金利があってもいいはずだ。同社の株の扱い額40兆円のうちの24兆円が信用取引であることを考えれば、正しい方法で制度を打ち立て、決済の仕組みを変えて顧客に提示すれば、独占的かつ勝てるビジネスモデルを生み出せるかもしれない。「商売とはそういうもの。社員に対しては常日頃から、どうか頑張らないでください。頑張らなくても収益が上がる方法を頑張って考えてくださいと言い聞かせている」。
無数の会社が生まれ無数の会社が消えていく。そうした時代には、個人だけが新たな価値を生む源になる。松井氏自身、徹底した個人主義を貫いている。哲学者である西田幾多郎氏が残した「人は人 吾は吾なり とにかくに 吾が行く道を 吾は行くなり」という言葉が座右の銘だと言う。組織に守られ、単純作業だけでやっていける時代は終わる。それは個人にとって決して不都合なものではなく、むしろやりがいに満ちた時代、楽しい時代であるべきだ。「大企業は優秀な人材に権限を与えて分社化すればいい。企業は個人の力を活かすための器にすぎないという発想で仕事に臨もう」と参加者に檄を飛ばした。
最後に、社長は自社の事業の社会的有用性を常に念頭におくべきだと訴えた。時代に求められるビジネスか否かを検証し、実行する。なぜなら、企業の最大のコストは設備でも人件費でもなく「時代とのギャップ」だからだ。そのギャップを埋めるのが社長の役割だが、「誰ができるのか、どういう人材がふさわしいかは、やらせてみなければわからない(笑)」。
特別講演 Ⅳ
「‘マーケティングを牽引するリーダー像’が本日のフォーラムのテーマですが、私はもう一歩先を行くリーダー像を示したい。それは‘知的感性時代の革新型リーダー’だ」。2000年以降、統廃合の嵐が吹き荒れたクレジットカード業界にあって、堅調に業績を伸ばし続けている株式会社クレディセゾン。今や会員数は3,500万人を上回る。「年会費無料カード」や「永久不滅ポイント」、American Expressと世界初となる「センチュリオン・デザインカード」を発行するなど、業界の常識を打ち破るイノベーションを次々に巻き起こしてきた。30年以上に渡り同社の中核で革新的事業の創出に取り組んできた代表取締役社長の林野宏氏が、イノベーションの創出法や「知的感性時代の革新型リーダー」の具体像を解説した。
イノベーションは誰にでも起こせる
経営トップは環境作りに注力せよ
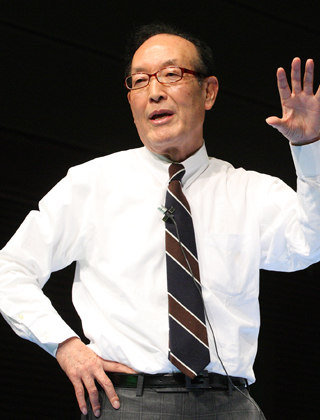
まずは「知的感性」というキーワードを用いて今日の社会と企業のあり様を示した。経済社会は製造産業経済から情報知識経済の段階を経て、感性創造経済に変化を遂げた。スティーブ・ジョブズという一人の人間の知的感性から世界トップクラスの企業が生まれた事実がそれを証明している。J・シュンペンターが唱えた「創造的破壊」と企業の本質である「競争」を両輪としてイノベーションは生まれるが、問題はその源泉となる力だ。今の時代は企業の技術力や価格競争力以上に、人が主役となって発揮される「知的感性の力」こそが最も重要だと林野氏は言う。すなわち人こそが企業にとって最大の資産となる。企業はこの資産がもたらすイノベーションとマーケティングをバランスよくマネジメントする役割を担ってはじめて社会的な存在意義をもつ。
その際、イノベーションと技術革新を区別する必要がある。後者は今の延長線上に既存の価値次元を変化させるものだ。つまり、「できるか、できないか」。それと一線を画すのがイノベーションであり、それは一業界に止まらず社会に劇的な価値の変化をもたらす発想から生まれる。つまり、「思いつくか、つかないか」。例えばそれは、19世紀の「クレジットの発見」であり、今の日本で言えば、空き地を利用したコインパーキング事業の発見などもそれに当たる。草分けであるパーク24で最初の構想が生まれたのは、実に40年も前だったという。
イノベーションは誰にでも起こすチャンスがある。ただし、イノベーターは好奇心に富み、どのような制約のもとでもクリエイティビティ(創造性)を発揮できるように自らを成長させる人間でなければならない。「現実にはそういう人材は100人のうちほんの数名程度の割合でしか存在しないだろう。それでもリーダーは諦めてはならない。旧来の部下との関係、すなわち管理・監督・指示・命令といったような硬直した関係を壊し、率先垂範してオープンでフランクなビジネス環境を作って、組織のどこからでもイノベーションが生まれるようにすることが求められている」。
知的感性時代に求められる「夢中力」と「S.Q.」
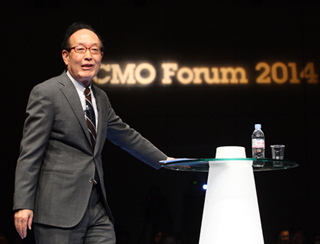
イノベーターに欠かせない資質がもう一つあると言う。「時間を忘れて夢中になれること」だ。本来であれば10代までの成長期に遊びに夢中になるなかで培われる資質である。しかし、成長を望むビジネスパーソンであれば「時間を忘れて夢中になれる遊びと仕事を常に意識せよ」と林野氏はアドバイスする。ここで、物理の法則を模して自ら考案したという「夢中力」の公式を披露した。
A=cs²

Ability(能力)、Concentration(集中力)、Second(秒)。能力は集中して努力した時間の2乗に比例するという意味だ。「CSはクレディセゾンの意味もあるんですよ」と補足し、会場の笑いを誘った。 では、リーダーはどうか。次のような公式で知的感性時代の革新型リーダー像を示した。 B.Q.(ビジネス感度)=I.Q.(知性)×E.Q.(理性・人間性)×S.Q.(感性) 感性創造経済のもとでは、とりわけ「S.Q.」の重要性が増している。「S.Q.」を磨く方法として、自分の周りの優れた「S.Q.」の持ち主を集中して観察し、絶えず模倣しながら自分のものにするなど様々なアイデアを示した。
クレジットカード業界を巡る現状についても解説を加えた。米国や韓国に比べて日本はまだ現金決済が主流だ。カード取扱高のシェアを見ると同社は約17%を占めるが、「挑むべきは他社との喰い合いではなく、現金の領域だ」と言う。また、韓国の成功例を踏まえて現在我が国でも国策としての導入が検討されている「ライフ・アシスト・ポイント制度」の概要と効果予測を示した。
最後に同社のイノベーションへの社会的な評価についてふれた。2012年、冒頭でも示した画期的な取り組みの数々が評価され、競争戦略論の第一人者であるハーバード大学教授、マイケル・E・ポーター氏の名前を冠した「ポーター賞」を受賞した。「クレディセゾンはこれからも『ヒューマニズムの風土創り』を大切にして、社内のあらゆる人材がイノベーションを生み出す可能性を持った企業であり続けたい」と結んだ。
