CMO Forum 2017
多様化する『顧客接点』と複雑化する『顧客ニーズ』に立ち向かう
CMOが創る、顧客と企業の新たな接点のデザイン
2017年9月12日、東京・JA共済ビル カンファレンスホールで『CMO Forum 2017』を開催しました(主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局)。4回目となる今回は「CMOが創る、顧客と企業の新たな接点のデザイン」がテーマです。多様化する『顧客接点』と複雑化する『顧客ニーズ』に、CMO(Chief Marketing Officer:最高マーケティング責任者)は、いかに役割を担うべきか。この日の講演やパネルディスカッションの模様を紹介します。
ゲスト事例講演Ⅰ【経営戦略 × “顧客接点”】
CMOがデザインする、これからの顧客接点創り
~企業と顧客のコミュニュケーションは新しい時代に~
ネスレ日本株式会社 専務執行役員 チーフ・マーケティング・オフィサー
石橋 昌文 氏

独自のマーケティング戦略を実践、成熟市場で確実な成長
ネスレ日本は「キットカット受験生応援キャンペーン」など、独自のマーケティング戦略の実践により、成熟する日本市場で確実な成長を遂げている。2012年には日本企業の中でも早い段階でCMOを設け、マーケティング思考の全社への浸透を図っている。専務執行役員CMOの石橋昌文氏が、ネスレ日本におけるCMOの役割、これまでの取り組みなどを語った。
縦割りを超えたマトリックス組織でマーケティング機能を発揮

私は2012年、ネスレ日本のCMOに就任しました。CMOという役職をつくったのは、日本企業の中でもネスレ日本は早い方だったと認識しています。CMOの役割は商品分野別の縦割りを超え、コミュニケーション、マーケティングリサーチ、消費者対応などの専門性を持ったマトリックス組織でマーケティング機能を発揮させること。具体的な業務にはコーポレートブランドの強化・広報、メディアプランニング、オウンドメディアの活用、消費者コンタクトセンターの運営、CSV(Creating Shared Value)や戦略的PR、デジタルマーケティングの推進などがあります。
ネスレ日本は成長戦略として「イノベーション&リノベーション」「消費者コミュニケーション」「いつでも、どこでも、どんな形でも製品の入手が可能」「低コストで高効率の運営」という4つの柱を掲げており、マーケティング施策もこの柱に沿って実行しています。2011年~2016年の売上高は年平均3.5%増、営業利益は同7.0%増を達成しています。
また、ネスレ日本はマーケティングを「顧客の問題解決を通して新たな価値を創造する」ことと定義しています。全社にマーケティング思考を浸透させるマーケティング経営を実行していきたいと思っています。そのための1つの施策として、2011年に「イノベーションアワード」を立ち上げました。社員を対象とする表彰制度で、顧客を定義し、問題を発見し、解決方法のアイデアとその実行結果を報告してもらいます。優秀な成果を上げた人には賞金100万円を贈呈します。初年度の応募数は79件でしたが、2016年度には4724件に達しました。ネスレ日本の社員は2500人ですから1人2件弱、応募している計算です。
戦略的PRを実行、「キットカット」は広告換算37億円分の露出

ネスレ日本はコミュニケーションの一環として戦略的PRを推進しています。その成功事例の1つが「キットカット受験生応援キャンペーン」です。キットカットは既に消費者への認知度が高く、広告を打っても効果が出にくい商材となっていました。そんな中、消費者の間で「きっと勝つ」の語呂合わせが受験の験担ぎになると購入するケースが増えていたことを活用。ホテルと連携し、宿泊した受験生にキットカットを手渡ししてもらったり、郵便局と手を組み、メッセージを書いて郵送できる「キットメール」を発売したりしました。このキャンペーンは「受験生をサポートしたい」第三者を核としてメッセージを発信する構図としたことが特徴です。こうした戦略的PRによってキットカットは2016年度、広告に換算すると37億円分もの露出を実現しました。
消費者との接点としてオウンドメディアの活用も進めています。2010年秋に「ネスレアミューズ」を立ち上げ、ブランドごとに所有していた消費者データやキャンペーンデータを統合。ショートフィルム、レシピ、ゲームといったオリジナルコンテンツによって情報発信を行うプラットフォームとしました。通販オンラインショップも備えています。現在のネスレアミューズ会員数は約530万人です。我々の調べではコンテンツへの接触数が多いほど購入意向が高まる傾向があるため、更新のタイミングを図り、リピート訪問を促しています。ネスレアミューズは今後、YouTube、Twitterといったソーシャルメディアとの連携の強化やアプリでの取り組みを推進していきます。
消費者との接点としてもう1つ、VOC(Voice of Consumer)センターも活用しています。2009年、従来のコールセンターを消費者の声を吸い上げてそれをビジネスに活用していく狙いでVOCセンターと名称変更しました。具体的にはアフターサービス、メンバーシップ、デジタルコミュニケーション、販売の機能を持っています。ネスレ日本は2020年までに、現在15%ほどの直販ビジネスの比率を20%に高めたいと考えています。現時点でVOCセンターには年間100万コンタクトがあります。20%の直販比率が実現すれば300万コンタクトとなると予想されます。コミュニケーターの確保、コミュニケーションの質のバラつき、コスト増大などの課題を解決しなくてはなりません。そこで昨年、VOCセンターにIBM Watsonを導入。現在、コンタクトの15%をIBM Watsonが扱っています。
ネスレは時代の流れを反映しながら新しい現実を理解しつつ、付加価値を創造しビジネスを伸ばしてきました。これからもその取り組みを続けていきます。
Sponsor Session 【行動データ活用×顧客体験の設計】
データ活用の常識が変わる!
売上140%を実現したUX改善の新手法「デジタル行動観察」
株式会社ビービット エグゼクティブマネージャ/エバンジェリスト
宮坂 祐 氏

顧客の理解がデジタルマーケティング成功のカギ
デジタルマーケティングを成功させるためには、顧客を理解し、顧客体験(UX)を改善していくことが欠かせない。しかしデータを集計し、まとめた数値からは顧客の真のニーズや心理を読み解くことは難しい。ビービットのエグゼクティブマネージャ/エバンジェリストの宮坂祐氏はデータを一人ひとりに分解し観察する新手法「デジタル行動観察」を紹介しながら顧客体験改善のポイントを示した。
集計した数値ではなく、データを一人ひとりの行動に分解して観察

デジタル化の時代となり、商品・サービスを起点とする「モノ」から顧客のストーリーを起点とする「コト」をベースとしたビジネスモデルへの転換が進みつつあります。企業にとってはモノという“点”でのコミュニケートから、その前後のカスタマージャーニー全体で価値提供できるようになっています。顧客に関するデータを分析し、顧客を理解した上で顧客体験の改善につなげることが必要です。しかし、データを集計し、数値を見る定量分析から顧客体験を改善することは容易ではありません。相関と因果を取り違えてしまったり、施策の効果がよく把握できなかったりという問題が生じがちだからです。そこで私はデータの見方を変え、一人ひとりの行動に分解して観察する新手法「デジタル行動観察」を紹介したいと思います。
デジタル行動観察とは、行動ログと顧客情報で一人ひとりの体験を見える化することを指します。まず誰の何の行動を観察するのかを決め、絞り込んだ顧客の行動を、一人ひとり、時系列に沿って観察します。次に一連の行動から、「なぜ、この顧客はこういう行動を取っているのか」を読み解き、解釈や気づきを得ます。そして、その解釈や気づきが全体に適用でき、量的に担保できるものなのかどうか、定量的な裏付けを取ります。デジタル行動観察はリアルユーザーによる行動観察をするのとは違い、仕組みさえあればいつでも手軽に実施できます。データが残っているので、確実に購入に至った顧客の行動を検証できます。ユーザーの記憶に頼らずに済むため、長期にわたって行動を確認することも可能です。
デジタル行動観察で「PDCA」を「STPD(See、Think、Plan、Do)」に転換

実際にデジタル行動観察を行って改善につなげた企業の事例を紹介しましょう。1つ目はカラーコンタクトのECサイトです。10~20代の女性に人気を集めるサイトですが、近年、大手企業の市場参入で競争が激化し売上が伸び悩んでいました。売上の大半を占めるリピート顧客を対象にデジタル行動観察を実施しました。従来の顧客データベースの分析では、リピート顧客のほとんどは毎回同じカラーコンタクトを購入しており、同じ商品にしか興味がないと想定されていました。ところがデジタル行動観察では、他のカラーコンタクトの口コミを何ページも見たり、一度購入した後にキャンセルしたりという行動が見られます。他の商品にも関心はあるものの決めきれない顧客の姿が浮き彫りになりました。そこでこのECサイトはいつもと違うカラーコンタクトを試したい顧客が思いきって意思決定できるような工夫を施しました。購入者がコメントを投稿する際には宣伝用の写真ではなく、装着したイメージが分かるような写真を投稿するよう促しました。またリピート顧客が「ブックマーク」からアクセスするのではなく、商品名の検索や広告経由でアクセスしてきている点にも着目。サイトの販促のためにWeb以外の施策も講じました。こうした顧客体験をとらえた施策によって売上は反転上昇しました。
化粧品を販売するエステティクスはECサイトで新しいラインナップの売り上げが想定よりも伸びないという問題を抱えていました。従来、トップページに新商品のキャンペーンページを作り、バナーを貼って誘導していましたが、デジタル行動観察の結果、ユーザーはトップページからすぐに「よく買う商品」のページに移動してしまうことが判明。よく買う商品のページにバナーを貼るように改善したところ、1週間で売上は前週比140%に達しました。
これまで企業の業務プロセスは「PDCA(Plan、Do、Check、Action)」で回っていましたが、デジタル行動観察を起点にすると「STPD(See、Think、Plan、Do)」となります。常に顧客を観ることから始め、その特徴や困りごとに気づけば、適切な課題設定、施策立案が可能になります。従来、データを個人に分解する作業は非常に手間がかかりました。今は一人ひとりを見ることに特化したツールが色々と出てきています。ビービットが提供する行動観察ツール「ユーザグラム」もそのひとつ。4月にリリース後、大手企業からネット専業企業までリリースから4か月で約60社に導入しています。まずは顧客体験の見える化を始めてみることが重要だと思います。
ゲスト事例講演Ⅱ 【多様化する“顧客との接点”構築とコミュニケーション 】
お客様との新しい関係作りを目指して
~お客様起点のコミュニケーションの取組み~
森永乳業株式会社 マーケティングコミュニケーション部 部長
寺田 文明 氏

「知ってもらう」「知る」「交流する」取組みを推進
1日1000万個の商品販売で顧客との接点を持つ森永乳業。テクノロジーを活用し、顧客と直接的に接触しながら、さらに良い関係を構築しようとコミュニケーション活動を強化する。「企業を知ってもらう」「顧客を知る」「交流する」という3つのポイントで進める取組みについて、マーケティングコミュニケーション部部長の寺田文明氏が語った。
マスとリアルをつなぐインタラクティブなアプローチで、共感の輪を広げる

森永乳業は今年9月に創業100周年を迎えました。現在、1日に1000万個の商品を販売しており、毎日、お客様と1000万個に及ぶ接点を持っていることになります。テクノロジーの発達により、企業はお客様とコミュニケーションを取るための様々な手段を手に入れました。これからは従来の商品購買ルートだけでなく、直接的な接点ルートも強化することでコミュニケーションを充実させ、共感の輪を広げ、お客様と良い関係を構築し、ブランドを確立していくことが重要だと考えています。
とはいえ、お客様から見れば情報が氾濫し、選択肢が数多くある状況です。我々が商品の「知覚品質」の差異を理解してもらい、選んでもらうことは簡単ではありません。従来、企業のコミュニケーション活動はマスを対象とした「企業発信」とリアルな「直接接触」という2つに絞られていました。これからはデジタル技術などを使って2つをつなぐような、「個対個」のエッセンスを持ち、感情を伝えられるインタラクティブなアプローチによって関係を構築する取組みが必要です。こうして関係をつくった上で、コミュニケーションによって知覚品質の差異を知ってもらうのが理想といえます。お客様と良い関係を作るためのポイントは「企業を知ってもらう」「お客様を知る」「交流する」の3つです。森永乳業はこの3つの活動を進め、お客様と「町内会以上友達未満」の関係を構築することを目指しています。
「企業を知ってもらう」ためにはまずコーポレートコミュニケーションを体系化し、「森永乳業と言えば…」という企業像を明確に持ってもらうことが重要です。このため、子供を応援するメッセージや研究・技術起点のメッセージを積極的に発信しています。また商品のステージごとにブランド像を作り上げていくことも求められます。導入したばかりの「イントロダクション」、ターゲット層を獲得した「成長」、市場に定着している「ブランディング」、発売から長い年月がたった「ロングセラー」と各ブランドが現在置かれたステージ別にコミュニケーション戦略を立案しています。例えばロングセラーの「ピノ」に関しては、チョコレートソースやマシュマロクリームなどを自由につけて楽しめる「ピノフォンデュカフェ」を期間限定で出店。リアルなブランド体験という価値を提供しています。いきなり広告するのではなく、お客様が我々に好意を抱き、話を自然と聞く気持ちになるような、広告ではない「プレコミュニケーション」を取っていくことも必要です。
「お客様を知る」ためには、データやデジタルを活用し、お客様のリアルの声を徹底して聞くことが求められます。重要なのは、同一対象者から多面的に情報を得るシングルソース、購買や視聴などの行動データ、そしてデータ連携です。さらにSNSから生の声を収集、分析する「ソーシャルリスニング」を積極的に行っています。
コミュニケーション活動の推進には横串機能の強化が必要

お客様と常に「交流する」姿勢を持つために、森永乳業は多くのイベントを実施しています。昨年は70件を超えました。単発のイベント実施にとどめず、それらをプログラム化することでイベントの規模感を醸成し、発信メッセージを強化しています。例えば女子栄養大学と手を組んだ「食のオピニオンリーダー向け基礎学問+応用研究+実用調理イベント」、元オリンピック選手が参加する「バレーボール女子 中学生応援企画」などのプログラムで交流に努めています。
コミュニティサイト「Newの森」にも力を入れています。こうしたコミュニティサイトは感情を伴う交流が多人数で可能なのが特徴といえます。「Newの森」には乳製品を使ったレシピ、乳製品に関する豆知識、掲示板機能などを備えていますが、分析の結果、コミュニティ内での関与レベルが上がるほど、当社に対する好意が向上し、実購買額が大きくなっていることがわかっています。
こうしたコミュニケーション活動を部門別の縦割り組織で進めるのは困難です。1つの人格としてコミュニケーションをしていくために横串機能の強化が必要となります。CMOを求める声もありますが、役職を設定しなくても、社内の草の根的な動きで小さな成功体験を重ね、それを拡大し、組織化していくことが有効だと考えています。横串機能を持つ我々マーケティングコミュニケーション部は、泥臭く、汗を流しながら、旗振り役となって、できることを愚直にやり続けようと思っています。
Main Sponsor Session :最適な“顧客接点”を創り出す、“AI活用と顧客理解”
顧客を知り、顧客の期待を超える、優れた体験を提供するためのマーケティングプラットフォーム
~AI・機械学習・ディープラーニングで顧客嗜好・タイミング・行動を予測する~
株式会社アクティブコア 代表取締役社長
山田 賢治 氏
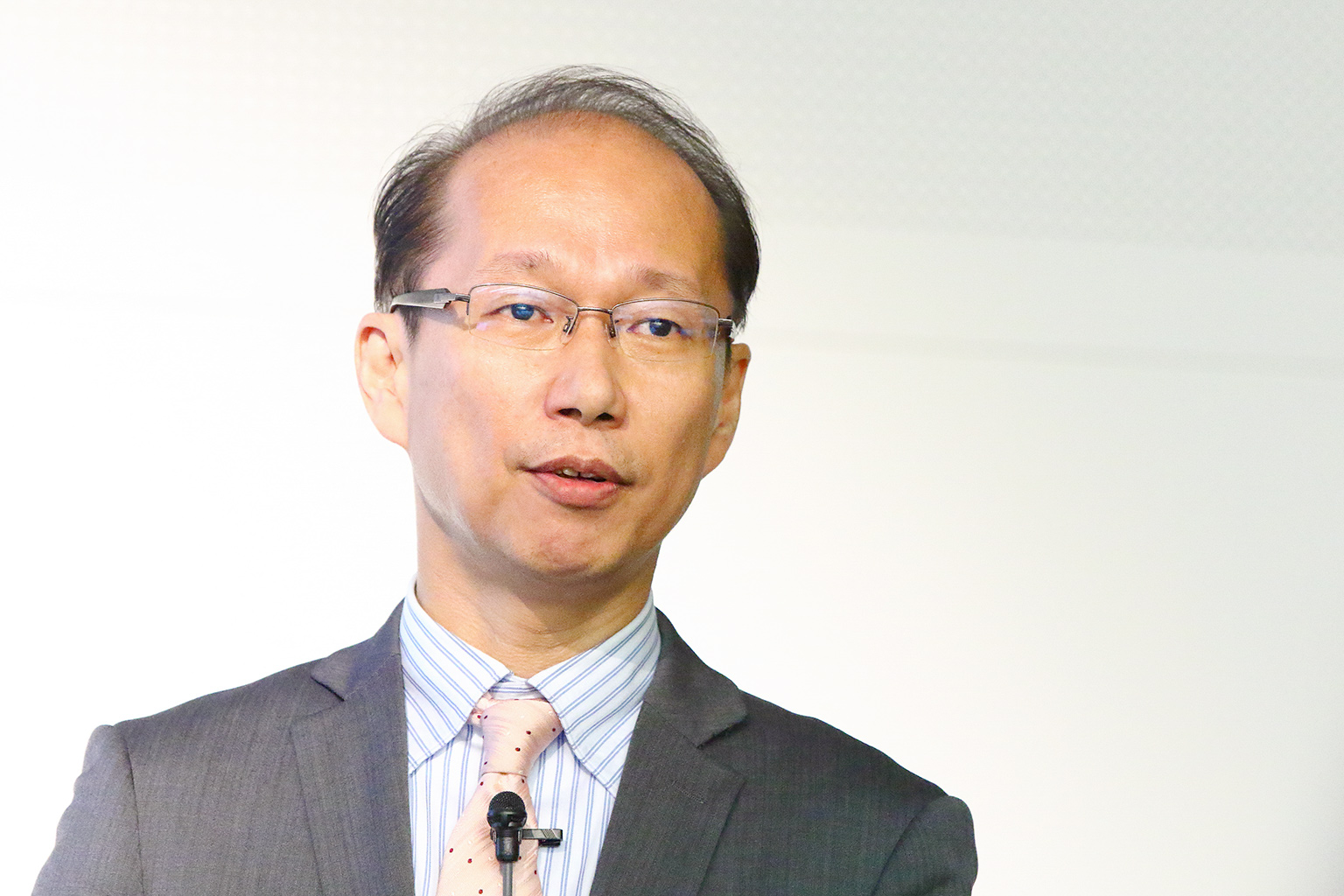
マーケティングにAIを活用、顧客への効果的なアプローチを実現
AI(人工知能)が急速に進化する中、マーケティング領域でAIを活用しようという動きが出始めている。企業のマーケティングを支援するアクティブコア代表取締役社長の山田賢治氏が、各企業に蓄積された顧客データをAIの活用により、顧客の嗜好に合わせ、適切なタイミングで効果的なアプローチを実現することで、よりよい顧客接点を創り出すためのポイントを語った。
コンバージョン(成約)率が1%程度から6.6%に向上

AI(人工知能)が急速に進化しています。先進的な企業では、このAIをマーケティング領域に活用しようという動きが始まっています。機械学習とは確率・統計モデルに基づくパターン認識のことです。与えられたデータからいくつかのパターンを認識・学習し、未知のデータを分類・予測します。機械が予測した結果を正解と比較し、その誤差からモデルを更新していきます。よく使われるアルゴリズムの1つがニューラルネットワークです。AIの多くはニューラルネットワークを使っています。ディープラーニングもAIの手法の1つです。ディープラーニングはニューラルネットワークを幾層も重ね、データを学習して特徴を自動的に抽出します。これがAIにおけるブレークスルーとなり、予測精度は大幅に向上しました。
マーケティング領域で進んでいるのは、企業が構築してきたプライベートDMP(データマネジメントプラットフォーム)に格納している顧客データ、広告データ、Web行動履歴、売り上げデータなどを分析・可視化し、ターゲット顧客を抽出して広告を掲示したり、メールやアプリで情報を配信したりレコメンドするプロセスに、機械学習やディープラーニングを取り入れたりする取組みです。そうすることで顧客の理解を深め、最適な顧客接点を創り出そうという試みが始まっています。

当社が手掛けている事例を幾つかご紹介します。1つは19,000人ほどのデータの中から、購買・コンバージョン(成約)しそうな顧客を予測し自動でセグメントする取組みです。Web行動履歴から資料請求につながる特徴を自動学習して学習モデルを作り上げ、学習を重ねてセグメントの精度を向上します。このモデルをBtoBの販促に活用したところ、送信したメールの開封率は54.7%に達し、コンバージョン率(資料請求)は通常1.0~1.2%のところ6.6%まで向上しました。
メールの配信時間の最適化も図っています。多くの場合、メールは配信後、数時間以内に開封されますが、それ以外の時間で開封する顧客もいます。メールを開封した時間、クリックしてウェブサイトにアクセスした時間、コンバージョンした時間などから顧客を自動分類。機械学習により配信時間を最適化します。従来12時に一斉配信していたものを1時間刻みにして個別配信したところ、開封率は19.1%から29.7%に上がりました。メールの開封率が上がればアクセス率、コンバージョン率も上がります。その結果をまた学習して次回以降の配信をさらに最適化しています。
AIは顧客の嗜好をあぶり出すのに有効なツール

レコメンドの最適化も進めています。レコメンドは性別、年齢、居住地、閲覧履歴、購入履歴など様々な要素が関係します。このレコメンドエンジンにディープラーニングを組み込んだアルゴリズムを実装しました。ディープラーニングで購入に相関の高い特徴量を自動で抽出してレコメンドする商品を発見します。その結果、マッチング率(レコメンド予測と実際に購入した実績データを比較)は従来の64.3%から78.0%に、コンバージョン率(レコメンド表示のリンクを実際にクリックしたユーザが該当商品を購入)は2.3%から2.8%に向上しました。
ABテストの自動化にも取り組んでいます。メール配信のABテストを自動化した事例を紹介します。 メール配信の対象ユーザの20%にABテストを実施して、その結果を統計モデルからどちらが効果があったかを自動で判定します。残りの80%に効果が高い方のメールを送信します。この一連の作業をAIで自動化します。 これまでテスト、検証後に改善し、実行していた作業を1サイクルでテスト、検証、実行と完結させることができます。
顧客接点に合わせたアプローチも自動化する取り組みを進めています。
ウェブサイトを閲覧後に店舗で購入するという事例も増えてきています。行動履歴データを分析し、メールやLINEで販促を行い、店舗に誘導するなど顧客接点の最適化を図っています。
機械学習・ディープラーニングを活用したプラットフォームを構築する上でのポイントは、第1にデータを顧客軸で整備・統合し、すぐに取り出せるようにすること、第2に学習モデルを複数持ち、最適なモデルを選択できるようにすること、第3に顧客の嗜好やタイミングに合わせることです。マーケティング領域においてAIは今後、画像認識、音声処理、データ分析・予測、自然言語処理と複数のディープラーニングの出力を統合して予測していくようになると考えています。顧客の嗜好、志向、思考は一人ひとり異なります。タイミング、興味・関心、ステータスなどをあぶり出していく上でAIは大きな役割を果たすものと考えています。
ゲスト事例講演Ⅲ 【“顧客起点”の組織変革】
流動客をインフルエンサー化する顧客体験アプローチ
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー
カンパニーエグゼクティブデピュティプレジデント
販促宣伝本部 本部長兼務
岡田 典一 氏

データ分析で顧客を理解、ターゲットや商品政策を見直す
業績低迷のトンネルに入り込んでいたプラザスタイル カンパニーは、2015年から顧客起点での改革を進めた。ポイントカード会員のデータ分析からコアターゲットを20代前半、コア商材を化粧品と絞り込み、施策の選択と集中を図った。インスタグラムと連動した店頭プロモーションで情報拡散を図り、新たな客層の来店につなげた。その一連の過程を同社の岡田典一氏が具体的に語った。
インスタグラムと連動した店頭プロモーションで、新たな客層の来店を促す

輸入雑貨店「プラザ」を運営するプラザスタイル カンパニーは2010年から5年間ほど客数が落ち込むトンネルに入り込んでいました。2015年、我々は「流動客をインフルエンサー化する顧客体験アプローチ」による改革に取り組み始めました。その中心的な戦術は「顧客理解と顧客化促進のための体制とコミュニケーション」です。
我々は従来、プラザのコアユーザーは20代後半から30代後半のOLと思い込んでいました。ところが「プラザパス」というポイントカード会員の年齢別買い上げ客数を分析した結果、19~24歳に最も大きなピークがあることが明らかになりました。全店に導入しているビーコンでこの年代の客層の滞在時間をはかると40代、50代よりも短い。店舗の滞在時間が長くなると売り上げが増えるという統計が出ていますから、19~24歳のお客様の滞在時間を長くする方法を考えることが重要ということです。
こうしたデータ分析から、我々はコアターゲットを20代前半、コア商材を化粧品に絞り込みました。あえて決めつけて絞ることで施策の選択と集中を図り、次の改革につなげたのです。改革を進めるために販促宣伝本部の組織変革も行いました。ポイントは「お客様が欲しい時に欲しい情報を欲しい形で出せる組織」にすること。ワントゥーワンでお客様に向き合うためにCRM、EC、オウンドメディアなどを販促部門に取り込みました。事業部門であるECを販促部隊に入れるというのはふつうではあり得ないことですが、お客様の立場で見れば、店頭であろうがECであろうが情報としては同じという発想で組織を構成しました。
店舗をメディアとして位置づけ、ユーザーに明確に示す

プラザの店頭では年間30本のプロモーションを行い、それに合わせて情報を流していますが、お客様の多くはメディアよりも店頭から情報を入手しています。店頭プロモーションが果たす役割は非常に大きい。ただ店頭プロモーションだけではお客様をインフルエンサー化することはできません。そのために力を入れているのがインスタグラムです。映画『怪盗グルーのミニオン大脱走』の公開前には店頭にミニオンズのフォトプロップスを設置。これを使って撮影した写真をインスタグラムに投稿してもらい、それを見た人がまた新たなお客様となって来店するという循環をつくり出しました。
店頭だけでインフルエンサー化する試みにチャレンジしたのが「I WRAP YOU」というイベントです。店頭でお客様を写真撮影し、その場で印刷し、ギフトラッピングに使いました。プレゼントされた人の驚きと感動は大きく、次々にギフトの写真をインスタに投稿したため、極めて拡散性が高い企画となりました。
2015年からの改革では、お客様の嗜好の多様化に対応するMD構築にも取り組みました。といっても、我々の規模のような会社はお客様のすべての要望に応えることはできません。「購入意欲が高いにもかかわらず購入金額が低い領域」をトライアンドエラーで探し出しました。個店ごとに対応するのでは非常に手間がかかるため、店舗をグループ化し、MDをパッケージ化して標準をつくりました。
またNTTドコモと手を組み「dポイント」を導入します。ドコモの持つDMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)の中から趣味・嗜好や購買傾向を分析し、顔の見えるお客様を新客としてつかんでいく考えです。ECが急成長している時代ではありますが、だからこそ、我々はメディアとしての小売店の位置づけをエンドユーザーに明確に示していきたいと考えて店舗を運営しています。
ゲスト対談 【次世代ECが創る、“顧客接点”とコミュニケーション】
マーケティングとテクノロジーで考える
次世代ECと組織への取り組みについて
オイシックスドット大地株式会社 執行役員 CMT(Chief Marketing Technologist) 西井 敏恭 氏
対談者:株式会社ビジネス・フォーラム事務局 進士 淳一

データベースを活用した定期購入型ビジネスモデルで競合に打ち勝つ
企業が顧客接点を考える際、ECはなくてはならない存在。有機野菜の宅配を手掛けるオイシックスドット大地はそのECにおいて、データベースを活用したサブスクリプション(定期購入)型モデルで競合他社の先を行く。CMOフォーラムの企画者であるビジネス・フォーラム事務局のプロデューサー、進士淳一が、オイシックスドットコム大地の執行役員CMT(Chief Marketing Technologist)である西井敏恭氏に質問する「ゲスト対談」のセッションでは、これからのECのあるべき姿が提示された。
購買履歴に基づいてお薦めリストを提示

進士: 西井さんはCMT(Chief Marketing Technologist)という役職に就いていらっしゃいます。CMOとは違うCMTという立場で、どのような取り組みをしているのですか。
西井: オイシックスドット大地では、マーケティングなど事業戦略は高島宏平社長を含む経営陣がトップダウンで構築していく部分と、事業部メンバーがボトムアップで構築する部分をミックスして実行しています。経営陣だけのトップダウンのみで事業戦略を押し進めていくと、社員とお客様との距離が遠くなってしまいます。社員すべてがマーケティング志向を持ち、お客様に近づき、ボトムアップでマーケティング施策を生み出すこと、それを吸収できるような体制をつくることが2014年にCMOとして入社した私の役割でした。
社内横断プロジェクトなどを推進し、2年ほどで社内全体がマーケティングに目を向ける文化ができたタイミングでCMTに就任しました。ITを活用しながら、より一層、デジタルマーケティングを推進する取り組みを始めています。デジタルマーケティングはテクノロジーが重要です。CMTになってから、マーケティングとともにシステムも管轄しています。今はテクノロジーを社内に浸透させようと教育などにも取り組もうとしています。
進士: オイシックスの特徴はサブスクリプション(定期購入)型のビジネスモデルを採用していることです。予算や配送日を指定した会員に対して、毎週、購買履歴に基づいてお薦めリストを提示する。データベースを非常にうまく活用してビジネスを展開しているという印象です。
西井: 私は以前、化粧品会社でECを担当していましたが、化粧品の場合、一人のお客様がECサイトにアクセスする頻度は年間3~5回程度、1回に購入する品目は2個程度でした。食品は週に1回はアクセスし20個ほどを購入します。得られる購入データ量が格段に多い。デモグラフィックデータと購入データを合わせると、お客様の食習慣をかなり正確に想像できます。「葉物野菜を何割買っているか」「何をリストから外したか」など、データを精緻に分析することでお薦めの精度を高めることもできます。オイシックスはEC中心でビジネスをしてきたため、そういうデータ分析能力、最適化能力が高い。その能力を生かしてサブスクリプションモデルを極めれば、決して負けないモデルがつくれると思っています。
顧客接点が多いECほど、UIの最適化が重要になる

進士: ECのアクセス頻度が高いということは、顧客接点が多く、触れている時間が長いということでもあります。ユーザーインターフェース(UI)をどう設計するかが重要ですが、どのような意識を持っていますか。
西井: 毎週使うのですから、UIはたいへん重要ですね。UIの使い勝手を良くすれば継続してたくさん使ってもらえます。顧客別にUIを変更できるような仕組みをつくり、一部のお客様に新しいUIを使ってもらって、購入金額がどう変わるかといったことも検証しています。私がオイシックスに入社してから最も力を注いだのがPCサイト、スマートフォンサイト、スマートフォン向けアプリケーションソフトの最適化です。以前は売り上げの6割はPCサイトによるものでしたが、今は2割まで縮小し、代わってアプリが3~4割に増えています。
進士: アマゾン・ドット・コムが「アマゾンフレッシュ」を始めたり、大手スーパーがネット通販に力を入れたりと、生鮮食品のネット通販は競合も激しくなりそうです。今後、オイシックスは次世代ECをどのように構築していきますか。
西井: 確かにアマゾンの存在は脅威です。米国ではEC市場の半分ぐらいをアマゾンが占めていますから。けれど、例えばファッションサイトのZOZOタウンはファッションに特化し、見た人が「買いたい」と思うサイトをつくって勝ち残っています。我々も生鮮食品に特化し、買いたくなるサイトをつくっていきたい。有機野菜の宅配というオイシックスのビジネスで、お客様との接点はまだ幾つも持てるはずです。例えば商品が届く瞬間、料理中、後片付けなどにも焦点を当てて考えたいですね。
今、カット済み野菜と調味料、レシピをセットにした「キットオイシックス」という献立キットがよく売れています。購入データでお客様の嗜好がわかるのですから、良いレシピ提案などもできるはずです。現在は宅配しかしていませんが、駅で取り置きしてもらえるような体制をつくればもっと便利になるでしょう。生鮮食品のECが浸透する中で「オイシックスの方がおいしい」「使いやすい」と感じてもらえるよう、食の体験を最適化するような新しい展開をしていきたいと思っています。
Panel Discussion
【これからの顧客接点・顧客関係構築における、コミュニケーションを考える】
顧客接点のリデザインと新たな価値提供にむけて
青山学院⼤学 経営学部 教授 ⼩野 譲司 氏
株式会社 東京海上日動コミュニケーションズ 執行役員 田口 浩 氏
日本ロレアル株式会社 長瀬 次英 氏
株式会社ニューバランスジャパン 鈴木 健 氏
株式会社アクティブコア 山田 賢治 氏
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 井上 千鶴 氏

顧客体験の最適化がマーケティングのカギ
デジタル化が進み、顧客接点が多様化している。あらゆる顧客接点で価値を提供し顧客体験を最適化することが企業のマーケティング戦略構築の重要な要素となっている。顧客接点を今後、どのようにリデザインするべきか。マーケティング、サービス・マネジメントを専門とする青山学院大学経営学部教授の小野譲司氏がモデレーターとなり、5人のパネリストが意見を交わし合った。
カスタマージャーニーにおいてどう接点をつくるか

小野: マーケティングの分野では、消費者がどのように商品やブランドと接点を持ち、関心を抱くようになり、購入や成約に至るのかという「カスタマージャーニー」や「顧客体験」に関する議論が盛んに行われています。「顧客接点」というキーワードで、皆さんの会社にはどのような課題があるととらえているか、聞かせてください。
鈴木: 顧客接点の中でニューバランスが重視してきたのは購買接点です。マーケティング費用の4割ほどを卸売先、流通店などの購買接点に充ててきました。今はメーカーでありながらも直営店、ECのような新しい購買接点をつくり、他の顧客接点に生かそうとしています。今後の課題は、購入前、購入後にどう接点をつくるかです。例えばランニングシューズは買って終わりではなく、必ずそのシューズを履いてランニングをするという場面があります。ランニング大会に協賛するとか、ランニングのプログラムを提供するとか、顧客の自己実現を支援するような接点を持つことも重要だと考えています。
長瀬: 日本ロレアル全社のデジタル化を推進するCDO(Chief Digital Officer)という立場でカスタマージャーニーの作成にかかわっていますが、そのパフォーマンスを見ようとした時にROI(投資利益率)をいかに計測するかが課題になっています。消費者が商品やブランドを認知してから購入に至るまでのジャーニーは実に多様です。ソーシャルメディアで情報をシェアする人、グーグルで検索する人、店舗で買う人、ECで買う人…。ステップは本当にバラバラなので、様々なツールを入れ、タッチポイントごとに見ようと努めています。
井上: オンライン、オフライン含めて、トリンプは顧客接点をたくさん提供しています。私が所属するオムニチャネル営業本部はリテール店舗、EC、CRMを束ねた組織で、顧客目線でアプローチし、顧客満足度を上げ、継続的に成長していこうという発想でつくられた部署です。これからは、どの接点でどういうベネフィットを提供するのか、お客様に喜ばれる顧客体験を最適化していく必要があると考えています。また、ライフタイムバリュー(LTV)を向上するためのコミュニケーションツールやコンテンツを見極めることも重要だと思っています。
田口: 国内のカスタマーセンターでは、最近、お客様からのコンタクトが音声からテキストに急激に変化してきました。各カスタマセンターは一斉にテキスト対応を始め、お客様の変化に追いつこうとしているところです。ただ費用対効果については、まだ十分に検証できていません。また、コンタクトセンター業界は、人材採用が大変難しくなってきており、人材不足とコスト削減のために、AIを導入し運用するケースも増えてきました。今後は、有人対応と無人対応をどのように最適に設計するかが課題です。
山田: 我々アクティブコアが手掛けているのはBtoBビジネスですが、この分野でもデジタル化の進化によって顧客が情報をいち早く入手するようになっています。企業はまずその情報収集の段階で、顧客から選ばれなくてはなりません。そのためにはオウンドメディア、コンテンツバリューの強化が課題だととらえています。
購入に結びつきやすい「ゴールデンパス」を見極める

小野: 一人の顧客が取引期間全体を通して企業にもたらす利益を表すLTVや、投資に対して生み出した利益を表すROIなどの数字に落とし込んだ時、カスタマージャーニーマップの作成や顧客体験の提供という視点は、それらの成果を上げるうえでどの程度、有効なのでしょうか。もし数値で可視化されているようであれば、それも踏まえてお話しください。
鈴木: LTVに関しては、短いスパンに限れば損益計算書(PL)で可視化している形になりますが、長いスパンでできているかというと難しいところがあります。例えば、コールセンターやコンタクトセンターはコストがかかるため、一生懸命削ろうとしがちです。そこから生まれるはずの価値を失う機会損失にまでは気が回らないことが多い。将来価値を現在価値に落としてマネジメントしている会社があれば教えていただきたいですね。
長瀬: カスタマージャーニーは戦略のベースになるものです。ROIとは分けて考えるテクニックも必要と思います。ブランドが評価される段階があるならば、ユーザーインターフェース(UI)や顧客体験をより良いものにするために積極的に投資すべきでしょう。例えばソーシャルメディアが頻繁にタッチポイントとして出てくるのであれば、そこでビジネスパートナーシップを構築し、クーポンを提供したり、先行的に新しいツールが使えるようにしたりすることが顧客にとっての価値創造につながります。
井上: お客様が購入に至るまでの過程には、「どこかで得た情報」が巡りめぐって、最後にインターネットで検索することによって到達するというケースもあります。ROIを見るには、それらのタッチポイントを把握した上で総合的に、はかれるような仕組みが必要です。一方、LTVについては、ラインナップを豊富に取り揃え、年代別のニーズの移り変わりに加え「ラグジュアリーな下着を身につけたい」とか「着心地のいい下着を選びたい」といったお客様のオケージョンごとのニーズを理解し提供することで自ずと上がると思います。過去のデータを見て、購入に結びつきやすい最適な「ゴールデンパス」を見極め、コミュニケーションを取っていくことが重要だと思います。
顧客接点では人が感情的なつながりをつくる
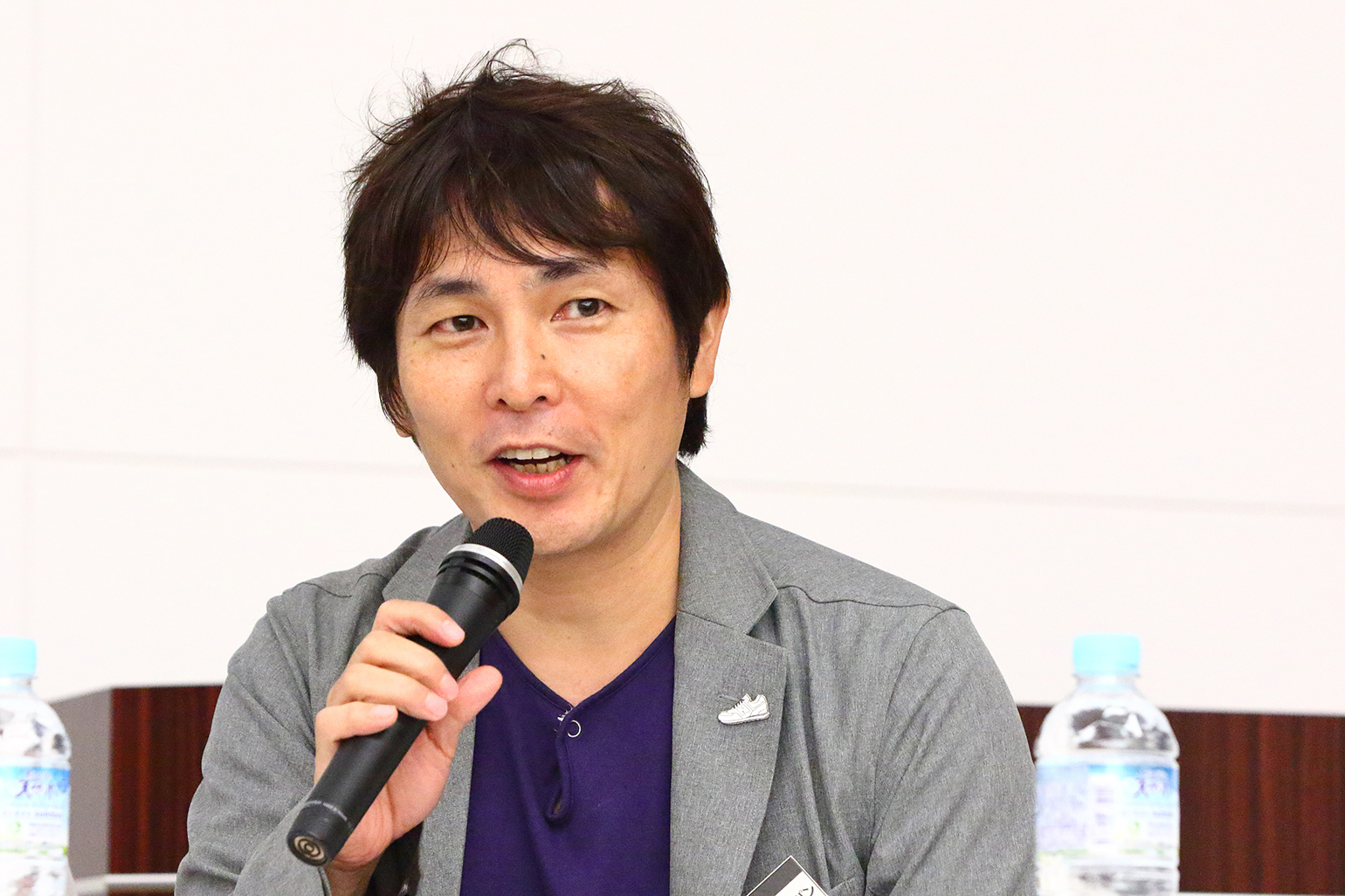
小野: 顧客接点において人が果たす役割は非常に大きいと考えます。人と接点を持つ時というのは良い面も悪い面も感情が生まれやすく記憶に残りやすい、と考えられるからです。そういう意味では東京海上日動コミュニケーションズが設置しているようなコンタクトセンターは、その最前線に立っている重要な存在といえますね。
田口: AIの導入など無人対応化が進み、コンタクトセンターでもお客様と人との接点が少なくなっています。お客様と接する機会をとらえ、どう価値を提供するかが重要です。いろいろ研究してみてわかったのは、社員満足(ES)がお客様満足(CS)に影響しているということです。ESが上がるにつれてCSも上がり、お客様から「本当に助かりました。ありがとう」「次もお世話になりたいから名前を教えて」といった感情のこもったお礼を言われる機会が増えました。また、お客様からの感情のこもったお礼は、社員のモチベーションアップにもつながり、「お客様のためにもっと頑張ろう」となって良いサイクルを生みます。企業は、AIやITへの投資とともに、社員への投資も重要です。

小野: 消費財ブランドも顧客接点における人の役割は大きいと思いますが、いかがでしょうか。
長瀬: 化粧品はブランドエクスペリエンスがすべてといっていい商材です。カスタマーセンターにも非常に力を入れています。AIの導入も始めていますが、プレミアムブランドとして価値を提供しようという時にAIはどうなのかと疑問に感じるところもあります。特に日本人はその辺りの感覚が難しいですから。時代に逆行するかもしれませんが、日本では24時間、人が対応するカスタマーセンターをつくる構想も持っています。
小野: アクティブコアはマーケティングデータやウェブサイトの行動履歴を統合して分析することで企業の経営を支援しています。顧客接点や人について、どんな問題意識を持っていますか。
山田: 以前の企業にとって顧客接点として重要だったのは、営業マンが最初に訪ねる段階でした。そこで資料や動画を使って製品やサービスを一通り説明していました。しかし、今ではお客様は事前にそういう情報は手に入れています。お客様を訪ねる時にはクローザーが登板することが必要です。企業は社員を成長させ、クローザーとしての力を付けさせることが必要になっていると思います。

小野: 今後、顧客接点のリデザインはどういう方向に向いていくのでしょうか。未来の方向性を一言ずつお願いします。
井上: キーワードは「シームレス」だと思っています。バックオフィスもフロントもシームレスにお客様にアプローチできるように注力していきたいと考えています。
鈴木: 今、ブランドが手掛けているコミュニケーション、サービス、ショッピングはひとつの塊のようなものだと思っています。例えばスターバックスはコーヒーを売っていますが、コーヒーを売るだけでは成立しないビジネスです。店舗があって、そこで働く店員がいて、ブランド体験できるのです。ニューバランスでもバラバラになっている接点を垂直統合し、ブランドをマネジメントしていきたいと思います。
長瀬: どれだけマーケティングツールを導入しても、店にモノがそろっていないとか、在庫管理が追いつかないといったことがあればブランドエクスペリエンスは完成しません。デジタルツールを最大限に活用しつつ、社内の業務を最適化した新しいエコシステムを早急につくらなくてはいけないと思っています。
田口: これから重要なのはカスタマー・エンゲージメントです。お客様と感情的なつながりをつくることでLTVは向上します。どのようにそのつながりをつくるかを考えていきたいと思っています。
山田: 顧客接点の1つである顧客サポートについて、昨年からすべての履歴をデジタル化し、時系列でデータベースに入れることを始めています。効率という点では劣るかもしれませんが、ここから新しい知見を得て価値提供につなげられるのではないかと期待しています。うまく活用していきたいと考えています。

