シリーズ マネジメントの未来@Business Forum
Corporate value strategy 2021
資本コスト経営と事業ポートフォリオ戦略
~未来を創る意思決定と競争優位性の実現に向けて~
開催概要
開催日時
- Online2021年 3月3日(水)11:00~16:50
開催趣旨
改定コーポレート・ガバナンス・コード(2018年6月公表)において、資本コストを意識した経営の必要性が初めて盛り込まれ、2020年7月に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」では、“更なる中長期的な企業価値の向上を目指し、事業ポートフォリオ戦略の実施など資本コストを踏まえた経営の更なる推進”(スピンオフを含む事業再編を促進するための実務指針との連携も検討する)が謳われた。新型コロナウイルス感染症拡大による市場環境の劇的な変化は、経営者にとって事業の選択と集中、そして自社事業の競争優位性の確立を再考する大きな契機となっており、資本コストを意識した経営の判断と運営がますます求められるだろう。
資本コスト経営とは何か?企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、日本企業に弱いとされる攻めのガバナンスを実現するために今求められるであろうマネジメント施策である。しかしながら、資本コストそのものは算出方法や前提条件で推定結果も異なり、また事業部門ごとの資本コストなどは的確に把握することが困難であったりなど、資本コストをどう捉え、経営の意思決定に活かしていくかは企業や経営者によってまだまだ差があるであろう。不確実性の先の見えない時代に、企業は、事業ポートフォリオの見直し、ノンコア事業の切り出し、両利き経営を一層進める必要がある。特に大企業については、企業価値向上のために、事業再編を積極的に行っていくことが重要である。機動的な選択と集中を図り、真の競争優位性を確立して、いかにして企業価値の向上を実現するか。そして、資本コスト経営をその実現の中でどのように活用していくべきなのか。
未曽有の混乱を最大のチャンスに変えていくべくスタートした、シリーズ「マネジメントの未来」。今回のフォーラムでは、「資本コスト経営と事業ポートフォリオ戦略」にフォーカスを当て、ROIC経営の実践や未来を創るであろうマネジメントの意思決定、事業の競争優位を実現するための構造改革などについて、様々な視点から議論を進めていきます。攻めのガバナンスにチャレンジする先進企業をお迎えし、COVID-19後の世界を生き抜くために今為すべき施策として、そして新たな世界で戦うためのキーファクターについて検証していきます。
概要
|
参加対象者 |
経営者、役員、CFO、経営企画、ファイナンス/経理財務部門、IR、総務部門、 |
|---|---|
|
参加料 |
25,000円(税込み/お一人様) |
|
参加定員 |
200名(事前登録制) |
|
参加形式 |
オンライン配信(ライブ視聴&1ヶ月間のオンデマンド視聴) ※本セミナーはオンラインでの配信となります。視聴方法はお申込み後にご案内いたします。 ※お申込者でない方への視聴用URL共有はご遠慮ください。同じ会社内で複数名でのご参加を予定されている場合にも、お手数ですがお一人ずつお申し込み下さい。 ※登録時のメールアドレスに登録完了メールを送付いたしますが、万が一届かない場合、大変お手数ですが、customer1@b-forum.netまでご連絡ください。 |
|
主催 |
株式会社ビジネス・フォーラム事務局 |
|
協賛 |
プログラム詳細
11:00~11:40 基調講演 【資本コストと企業価値向上】
コロナ禍における企業価値向上に向けて
~ROIC経営の実践と日本企業の課題~
- 攻めのガバナンス改革の現状と課題
- withコロナ時代における資本生産性を高めるためのカギ
- 企業価値向上に向けて~経営者、CFOが果たすべき役割とは

一橋大学 CFO教育センター長
経営管理研究科 経営管理専攻 名誉教授
伊藤 邦雄 氏
一橋大学 CFO教育研究センター長。1975年一橋大学商学部卒業。1980年同博士後期課程単位修得、一橋大学商学部専任講師。92年同教授。その後、商学部長・商学研究科長、副学長を歴任。2015年より現職。中央大学大学院戦略経営研究科特任教授を兼務する。商学博士 (1996年) 。専門は会計学、コーポレートガバナンス論、企業分析・評価論。2017年より経済産業省「持続的成長のための長期投資 (ESG・無形資産) 投資研究会」の座長を務め、「伊藤レポート2.0」を公表。また2018年には同省の「SDGs経営/ESG投資研究会」座長。2019年より「TCFDコンソーシアム」会長。
11:40~12:10 協賛講演 【ROIC経営とDX】
ROIC経営に向けた日本企業のチャレンジ:グローバル×ガバナンス×DX
- ROIC経営の前提となるグローバルオペレーションの透明性向上
- グローバル企業の資本効率向上に必須となるガバナンスとデジタル
- 欧米グローバル企業が試行錯誤の結果たどりついた新たなDXの姿
- 日本企業のチャレンジをためらわせるDXへの誤解を解く
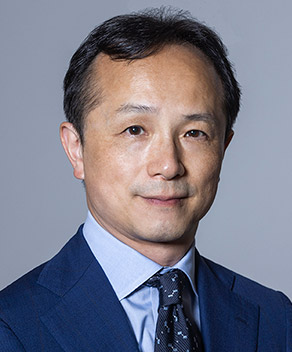
Celonis株式会社
代表取締役社長
小林 裕亨 氏
Celonis株式会社 代表取締役社長。1988年東京大学工学部卒業。1992年米国カーネギーメロン大学経営学修士。1988年にアーサーアンダーセン(現アクセンチュア)、1992年に戦略コンサルティング会社アーサー・D・リトル社にて経営コンサルタントとして従事したのち、1997年にマイクロソフトにてインターナショナル・ポートフォリオプラナーとして日本を含むアジア地域の事業開発に従事。2002年に経営コンサルティング会社であるジェネックスパートナーズを共同設立し大企業のトランスフォーメーション及びPEファンド投資先の企業価値成長に従事。2019年に、AIを活用したプロセスマイニングとプロセスエクセレンスのマーケットリーダーであるソフトウェア会社、Celonis株式会社を設立し現職。
講演内容のポイント
ROIC経営を志向し資本効率を高めるためには、投資事業の選定(最適なポートフォリオ構築)とともに、投下した資本をもとに現有組織の力をフルに発動して最大の成果を出しきるオペレーション体制が必要となる。グローバルで活躍する多くの日本企業が既存事業のポテンシャルをフルに発揮するためには、まずはグローバルオペレーションの透明性を高めた上で効率性を追求しなくてはならない。そのためには、デジタルによるトランスフォーメーションが必須である。ただし、それは眼前の繰り返し手作業を自動化するという小手先のものではなく、ガバナンスの確立も視野に入れたものでなくてはならない。よって、経営トップが組織をリードし事業の戦略立案から実行そしてその監視までend-to-endでDXを採り入れた体制を確立すべきである。この戦略からDXを取り込む俯瞰的で創造的な視点を持つことは、これまでカイゼンで成功体験を積み上げてきた日本企業にとってはチャレンジである。しかし、この体制を実現することが今後の飛躍を約束する鍵ともなっている。講演では、シーメンスなどROICに優れたグローバル企業が試行錯誤を経て、いかにDXをend-to-endで活用するグローバルオペレーションの構築に取り組み、成果を上げて来たかを事例とともにご紹介します。
12:10~13:00 休憩
13:00~14:00 特別講演 【経営視点からの資本コスト経営】
AGCにみる“両利きの経営”の実践
~未来を創るマネジメントに求められるもの
- 両利きの経営を実現した2015年からの経営改革
- 事業ポートフォリオの見直し、組織・カルチャー変革
- 事業の競争優位を実現する意思決定を目指して~CFO、経営企画部門の役割

AGC株式会社
代表取締役 兼 副社長執行役員
CFO、CCO、経営企画本部長
宮地 伸二 氏
上智大学理工学部機械工学科卒業。ハーバードビジネススクールAMP修了。精密機器メーカーでITエンジニアとして勤務後、1990年旭硝子(現AGC)入社。システム部門を経て経営企画部門に配属され、中期経営計画、ガバナンス改革などを担当。その後、国内関係会社社長、新規事業部門長、経営企画部門長、米国関係会社社長、電子部材部門長など幅広い分野での経験を経て、2016年1月CFOに就任、現在に至る。
講演内容のポイント
世界トップレベルの技術を強みに、「ガラス」「電子」「化学品」「セラミックス」の事業領域で日本・アジア、欧州、米州、3極体制をベースに30を超える国と地域でグローバル事業を展開しているAGC。2000年代に売上、ROEが長年停滞する中で、2015年に高収益な事業体への変革を目指し、事業ポートフォリオの見直しや組織・カルチャー変革などを柱とした経営改革に踏み切った。長期安定的な収益基盤となる「コア事業」と高い成長を目指す「戦略事業」を2つの柱と設定し、経営資源の配分方針と戦略の方向性を明確化、社内指標としてROCEを採用し、全社として10%以上をターゲットにその改革を進めている。既存事業の深化と新しい事業への探索、その取組みは、スタンフォード大学経営大学院のケーススタディにも採用され、『両利きの経営』を実践していると評価されている。その改革を牽引し経営の舵取りを担う、代表取締役 兼 副社長執行役員の宮地氏を迎え、これまでの改革の道のり、そして『両利きの経営』と評されるマネジメントの意思決定はどのように実践されたのか、そのキーファークターなどについてお話しいただきます。
14:00~14:30 協賛講演 【フレームワークと先進のEPMツール】
ROIC経営を実現する意思決定プラットフォーム ~経営管理・BI:Boardとは?
- ROIC経営・事業ポートフォリオ戦略を推進するフレームワーク:EPM
- 未来をデータで把握するEPMフレームワーク実現のための要件とは
- Board経営管理プラットフォームのご紹介 EPM:Enterprise Performanece Manegement

一般社団法人日本CFO協会主任研究委員
株式会社アカウンティング
アドバイザリー マネージングディレクター/公認会計士
櫻田 修一 氏
1985年にアーサーアンダーセン入所、元アーサーアンダーセン ナショナルパートナー。監査部門での8年間の会計監査業務および株式公開支援業務を経て、同ビジネスコンサルティング部門に転籍。経営・連結管理、会計分野を中心とした、経営・業務改革コンサルティングおよびERPシステム導入コンサルティング、プロジェクトマネジメントを手がける 。2010年に創業メンバーとしてアカウンティング・アドバイザリーを設立。現在はIFRS財務諸表作成・導入コンサルティング、過年度遡及修正支援、さらにEPM(経営管理)・連結会計システム・ERP導入などシステム関連プロジェクト実行支援サービスを提供している。

Board Japan株式会社
カントリーマネージャー
篠原 史信 氏
Business Objects社から、Oracle、Hyperion、SAP、Adaptive Insightsと、現場のデータ活用から情報戦略、PSI、管理会計、BSC、TOCなど多くの「情報活用」を提案してきた。2018年より現職。現在は、EPMが暦年の課題感の答えであると考え、DXを実現する重要なテーマとして提案を続けている。欧米と異なり、情報活用を最大活用できていない日本企業を、欧米企業の組織や考え方と対比し、どう導入すれば適切な業務として実現できるか色々な意見をもつ。計画系システムの改良を行い、情報の時間軸での断絶、本部と現場の組織での断絶の2つのギャップを埋める事で、朝令暮改に対応できる組織、変化に追従できる組織が実現できると主張している。
講演内容のポイント
VUCAの時代と呼ばれるように環境変化スピードが速い現代において経営意思決定に必要な情報は、過去の分析から将来予測重視にシフトしさらにはマーケット・顧客など企業外部の情報まで拡がりをみせています。このためには多くのデータを収集・統合・処理する必要がありテクノロジーの活用が必須と考えます。さらに資本コスト概念を取り入れたROIC経営・事業ポートフォリオ戦略を推進・実現するための全体像・フレームワークを理解し、意思決定プラットフォームとして構築しなければなりません。これを実現する概念・システムをEPM=Enterprise Performance Management と呼びます。本セミナーでこのフレームワーク、必要とされるデータおよびシステム要件の概要そしてEPMツールであるBoardをご紹介します。
14:40~15:40 事例講演 【企業価値向上と経営管理】
グローバル市場で競争優位性をいかにして実現するか
~村田製作所に見る企業価値向上の取り組み
- マトリックス経営と経営管理制度
- ポートフォリオ経営の実践と事業性評価モデルによる成長戦略
- 経営管理機能のトランスフォーメーション~更なる価値向上への挑戦

株式会社村田製作所
取締役 上席執行役員
企画管理本部 経理・財務・企画グループ 統括部長
南出 雅範 氏
1987年4月 株式会社小松村田製作所 入社。2010年10月 株式会社村田製作所 企画部 担当部長、11年3月 Murata Electronics Singapore (Pte.) Ltd. Managing Director、16年8月 企画管理本部 経理・財務・企画グループ 企画部 部長、17年7月 企画管理本部 経理・財務・企画グループ 統括部長(現在)。18年7月 執行役員 就任、19年6月 取締役 上席執行役員に就任、現在に至る。
講演内容のポイント
“Innovator in Electronics”をスローガンに掲げ、最先端の技術、部品を創出する総合電子部品メーカーの村田製作所。海外売上高比率は90%にのぼり、日本発のグローバル企業として、マトリックス経営の実践と独自の経営管理システム(価値創造モデル)で、長期にわたる企業価値向上を実現している。同社におけるROIC経営とはどのようなものか。また、激しい市場環境の変化、事業成長に伴う会社規模の拡大や組織の肥大化、そして進化するITテクノロジーへの対応など、近年におけるこれらの経営課題に対して、価値創造モデルの更なる進化とグローバル市場で持続的な事業成長を果たすため、経理・財務及び経営企画機能のトランスフォーメーション(変革)をスタートしている。その改革を牽引する南出氏を迎え、これまでの取り組みと「自律分散型経営」の実現に向けた挑戦の一端をご紹介いただく。
15:45~16:50 パネルディスカッション 【経営判断と事業成長】
資本コスト経営と事業ポートフォリオ戦略~未来を創る意思決定と競争優位性の実現に向けて~
- 各社の取組み、実践にあたっての課題
- 攻めのガバナンスと事業ポートフォリオ改革
- コロナ禍における企業価値向上に向けて~課題と展望

パネリスト
日清紡ホールディングス株式会社
代表取締役社長
村上 雅洋 氏
1982年⽇清紡績株式会社(現⽇清紡ホールディングス株式会社)⼊社。4つの事業場において、⼯場付属学園の運営や寮管理・運営を起点に、採⽤や安全衛⽣など⼯場労務管理業務に従事。その後、本社⼈事部での⼈事制度設計や⼈財教育等の業務を経て、2002年より研究開発センターにて新規事業の⽴ち上げに従事。06年より秘書、法務、財務・経理、⼈財部⾨および不動産事業の責任者を経て、10年 取締役 事業⽀援センター⻑、14年 取締役 経営戦略センター⻑、18年6⽉より代表取締役副社⻑、19年3月、代表取締役社長に就任、現在に至る。

パネリスト
味の素株式会社
代表取締役 専務執行役員
グローバルコーポレート本部長 兼 コーポレートサービス本部長
栃尾 雅也 氏
1983年4月、味の素株式会社入社。タイ味の素株式会社出向、タイ味の素冷凍食品株式会社出向などを経て、2007年7月 味の素株式会社 食品カンパニー海外食品部長、11年6月 執行役員 経営企画部長、13年6月 取締役常務執行役員、17年6月 取締役専務執行役員、19年6月 代表取締役 専務執行役員 グローバルコーポレート本部長 兼 コーポレート本部長に就任、現在に至る。

パネリスト
オムロン株式会社
取締役
社長指名諮問委員会、人事諮問委員会、報酬諮問委員会 各副委員長
安藤 聡 氏
1977年慶應義塾大学法学部卒業、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、資産運用業務や米国・インドネシアでの海外勤務などに従事した後、2007年同行退職。同年オムロン株式会社に入社し、常勤監査役、2011年執行役員経営IR室長、2015年執行役員常務グローバルIR・コーポレートコミュニケーション本部長を経て、2017年6月取締役に就任し、現在に至る。
<主な社外活動>
経済産業省主催「伊藤レポート」、「株主総会のあり方検討分科会」、「持続的な価値創造に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)のあり方検討会」などの研究会に委員として参画。一橋大学CFO教育研究センター客員研究員、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)主催「企業・アセットオーナーフォーラム」企業側代表幹事、公益財団法人 国際高等研究所 評議員、内閣府主催価値デザイン経営ワーキンググループ委員、兼任。

モデレーター
一橋大学 CFO教育センター長
経営管理研究科 経営管理専攻 名誉教授
伊藤 邦雄 氏
16:50 終了
※ プログラム内容や時間は急遽変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

