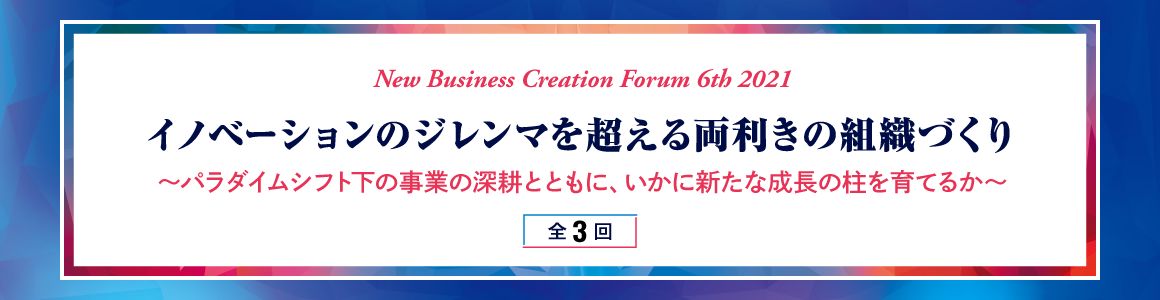
開催概要
開催日時
-
Vol.1<組織経営編> オンデマンド配信
(※11/1~12/1までの約1カ月間)Vol.1<組織経営編> オンデマンド配信
(※11/1~12/1までの約1カ月間) ※申し込みは終了いたしました -
Vol.2<人材戦略編> Live配信 2021年11月12日(金)13:00~16:35 (予定)Vol.2<人材戦略編> Live配信 2021年11月12日(金)13:00~16:35 (予定) ※申し込みは終了いたしました
-
Vol.3<事業戦略編> Live配信 2021年11月17日(水)13:00~16:35 (予定)Vol.3<事業戦略編> Live配信 2021年11月17日(水)13:00~16:35(予定) ※申し込みは終了いたしました
※Vol.1に11月1日以降お申込みの場合、お申込み後3営業日以内に視聴URLを送付いたします。
※Vol.2、Vol.3も、開催後はオンデマンド配信(約1カ月間)でご視聴いただけます。
開催趣旨
世界的なパンデミックにより、多くの企業がこの有事をどう生き抜くかという未曾有の困難に直面し、かつてのビジネスモデルそのものの見直しや、新たな成長領域となる事業・サービス創出をはじめとする「第二の創業」の必要性に迫られています。
しかし、こうした非連続的な変化の時代において、企業にとって過度な選択と集中はリスクであり、今後は「変化に適応する柔軟性を備えること」が新たな競争優位となっています。実際、これまで多くの成熟企業が数々の新規事業に着手しつつも真のイノベーション創出に繋がらない大きな理由として、新規事業が既存の事業に潰されてしまう所謂イノベーションのジレンマに陥っています。既存の主力事業とこれまでのマネジメント方法ばかりに囚われることでは、大きな変革へ脱却することは難しいのが現状です。
このような中、昨今、世界的な経営・組織進化論として「両利きの経営」理論が注目されています。既存事業の強化(既存の資源の深堀・活用)と同時に、新たな成長事業の発掘・育成を行い、それら両方を併存させる“両利き”の視点での組織経営が求められているのです。変化に適応し持続的な成長を目指すためには、事業ポートフォリオや経営資源の配分はもちろんのこと、既存事業と新規事業のそれぞれ相矛盾する領域をいかに両立させ、マネジメントするか、その組織構造設計や行動を促すための仕組みを含む、経営・組織能力そのものが問われています。
では、こうした時代を勝ち抜くために、企業は今、具体的にどのような要点のもと戦略と打ち手の見直しを図るべきなのでしょうか。
本セミナーでは、両利きの理論とその実践事例をもとに、主に「組織経営の視点」「人材戦略の視点」「事業戦略の視点」それぞれの視点から、今こそ成熟企業におけるイノベーション、新たな成長の柱の創出に向けた変革の方向性とアプローチについて考察します。経営・マネジメントに携わる責任者の方々へ向け、両利きの組織づくりを推進していくための具体的な方法を紐解き、検証していくものです。
概要
|
参加対象者 |
経営者・役員、および経営企画、事業企画、事業開発、人事、他各事業部門、改革関連部門の意思決定層の方々 |
|---|---|
|
参加料 |
Vol.1 組織経営編(オンデマンド配信) 12,000円(お一人様 / 税込み) Vol.2 人材戦略編 18,000円(お一人様 / 税込み) Vol.3 事業戦略編 18,000円(お一人様 / 税込み) ※複数回お申込の方は、一律5,000円割引を適用させていただきます。(ご招待の場合は除く) ※Vol.1に11月1日以降お申込みの場合、お申込み後3営業日以内に視聴URLを送付いたします。 ※Vol.2、Vol.3も、開催後はオンデマンド配信(約1カ月間)でご視聴いただけます。 |
|
参加方法 |
オンライン配信 ※本セミナーはオンラインでの配信となります。視聴方法はお申込み後にご案内いたします。 ※お申込者でない方への視聴用URL共有はご遠慮ください。同じ会社内で複数名でのご参加を予定されている場合にも、お手数ですがお一人ずつお申し込み下さい。 ※登録時のメールアドレスに登録完了メールを送付いたしますが、万が一届かない場合、大変お手数ですが、customer1@b-forum.netまでご連絡ください。 |
|
主催 |
株式会社ビジネス・フォーラム事務局 |
|
協賛 |
プログラム詳細
Vol.1 <組織経営編> オンデマンド配信(※11/1~12/1までの約1カ月間)
※本Vol1プログラムは、8/31にライブ配信した内容のオンデマンド配信となります。
特別対談セッション (約100分間)
両利きの組織づくりと経営 ―実践知に学ぶ、その要諦
Ⅰ.両利きの組織づくり ~AGC事例から考察する、理論と実践~
- 両利きの組織とその特徴
- 成熟企業にこそ求められる組織の再構築 ~組織課題をめぐる変遷~
- 「攻めと守り」「既存事業と新規事業」を両立させる、戦略・組織のバランスと重心
- AGCにおける両利きの経営
Ⅱ.AGCが挑む、変革の取組みと要諦 ~組織体制づくりとカルチャー変革~
- AGCが直面していた課題と変化までの道程
- イノベーションを生むための「分離と統合」のプロセス
- 既存事業と新規事業のつなぎ方
- 異なる事業と組織、カルチャーをどう束ねるか
- 組織構造とマネジメントの改革
- 両利きの組織に求められる、経営層・マネジメントの役割
Ⅲ.質疑応答

AGC株式会社
取締役会長
島村 琢哉 氏
1980年 旭硝子株式会社(現AGC)入社。2003年 アサヒマス・ケミカル株式会社 社長、2009年 旭硝子(現AGC)執行役員 化学品カンパニー企画管理室長、2010年 執行役員化学品カンパニープレジデント、2013年 常務執行役員 電子カンパニープレジデントを経て2015年 代表取締役社長 執行役員 CEO就任。2021年1月 代表取締役会長。同3月より現職。

株式会社アクション・デザイン 代表取締役
エグゼクティブ・コーチ・組織コンサルタント
早稲田大学ビジネス・スクール 非常勤講師
加藤 雅則 氏
株式会社アクション・デザイン代表取締役、エグゼクティブ・コーチ・組織コンサルタント。「両利きの経営」の提唱者であるオライリー教授の日本における共同研究者。日系企業の組織力学を熟知した変革支援者として、20年にわたり企業の組織開発に携わる。早稲田大学ビジネス・スクール非常勤講師。主著に「両利きの組織をつくる」など。
Vol.2 <人材戦略編> 2021年11月12日(金)
13:00~ <特別対談> 【イノベーター人材の発掘と活用・育成】(50分間)
イノベーション創出のための人・組織づくり
~イノベーターの要件から紐解く、企業における活用・育成のあり方
- 日本企業のイノベーション創出、イノベーター輩出における課題と特性
- 企業内イノベーターの資質、人材を生かすリーダー・マネジメントの役割
- 戦略としての組織デザインとエコシステム

東京大学大学院経済学研究科 特任教授
東京大学グローバルリーダー育成プログラム(GLP/GEfIL)推進室兼任
半田 純一 氏
日本の製造業企業での勤務後、約17年間に渡り、マッキンゼー、A.T.カーニーなどにて、戦略からイノベーション、組織・人事等、広範囲のコンサルティング支援や経営に従事。その後、企業のリーダー育成に力点を置いたコンサルティング会社を起業。2013年から、武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー人事部長として同社の変革を牽引。2016年4月より現職。経済同友会会員。組織学会会員。主な著作に、『リアル企業内イノベーター』(日本経済新聞出版社、2021)『100年企業の研究(東洋経済新報社、2004)』等。経済同友会の企業白書「新・日本流経営の創造」(日・英、2009)の共同主執筆者。ハーバード大学経営学大学院修了(MBA)、東京大学社会学科卒。

オムロン株式会社
技術・知財本部 副本部長 兼
オムロン サイニックエックス株式会社
代表取締役社長
諏訪 正樹 氏
1997年 オムロン株式会社入社。入社以来、画像・光センシングの研究開発に従事。ファクトリーオートメーション向け画像処理装置や画像型車両感知器などの商品化にも携わる。 2018年より技術・知財本部に籍を置きつつ、オムロン サイニックエックス株式会社 代表取締役に就任。2021年よりオムロン株式会社 技術・知財本部 副本部長に就任。奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科および九州工業大学大学院 生命体工学研究科 客員教授なども務める。
講演のポイント
創業以来「ソーシャルニーズの創造」を掲げてきたオムロン。まさにそのイノベーション精神を体現した“出島”のような存在として、全社のイノベーション加速化と“近未来デザイン”創出のため2018年に設立されたOSX。既存組織とは異なるバックキャスト型の探索アプローチや組織のルール・評価のもと、多様な外部人材を集め、社外を含めたエコシステムを形成することで人材流動化による探索活動の活性化へ挑戦されています。―日本の大企業においてイノベーションは起こせるか。OSXの組織を牽引する諏訪様と、イノベーターの特性や育成、特に大企業におけるイノベーション/エコシステム研究に詳しい半田様の対談を通して、この至上命題の肝となる「人材」とそのマネジメントのあり方を紐解きます。
14:00~ <特別講演>【革新を支える人財・組織改革】(45分間)
イノベーション創出のための成長基盤改革と人・組織づくり
~中外製薬が目指す、トップイノベーターへの挑戦~
- トップイノベーターを目指すための成長戦略と構造改革
- ポジションマネジメントとタレントマネジメントの連動
~イノベーション加速のための適所適材とリーダー人財創出の取組み~ - チャレンジを促す組織風土の醸成、人事評価制度、自律的な学び/成長の支援、新しい働き方等

中外製薬株式会社
執行役員 人事部長
矢野 嘉行 氏
1986年 中外製薬株式会社入社。営業本部、国際本部、5年の海外駐在を経験したのち、経営企画部マネジャー、調査部長を歴任。2016年から人事部長となり、2019年に執行役員 人事部長(現任)。
講演のポイント
世界最大の製薬会社スイス・ロシュ社と戦略的提携を結び、ビジネスモデルの再編により急成長を遂げている中外製薬。直近10年間で営業利益を5倍超に伸ばし、革新性と創薬力で時価総額国内業界トップに躍進しています。さらなる成長と世界のトップイノベーターを目指し挑戦を続ける同社では、その基盤となる「人・組織」の改革を重点に掲げ、2020年には新たな人事制度を開始するなど、特に事業戦略を実現させるための適所適材と中長期的なタレントマネジメントの高度化、リーダー人財の育成に注力しています。業界を取り巻く環境変化も激しさを増す一方、革新性を武器に成長を続ける同社の、そのイノベーション創出の土台となる人・組織づくりの現在地とは、如何なるものか。先端を行く改革の舵取りを担う矢野様よりお話いただきます。
14:45~ <協賛講演>【人的資本の高度化とHRテクノロジー】(25分間)
人的資本経営を支える Oracle Cloud HCM
- 人的資本経営におけるHRテクノロジーの活用
- 人事戦略におけるDX・従業員エンゲージメント・生産性向上
- オラクルコーポレーションの事例紹介

日本オラクル株式会社
クラウド・アプリケーション事業統括
ERP/HCMソリューション・エンジニアリング本部
HCMソリューション部 部長
矢部 正光 氏
大学卒業後、国内SI企業にてHRソリューションを担当。数多くのHRソリューション提案・導入活動に加え、ソリューションの商品企画・事業計画にも携わる。その後、コンサルティングファームにて、人事業務のコンサルティングやソリューション選定のサポートを行い、2018年4月、日本オラクルに入社。Oracle Cloud HCM のセールスエンジニアとして活動し、2019年6月より現職。
講演のポイント
今、人事/人材戦略の一環として「人的資本経営」への取り組みが注目されています。経済産業省でも、昨年9月に公表された報告書(人材版伊藤レポート)のとおり、企業価値向上の観点から「人的資本経営」を推進しています。この「人的資本経営」の実現には、HRテクノロジーを活用したクラウドソリューションの利活用が必須であると考えられています。クラウドソリューションをはじめ、様々なITソリューションを提供するオラクルから、「人的資本経営」に寄与する「DX・従業員エンゲージメント・生産性向上」について、オラクルコーポレーションの事例を交えながら紹介します。
15:10~ 休憩(10分間)
15:20~ <パネルディスカッション>【経営戦略と人材戦略の連動】(75分間)
実践から考察する、変革と挑戦を促す人材戦略
~イノベーション創出のための人材活用・育成・評価のあり方~
- 各社における人材戦略の取組み ~背景と課題~
- 人材育成、評価制度、多様性等から紐解く、組織の活性化/イノベーションを生むための仕組み・仕掛け
- 求められる人材戦略、マネジメントの役割とは ~深化と探索の実現に向けて

パネリスト
株式会社ブリヂストン
HRX推進・基盤人事統括部門長
江上 茂樹 氏
1995年に東京大学経済学部卒業後、三菱自動車工業株式会社に入社、工場人事・労務を担当。2003年、三菱ふそうトラック・バス株式会社へ移籍。開発管理部長等を経て、2010年人事・総務本部長。独ダイムラー傘下となった同社人事制度の変革を図った。2015年サトーホールディングス株式会社に入社、執行役員最高人財責任者(CHRO)兼北上事業所長等を歴任。2020年12月に株式会社ブリヂストンに入社し、2021年9月よりHRX推進・基盤人事統括部門長。

パネリスト
トヨタ自動車株式会社
総務・人事本部 副本部長
東 崇徳 氏
1999年 一橋大学経済学部卒業。同年4月 トヨタ自動車株式会社入社、人事部 厚生室所属。2002年 厚生労働省出向2年。2008年 人事部 主任、2014年 人材開発部 主幹、ブラジルトヨタ出向3年(TOYOTA DO BRASIL LTDA.)を経て、2017年 人材開発部 室長。2019年1月 人材開発部 部長。2020年 9月より現職。
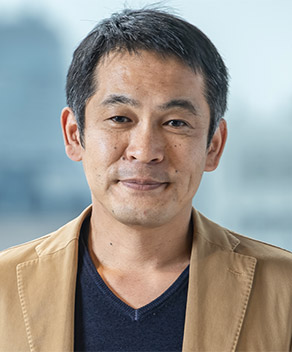
パネリスト
日本オラクル株式会社
人事本部 本部長
Vice President, Human Resources
一藤 隆弘 氏
大学卒業後、富士通に18年在籍し、本社人事、部門人事、工場人事、社長室等を担当。2001~2004年にドイツ駐在し富士通とシーメンスの合弁会社で人事を経験するなかで組織開発をキャリアの軸にする。その後、レノボ、ゼンショー、EYで人事ディレクター等を経て、2021年5月より現職。全員にとって優しい組織をつくるが仕事(そうありたいと日々模索)。好きなことは、HRテクノロジー、 D&I、スタートアップ/起業家支援、学び、産学連携等。1993年一橋大学社会学部卒業。2001年マギル大学MBA修了。
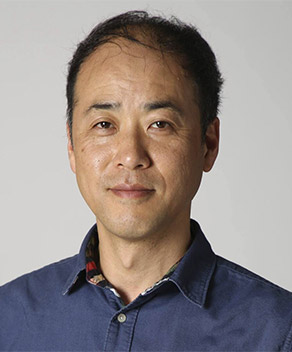
モデレーター
法政大学大学院
政策創造研究科 教授
石山 恒貴 氏
一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院経営情報学研究科修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。越境的学習、キャリア形成、人的資源管理、タレントマネジメント等が研究領域。日本労務学会副会長、人材育成学会常任理事、人事実践科学会議共同代表等も務める。著書に『日本企業のタレントマネジメント』中央経済社、『越境的学習のメカニズム』福村出版、等。主な受賞歴に、経営行動科学学会優秀研究賞(2020)、人材育成学会論文賞(2018)等。
16:35 終了予定
Vol.3 <事業戦略編> 11月17日(水)
13:00~ <特別講演Ⅰ>(45分間)【探索と深化の戦略的創造】
コマツのイノベーション戦略
~“社会課題の解決”と“新たな顧客価値の創造”~(仮)
- コマツの経営と構造改革への取り組み
- コマツが定義する「イノベーション」と向き合い方
- コマツにおけるオープンイノベーション
※講演資料は当日(ライブ配信中)のみの公開となります。資料配布もございませんので、予め、何卒ご了承くださいませ。

コマツ
特別顧問(元代表取締役会長・社長)
野路 國夫 氏
1969年 大阪大学 基礎工学部機械工学科卒業後、株式会社小松製作所入社。1993年 建機事業本部技術本部生産管理部長。1995年 コマツドレッサーカンパニー(現 コマツアメリカ株式会社)チャタヌガ工場長。1997年に取締役就任。情報システム本部長、生産本部長、建機マーケティング本部長など、製造・販売それぞれのトップを歴任。また、コマツウェイ推進室長として、コマツウェイのものづくり編を取りまとめた。2007年 代表取締役社長 兼 CEOに就任。2013年 代表取締役 会長。2016年 取締役会長。2019年6月 取締役退任後、特別顧問に就任。
講演のポイント
既存事業の選択と集中を行う一方、早くからデジタル化やコトづくりなど新たなビジネスモデルに先駆けて取り組むなど、まさに両利きの“ダントツ経営”で高い競争力を維持してきたコマツ。コムトラックスやダンプトラックの自動化など、常に社会的な価値創出のためのイノベーションを加速し続けています。ともすれば既存事業との市場の共食いや、競争相手との共創といった「矛盾」、さらに社内の「抵抗」等、様々な困難が生じる新規事業創出において、このようなジレンマを恐れず成功へ導いた背景には、トップ自らが現場に赴く探索活動や、地道なコマツウェイの浸透などの取組みがあります。まさに、探索と深化のジレンマを超えたイノベーションを戦略的に創造されてきた野路氏より、コマツにおける戦略事例を通して、新規事業を進めるための考え方や向き合い方のヒントなどについて、お話いただきます。
14:00~ <特別講演Ⅱ>【両利きの価値創造とR&D】(45分間)
ソニーグループの進化に向けた価値創造戦略
- ソニーグループにおける価値創造を推進する体制と取組み ~ダイバーシティを活かした価値創造へ~
- これからのR&D組織の役割とあり方 ~メガトレンドの理解、デジタルデータの向き合い方など
- 人と技術を通じた事業の進化と成長、深化と探索の両立への展望

ソニーグループ株式会社
コーポレートテクノロジー戦略部門 部門長
住山 アラン 氏
三菱商事株式会社、Eコマース系スタートアップ、コニカミノルタ株式会社を経て、2019年にソニー株式会社に入社。2020年より現職。ソニーグループの技術戦略策定および社内外連携によるイノベーション推進に従事。カリフォルニア工科大学工学部卒(電気工学)、ハーバード大学 修士(経営学)。
講演のポイント
過去約9年間に渡り、選択と集中やビジネスモデルの転換など大規模な構造改革を進め、今年4月から新たな経営体制へ移行し、過去最高益を更新するなど、かつての低迷期から復活を遂げているソニーグループ。従来の電機メーカーのイメージとは異なり、エレクトロニクスだけでなく、ゲームやエンターテインメント、金融など多様な事業を手掛け、リカーリングビジネスの強化も進める一方、その事業戦略と連動して、成長の柱となるR&Dのあり方も「技術偏重」や「商品起点の発想」から大きな変貌を遂げています。新生ソニーグループとして、今後の価値創造の戦略やシナジーをどう描き、新たな事業の芽をどのように育て、変化するR&Dのあり方をどう捉えているのか。R&D組織の舵取りを担う住山氏よりお話しいただきます。
14:45~ <協賛講演>【新事業の成否とリーダーシップ】(25分間)
ポストコロナ時代にとるべき探索戦略と経営者・リーダーの覚悟
- COVID-19が各企業の新規事業戦略、探索活動に与える影響
- 現在の潮流の中で探索成果を上げるための要諦や視点
- 経営者または探索戦略のリーダーに求められる覚悟とは

KPMGコンサルティング
執行役員パートナー
ビジネスイノベーションユニット統括
佐渡 誠 氏
大手日系企業・外資系戦略コンサルティングファームを経て現職。約20年にわたって様々な業界、約100社以上の成長戦略や新規事業戦略の策定をリード。現在、ビジネスイノベーションユニットの統括役員として、社会課題解決やクライアントとの協業サービスなど、コンサルティングファームの新たなビジネスモデル変革を牽引。
講演のポイント
企業が永続的に発展・成長していくためには、常に市場変化を的確に読み取った戦略シフトが求められます。しかし、いざ新たな事業の創発活動に資源を投下して成果を挙げようとするものの、多くの企業が思うような成果を挙げられていないのが実態です。これまで20年以上に渡り多くの企業の新規事業やサービス開発、探索戦略を支援してきた立場から、改めて現在の潮流を押さえた上で探索活動を成功させるための勘所、そして経営者・リーダーに求められる覚悟についてお話します。また、コンサルティング会社自らも「クライアントイシューの支援」を超えた新たな“提供価値シフトへの探索”が求められており、その改革を推進している立場から、リーダーとして重視している点や推進上の要諦などを実際の取り組み事例と共にご紹介します。
15:10~ 休憩(10分間)
15:20~ <パネルディスカッション>【両利きのマネジメントと新事業戦略】(75分間)
実践から考察する、新事業創出に向けた戦略と課題
~深化と探索を両立するマネジメントはどうあるべきか~
- 新事業創出に向けた取り組み ~テーマ創出、探索活動とその価値判断、事業性・収益性への考え方等
- 深化と探索を両立させる仕組み ~既存資源の活用、組織体制、ポートフォリオマネジメントのあり方等
- さらなる成長と進化へ向けた課題と展望

パネリスト
株式会社日立製作所
執行役専務 CSO
戦略企画本部本部長
森田 守 氏
一橋大学経済学部卒業。ルイジアナ州立大学(MBA)修了。1983年 株式会社日立製作所入社。1987年 株式会社日立総合研究所出向。株式会社日立製作所 グローバル事業開発本部長代理、事業開発室長を経て、2008年 株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ Vice Presidentに就任。戦略企画本部 経営企画室長、理事 戦略企画本部長を経て、2016年 執行役常務 戦略企画本部長に就任。2017年 投融資戦略副本部長 兼 未来投資本部副本部、2018年 投融資戦略本部事業開発室長も兼務。2020年4月より執行役専務 CSO 戦略企画本部長、投融資戦略副本部長 兼 投融資戦略本部事業開発室長 兼 未来投資本部長に就任。

パネリスト
株式会社村田製作所
執行役員 工学博士
技術・事業開発本部 事業インキュベーションセンター センター長
兼 同センター 新商品事業化推進部 部長 兼 同センター RFID 事業推進部 部長
安藤 正道 氏
1988年入社、17年間は通信基地局用誘電体多重モードフィルタの開発と事業推進に携わる。その後有機圧電体の研究を三井化学と共同で始め2013年にセンサを商用化した。2016年に圧電繊維の抗菌性を発見し、帝人フロンティアと合弁でPIECLEX社を昨年発足させた。現在は新規事業テーマ創出と、様々な開発品の事業化に携わっている。
パネリスト
KPMGコンサルティング
執行役員パートナー
ビジネスイノベーションユニット統括
佐渡 誠 氏
prof
モデレーター
株式会社ビジネス・フォーラム事務局
井内 康徳
prof
16:35 終了予定
※ プログラム内容や時間は急遽変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。



