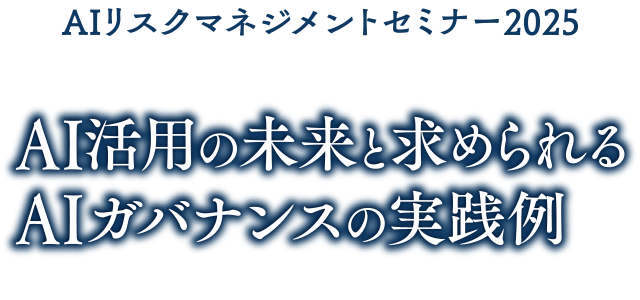開催概要
開催日時
- Online 2025年 4月21日(月)14:00~17:00
開催趣旨
Chat GPTといった生成AIが登場するなど、技術の急速な進化と普及により、AIに伴うリスクが顕在化するようになりました。AIリスクは、予測や説明が困難、技術革新や普及の速さ、信頼性・倫理的な判断の難しさがある上に、SNSでの炎上や重大な情報漏洩事項など企業の信頼に大きなインパクトを与える可能性を持っています。
各社がAI活用を模索する中、世界の主要国では、AIに関するガイドラインの策定が進んでおり、日本も2023年のG7広島サミット以降取り組みが加速しているものの、企業が果たすべき責任の議論はまだまだ発展途上であるといえます。こうした中、EUでは、2024年の5月に人工知能を包括的に規制する「AI法案」が成立し、世界初の規制として、今後大きな影響力を持つことが予想され、どのような対策をしていくか、日本企業にとって喫緊の課題となっています。
本セミナーでは、AIがもたらす価値と可能性を最大化するために、いかにAIリスクを管理する体制を構築し、管理プロセスを定めて運用していくか「AIガバナンス」の最適解を有識者と先進企業の事例から探ります。
概要
|
参加対象者 |
経営者・役員、経営企画、法務、リスクマネジメント、情報システム、研究開発部門、生成AIなど先端テクノロジーを活用した関連部門等の管理職の方々 |
|---|---|
|
参加料 |
無料(事前登録制) |
|
参加定員 |
100名 ※申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。 |
|
開催形式 |
オンライン配信 ※本セミナーはオンラインでの配信となります。視聴方法はお申し込み後にご案内いたします。 ※お申込者でない方への視聴用URL共有はご遠慮ください。同じ会社内で複数名でのご参加を予定されている場合にも、お手数ですがお一人ずつお申し込み下さい。 ※登録時のメールアドレスに登録完了メールを送付いたしますが、万が一届かない場合、大変お手数ですが、customer1@b-forum.netまでご連絡ください。 |
|
主催 |
株式会社ビジネス・フォーラム事務局 |
|
協賛 |
プログラム詳細
14:00~14:50 基調講演
先進的AIとAIガバナンスの在り方
- AIの社会的インパクトとは
- 世界各国のAIガバナンスの動向
- 日本企業がAIを活用する上で考えるべきリスクやガイドラインの作成など

中央大学 教授
ELSI センター長
経済学博士
東京大学 名誉教授
須藤 修 氏
東京大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士(東京大学)。東京大学助教授などを経て、1999年4月より2020年3月まで東京大学教授。2020年4月より2023年12月まで東京大学大学院特任教授。2020年4月より中央大学国際情報学部教授(現在に至る)。この間、東京大学大学院情報学環長・学際情報学府長(2012年4月ー2015年3月)、東京大学総合教育研究センター長(2016年4月ー2020年3月)を歴任。さらに東京大学大学院特任教授(2020年4月1日―2023年12月)などを歴任。また、ストックホルム経済大学(Stockholm School of Economics)客員教授(1995)、東京大学総長補佐(1996年度)、参議院商工委員会客員調査員(1997)、筑波大学先端学際領域研究センター客員研究員(1995-1998)、NTTサービスインテグレーション基盤研究所リサーチ・プロフェッサー(1997-1999)、日本経団連21世紀政策研究所主幹研究員(2008-2009)、国立情報学研究所客員教授(2010-2014)、地方公共団体情報システム機構代表者会議委員(2014-2023)、一般社団法人次世代放送推進フォーラム(NexTV-F)理事長(2013-2016)、Member of the OECD Global Science Forum Expert Group (2014-2016) 、Member of AI expert Group at the OECD (AIGO) (2018年9月―2019年3月)、UNESCO人工知能に関するハイレベル会合日本代表(2019年)などを歴任。
講演のポイント
科学技術の発展や社会実装においては、包摂的にコントロールする政策やルールなどによるガバナンスが重要であり、ELSI(Ethical, Legal, and Social Issues)の観点から、全体最適化を図ることが求められます。すでにその取り組みが進んでいるEUとアメリカを中心に、AI開発や利用に関する世界的な動向をご紹介いただいたうえで、日本国内の動向や今後の研究・開発に関する課題について、内閣府「人間中心のAI社会原則検討会議」の議長等多くの要職に就任しており、国際的なAIガバナンスの構築にも携わっている須藤様にお伺いします。
14:50~15:20 講演1
AI法をも見据えたISO/IEC42001に基づくAIガバナンスの実践と勘どころ
- EU AI法とISO/IEC42001の関係性について解説
- AIリスクマネジメントに求められる特性を解説
- ISO/IEC42001の事例を踏まえた実践的活用法を解説

ニュートン・コンサルティング株式会社
取締役副社長 兼 プリンシパルコンサルタント
勝俣 良介 氏
日本で、セキュリティスペシャリストとして活躍後、2001年に渡英し英国企業へ入社。欧州向けセキュリティソリューション部門を立ち上げ、部門長として新規事業を軌道に乗せた。2006年、副島と共にニュートン・コンサルティングを立ち上げ、取締役副社長に就任。コンサルタントの教育、自社サービスの品質管理、新規ソリューション研究・開発を率いる。多くの書籍や記事を執筆するなど豊富な知識・経験を持ちながらも、伝統的な考え方にとらわれない実践性と柔軟性を駆使したコンサルティング手法には定評がある。幅広い業界/規模のお客様に支持されている。全社的リスクマネジメント(ERM)、内部統制、BCP/危機管理、ITガバナンス/セキュリティ管理など幅広いコンサルティングスキルを有する。
講演のポイント
AIは企業競争力を底上げする上で欠かせない存在になりつつあります。一方で、AIの活用が急速に広がる中で、規制強化の動きも加速しています。例えばEU AI法は、企業がAIを活用する上で無視できない存在となっており、適切なリスク管理とガバナンス体制の構築が求められます。言い換えれば、AIのメリットを最大限享受するためには、少なくともそのための足場固め、すなわち、AI関連法規制への対応や、その他、多様なAIリスクを封じ込める基盤づくりが欠かせません。本講演では、そうした基盤づくりを目指すにあたり、ISO/IEC42001を活用したAIガバナンス整備・運用の具体的なアプローチやその際に直面する課題や解決の勘どころを解説します。
15:20~15:50 事例講演1
OKIにおける生成AI活用とAIガバナンスの取り組み
- 信頼されるAIの提供・利用に向けて
- OKIグループの生成AI活用基盤構築と活用推進
- AIリスクマネジメントの課題と今後の展望 など

OKIクロステック株式会社
AI・RPA推進部 部長
須崎 昌彦 氏
1992年 神戸大学大学院自然科学研究科電子工学専攻修士課程修了。同年 沖電気工業株式会社入社。顔認識、虹彩認識、文書画像の電子透かしなど画像認識技術の研究開発に従事。2012年よりAI・データ分析に関する研究開発部長。2019年よりAIの安全な社会実装に向けた社内環境整備プロジェクトリーダー。2023年から、データマネジメント室にて全社のデータ利活用・生成AI活用を推進。2025年4月から、OKIクロステック株式会社 AI・RPA推進部 部長としてOKIグループでのさらなるAI活用のために活動。博士(工学)。
講演のポイント
30年以上AI開発に取り組む沖電気工業様。AIに関するさまざまなサービスを提供される中で、「安心安全なAI」を目指し、AIガバナンスにおける取り組みについても推進されてこられました。2019年に「OKIグループAI原則」を策定、「AI契約ガイドライン」の公開や「AI品質チェックリスト」の作成、そしてAIリテラシー教育を7,000人以上の社員に実施されています。生成AI導入を進めてきた立役者である須崎様より、AI環境整備プロジェクトやリスク管理体制の構築などのプロセスに加え、AIガバナンスの在り方へのお考えなどをお伺いします。
15:50~16:20 講演2
AIガバナンス構築における関連指針の活用
- AI事業者ガイドライン等の諸指針から抽出されるAIガバナンスの主要ポイント
- EU AI Actから得られるヒント
- AIに関する法整備、その他最新の動向の紹介

シティユーワ法律事務所
弁護士 (オブ・カウンセル)
後藤 出 氏
シティユーワ法律事務所所属弁護士(オブ・カウンセル)。1986年弁護士登録。各種金融取引の組成とそれに関連する民事法・金融関連規制法、デジタルアセット全般についての法規制を専門とするが、近時は、AIの運用に関連する社内ルールの策定に向けてのアドバイスに積極的に取り組んでいる。 最近の関連著作として、「データと信託」(畠山久志監修・後藤出編『デジタル化社会における新しい財産的価値と信託』(商事法務 2022年)所収)、「EU AI Actの概要とその背景」(法の支配第215号 2024年)所収。

シティユーワ法律事務所
弁護士(パートナー)
池辺 健太 氏
シティユーワ法律事務所所属弁護士(パートナー)。2011年弁護士登録。国内外のクライアント向けに金融、不動産取引のほか、AI、暗号資産その他デジタルアセット、資金決済、プラットフォームビジネス等フィンテック全般についてのアドバイスを専門的に取扱う。
講演のポイント
AIガバナンスの構築にあたり参考にすべき指針としてAI事業者ガイドライン等の指針が公表されていますが、これらの指針は極めて広汎かつ詳細な内容を含んでおり、これをどのように整理、選択して自社のAIガバナンスに取り入れていけばよいのか悩まれている事業者は多いのではないでしょうか。 本講演では、AIガバナンスに関する諸指針の内容から抽出されるガバナンス構築上の主要な着眼点を解説することをメインテーマとしつつ、EU AI Actから得られるヒント、AIに関する法整備の動向等についても解説します。
16:20~17:00 事例講演2
富士通におけるAI活用事例とAI倫理を主眼としたガバナンスの取組み
- 富士通グループにおけるAI活用の現在地
- 富士通グループ全体で取組むAIガバナンス
- AIガバナンスにおける課題と今後の展望 など

富士通株式会社
AIガバナンス推進室・AI倫理室
室長
荒堀 淳一 氏
AIを始めとする最新テクノロジーの信頼を確保し活用を促進するために、富士通株式会社AI倫理ガバナンス室長として、富士通グループにおけるAIガバナンスをグローバルに主導する。また、同社デジタルテクノロジー法務統括部エグゼディレクターを兼務し、データ・プライバシーに関する規制対応など法律面からもデータドリブンな経営やビジネスの推進をサポートしている。さらに、総務省のAIネットワーク社会推進会議AIガバナンス検討会構成員や経団連のAI活用戦略タスクフォース委員を務めるなど、社外でも施策に取組む。2015年から2018年まではワシントンD.C.事務所長として米国に駐在し、テクノロジーやイノベーションを取り巻くグローバルな政策環境の調査に従事した。
講演のポイント
他社に先駆けたAI研究・利活用のお取組みがある中で、2019年にいち早く「富士通グループAIコミットメント」を策定、「富士通グループAI倫理外部委員会」を設置し、 2022年には「AI倫理ガバナンス室」を新設されるなど、そのお取組みを進化させ続けている富士通様。パーパスに掲げられた「信頼」をAI分野でも担保し、「信頼できるAI」を実現するため、AI倫理ガバナンスの取り組みを強化されてきました。AI指針の起草メンバーであり、 AIガバナンスの全社方針の推進・浸透だけでなく、 AIガバナンス体制の構築・推進をされてきた荒堀様より、お取組みの現在地や課題、展望をお伺いします。
※プログラム内容や時間は急遽変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。