CMO Forum 2015
マーケティング主導の経営
~効果を最大化させる、CMOの役割と組織~
2015年5月21日、東京・青山ダイヤモンドホール、サファイアルームにて「CMO Forum 2015マーケティング主導の経営~効果を最大化させる、CMOの役割と組織~」をテーマとしたセミナーを開催しました。(主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局、協賛:アドビ システムズ 株式会社)
現代のビジネスシーンでは、優れた技術や製品だけで長期にわたる競争優位を維持することは困難であることは言うまでもありません。「他社との差別化をいかにして図り、顧客に価値を届けるか?」多くの経営者にとって、日々の問いであり、ビッグデータを始め情報技術が急速に進化する中、マーケティング部門への期待が高まるのも必然と言えるでしょう。しかしながら、マーケティングをデジタル部門や、リサーチ・宣伝・広報など、限られた業務として捉えることは、大きな事業機会を逃してしまうことにもなりかねません。そのような中、マーケティングを経営と一体化させるため、各部門とリンクさせ、全社横断的に統括する役割を担うCMO(Chief Marketing Officer:最高マーケティング責任者)を設置するなど、経営におけるマーケティングの在り方を模索する企業が増えてきています。
第2回となる今回のフォーラムでは、企業のCMOやマーケティングトップの方々をお招きし、各社の戦略とともに、“マーケティングの在り方や組織体制、CMOの役割”など、マーケティング主導経営のキーファクターをご紹介頂きました。また、後半のセッションでは、これからの時代に必要な顧客創出のカギやマーケッターが養うべき力などについて、経営トップ、起業家、脳科学者の立場から、多角的な視点でお話し頂き、これからのマーケティングと日本企業の戦い方を検証しました。
特別講演Ⅰ
マツダのグローバルマーケティング戦略

マツダは、昔から鉄の生産が行われ、開拓移民の多い広島に大正時代に産声を上げたこと、原爆投下からわずか4ヶ月後に生産を再開し、街が活気を取り戻す原動力となったことなど、マツダが単なるジャパニーズではなく、広島という地域に根ざしながら、地元を盛り立てつつ、グローバルに挑戦していく企業であることを、印象的な映像で綴るビデオがまず講演の冒頭で紹介された。
世界初の2ローター、ロータリーエンジンの実用化、世界で最も売れているオープンスポーツカー、ロードスター、日本車メーカー史上初の「ルマン24時間耐久レース」での総合優勝など、マツダが成し遂げてきた数々の偉業をもう一度社員に思い出してもらうためのビデオは、これまで社外ではほとんど公開されてこなかった。
マツダは、自らのチャレンジャーとしての過去を今に取り戻すことによって復活してきたといえる。「マツダが元気だ」と言われるようになり、業績も好調だ。それは、ブランド価値経営を推し進めた成果だと言われる。その立役者ともいえる常務執行役員 毛籠 勝弘氏が復活への道筋を語った。
ヨーロッパでは、
マツダのシェアは小さかったけれども、ブランドの評判は高く、
従業員や販売店が自信や誇りを持っている、という気づき
業界の常識を打ち破る商品を数々生み出してきたマツダは、技術はすぐれているが、個々のヒット商品で終わってしまい、業績の浮き沈みが激しいという課題をずっと抱えてきた。
業績の浮き沈みは、為替の変動を受けやすい業種ゆえのものでもあった。その是正ために、グローバル生産体制の再構築や、海外調達比率の拡大、外貨調達比率の向上などの改善を行った。しかし、それは、グローバルビジネスにおける必要条件にしかすぎなかった。
また、2000年以降、グローバルブランド戦略を導入した。しかし、本社は、ブランド戦略が大事というが、販売店側は、ブランドでは食えないと言い、本社の戦略と現場の実情が乖離し続けた。そしてブランドが大事と言いつつ、本社も規模の優劣という価値観を持ち続けていたため、ビジネスオペレーションの本質は変わらなかった。生産を拡大し、在庫が増加し、値引き販売で下取り価格が下落し、さらに値引きによる囲い込みを行うという悪循環が続いていた。そこに、リーマンショックが襲い、在庫がものすごい勢いで積み上がったという。

そこに当時、ヨーロッパの副社長をしていた毛籠氏が呼び戻された。毛籠氏は、ヨーロッパで一つの気づきをえていた。ヨーロッパでは、マツダのシェアは小さかったけれども、ブランドの評判は高く、従業員や販売店が自信や誇りを持っていた。そこにマツダが当時の悪循環から抜け出す処方箋があると毛籠氏は見ていた。
経営的には悪循環のなかにあったけれども、マツダとして自信を持って世のなかに出していける技術も、すでに育ちつつあった。二酸化炭素の 排出量の削減という地球規模での課題を前に、多くの自動車会社は、ハイブリッドなどにシフトしようとしていたが、マツダは「モノ造り革新」を進めるなかでエンジン(内燃機関)の効率改善にリソースを集中していた。2008年、技術開発の長期ビジョンとして、グローバルでの平均燃費を2015年には30%向 上*させる、という目標をかかげ、すでに実現しているSKYACTIV Technologyの開発に向かっていた。ユニークな車を出し続けるための、部品の共通化に頼らないコスト削減の方法や開発リードタイムの短縮化なども 進んでいた。(*2008年比)
規模の優劣からブランドの優劣へと
ブランド戦略の背景にある考え方から改めていった

世界で戦える商品は揃いつつあった。それをどう販売に結びつけていくかが課題だった。そこで営業領域に大なたが振るわれることになる。マーケティングがブランド戦略に基づき、ビジネス戦略とオペレーションをけん引するような形にもっていった。
以前にもブランド戦略はあった。しかし、その前提にある考え方は依然として従来の自動車業界のものである規模の優劣であった。その考え方から改めていった。規模の優劣から、ブランド価値の優劣へと、ビッグプレーヤーとは違うルールで戦うことを徹底した。
ブランド価値経営によって、唯一無二の提供価値(=ブランド)により、お客様に選ばれ続け、愛され続けることで、ビジネスを強化し、企業価値を高めていこうというものだ。ビッグプレーヤーのように、新車販売台数至上主義によって新車販売時点での利益を極大化するために、顧客を囲い込むのではなく、ブランド商品価値を訴求して、ライフサイクル利益を重視する。
この考え方のベクトルを統一したあとで、つながり革新という戦略を打ち出していった。商品・技術価値戦略、人材戦略 販売店戦略、価格戦略、コミュニケーション戦略など、すべてを顧客ロイヤリティ中心に作り直した。
商品技術価値戦略では、値引きに頼ったお客様への訴求をやめて、商品技術の価値と、その開発背景や開発者の思いが「きちんと語れる」販売現場をつくっていった。
価格戦略では、それまでの大幅値引きをやめて「正価販売」を導入していった。正価とは、お客様にとっての価値と価格が釣り合うポイントであり、お客様の納得、信頼、確信が値引きを抑え、「正価」を引き上げるものとなる。
コミュニケーション戦略は、かつては個別車種を中心に行っていたが、プライマリーブランドフォーカスとして「マツダが好き」という顧客が増えるような発信を増やしていった。さらには、販売店戦略として新世代店舗をグローバルに展開した。
そうやって、マツダらしい提供価値が明確になれば、共感するファンが増え、絆が生まれ、愛着が沸き、優良顧客が増加し、マツダの評判が広がっていく。それによって台当たり収益が拡大し、経営が安定し、社員のモチベーションも上がり、商品やサービスの質が向上していく。それがまたマツダらしい提供 価値のさ らなる明確化へとつながっていくというサイクルできあがっていくはずで、そのためにまず、社内のブランディングを徹底した。
セミナーやブログなどを通して役員が従業員に直接語りかけていった。セミナーと同時にマツダが理想とする「人馬一体の走り」を体感できるドライビングアカデミーも実施した。ブランド価値経営の戦略の理解を深めていくために、エグゼクティブブランドフォーラムを全世界レベルと地域レベルで毎年行っている。一方、実行計画においては、市場の特性にあわせた最適化を重視している。これら活動の結果を主要国ごとにTPI(つながりパフォーマンスインジケーター)で数値化して進捗を管理 している。
今は、New Engagement Marketing Modelを通して、不特多数ではなく特定多数のカスタマーを対象にしたエンゲージメントにフォーカスし、すべての顧客接点でのブランド価値体験の強化を目指している。生涯にわたってマツダのある生活をしていただけるよう、お客様に選ばれ続けるマツダになろうとしている。
マツダ株式会社
常務執行役員 営業領域総括 グローバルマーケティング・カスタマーサービス・販売革新担当
毛籠 勝弘 氏
1983年3月、マツダ株式会社入社。2002年4月、グローバルマーケティング本部副本部長。同年8月、グローバルマーケティング本部長。2004年3月、マツダモーターヨーロッパGmbH.副社長。2008年11月、執行役員 グローバル販売統括補佐、グローバルマーケティング担当。2012年4月、執行役員 営業領域統括補佐、顧客つながり推進担当補佐、グローバル販売&マーケティング担当。2013年6月より現職。
特別講演Ⅱ
帝人の横串変革 ~マーケティングとCMOの役割~

2008年のリーマンショック後、帝人の業績は低迷。その主な理由は、帝人本体の事業である素材事業の不振によるものだった。そこを立て直すために起用されたのが、関連会社の医療分野で実績をあげてきた荒尾 健太郎氏だ。帝人株式会社の専務執行役員として、新事業推進などを兼務しつつ、マーケティング最高責任者をつとめる荒尾氏が、自らの体験をもとにCMOの役割について語った。
社内にできた四つの壁を打破していくための
演出と仕組みを重層的に打ち出していく
帝人には、炭素繊維・複合材料、高機能繊維、フィルムや樹脂といった素材に留まらず、そこから派生した製品やITサービス、ヘルスケアなど、様々な事業領域がある。2003年以降、持株会社へ移行し、事業を分社化し、経営効率を追求して、それぞれの事業の競争力を強化しようとしたが、結果として働いたのは遠心力だったという。各事業が他部門との連携なくそれぞれの道をいき、帝人としての総合力をだせない事態に陥っていた。
かつては素材メーカーとして、素材を供給していればいいところがあり、それでも通用した。しかし今は最終製品メーカーの側の素材メーカーに対する期待が膨らみ、彼らの真のニーズを理解して、素材を組み合わせ、川中川下技術との連携によって高付加価値領域へ参入することがまさに求められていた。そこに必要なのは、帝人としての求心力であり、顧客が真に必要とするソリューションを、総合力を結集して提供していくことだった。
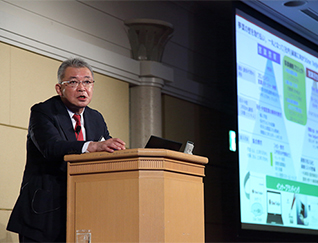
2013年4月に、マーケティング最高責任者となった荒尾氏は次のような問題意識をもっていた。社内の4つの壁が帝人としての最適ソリューションの提供を妨げているのではないかというものだ。第一の壁が地域間の壁で、各拠点(日本・海外)が、自身の売り上げ・利益だけを考えてオペレーションを行いがちだった。第二の壁が機能間の壁で、技術・営業間で情報の共有化が十分になされていなかった。第三の壁が事業間の壁で、事業間で人材や情報の共有化が十分になされていなかった。第四の壁が、営業担当者間の壁で、個人レベルでベストプラクティスが存在していても、共有する場や機会がなく強みを活かせなかった。
そこで、これら四つの壁を打破すべく、全社一丸となって顧客に向かうための演出と仕組みを打ち出していった。まずは、演出としてOne Teijinというコンセプトを打ち出し、営業大会や社内報などを通して浸透させていった。またその機運を支える仕組みとして、教育や人材育成を継続して 行い、社内の連携をはかるために全社横断プロジェクトや展示会、他社との協業などを立ち上げていった。
社員全員にマーケティングマインドをもたせる。
CMOの役割はそのための事業間の接着剤として、社内を固めることだ。

2013年10月に社長がOne Teijinでいくことを宣言すると同時に、自分の部署の素材だけでなく、他部署の素材についても学ぶという事業横断教育が始まった。部課長は多忙ということで、最初は課長職以下の素材営業担当者159名を対象に行った。テキストも各担当者が手作りし、それぞれの素材につき80点を合格点とする試験も行われた。受講者を対象に行ったアンケートによると、自分が担当する素材についてはもともと理解していたが、さらに深く理解できたと回答する人が多かった。そして他事業の素材については、受講前は「知らない」が半数に及んでいたものが、その概要を理解できたと実感するようになっていた。またこのアンケートでは、部課長以上も受講すべきという声が寄せられ、部課長も受講する形に発展していった。
素材についての知識教育を行うと同時に、正しい戦略を実行していくためのマーケティング教育を実施していった。第一線の課長・課長代理クラスにおける、戦略を立案し実行していく力を強化することを目的とする、フロントラインマネジャー研修が2014年から開始された。毎年15名ずつ受講していくことで、5年間で素材営業の半数が受講する計画で進んでいる。併行して、部課長を対象としたマーケティング一日研修なども行われ、研修後のアンケートでは、マーケティングや戦略策定に有効なフレームワークやツールについて、95%以上が十分に理解できていなかったという気づきを得、8割が研修の継続を希望していた。
これら教育と併行して、営業大会を半年に一度行い、ベストプラクティスの共有化や事業の壁を超えた懇親会を行って、同じ顧客に対して営業をしている別部署の担当者との対話が始まったりしている。また重要顧客のトップに話をしてもらうOne Teijin セミナーを年に数回行うことで、懇親を深めていくようなことも継続している。
さらに「顧客の見える化」をしていった。限られた経営資源を効率的に投下して営業成績を極大化するために、重要顧客の選定と各顧客やその産業分野ごとの戦略策定が必要との考えによるものだ。
学び、親しんだことを実際の成果に結びつけていってもらうために、事業横断プロジェクトも立ちあげていった。第一弾としてニトリプロジェクトと銘打って、ニトリの社員を対象に初の帝人グループ展示会を開催した。ニトリなど最終製品メーカーの素材メーカーに対する不満は、「素材だけもってきて、あとはメーカーさんで考えて」という姿勢にあった。素材起点ではなく、消費者が困っていることを、素材でどう解決していくかという第三者視点で提案してほしいという要望に対して、帝人の責任者を拡充し、さらには社内の女性社員によるブレストチームを発足させ、すでに商品化にこぎ着けたものもある。
他にも、自動車各社やエレクトロニクスメーカーを対象に、帝人一社での展示会を海外でも行い、協業が進みつつある。オリンピック・パラリンピック委員会を設けて、未来を見据えてプロジェクト化すべきビジネステーマを選別し、実行に移していくようなことも始まっている。
荒尾氏が始めてから2年間の活動を振り返り、アンケートなどの結果を踏まえ、そこから次の課題が見えていき、2015年度は、営業と技術の一体化や、マーケティング教育の強化、用途別タスクフォースの立ち上げなどを活動方針として採用し、One Teijinをさらに推し進めようとしている。
これら自らの体験を通して荒尾氏は、CMOにとって一番大事なことは、社員全員にマーケティングマインドをもたせることだと力説する。そのためにCMOは事業間の接着剤として、社内を固めることから始めるべしと。予算を確保して、体制と制度を構築し、実施したことの成果を定量的に検証することが大事だという。 特にアンケートは必須で、社内の壁の元凶は管理職以上にあり、新しい試みは必ず社内の反対にあうから、そこで粘り強く説得していくときの材料になるからだ。そして社員は何よりもトップの本気度をみており、CMOの活動はCEOに強力に支援され継続していくことが大切だと結んだ。
帝人株式会社
帝人グループ専務執行役員 新事業推進本部長 兼 マーケティング最高責任者 兼 BRICs担当
荒尾 健太郎 氏
1952年生まれ。1975年4月慶応義塾大学卒業後、帝人株式会社入社。人事勤労部、医薬営業、医薬営業マーケティングを担当し、2000年4月、医薬営業部門 医薬営業推進部長、2010年4月帝人グループ常務執行役員、帝人ファーマ株式会社専務取締役 医薬事業本部長、2011年4月帝人グループ専務執行役員、帝人ファーマ株式会社代表取締役社長、2014年4月より現職。主に医薬品の営業、マーケティングを担当し、現在は帝人の素材事業の融合と新事業の創生を担当。
協賛講演
マスマーケティングの一環として
デジタル戦略を持つことの重要性
個客のデジタル体験の改善で、62.6%の機会損失を回避する
顧客がおかれているデジタル環境は日々めざましい勢いで進化している。家庭でくつろぐ家族の前にテレビやタブレット、スマートフォンといった複数の液晶画面がある。あるデータによると1日に150回、時間にすると6分に1回、スマートフォンや携帯にふれているという。こうしたデジタル化のなかでビジネスの成功の鍵はどこにあるのかを、アドビ システムズ 株式会社 代表取締役社長、佐分利 ユージン氏が語った。
ウェブサイトで期待した体験が得られない場合、
6割以上が購入を断念している

アドビ システムズはまず、消費者行動モデルとして、認知→関心→検討→購買という一般的なモデルを想定した、デジタル化が消費者行動に及ぼした影響の調査結果を発表した。
認知の段階では、広告投資によるテレビをはじめとしたマスマーケティングが依然として有効であった。日本は特にそうだが、他方アメリカなどではインターネット広告にかける予算が地上波テレビを上回るような状況も起きていて、デジタルシフトは着実に起こりつつある。それを証拠づけるかのように、この調査でもニュースやポータルサイト、企業のウェブサイトなどのデジタルのみが、5年前と比べて伸びていた。
広告をみて関心をもった顧客の9割が、ウェブサイトに追加情報を求めにいくという。これは認知後の関心をつなぎとめるデジタルメディアがいかに重要かを物語っている。
検討段階では、消費者がデジテルメディアに何を期待しているかを調査したところ、商品の便益を知ることだった。また購買段階では、購買の阻害要因は何かを調査したところ、ウェブサイトにいって期待した体験がえられない場合、6割以上が調べるのをやめてしまい、購入にもいたらないという結果がでた。

このような状況を踏まえて、マスメディアとデジタルメディアを効果的に組み合わせて活用している日本企業の事例として、日産自動車の事例がデモンスト レーションを交えて紹介された。対面販売力の低下が、日産にとって非常に大きな課題だったのだが、顧客が実際に購入するまでにディーラーを訪問する回数が 5年前までは7回あったのが、最近では1.5回に減っているといわれており、減少分がデジタルに置きかえられていると考えられた。そこで、マーケティング関連の予算を大幅に組み替え、デジタルコンテンツの充実を図っていった。
ステージ上のデモは、テレビ広告で気にいった日産の車ローグを、パソコンのウェブで確認していくというところから始まった。車のイメージ、価格、内装や機能を細かにみていく。車は大きな買い物だからすぐには決断せず、しばらく考えることになるが、翌朝、通勤途中に車のことが気になって、今度はスマートフォンで日産のウェブサイトにいく。そうするとスマートフォンに最適化された形でページが表示される。パソコン用にできたコンテンツはスマートフォンでは見づらいといったポイントが指摘される。タブレットでも日産のウェブサイトにいく。車の外装や内装をさまざまな角度でみたり、色を変えてみたりする。ショールームでさえ再現できないようなことができてしまうのがデジタルの強みだ。車が気にいったところで、ディーラーに見積もり依頼をすることになる。必要な情報を入力すると、翌日近所のディーラーから電話がかかってきて、早速試乗にいくことにしたとデモは終わった。顧客との最初の対面のときにディーラーの側にも、顧客がどういうコンテンツをみてきたかの情報があり、それが話を進めやすくする材料ともなるという。マス、ウェブ、モバイルと広がる顧客の行動にあわせ、特長を活かして、最適なエクスペリエンスを提供している事例だった。
「個」客理解と「個」客体験の両輪を
テクノロジーで結びつけて「個」客の期待に応える

顧客はマス、パソコン、スマホ、タブレット、ウェブ、ソーシャル、メール、検索、広告、アプリなど、多様なメディアを通して企業と接触している。二つとして同じ経路は存在せず、企業はそれをコントロールすることもできない。
ゆえに、一人ひとりの「個」客中心を前提として、「個」客との関係を構築する戦略が求められると佐分利氏は力説する。本質的に大事なことは、マス対応から個々対応へとビジネスの進め方を変革していくことだ。標準的なビジネスプロセスを支える社内システムでは、どの顧客も同じに見えてしまうことがあり、業務効率化システムだけでは、パーソナライゼーションや個人対応はできない。「個」客を対象としたビジネスを行う体制とビジネステクノロジーが必要になる。
個客を対象としてビジネスを展開するには、個客を総合的に理解し、個客の期待するものを提供するという二つの課題がある。個客理解につながるデータには、行動データや属性データ、心理特性データなどがあり、個客を理解する適切な仕組みを通して様々なデータを集めて、オーディエンスを把握・管理し、ビジネスに活用していくことが重要になっていく。
ウェブサイトを個客の期待に見合うものにしていくためには、認知段階では複数のメディアとのメッセージの印象の一貫性を保つことが必須といったポイントが語られた。関心段階では、いつどこでウェブを訪れてもいいような状況にしておくこと。検討段階では、買う気を高める、知りたいという期待に応えることが重要で、比較やシミュレーションなどの対話性、提案、動画、説明、第三者の意見などが効果的だ。購買段階では、サイト内のコンテンツを常時更新し、情報の矛盾が起きないような体制を整えておくことが大事だという。
要は、継続性、動機につながるような提案、双方向性、迅速な対応を備えたウェブを構築していくことが求められているのだ。それは現代の消費者動向に対応できる形でコンテンツを管理し、最適なエクスペリエンスを提供するための仕組みを整備することでもある。
そのためにウェブテンプレートを統一し、動画や画像を集中管理し、自社サイトだけでなく、関連会社や販売サイトなどでも、最新の画像や動画が映し出されるようにしていくことが大切だ。また、顧客接点から収拾したデータを、ひとつの基盤に集約することによって、製作、公開、分析のプロセスの連携がとれるようにしていく。こういったことを進めている企業の事例としてパナソニックのウェブ戦略のビデオも放映された。
このようにして、個客の理解と顧客体験の両輪をテクノロジーで結びつけることによって、個客の期待に応えられる世界ができていく。そしてこの世界の構築に、米フォーチュン誌が世界で最も賞賛される企業50社として選んだ企業の76%が採用しているAdobe Marketing Cloudの内包する製品群が役立っている。
アドビ システムズ 株式会社
代表取締役社長
佐分利 ユージン 氏
2014年7月にアドビ システムズ 株式会社の代表取締役社長に就任。IT業界で培った豊富な経験と知見を活かし、セールスやマーケティングからカスタマー サポートに至る全事業部門を統括し、日本のお客様に革新的なソリューション、高品質なサービスおよびサポートを提供することに注力。前職は、マイクロソフト社において19年間、リーダー職を務め、プロダクトマーケティング、オペレーション、営業、パートナー プログラムなどを牽引。2006年から2009年まで最高マーケティング責任者 (CMO) として同社の日本におけるマーケティングおよびオペレーションを統括。
特別講演Ⅲ
マーケティングトップが考える、組織の在り方とトップの役割
経営破綻から新しく生まれ変わった合同会社西友のマーケティングを、斬新な企画で指揮しているのがマーケティング本部担当執行役員の富永 朋信氏だ。「前例がないから新しいことをやるし、誰もやったことがないからリターンが大きい」を信条に、自ら手がけた具体的事例をまず披露していった。
一夜にして変身してしまったことをいかに顧客に伝えるか
メディアが取り上げたくなるような企画を考え抜く
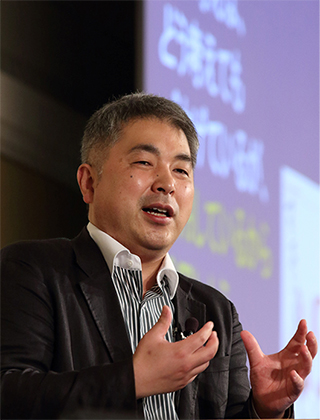
西友に転職するまでに数々のマーケティングの仕事をしてきた富永氏が、西友で最初に取り組んだ課題が、顧客の心に価格認知をいかにつくるかだった。西友は2002年からウォルマートの支援のもとに経営再建への道をたどったのだが、それは正反対の会社になることだった。西武グループの一員としてのスーパーマーケットだったころは、無印良品を世に送り出したり、糸井重里さんや林真理子さんをコピーライターとして起用したりと、文化のにおいのする会社だった。それがEveryday Low Priceを標榜するウォルマート傘下に入った途端、価格を売りにするスーパーに一夜にして変身した。
ウォルマートは、日本のスーパーがやるような特売にかけるコストをかけないことによって、すべての商品を少しずつ安くしていき、一品一品の値段は特売に負けることはあるけれども、買い物かごトータルで安くしていくという戦略をとる。

だから、特売をやらずに、価格認知を顧客の心につくらなければならなかった。そこでやったことが、新聞の全面広告。よく売れる10品目を買ったときのレシートを競合他社と比較するというもので、西友が一番安いですよというメッセージを伝えるものだった。
新聞広告ということで、スーパーのメイン顧客である主婦にメッセージが届かないという声が社内にあった。でもそれは織り込み済みで、ストレートな形の比較広告は、インパクトがあって、興味をひくから、かならずメディアが取り上げてくれるという読みがあった。そうすればテレビや雑誌を通してメインターゲットである主婦の目に届くと考えた。社内の会議では寒い空気が漂ったが、地道な説得を重ねて広告をだした結果、価格認知がそれ以前の10%から25%にはね上がり、今は50%くらいに上がっているという。
また、ユニクロなどのファストファッションがもてはやされた2008年頃、ウォルマート傘下でイギリスにジョージというブランドがあり、それをスーパーで売ろうとしたが全く売れず、マーケティング的にてこ入れした事例も紹介された。いろいろ考え抜いたすえ、原宿ラフォーレ最上階の大きなイベントホールでアパレルメーカーがやるような本格的なファッションショーを、全テレビ局とたくさんの雑誌を招待してやった。そのイベントにかけるお金があればテレビ広告を打つこともできたけれども、自己宣伝よりもメディアに代弁してもらったほうが効果的との判断によるものだった。
他にも、民意反映型のソーシャルCMという、およそスーパーのCMとは思えない支離滅裂なCMをだして、話題をかきたてたこともあった。ツイッターなどを通してこのイベントに直接参加した人たちは4万人、関連するリーチは300万件を超え、ふだん西友をあまり利用しない人たちに関心をもってもらうことができた事例でもあった。
CMOの心がけ
考え抜くこと、そして空気をつくって動かすこと

実際にだした広告や、社内の雰囲気が伝わるスライドを交えて、会場の笑いをとりながら事例を紹介したあと、富永氏が考えるCMOの仕事について語っていった。
社内を啓蒙することの大切さや、情報が氾濫している世の中で認知されることの難しさなどを前置きしたあと、CMOの心がけとして、一つは考えることと、もう一つは空気をつくって動かすことを敷衍していった。
まず考えるという点で、考え抜くことの大切さを語った。このアイディアでいけると思えるところまで考えているかだ。さらに考えるときに、アイディアのどこがダメかの減点法と、どこがいいかの加点法でみる見方があるが、加点法で考えないと、磨けば光るものも捨てられてしまうと注意を促した。
また、「空気をつくり、動かす」という点では、その前提となる注意点を語っていった。「コンコルドの誤謬」という、一回コミットすると引っ込みがつかなくなるような人間心理に言及し、会社のなかで、何かに拘泥してしまって正しい判断ができず、正しいお金の配分もできないような状況になっていないかを常に自分で考え、そのうえで空気をつくって組織を動かしていくことが重要だと指摘した。
上司の功罪というものも挙げられた。上司が「いいね!やってみれば」ということはあまりなく、「前例はあるの?去年はどうしていたっけ?」といった話になったりする。人間は現状維持が好きで、その人間としての性向をきちんと抑えて、みんなの反論は違うと、一見もっともらしく聞こえるけれど現状に固執しているだけだと理詰めで説明していくようなこともしないと、いいマーケティングはできないと声を上げた。
上司の誤謬もあるが、部下や代理店にも危険が潜んでいると続けた。気づいてみると、「このアイディア富永さんが好きそうだからもってきました」といったものにひっかかってしまうと。マネージャーとして自分が関所になってしまっているのだが、こうなると本当の意味での顧客志向が失われる。そもそも何が問題でどのようなソリューションを提供すればいいかが忘れられて、富永対策になってしまっている。だから、部下や代理店がもってくる提案の背景にある考え方のプロセスをよく考える必要がある。そこに自分対策のにおいを感じたら、うまく排除するようにリーダーとして動いていかないと、自分向けに矮小化されたアイディアしかでなくなり、お客様の心も離れていく、と。
これらの注意点を念頭に置きながら、前述したような社内でひんしゅくを買いそうな企画を通す場合、「まず大原則として、松竹梅のような選択肢を提示することは絶対にしないことだ」と富永氏は力説した。こちらが松をいいと思っていても、社長が梅を選択して、その真ん中の竹に落ち着いてしまうようなことが起こりがちだからだ。そして、一対多は不利だから会議の場で何か言われたら、完全にやっつけられないうちに撤収して、次の会議までに一対一で説得していくという。そして、相手が感情的になっていて理詰めがきかないときには泣き落としたこともあるそうだ。
とはいえ自分がやりたいことと、組織がやりたいことのギャップにも注意が必要だと念押しした。やりたいことばかりしていると周囲のサポートが得られなくなるから、組織に迎合するようなことや、他の人がやってほしいこともたくさんやりつつ、そのバランスした結果として面白いこともやって、自分の信頼やプレゼンスをつくっていくことが大事だと釘をさした。
合同会社 西友
マーケティング本部担当 執行役員 シニア・バイス・プレジデント
富永 朋信 氏
お客様の認知変容・態度変容・行動変容に関係することこれすべてマーケティング、という信念のもと、日本コダック(現コダック)、日本コカ・コーラ、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン、ソラーレホテルズアンドリゾーツなど、いくつかの企業でマーケティング関連の職務を歴任。現在は、合同会社 西友でマーケティング本部担当 執行役員シニア・バイス・プレジデントとして、コミュニケーションや調査関連業務に加え、プライベートブランドの開発も担当。座右の銘は「渾身のアイデアは全てを解決する」。
特別講演Ⅳ
「ななつ星in九州」にみる、顧客創出のマーケティング戦略

「『ななつ星in九州』はなぜ人気がたえないのか」という問いに、その生みの親である九州旅客鉄道株式会社代表取締役会長の唐池 恒二氏は、「気がぎっしりつまっているから」と答えられた。気とはエネルギーであり、具体的な行動でいうと手間を指す。
ぎっしりとつまった気がお客さまの感動をうみ
手間は価値をうみ、気は奇跡をうむ
「ななつ星in九州」が2013年10月に九州全土をめぐる最初のクルーズに出たとき、10万人を超える人々が沿線から手を振ってくれた。そのうちの5人に1人は涙ぐんでいたという。乗車されるお客さまは今も、列車がホームに入ってくると涙ぐまれ、列車に乗り込まれて再び涙するという。それくらいの魔力があり、それを何かと考えると唐池氏は「気」だという。ぎっしりと詰まった気がエネルギー変化を起こして、感動とか感激とかをうむのだと思うと。
「ななつ星in九州」はものすごい手間をかけてつくられた。長年一緒にデザインアンドストーリー列車をつくってきた工業デザイナーの「水戸岡鋭治さんの気の入れ方は尋常ではなかった」と唐池氏は言う。図面だけでも5000枚くらい描かれ、列車製作中にも新しい考えをどんどん具体化されるから、かかわった川崎重工と日立製作所の何千人という職人さんは、最後の数ヶ月ほとんど寝ていなかったという。弱って倒れそうになっている職人さんに、水戸岡氏は、「これをする」、「5ミリ狂っている」、「よくやった」と、叱咤激励を続け、車両製作の場が一つの戦場と化していた。

みんな世界一の列車をつくるんだと思っているから、それぞれが妥協せず、ものすごいエネルギーが投入された。塗装の前に鉄板を何度も磨き、その上に何重にも塗装したから列車はぴかぴかに輝いていて、周囲の景色がすべて映り込む。「こんな列車は世界に二つとない」と。
客室の洗面台には、人間国宝で十四代酒井田柿右衛門氏の有田焼の洗面鉢が据えられている。2013年6月に納品されたものだが、その一週間後に亡くなられている。ガンと戦いながら魂をこめてつくられた遺作だ。洗面鉢も含め、列車のなかの内装や家具調度はすべて部屋毎に少しずつ違う。
列車の壁には大川の組子という小さい木片を組み合わせてつくった建具が取り付けられている。福岡県大川の家具職人が総出でつくった。つくるのも大変だが、掃除も大変な代物で、木片の間の狭い隙間を毎日綿棒のようなもので掃除をしている。
この列車でどんな旅を提供するのかもゼロから考えていった。スタッフが世界中の豪華列車に乗って勉強した。三越やJTBのVIP対応の社員に話を聞いたりしながら、自分たちで勉強して悩んで考え抜いてつくっていった。
サービスにも手間をかけた。JALの国際線に17年乗ったキャビンアテンダントの人がクルーに応募してきたのだが、そのくらいのベテランですら、また1年間研修し直した。ディズニーランドや湯布院の亀の井別荘など、いろんなところにいき自分たちでサービスを考えていった。
そうやって車両の隅々まで、ソフトとハードのすべてに何千人という人の気が充満していて、そのエネルギーが乗られたお客さまの感動というエネルギーに変化するのだと唐池氏はいう。「気というものを投入すればするだけ、お客さまの感動の大きさに跳ね返ってきて、手間は価値をうみ、気は奇跡を呼ぶ」と。
世界一の列車の旅でお客さまを元気にし、地域も元気にする
「ななつ星in九州」が目指すものを全員で共有

だから、気がぎっしりつまっていることが一番のポイントだと強調したあとで、付随するいくつかの要因として、まず「夢見る力」を挙げた。それは25年ほど前、まだ唐池氏が副課長の頃、信頼する知人からアイディアをいただいたことに端を発していた。九州に豪華な寝台列車を走らせたら絶対に当たると言われたそうだ。当時の自分にはできるはずもない企画で、でもいつかつくりたいとそのアイディアをずっと温め続けた。そして6年前、2009年6月に社長になった翌月に、豪華寝台列車の検討を社内に指示した。
出来そうですという回答が2ヶ月後にでて、2010年頃に水戸岡氏に、「オリエントエクスプレスに負けない列車をつくりませんか」と持ちかけた。まだ自分自身その実現に半信半疑だったが、水戸岡氏も20年以上前から同じ夢をもっていたと聞いた。1ヶ月後に水戸岡氏が絵を描いてきてくれ、乗り気なのを知って、やろうと決断した。世界一の列車をつくろう、認知度の低い九州を世界に発信しよう、なによりも九州の人が盛り上がっていくような列車をつくりたいと、二人で手を握った。
そして、「ななつ星in九州」が目指すものをかかわる人全員で共有していった。お客さまの心を豊かにするような鉄道の旅を提供し、世界一の列車で九州を世界に発信するというコンセプトを明確にした。サービスの基本的な考え方として、お客さまを家族の一員、友人のように寄り添うサービスにしようと決めた。「ななつ星in九州」はお客さまを元気にし、地域も元気にし、私たち自身も元気にすることをみんなで誓った。
そして広告宣伝よりもブランド価値を高めることに重きをおいた。駅に一枚のポスターもはらず、駅で販売せず、申し込みはすべてツアーデスクに一元化し、販売チャネルを限定した。
お客さまから最初の問合せや申し込みの電話をいただいたときから、旅を終えて家に帰るまでを想定してサービスを考えていった。出発のときには旅の感動の半分は終わっているという。なぜなら、当選の電話から乗車までに20回くらいのやりとりがあって、食事の好みや身体の状況など含め、詳しく聞いて準備をしていくからだ。
広報宣伝戦略では情報をコントロールした。なによりも「ななつ星in九州」をみせない方法をとった。車両製作でも職人さんの携帯を没収し、映像がインターネットなどに流れるのを防いだ。車両にカバーをかけて試運転もした。見せないからマスコミもいらだってきて盛り上がるという効果もあった。だからオープンにしないのも一つの方法だという。
そうやってブランド価値を高めた「ななつ星in九州」は、今も半年毎に行われる申し込みに20倍以上の申し込みがあるという。そして乗車されたお客さまの4組に1組は、降りたと同時に次の旅の申し込みをされるという。
最後に唐池氏はマーケティングといっても、所詮「人の力」ですと声を大にした。トップの思いと決断、水戸岡氏の神のような業、リーダーの情熱、職人さんやクルーたちの高い意識、すべてが結集して「ななつ星in 九州」は可能になった。
九州旅客鉄道株式会社
代表取締役会長
唐池 恒二 氏
1977年日本国有鉄道入社、1987年国鉄分割民営化に伴いJR九州に入社。「ゆふいんの森」などデザイン&ストーリー(D&S)列車の運行や、博多~プサン間の高速船就航に尽力。その後グループ会社JR九州フードサービス社長に就任し、赤坂「うまや」を出店し東京進出を果たす。2009年6月、JR九州社長就任後、九州新幹線全線開業、博多駅駅ビル「JR博多シティ」開業、外食事業の上海進出、農業への進出も果たす。クルーズトレイン「ななつ星in九州」は企画から運行までの陣頭指揮を執った。2014年6月、JR九州会長に就任。
SPECIAL LIVE対談
日本から世界を面白くする!
これからのマーケティングと日本の戦い方!
僕たちよく似ているんですと肩を組んで意気投合したあと、脳科学者の茂木 健一郎氏がモデレーターをつとめ、起業家 森川 亮氏 との「日本から世界を面白くする」と題した対談が始まった。以下そのハイライトを紹介する。
商品やサービスはわかりやすさが肝
日本のよいところをシンプルにだしていけばいい

茂木 森川亮さんはLINEというインターネット上の新しいサービスを立ち上げて、世界でもユーザーを獲得した方で、今度、日本初の世界プラットフォームを目指す「C CHANNEL」という事業を立ち上げられたと聞きまして、その内容からまずお話しいただけますか。
森川 日本を元気にするようなビジネスをやりたいと考えるなかで、世界で成功したメディアブランドが日本から生まれておらず、昔のMTVのようなブランドをつくりたいと思って立ち上げました。CはコミュニケーションのCで、映像文化のなかで映画は見に行く時代、テレビはそれを家で受像器で受け止める時代をつくったから、自分たちは映像でコミュニケーションする時代をつくろうと思って社名につけました。
かわいいファッションとかヘアメイク、和食を中心とした食文化、日本の観光スポットなどを、クリッパーという人気モデルやタレントが自分たちでとった画像で紹介していきます。中身を審査しているのでクオリティは保たれています。
今世界でインターネットの動画へのシフトが起きていて、それが地上波からケーブルに移ったころ、CNNやMTVがでたころに似ているんです。アメリカではスターがテレビから生まれておらず、YouTuberのようなところからでてきています。日本は少し後れていますが、その波がくると思っています。

茂木 日本から海外に発信する際のポイントは何ですか。
森川 サービスや商品のわかりやすさがとても重要です。潜在的なニーズからイノベーションは起こるけれども、潜在的なニーズをメッセージでだすと、だいたいはずしてしまいます。潜在的なニーズを商品化するけれども、メッセージは顕在化に置き換え、そうすることでユーザーが受け止めやすくするのです。
たとえば、LINEの場合、その潜在的ニーズはテキストとかスタンプのメッセージでしたが、そういうメッセージングというのが一般には理解されませんでした。それで無料通話だと宣伝したんです。通話は有料だとみな思っていますから、それが無料になっただけでものすごい価値を感じるわけです。わかりやすい一言が重要で、それが潜在的ニーズとマッチしていなくてもユーザー数を伸ばしていけます。
茂木 人間の脳をアディクション(中毒)させるのが一番のポイントですが、なんでこのサービスにアディクションしているのかがわからないときに一番強烈にきくというところをついていますね。わかってしまうとあきるんですよね。
森川 海外で展開するときは、顕在化するメッセージに、各国の幸せの像をかけあわせるようなことをしていました。ラテン系の国だとカップルが一番幸せそうに見えるそうで、そうすると、けんかしたカップルがラインを使って仲直りするような動画をだしたあとに、「無料通話」というメッセージをだすとかなりひきが強かったりしたんですね。
成長のスピードが鈍化したときに新しいことを始められるか(森川)
らしさの壁を破る(茂木)

茂木 転職したり、事業をがらっと変えたりするときのコツは。
森川 なぜ変えるのかという問いに置き換えさせてもらうと、人間で一番大事なのは時間単位あたりの成長のスピードだと思っているからです。仕事になれると成長のスピードが鈍化しますし、能力が高くなると、その分野において上がいなかったりして、そこも鈍化します。成長のスピードが遅くなったときに次の成長をいかに見出すのか、それは事業にも言えることで、一つ成功して、それが成熟すると成長率が鈍化する。そういうときに新たなことを始められるかということを、事業でも個人でも僕は意識しています。
茂木 脳科学でいうと、ドーパミンは新規なもので放出されるので、ドーパミンをだしつづけるには新しいことにチャレンジし続けなければならない。チャレンジするには不安を乗り越えなければならないのですが、不安を乗り越えるには安全基地が必要だといわれています。これを確保しているから安心してチャレンジできるというようなことですが、森川さんの安全基地は何ですか。
森川 死なないことではないでしょうか。日本は平和だからがんばれば食べていけますから、ある意味、日本は失敗してもいい大国ですよ。
生きるとは何かを考えたんですが、どれだけ多くの人を幸せにできるかではなないかと思うようになったんですね。多くの人を幸せにすることが生きる実感につながるといったことです。だから僕が金儲けをするとか有名になるとかではなくて、元気がないこの今の日本を元気にするために全力をつくすことかなと考えて、C CHANNELも立ち上げたのです。若くて元気な人を見ていると元気になるからということもありましたね。
茂木 自分のためだと一人分のエネルギーしかでないけれど、みんなのためというと、たくさんいるからものすごいエネルギーがでるし、脳には他人のためにやると、自分が嬉しい回路と同じ回路が働くことがわかっています。日本のため、他人のためとやっている森川さんは自分の報酬回路が働いているんですね。ところが、若い時は自分がなんとかなりたいと思うから、自分に閉じてしまってなかなか話が広がらないんですね。
会場からの質問 人間の本質的な欲求は脳科学の観点で何ですか。
茂木 物質的な欲求が満たされたあとは、関係性欲求や承認欲求でしょう。ラインにしろツイッターにしろソーシャルメディアといわれているものは関係性の欲求を満たそうとするものです。
そういう点でこれから面白いのは、人工知能が未知の人に出会うときのリスクをどうヘッジして、フィルタリングやマッチングを洗練させていくかで、私は次のものすごいビジネスチャンスがそこにあると思っています。たとえば英語を習いたいとして、ある人とマッチングされても、その人のことを知らないから少し不安になる。実はわれわれはもっといろいろな人と知り合いたいという欲求はあるのだけれども、リスクだとかが分からないから二の足を踏む。そこを人口知能技術でマッチングしていくようなサービスが伸びていくと思っています。
森川 採用などでそれを使うべきだという話がすでにあります。企業と個人のマッチングにおいて今は面接など無駄な時間が多い。それで、企業のニーズと個人のニーズをある程度自動的にマッチするような技術はいくつかでてきています。
会場からの質問 自分の壁をどのように打ち破ってきましたか。
森川 後悔はしたくないと思って、いつも辞表をカバンに入れ、それがだめならやめますくらいの気持ちでやってきました。
茂木 自分は大学教授や小説家、キャスターや科学者などの多面な顔をもってやっていて、学者の人たちからはひんしゅくをかったりしていますが、らしさにとらわれることが人間の壁をつくりますから、らしさの壁を破ることを心がけています。
起業家
森川 亮 氏
1967年1月13日生。1989年筑波大学卒、日本テレビ放送網株式会社入社。1999年、青山学院大学大学院国際政治経済学研究科修士課程を修了しMBA取得。その後ソニー株式会社に入社。2003年、ハンゲームジャパン株式会社に入社、取締役を経て、2006年10月、取締役副社長に就任。2007年10月、NHN Japan株式会社(ハンゲームジャパンより商号変更)代表取締役社長に就任。同年11月、ネイバージャパン株式会社設立に伴い、ネイバージャパン代表取締役社長を兼務。2013年4月、NHN Japan株式会社の商号変更により、LINE株式会社代表取締役社長に就任。2015年3月、同社代表取締役社長を退任し、アドバイザーとして顧問に就任。
脳科学者
茂木 健一郎 氏
1962年10月20日東京生まれ。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て現在に至る。専門は脳科学、認知科学。「クオリア」(感覚の持つ質感)をキーワードとして脳と心の関係を研究するとともに、文藝評論、美術評論などにも取り組みながら、作家、ブロードキャスターとしても活躍の幅を広げている。2005年、『脳と仮想』で第四回小林秀雄賞を受賞。2009年、『今、ここからすべての場所へ』で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。2006年1月~2010年3月、NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』キャスター。

