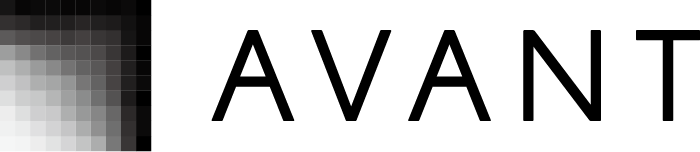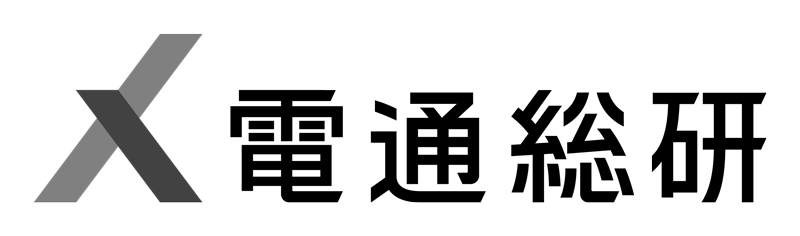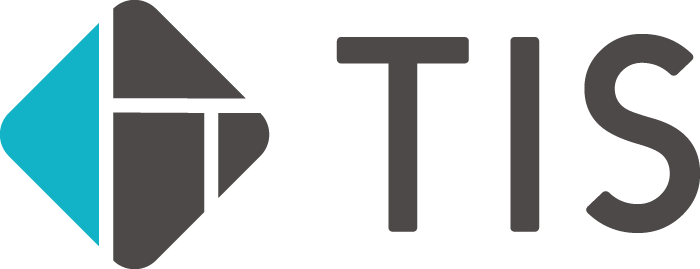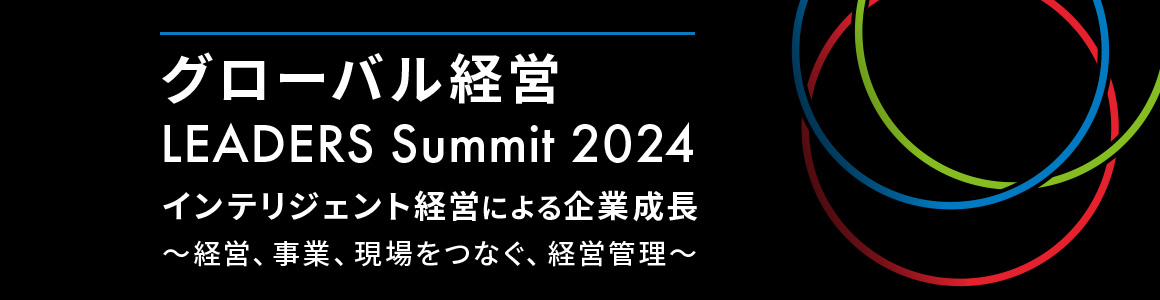
開催日:2024 年 11 月 14 日(木)
会場:ホテル雅叙園東京
共催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局、 Wolters Kluwer CCH Tagetik
協賛:
プラチナスポンサー: 株式会社アバント、イー・アール・エム日本株式会社、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社、株式会社電通総研、PwCコンサルティング合同会社
ゴールドスポンサー: 日本アイ・ビー・エム株式会社
シルバースポンサー: FPTコンサルティングジャパン株式会社、TIS株式会社
近年、国内投資の重要性が高まる一方、日本企業の海外事業展開は加速し、グローバルでの売上高は拡大傾向が続いています。加えて従業員も連結では海外拠点法人に従事する割合も増え、まさにあらゆる経営資源、ヒト・モノ・カネのグローバル化は加速しています。
しかし、グローバルでの売上は拡大している一方、“稼ぐ力”は低水準に留まっているのも実態です。製造拠点の海外移転や海外での販売網の構築など、いわばオペレーションのグローバル化は進んできたものの、そのグループ全体をいかに束ね、ガバナンスを効かせるかというマネジメントについては、未だ日本型の経営を維持したままの企業や、なかなか上手くいかず苦慮している企業が多いのではないでしょうか。
このような環境変化が激しいグローバル市場において、日本企業がグループ全体で稼ぐ力を高め、競争力をさらに強化するためには、全社視点で最適化された仕組みの整備とマネジメントが必要です。ヒト・モノ・カネ・データに関する経営の共通基盤を、個別最適ではなく、グループ全体でタテヨコをシームレスに繋げ、全社視点でタイムリーな経営の意思決定を行っていくことが、真のグローバル経営を実現する鍵となります。
本イベントでは、このような真のグローバル経営による企業成長を実現するマネジメント、そして、経営・事業・現場をつなぐ経営管理基盤のあり方について、先進企業の取り組み事例や今押さえたい最新トピックをもとに、考察を深めていきました。
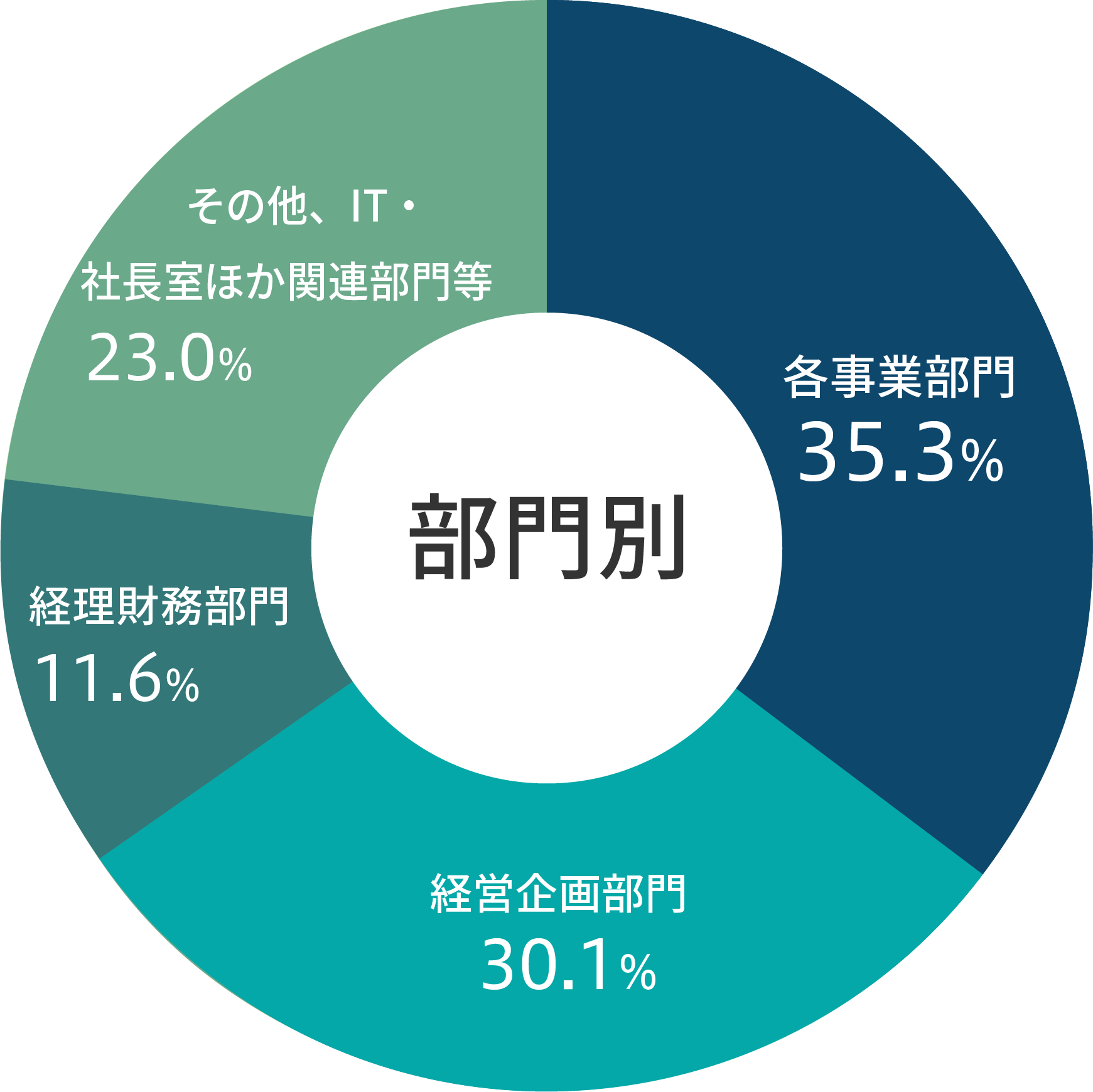
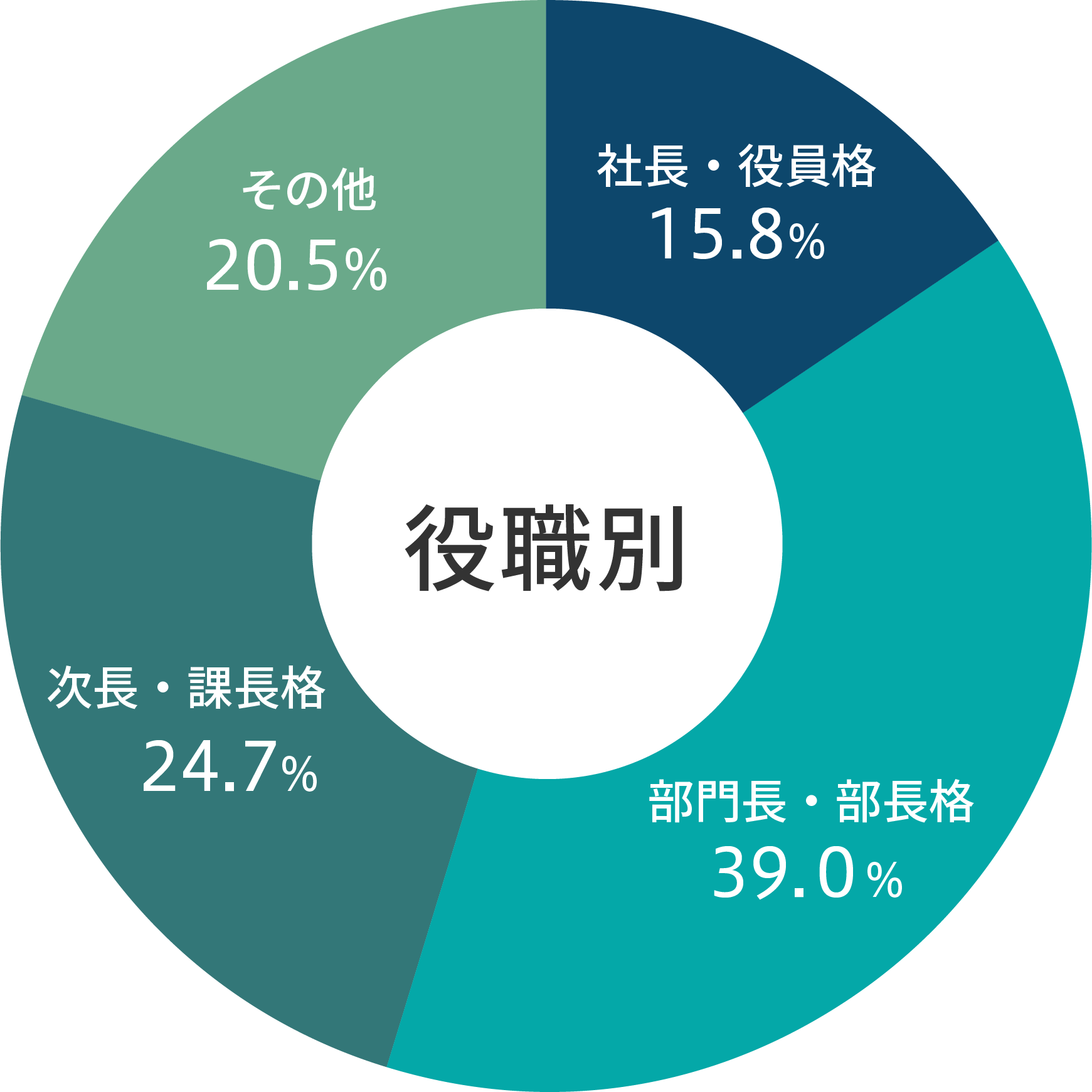
オープニング
経営管理の新時代を切り拓く
Wolters Kluwer CCH Tagetik 日本代表/日本マネージングディレクター
箕輪 久美子

グローバル経営 LEADERS Summit 2024は、Wolters Kluwer CCH Tagetik日本代表の箕輪久美子の挨拶で幕を開け、企業価値向上に向けた新たな経営管理の在り方を提起しました。
日本では企業価値の向上が大きなテーマになる中、「その実現に向けて『組織の稼ぐ力』と『将来に向けた成長投資』との両面から取り組む必要があります」と強調。
「そのためには、ROICの仕組みの構築とより現場を巻き込んだ改善活動や、事業ポートフォリオを分析、シミュレーションし、ESGの視点を盛り込みながらイノベーションに投資して新陳代謝を推し進めることが重要です。しかし、多くの企業ではシステム面での課題に直面しています。ERPに大規模な投資をしたものの、データの整合性や粒度が合わなかったり、コード体系がバラバラで必要な経営情報をタイムリーに分析できなかったりするという声も聞かれます。
さらにESG/サステナビリティへの対応という新たな課題も浮上しています。非財務情報の開示要求が加速し、グループ会社からのデータ収集が大変という課題も顕在化。将来的には第三者保証の段階的な導入が予定され、会計監査と同じレベルでワークフローや履歴管理、財務・非財務を合わせたデータガバナンス基盤が求められているのです」
企業変革を支える経営管理プラットフォーム

こうした経営課題や規制対応を支援するのがCCH Tagetikの経営管理プラットフォームです。
「グローバルの経営情報を明細から財務・非財務まで1カ所に集約し、制度連結・開示、事業ポートフォリオ、各事業の業績管理、収益性分析、予算管理、国際税務、ESGまでも、1つのプラットフォームで管理できる業界唯一のソリューションです」
連結ベースのサマリー情報から明細情報へとドリルダウン分析することができ、明細や現場の情報を的確に把握したいという経営者の方々から評価されています。
「ここ数年、CCH Tagetikが積極的に投資してきたのがAI領域です。Intelligent PlatformとしてAIを経営管理プラットフォームに組み込んで提供。通常、AIの導入にはデータを準備するプロセスが必要ですが、CCH Tagetik上に一元管理されているデータを使い、高度なAIをすぐ経営に生かすことが可能です」
グローバル競争が激しくなり、変化が加速する社会において、「日本企業が新たなイノベーションを起こし、世界をリードしていけるよう、CCH Tagetikはパートナー企業の皆様と一丸となり、日本企業のさらなる成長のための変革を確かな技術と実績でしっかり支えてまいります」と箕輪氏は思いを新たに語りました。
基調講演
財務・非財務戦略によるPBR改善の処方箋
~非財務資本と企業価値を繋ぐ柳モデルとインパクト会計~
早稲田大学大学院会計研究科 客員教授
元エーザイ株式会社 専務執行役CFO
柳 良平 氏
柳良平氏は「財務・非財務戦略によるPBR改善の処方箋」をテーマに基調講演を行いました。まず、企業が稼ぐ力を取り戻すには、イノベーションや成長のための投資ありき、企業経営ありきが重要であり、インテリジェント経営、データドリブン経営を進める必要があると言います。
そして、PBR(株価純資産倍率)向上への処方箋として、株主資本コストを上回るROE、価値創造を前提とする正のエクイティ・スプレッドを創出する財務戦略が鍵を握ります。さらに、「PBR向上のためにはESGや見えない価値を見える化し、非財務資本を定量化して企業価値をつなぐことが重要です。そのツールとなる柳モデル・インパクト加重会計を提案しています」
ESG・見えない価値を見える化する
非財務戦略

PBR向上が日本企業の課題となる背景として、2022年度の東証のデータではTOPIX500の企業のうち43%がPBR1倍割れ、40%の企業がROE8%未満であり、ROEが株主資本コストの目安に届かず、エクイティ・スプレッド(ROE-株主資本コスト)がマイナスになっている実態があります。PBRの国際比較でいえば、世界の平均はPBR2倍となっており、「日本も同等のPBR2倍になれるはずです」と柳氏。
「PBR、企業価値を向上させるには株主資本コストを上回るリターン、エクイティ・スプレッドをプラスにしないとPBRが1倍以上になりにくいという傾向が長期的にあり、イノベーションによって稼ぐ力を取り戻すことがポイントになります。この稼ぐ力を取り戻すのが財務戦略であり、人的資本や知的資本、製造資本などの見えない価値を見える化するのが非財務戦略です」
財務資本とともにESGのような非財務資本を企業価値としてPBRの倍数に反映すべきという仮説に基づき、非財務とエクイティ・スプレッドの同期化モデルとして提案されたのが「柳モデル」です。
「非財務資本は5年、10年超といった長期の遅延浸透効果によって企業価値を高めるという仮説から、重回帰モデルを策定しています」
人材や研究開発などへの投資が
5~10年超先のPBRを向上
柳モデルの例として、柳氏がかつてCFOを務めていたエーザイの事例を紹介しました。「人件費投入を1割増やすと5年のPBRが13.8%向上する」「研究開発費を1割増やすと10年超でPBRが8.2%拡大する」「女性管理職比率が1割改善すると7年後のPBRが2.4%上がる」「育児時短制度利用者を1割増やすと9年後のPBRが3.3%向上する」といったデータが示されています。
「この結果、エーザイのESGのKPIが各々5~10年超の遅延浸透効果で企業価値が500億円から3,000億円レベルを創造することを示唆しています。ただ、こうした数値は相関であって因果ではないという声も聞かれます。そこで、企業としてはこの相関関係をアカデミックな重回帰分析で示す一方、ESGと企業価値の説明、開示を徹底的に行う必要があります」と助言します。
柳モデルは日本企業全体(TOPIX100、500)の傾向に人材への投資(人件費)、知的資本への投資(研究開発費)のPBRへの遅延浸透効果があることも示されています。
「1~2年の短期間では効果は発揮されず、5~10年以上といった長期的なビジョンで人的資本や知的資本に投資し、そのプロジェクトの意義を説明、説得することが重要です」
データドリブン経営を進め
経営管理基盤を整備

さらに、柳氏はインパクト加重会計について説明。インパクト加重会計とは、売上収益から費用を引いた財務上の利益に対し、環境、製品、雇用のインパクトのプラス・マイナスを計算してインパクト利益を算出するものです。
「エーザイの製品インパクト会計を例にすると、発展途上国でまん延していた熱帯病治療薬を無償で提供しています。延べ1,900万人が服用し、治療薬によって削減できた医療費や生涯の労働時間などを試算するとライフタイムで約7兆円(年間約1600億円)の価値を創造したことになります」
柳モデルやインパクト加重会計をツールとした非財務戦略を進める上で重要になるのがパーパスです。エーザイでは患者様と生活者の皆様への貢献を企業理念として定め、熱帯病治療薬の無償供与もパーパスに沿ったものです。
「人件費や研究開発費に投資し、患者様を救うことが5年、10年後に企業価値、PBRを高めるのにつながります。柳モデルはパーパスの証明でもあるのです」
柳氏は「非財務の定量化などの基盤として、データドリブン経営を進め、ソリューションパッケージなどを通じて財務、非財務データのシミュレーションを行うなど、目標設定の仕組みづくりに向けて経営管理基盤を整えることが重要です。皆さんと一緒に日本企業の価値を高め、世界を変えていきましょう」と締めくくりました。
特別講演
味の素グループの企業価値最大化へ向けた
パフォーマンスマネジメント
味の素株式会社 執行役常務(財務・IR担当)
水谷 英一 氏
味の素株式会社執行役常務の水谷英一氏が特別講演を行いました。まず、味の素グループが取り組む「ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)」について説明。企業が自社の売上げや利益を追求するだけでなく、自社の事業を通じて社会が抱える課題や問題に取り組むことで社会的価値を創造し、その結果、経済的な価値も創造されることを意味します。「経済価値と社会価値を創造する取り組みがASVであり、ASVを進化させていくことが味の素グループのビジョンの実現につながります」と語る水谷氏。
その取り組みの一例として、東南アジアの小学校で行われている栄養教育の支援や、牛の飼料を自社技術で改善した飼料に置き換えることで乳業メーカーや畜肉メーカーのGHG排出量削減や飼料コスト低減を可能にするなど、社会貢献の事例を紹介しました。
投下資本利益率の向上に加え
資本コストの低減に注力

続けて水谷氏は、味の素グループの「中期ASV経営 2030ロードマップ」と企業価値向上へ向けた取り組みについて解説しました。グループでは経済価値の指標の一つとしてROIC(投下資本利益率)を導入。FY23の実績8.7%に対して、FY30の計画は約17%の目標を打ち出しています。
「社会価値の指標の一つである環境負荷削減の取り組みでは、FY30に環境負荷50%削減の目標のほか、栄養コミットメントの取り組みでは10億人の健康寿命延伸の目標を掲げています。ASV指標が飛躍的、継続的に向上し、ステークホルダーや社会にとって魅力的な企業であり続けることを目指しています。
そして、ステークホルダー価値の向上、企業価値の向上には着実なキャッシュ・フローの創出がポイントになります。その算定ではPL、BSのみにフォーカスするのではなく、PL・BS・CFそれぞれに与えるインパクトを定量化し、フリーCFにプラスの影響を与える取り組みになっているか検証することが肝要です」
また、ROICの向上に加え、WACC(資本コスト)低減の取り組みにも注力。WACC低減のためには、明瞭かつ投資家にフレンドリーな開示、ローリングフォーキャストの推進、事業ポートフォリオの構築などの施策が挙げられます。
「グループ全体でローリングフォーキャストを推進することで、グループ会社の業績のブレを少なくすることにより、WACCの低減を図る活動を進めています」
FP&A人財を適材適所で配置し
組織とネットワークを構築
水谷氏はファイナンス部門主導で行ったASV向上に向けた取り組み事例も紹介しました。味の素の組織は10事業部、200超のビジネスユニットで構成され、約135カ国、117の生産工場で事業を展開しています(2023年3月末現在)。
「経営管理マトリクスも複雑になり、経営管理にはFP&A(Financial Planning & Analysis)とT2(Treasury & Tax)の思考と実地に基づいた経験則(タフ・アサインメント)が必要です。理想のFP&A像は、地域本部や事業本部、各法人の事業部など、FP&A人財を適材適所で配置することです。そして、事業部組織と人財ネットワークを構築するとともに、財務組織でも全社視点を持ち高品質なサービスの提供や外部・他部門とのつながり、人財育成、DX推進を担い、企業価値の向上に寄与することで、ASV向上の取り組みをグループ全体に浸透させていきます」
CCH Tagetikを活用し
管理会計データの一元化を推進

また、同社は適切な税対応、税情報の開示を行うことで、DJSI(The Dow Jones Sustainability Index)における税務戦略の評価点数の向上を実現しています。
「税務法規の順守、税務リスクの管理および適切な納税と、これらを支える透明性の高い税務ガバナンス体制を運用するため、グローバル・タックスに関するグループポリシーを制定、開示しています。またさらに透明性を高めるため、TTC(Total Tax Contribution)レポートの作成・開示にも取り組んでいます」
従来は管理会計にかかわるデータ(予算、見込、実績、財務、非財務情報)を個別のシステムから収集していましたが、「現在はCCH Tagetikの機能を生かして各種データを一元的に抽出・処理が可能になるなど、管理会計データの一元化を進めています」。
さまざまな取り組みの結果、2013年からの10年間で時価総額は約3.5倍の2.95兆円になるなど企業価値の向上につなげています。また、EPSはFY2030に3倍(FY2022比)を目標に掲げており、今後も企業価値向上の取り組みを加速します。「味の素グループの財務部門は、財務、非財務の両面からさまざまなステークホルダーへの情報提供を行い、価値創造に貢献していきます」と強調しました。
ブレイクアウトセッション <電通総研 & 味の素>
味の素グループの経営を支えるCCH Tagetik
~中長期的な課題対応力強化に向けた取り組み~
味の素フィナンシャル・ソリューションズ株式会社 シニアマネージャー 依田 忠之 氏
株式会社電通総研 グループ経営ソリューション事業部 プロジェクトマネージャー 高橋 良 氏
味の素フィナンシャル・ソリューションズの依田忠之氏が「味の素グループの経営を支えるCCH Tagetik導入事例」の講演を行いました。味の素グループでは企業価値の向上を目指し、管理会計の高度化と情報の一元化に向けた取り組みを行っています。
その一つが、中期経営計画を廃止し、精緻な数字の作り込みを伴わない「ロードマップ」への考え方のシフトです。ただ、ロードマップで求める財務数値は要約された連結PL、BS、CFと主要なKPIに限定し、大きな戦略ストーリーや課題を議論するためのものです。
多種多様な管理会計データの対応や
非財務データの拡張性を考慮して選定

環境変化をタイムリーに捉えて対応するには「業績見通しと実績のギャップを早期に把握し、アクションにつなげることがロードマップに欠かせません。そこで、ASEAN地域で先行導入していたローリングフォーキャスト(RF)をベスト・プラクティスとしてグローバル展開を進めています」と依田氏は説明します。
RFの実装にあたりシステムで考慮した点として、予算、業績見通し/RF、実績といった多種多様な管理会計データをカバーできることと、数量や重量も含めた非財務データの収集に関して拡張性があることです。「この2つに特に焦点を当てて複数のEPMツールを検討した結果、CCH Tagetikを選定しました。ソフトウエアとして優れていることはもちろん、システム開発に際して技術力と知見のあるベンダーがいることも、重要な要素となりました」(依田氏)。
CCH Tagetikで経営管理データの
一元管理や収集業務を効率化
味の素グループでは、財務データ、非財務データを別システムで集めており一体的な活用が難しいことや、決算、予算、RFなどの管理会計業務プロセスが別々のシステムに点在していること、Excelファイルの手集計やデータの分断などで作業負荷が大きいといった課題がありました。
そこで、「CCH Tagetikの導入により、経営管理データの一元管理と処理の自動化・効率化をはじめ、経営管理データの収集業務プロセスの簡素化・集約、そしてレポート作成業務の効率化・分析の高度化など、経営管理基盤の構築を目指しました」(依田氏)。
CCH Tagetikの開発はステップに応じて、適用範囲を拡張。ステップ1はRFの実装で、すでに完了しています。ステップ2は非財務データの収集・移管で、現在進行中です。ステップ3は連結予算の作成・移管、ステップ4は連結実績作成・移管というように、「RFの実装から開発に着手しましたが、今後は連結予算作成、連結実績作成など、関連する連結業務のプロセスを順次CCH Tagetikに集約し、管理会計用途のデータ一元化を進めます。また、事業部門でのユースケース開拓を進め、管理会計基盤の充実を図る計画です」と依田氏は話します。
RF業務をシステム化し、収集から
分析までCCH Tagetik内で完結

味の素グループのCCH Tagetik導入を支援するのが電通総研です。同社は認定技術者を多数有し、プラチナパートナーとして豊富な導入実績があります。味の素グループの導入プロジェクトを担当した電通総研の高橋良氏は「味の素グループ様は、最終的には管理/制度の財務、非財務データの収集機能をCCH Tagetikに一本化することを予定しています」と話します。
具体的には、入力機能やワークフロー機能を活用し、グループ会社からの予算、実績、RFといった管理/制度データの収集を一本化することで作業負荷の軽減が可能なほか、標準機能のETLを活用し、効率的なデータ連携機能の構築が可能です。
また、連結/単体、財務/非財務の経営管理データを同じプラットフォームで一元管理が可能なことや、標準機能の連結処理を活用して管理連結などの処理の自動化、効率化が可能なこと、多彩なレポート機能と既存BIツールを活用してレポート作成業務の効率化や分析の高度化が可能なことなど、「経営管理データの収集からアウトプットまでのプロセスをCCH Tagetik上で簡素化し、集約することができます」と高橋氏は一本化のメリットを説明します。
そして、収集プロセスのうち、グループ各社、事業部、本社のRF業務のシステム化について説明。「短期目標(予算)および中期目標の達成に向け、アクションプランをスピーディかつ的確に立案、実行するために、階層ごとのRF業務をシステム化し、データの収集から処理、分析までのプロセスをCCH Tagetik内で完結するものです」(高橋氏)。
また、CCH Tagetikで収集したデータをもとに事業別ROICを自動計算し、前年同期と比較が可能な事業別ROIC管理について解説。「味の素グループ様では経営管理データの一元化に向けてCCH Tagetikの導入を段階的に進めているところです」と高橋氏は味の素グループの経営を支えるCCH Tagetik導入の進捗状況を説明しました。
ブレイクアウトセッション <アバント>
データドリブンな経営判断でビジネス変革を推進
~CCH Tagetikによる「製品別損益管理・分析」実現事例~
株式会社アバント 事業統括本部 CPMソリューション事業部 執行役員事業部長
梅田 信介 氏
グループ経営管理・連結会計などのソフトウエア開発を行うアバントは、数多くの企業へCCH Tagetikの導入支援を行い、ゴールドパートナーに認定。さらに日本のパートナーの中で最多のプライムプロジェクトを完遂したことによりBEST PROJECT OF THE YEARを受賞しています。アバントの梅田信介氏は、データドリブン経営の実現に向けた取り組みの一つとして、経営管理の基本である「製品別損益管理・分析」のポイントをCCH Tagetik導入事例とともに紹介しました。
顧客・製品・製造原価・運賃など
さまざまな軸で管理する多軸収益管理

アバントが取り扱う経営管理領域の主要テーマとして、顧客・商品・組織の情報を明細レベルまでドリルダウンが可能な「連結・多軸収益管理」、国内・海外の子会社から予算や実績などの情報を効率的に収集し、連結予算などを迅速に行う「グループ予算管理」、グループ全体での原価を策定することで連結コスト構造を明らかにする「連結原価分析」、ROIC算出の仕組みを作り、事業評価を行う「ROIC経営情報管理」の4つを挙げます。
そして、多軸経営管理について、梅田氏は「シンプルに考えると、誰に何をどれだけ売り、いくらで、どれだけ費用をかけて、いくら稼いでいるのか。そして、どこで生産すると最適なのか。顧客、製品、販売数量、販売単価、製造原価、運賃・物流費、販売管理費などの多軸で管理・分析することが重要です」と説明します。
「例えば、顧客、製品に対する販売数量を分析することで販売戦略通りに進捗しているかどうかを把握したり、販売単価についてはコストを価格に転嫁できているかといった市場価格の変化とプライシング戦略に役立てたりできます。収益の観点だけでなく、コストについてもどれだけ費用がかかっているかを、製造原価、運賃物流費、販売管理費を適切に分け、粗利、限界利益、営業利益の断面から、顧客、製品の軸で管理できるようにすることがポイントです」
多軸収益管理のシステム構成に
適した機能を備えるCCH Tagetik
多軸分析により、経営層は連結・会社・事業の単位で担当レイヤーの業績を把握できます。また、事業、商品、顧客のポートフォリオを可視化し、戦略的にどこに経営資源を投資すべきか検討し、そのリターンを計画通りに得られているかを把握するなど、経営層と事業サイドが一体となり、戦略の策定から計画、実行のPDCAサイクルの実現を支援するシステムとなるのが多軸収益管理です。
「多軸収益管理を実現するシステム構成のポイントは、多次元管理と明細管理、多軸配賦ができることです。いずれのポイントにおいても、CCH Tagetikは機能群をそろえており、多軸収益管理テーマにおいて、多くのお客様にCCH Tagetikを活用したシステム導入を進めています」
CCH Tagetikによる製品別収益管理・分析実現の事例として、大手化学メーカーの株式会社UBE様の取り組みを紹介しました。システム導入の目的は、業務のシンプル化・効率化による予算業務の効率化をはじめ、PLベースでの損益管理PDCAサイクルの定型化、シンブル化された業務管理プロセスを展開することです。これらに加え、グループ全体でデータに基づく迅速な意思決定が可能なマネジメントシステムを確立する狙いがあります。
「UBE様は約20の事業領域があり、それぞれの事業で業務プロセス、特に製品別PLを作成するための配賦ロジックが異なります。CCH Tagetikの導入により、基本予算作成業務の核となる製品別PL作成業務をシンプルにするためシステム化することと短期導入を目指し、まず11事業領域からスタートしました」
CCH TagetikのFW配賦など
標準機能をPoCで評価・検証
ステップ1は既存業務の運用ルールおよび業務フローの見直し。ステップ2は事業領域の対応など基本予算策定機能の開発、ステップ3は販売計画データや人員データなど上位システムとの自動連携対応です。「ステップ1では1つの事業領域に絞ってPoCを行い、多数の配賦ロジックをCCH Tagetikのファイナンシャルワークスペース(FW)機能でノーコード開発できることを確認しています」と説明。
そして、短期導入を実現したポイントとして、PoCを通じて要件や課題を整理し、CCH Tagetikの標準機能をベースに実装するなど想定した機能を大幅に変更することなくプロジェクトを推進できたことや、利用部門とミーティングを行い、機能と業務要件のギャップなどはその場で解決したことなどがあります。
「ステップ2では、膨大な配賦設定とその他機能を短期間で導入しています。CCH Tagetikの標準機能が優れているだけでなく、お客様とアバントの密接なコミュニケーションが成功のポイントです。当社はお客様の経営課題に対して、経営管理プロセスの設計整備、データ設計の観点から分析モデルを用いて支援します。そして、CCH Tagetikを利用してお客様の業務に最適な形でアジャストすることができます」と梅田氏は強調しました。
ブレイクアウトセッション <EYストラテジー・アンド・コンサルティング>
待ったなし!失われた30年を取り戻すために
CFOが今すぐ取り組むべき7つのアジェンダ
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 ファイナンスリーダー パートナー
田中 雅史 氏
CFOは人員不足などの課題を抱えながら業務を確実にこなし、経営の期待にどう応えていくか悩みは尽きません。EYストラテジー・アンド・コンサルティングの田中雅史氏は、同社が多数のCFOと議論を重ねる過程で見えてきた、CFO共通の悩みと取り組むべきアジェンダや、アジェンダに共通するデータの手の内化の必要性、グループ統合データ基盤を作る上での要諦について話しました。
まず、CFOが抱えるフラストレーションについて言及。
「株主の利権確保のプレッシャーなど外部要請への対応や、経理財務部門の人材確保の難しさや働き方や価値観の変化など、時代背景や複雑化する経営環境により、CFOのフラストレーションは溜まる一方です。さらに既存の成果を上げながら改革に挑むジレンマや、事業・地域へのガバナンスのジレンマ、利益を適正に配分するジレンマなどに対してうまくバランスを取っていかなければなりません」
競争環境に取り残されないよう
CFOが取り組むべきアジェンダ

これらのジレンマに対して、CFOが取り組むべき7つのアジェンダについて説明しました。
(1)変化に左右されないサステナブルなプロセス・組織設計。財務・経理部門の人員が減ったなど環境の変化にも左右されないよう持続可能な業務プロセスの設計やBPOの活用、人材の登用といった取り組みが必要です。
(2)少子高齢化の中でのファイナンス人材育成・リテンション。優秀な人材の流出防止策や、経営課題の解消に参画するなど財務・経理の実務家からビジネスパートナーへと役割をシフトするための人材育成が必要です。田中氏は「日本の労働人口が減少する中、欧米企業のようにグローバルな人材獲得を進めることが重要です。でなければ、日本は世界から取り残されてしまいます」と警鐘を鳴らします。
(3)FP&A機能の強化。コーポレートだけではなく、事業・地域に対するFP&Aが課題の企業は少なくありません。
(4)両利き経営の推進(事業ポートフォリオ最適化)。ROICを導入する企業は増えているものの、経営での活用やイノベーションの促進などCFO本来の役割を果たし、両利き経営を進めていく必要があります。
(5)長期的な価値創出と社会課題解決の両立。自社で取り組むべき社会課題を解決しつつ長期的な価値を創出し、成長につなげていきます。
(6)サステナブルな成長ストーリーに基づくIR戦略。マルチステークホルダーに利益を適正配分するには株主に対して中長期的なストーリーを語り、IR戦略を実行していきます。
(7)非財務情報を含むデータ収集と利活用。上記の6項目を進めていく上で重要になるのが「データを収集・利活用するための情報基盤の整備です。これがすべてに共通するアイテムになると考えています」と田中氏は強調します。
次世代の経営管理を支える
グループ統合データ基盤
CFOが7つのアジェンダを推進する上で、統合されたグループデータ基盤の構築が欠かせません。経営管理基盤を構築する上で考慮すべきトレンドとして、田中氏は4つのポイントを挙げます。部門間の業務を横断的に融合する仕組みや、それぞれのデータ間の整合性を確保する「業務融合化」がその1つです。また、従来は部門に個別最適化されていたシステム基盤を共通化してTCOを削減する「システムROI」、分散するデータを共通化してデータガバナンスを適用する「ガバナンス」、機械学習や生成AI活用による業務の高度化や効率性を向上する「AI活用」です。
そして、次世代の経営管理を支えるグループ統合データ基盤のあり方として、CCH TagetikなどEPM製品を活用した部門間業務連携の事例について説明。財管一致、統合報告書開示、非財務情報と企業価値の連関性モデリング、税務ガバナンス最適化、中長期キャッシュポジション予測といったトレンドを挙げます。
CFOのリーダーシップのもと
統合データ基盤構築を推進
田中氏は次のように話します。「部門横断の情報活用機会が増えるとともに情報の一元管理が重要です。CCH Tagetikにより、制度連結やグループ業績管理、非財務情報開示・活用、税務、資金管理・財務リスクなどCFO組織で扱うさまざまな情報の統合管理が可能になりました。グループ統合データ基盤構築の要諦について、単独部門での推進は困難で、CFO自らがリーダーシップをとって推進しなければなりません」
構築の進め方は、制度連結など単一の用途からはじめ、徐々に他の領域に染み出していく方法があります。推進体制は、CFOが自ら旗振り役となり、部分横断的なタスクフォースをつくって進めます。そして、ポイントとなるのがシステムアーキテクチャです。田中氏は「CCH Tagetikにより、サマリー情報に加え明細情報にもダイレクトにアクセスできるデータベースも実現可能になってきました。データの一元管理が可能なプラットフォームを活用することが、グループ統合データ基盤構築の要諦になります」と語り、この講演を締めくくりました。
ブレイクアウトセッション <PwCコンサルティング>
企業価値向上の実践と予測型データドリブン経営
PwCコンサルティング合同会社 パートナー
小林 たくみ 氏
長期的な企業価値創出の観点から、経済的価値と社会的価値を両立する「価値創造経営」が求められる昨今、経営は、果たして「過去の延長に未来がある」という前提に立ち続けて良いのでしょうか。PwCコンサルティングの小林たくみ氏は、講演の冒頭に、各企業が活発に取り組む「経営改革」に対して1つの問い掛けを実施しました。
それは、「経営改革」に関する多くの講演、記事、書籍では、「経営管理基盤を用いて何を見ているのか」という What の解説や「ソリューションや製品をどのように活用しているか」という How の解説には多く触れる機会がある反面、「なぜ経営に、これらの取り組みが必要なのか」という Why の議論が不足しているのではないか、というものです。
小林氏は、「本質を捉えて、経営に貢献する経営改革を必要十分に推進するためには、足元の手法論ではなく、Why の明確化が不可欠です」と、Why に着眼した上で、価値創造経営に求められるポイントを事例とともに解説しました。
なぜ、いま「価値創造経営」なのか

昨今、財務・非財務を統合した価値創造経営が加速している背景として、東京証券取引所から全上場企業に対する資本コストや株価を意識した経営実現の要請や、開示制度の変化といった外発的な危機感があります。それに加えて、「日本のCEOの64%がビジネスのやり方を変えない限り、現在のビジネスは10年持たないと考えている」というPwCが実施した第27回世界CEO意識調査の結果から、小林氏は、経営者自身の持続性に対する内発的な危機感を、加速の背景に挙げています。
また、これには経営や周辺環境の変遷が影響しており、「不確実性が高い『脱・計画経済的』な現在の経営環境が、経営管理基盤を通じた『可視化』を、しかも、『過去』ではなく『未来の可視化』を要請していることが、経営改革の必要性につながっています」と小林氏。
さらに、経営者が、『未来の可視化』を通じて、価値向上に向けた現状と目標の差を定量的に把握し、目標達成に資する道筋を描くべき状況に対して、日本企業が解決すべき課題として「現状と目標の企業価値を定量的に認識できていないこと」、「ESGなどの関連要素の影響を把握出来ていないこと」「目標到達に資する価値創造ストーリーを描けていないこと」という3種類を挙げた上で、経営改革の本質は「企業価値の最大化」であり、ESGの価値貢献などへの着眼は部分に過ぎない、と小林氏は強調しました。
企業価値向上に資する
10個のチェックポイント
続いて、小林氏は、企業価値向上にブレークスルーをもたらす10個のチェックポイントを解説しました。「経営が『価値創造の連鎖を見極めて、企業価値を最大化すること』であるならば、経営管理とは『中長期的に何を目指し』、『どの無形資産を強化するために』、『どれだけ投資するのか』を管理することです。そのため、経営管理の取り組みが、最適な資源配分の実現に寄与しているかを見つめ直すことが要諦となります。」と小林氏。
価値向上が本質だからこそ、売上高や営業利益、ROICなどの中間指標だけでなく、企業価値自体を目標設定することの重要性を小林氏は説きます。合わせて、企業価値向上に向けた経営管理では、企業価値を起点に戦略目標を定義し、戦略目標の達成に資する価値構造の連鎖を解き明かした上で、それらを実行体系に落とし込むために各項目にKPIを定めて管理することが経営者に求められると指摘しました。従来の経営では十分にカバーしていなかったWACCの低減や期待成長率の向上に着眼する必要性が高まっていることも、企業価値自体を目標設定している点に由来している、と小林氏。
その上で、「経営管理のPDCAの過程において、10のチェックポイントで自社の経営管理を検証することが、企業価値向上に資する経営管理を実現する上での要諦です」と、小林氏は経営管理基盤改革を推進する上で検証すべきポイントを紹介しました。チェックポイントには、「活動目標は企業価値の目標値からブレークダウンされているか」「何に投資することが、企業価値向上につながるか明らかであるか」といった財務だけではない価値構造の解明に関わる点や、「外部変数・内部変数は月中で更新され、変化を検知できるか」「結果を参照するだけでなく、シミュレーションを通じて先読みを半自動化しているか」といった未来の予測に関わる点が含まれています。
データを活用した
「未来の予測」と「価値構造の解明」
小林氏は先進企業が企業価値向上に向けて実践している事例として、「ある企業では、データを活用して『未来の予測』に資する取り組みを実施しています。AIを活用して環境変化を自動検知し、ビジネスインパクトを予測する『環境変化の先読み』です。業績に影響する本質的な要素(影響因子)と財務パラメータの関係性を明らかにすることで、環境変化の検知・ビジネスインパクトの予測を可能にしています」と話しました。
また、データを活用して「価値構造の解明」に取り組む企業の事例も解説しています。価値創造ストーリーで合理性・説明性を得るには、財務・非財務属性が企業価値に与える影響を分析する必要があると考え、投資家目線での企業価値(=PBR)の統計的分析や、財務・非財務データが業績に与える影響に対する機械探索を活用して、その証明に先進企業が取り組んでいることを解説しました。「未来の予測」においても、「価値構造の解明」においても、「勘と経験、主観ではなく、いずれもデータを活用し、データによって導出された結果を用いる点がポイントです」と小林氏は解説しました。
最後にまとめとして、多くの企業が情報開示に終始し、具体的な「価値創造」にはまだ至りきれていない現状に対して、東京証券取引所や金融庁が示す外発的な危機感のみならず、日本企業の経営者が抱える内発的な危機感からも「価値創造経営」の必要性の高さに改めて言及した上で、先進企業の実践事例と共に、経営者が経営管理基盤に求める要素は、「可視化」でありながら、それが「過去の可視化」ではなく「未来の可視化」に他ならないことを強調して講演を締めくくりました。
ブレイクアウトセッション <イー・アール・エム>
デジタルプラットフォームによる
ESGエクセレンスと取組事例
イー・アール・エム日本株式会社 コンサルティングパートナー 西 利道 氏
Wolters Kluwer CCH Tagetik プリセールス セールスサポート 永島 亜美
欧州で運用が開始されているCSRD(EUにおける企業サステナビリティ報告指令)に続き、日本でもSSBJ(サステナビリティ基準委員会)によるESGディスクロージャー規制が検討されるなど、今後、バリューチェーン全体を網羅する各種規制に対応することが求められます。イー・アール・エム(以下、ERM)日本の西利道氏は、CSRDを中心とするESG情報開示規制に対応するためのESGエクセレンスとデジタルプラットフォームについて解説しました。
ESGや気候変動の専門家が
戦略から実行までサポート

ERMは1971年に設立されたサステナビリティ専門のコンサルティング会社。ESGのワンストップショップとなるERMデジタルサービスは、お客様のニーズに合った適切なソフトウェアを選択し、ソリューションの実装から維持運用における継続的な改善までサポートしています。そして、デジタルの専門家とサステナビリティ、CSRDなどの規制に精通した専門家がチームを構成。ESGや気候変動対応の戦略から実行までエンド・ツー・エンドでサービスを提供できることが強みであると言います。
ESGデータ管理では、コンプライアンスの観点だけでなく、ESGパフォーマンス管理を考慮し、継続的改善のための目標設定の戦略策定を支援。「ESGは株主、従業員、顧客、サプライヤーなどさまざまなステークホルダーに影響を与えるため、適切に計画しないと後々手戻りが発生するなど大変な作業になりかねません。そのため、段階的なロードマップの確立が重要です。ESGコンテンツに関する専門知識や、主要なテクノロジープロバイダーとのパートナーシップなど、お客様がより高いレベルのESG成熟度を達成できるよう支援しています」と西氏は語ります。
世界中で検討されている
ESG情報開示規制に対応
続いて、CSRDやSSBJ基準などグローバル情報開示規制への準拠に必要な対策について解説。欧州ではCSRDが施行され、2028年度には欧州市場で一定の売上高を持つ第三国企業も対象となり、多くの日本企業も対象になると見込まれています。
「そのため企業は、グループ会社のどこがCSRDのスコープ内にあるのか特定し、ダブルマテリアリティ評価を実施する必要があります。また、重要な項目について、現状を踏まえた目標を設定し、その状況を開示しなければなりません」
CSRDと同様の動きとして、国際会計基準であるIFRSサステナビリティ開示基準や米国証券取引委員会の気候関連開示規則案、日本国内ではSSBJのサステナビリティ開示基準など、ESG情報開示規制が世界中で検討されています。
「グローバル企業は、ESGの包括的な課題とバリューチェーン全体を対象とするこれらの開示規制に対応することが求められています。タッチポイント、データポイントの量を考えると、これまでのように手動のExcelで管理するのは現実的ではありません。データの合理化、データガバナンスの確立、一元化されたソリューションとしてのバリューチェーン全体をカバーできる、監査対応が可能なデジタルソリューションが不可欠です」
CSRDで必要なデータポイントを
組み込んだソフトウェアを選択

CSRDでは第三者保証が求められており、監査可能な開示を進めていくためには、計画的なプログラムアプローチが重要です。例えば、化学物質による大気汚染の場合、報告企業が使用している物質が化学物質リストに関連するものがないか調査・識別する必要があります。
「当該物質の使用、生産、排出がどのサイトでどのように取り扱われているかを特定し、それらのデータを適切に収集しなければなりません。さらにデータの粒度がCSRDの報告に使用できるか精査した上で、データギャップをなくし、正しく計算した上で報告するといった一連の対応が必要です。当社ではこうしたプログラムをお客様と一緒に構築し、支援することができます。
また、情報開示規制への準拠に必要なソフトウェアの選択について、日本国内でもGHG排出量を算定するさまざまなソフトウェアが提供されていますが、CSRDの対応を考慮した場合、CCH TagetikのようにCSRDで必要とされるデータポイントを組み込んだツールを選択することをお勧めします」
ERMが実施したCSRDの事例として、米国の石油・ガスセクター企業に対する、CSRD監査対応のためのコンプライアンスプログラムを確立する支援について説明。支援内容には、組織およびバリューチェーン全体でのダブルマテリアリティ評価の実施、ギャップ分析、スタッフへのトレーニングなどが含まれています。
西氏は「CCH TagetikはCSRDに対応し、環境、社会、ガバナンスの側面をシステム上で管理するための主要なソリューションです。ERMの専門知識とCCH Tagetikの技術は、CSRDやESG情報開示規制に対するベストソリューションの1つとなります」と指針を示しました。
ネットワーキングレセプション「InTouch24」
企業・パートナーに支持され
世界に広がるCCH Tagetikのコミュニティ
Wolters Kluwer CCH Tagetik シニアバイスプレジデント/ジェネラルマネージャー
ラルフ・ガートナー
グローバル経営 LEADERS Summit 2024を締めくくるネットワーキングレセプションでは、CCH Tagetikシニアバイスプレジデントのラルフ・ガートナーが登壇。CCH Tagetik in Touchは今年、世界11カ国で開催され、CCH Tagetikのコミュニティを築いています。
日本市場でビジネスを開始してから7年、CCH Tagetikは多くのグローバル大手企業から支持されています。「日本でのパートナーネットワークは70社以上となり、1,000名以上のパートナーコンサルタントの皆様によってCCH Tagetikは支えられています」と話します。
経営管理を革新するAI搭載
CCH Tagetik Intelligent Platform
CCH Tagetikは進化を続け、AIベースの経営管理プラットフォームとして、分析、予測、連結決算、開示、コンプライアンスを「One Intelligent Platform」で管理し、スピーディな意思決定を可能にしています。
そして、経営管理を革新するAI搭載 CCH Tagetik Intelligent Platformについて説明。プラットフォームは3層で構成され、AI機能やデータ統合などの基盤となる「インテリジェント・ファンデーション」(1層)、連結管理やESG・開示、国際税務、予算管理・IBPなどの機能が含まれる「インテリジェント・ソリューション」(2層)、新ダッシュボードや生成AIを活用したAsk AI機能を搭載する「インテリジェント・インサイト」(3層)で構成されます。
Ask AIはユーザーがテキストや音声で質問するとリアルタイムに視覚的な応答を受け取ることができ、分析や意思決定をサポートします。
「皆様から信頼されるパートナーとして、一緒に経営管理の変革を進めていきます。そして、テクノロジーを経営価値、企業価値に変える力を提供し、皆様を支援してまいります」と述べました。
続いて、CCH Tagetik ジャパンカスタマーアワードの発表と授与式が行われました。
カスタマー部門は、「Finance Transformation Leader 2024」に味の素株式会社、「Vision and Innovation 2024」にトヨタ自動車株式会社が選ばれました。


パートナー部門は、「Best Project Partner 2024」にアクセンチュア株式会社、「Best Competence Partner 2024」にEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社、「Top Performing Reseller 2024」に株式会社アバント、「Partner of the Year 2024」に電通総研株式会社が選出されました。
CCH Tagetik日本代表の箕輪久美子は「これからもユーザーとパートナーの皆様の期待に応え続けられるよう、CCH Tagetik日本のメンバーが一丸となって頑張りますので、ご支援をお願いします」と呼びかけました。





※登壇者の所属・肩書は登壇当時のものとなります。予めご了承ください。