Innovation Seminar 2018
第2回:2018年2月22日(木) Innovate!
オープニング
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 マネージングパートナー・日本代表
原田 裕介 氏

まず、アーサー・ディ・リトル・ジャパン(ADL)の原田氏から、ADLの会社概要について簡単に紹介がありました。ADLはイノベーションやテクノロジー、社会や産業のパラダイムシフトにこだわりを持ったコンサルティング会社であると原田氏は語ります。ADLでは、社会や産業が将来どうなるのかを洞察・予見し(Anticipate!)、次に、予見した未来を踏まえ、新しい道筋や方向性を策定・提示します(Innovate!)。その上で、会社の組織やマインドセットを含めて「Transform!」していくところまでを一貫してサポートするそうです。今回のセミナーも、この3つのキーワードを各回のテーマにしていることを紹介します。
最初に次回の「Transform!」をテーマにした第3回について触れ、ヘルステックカンパニーへの変革を目指すフィリップス・ジャパンの相澤仁氏から、会社全体をトランスフォームするということの学びについて語っていただくと紹介しました。また、西海岸において、ロボットバイクなどの開発に関わっているヤマハ発動機の西城洋志氏には、大企業における新しいものづくりの取り組みについて語っていただくと紹介しました。
次に前回の「Anticipate!」をテーマにした第1回を振り返り、ソフトバンク コマース&サービスの近藤正充氏から、スタートアップや大企業のものづくりを支援するプラットフォームよる、ものづくりの変革についての紹介があったことを報告しました。また、東日本旅客鉄道の中川剛志氏から、JRが取り組むIoTやAI、ビッグデータを活用した新しい鉄道のサービスの取り組みについて紹介があったことを報告しました。
最後は、本日の「Innovate!」をテーマにした講演についての紹介がありました。ソニーの斉藤博氏からは、社長直下のオープンイノベーションで行っている新しいものづくりの取り組みについて、三菱ケミカルホールディングスのCDOである岩野和生氏からは、伝統的な化学企業における、デジタル変革について、それぞれ語っていただくと説明がありました。
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 マネージングパートナー・日本代表
原田 裕介 氏
ゲスト講演Ⅰ:新しいモノや体験を生み出すソニーの取り組み
ソニー株式会社 TS事業部門副部門長
斉藤 博 氏

斉藤博氏はソニー入社後、デジタルカメラ事業やゲーム事業等、多岐にわたる商品を手掛け、特にミラーレス一眼カメラNEXシリーズやPlayStation4など、新規性の高い商品を立ち上げてきました。2013年には社長直下組織として発足したTS事業準備室に社内起業家(イントレプレナー)として参画し、現在は組織を新たにしたTS事業部門の副部門長を務めます。ソニーの中で取り組む新たな挑戦について、ご講演いただきました。
家電ではなく、“ユーザー体験”を企画する
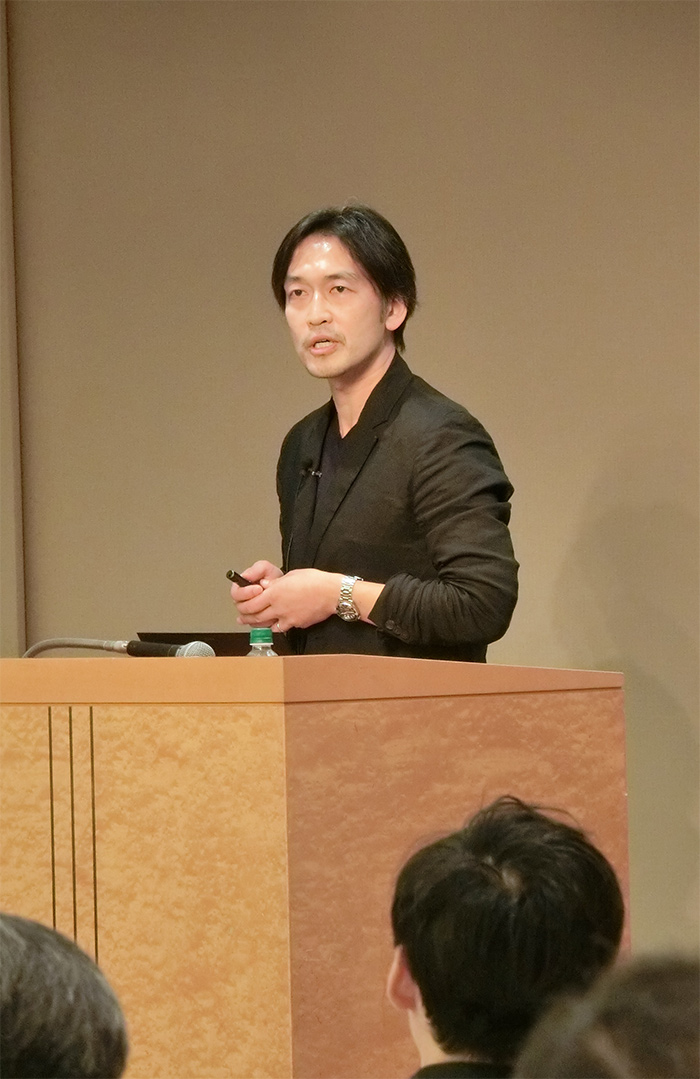
TS事業部門が組織発足当初から企画・開発しているのは、Life Space UXというコンセプトの商品群です。「Life Spaceは住空間を表し、UXはユーザーエクスペリエンスを表しています。つまり、家などの居住空間で新しい体験を作り出すこと、それがLife Space UXの目指すところであり、4年間で4つの商品を発売しました」と斉藤氏は語ります。その中でも、2016年に発売したポータブル超短焦点プロジェクターとグラスサウンドスピーカーが好評とのことで、発売から約2年たった今も実売が落ちないという、家電分野では異例のヒット商品を生み出すことになったのです。
こういった商品を開発するきっかけになったのは、建築系やインテリア系の、家に関するさまざまな写真、とりわけ雑誌に掲載されるような素敵なイメージ写真を見ていた時でした。「それらの写真に写っている家の中には一つも家電製品が置かれていませんでした。すてきな住空間であればあるほど、家電製品を置くと違和感があるようで、その“違和感”は何なのかを追及しました」と斉藤氏は語ります。そこで、斉藤氏らはどのような家電製品であればそこに置いてもらえるのかを考えました。最初は見た目がなじまないからデザインを考え直そうという議論になりましたが、そのうちに、一般の人が家電に求める価値と我々作り手が提供したい価値が乖離しているのではと考えはじめたそうです。
斉藤氏は「一人一人の価値観が多様化し、便利な機能を新たに家電を買い足す事で得るだけではなく、いかに自分らしい時間をその場で過ごすのかが重要なのではと考え、一人一人にとって家はどういう場所であるのか、家のあり方やその中での家電の役割そのものも捉え直しました。その結果、“家電は世界で唯一自分らしく過ごせる空間を作るサポートをしてあげればいい”という考え方にたどり着きました」と語ります。そうして、Life Space UXの基本方針ともいえる「モノよりも、提供できるコト・体験を重視するプロジェクト」が生まれたのです。
どんどん生み出す組織づくりとは

4年前、TS事業準備室が社長直轄の組織として発足した当初、斉藤氏が社長から言われたことは、「リスクを取ってでもどんどん商品を出す組織を作れ」。一度も売り上げについて聞かれた事もないといいます。斉藤氏は、その実現のためにどのような組織であるべきか、そしてどのような商品を出すべきかを考えました。一般的な組織とTS事業部門で、新規事業への取り組み方の違いを考えました。既存の事業の枠組みから離れた独立した組織、且つ売り上げの確約も必要がない。そのような恵まれた環境で取り組むのであればなかなか挑戦できない全く新しい商品を生み出したい。新しいことを始めるには「今ある常識や前提を疑うこと」から始める必要があると考えました。また、新しいアイディアに対してはコンセンサスも求める必要はなく「新しいアイデアは賛否両論が出たほうがよい」と斉藤氏は語ります。なぜなら、みんなが賛成するものは既存の軸に沿って提案されているので、結果として新規性がないからです。
案件ごとに少人数で話し合いをして、やろうと決めたらすぐに動くという体制のTS事業部門。それにより、通常はハードウエア開発を含む商品の場合1つの商品を作るのに1年から1年半はかかるのですが、4年で4つの、しかも映像や音といったコア技術が異なる商品を次々に出せたというスピード感を実現できました。また、ポータブル超短焦点プロジェクターの商品化においては、唯一無二の全く新しい体験を実現できる商品として通常のプロジェクター市場のスペック競争に埋もれない大ヒット商品になりました。既成の概念にとらわれないことの重要性について語りました。
新規事業に必要な“人”軸の工夫

Life Space UXの商品はスピーカーにプロジェクターにと、さまざまなコア技術を活用しています。そのため実際に製品開発を進めていくとさまざまな領域のエンジニアが必要になるのですが、スピード感を持ってアイディアを形にするその組織の特性からその時期を長期的に見込んでおく事が難しい。どういう人がどのタイミングで必要になるか分からないという壁にぶつかったそうです。異なる技術を組み合わせた製品を作るには、その都度さまざまな領域のエンジニアが必要になります。新規事業の鉄則は、最小限、最低限のメンバーで動かしていくことなので、斉藤氏は、TS事業部門としてさまざまな領域のエンジニアを抱えるのではなく、それぞれのアイディアやプロダクト毎に最適なエンジニアを社内からかき集めてプロジェクト化する形をとったそうです。「彼らには現所属組織とTS事業部門を兼務してもらい、そのアイディアやプロダクトが完成したら元の業務に戻ってもらいました。また、社外からも人材が必要になった時のために、Hub型のコネクション作りに力を入れています」と斉藤氏。実際に予期せぬ局面に備えてさまざまな分野の社外の人材に一人ずつあたっていくのは大変なので、いろいろな方面に繋がりを持っているHub型の人とのコネクションを作ることに力をいれているのだそうです。
斉藤氏がイノベーティブな組織において重要と考える点の一つが、左脳人材と右脳人材の違いです。多くの企業がイノベーション型ではなくオペレーション型の組織になっています。オペレーション型の組織では、今ある既存の事業でいかに効率化・最適化するか、利益を最大にするかが重要で、その結果左脳的な思考ができる人材が主流となります。しかし、「新規事業はいかにアイデアを生み出すかが重要で、出てきたアイデアを商品に落とし込む際に、お客さまがそれぞれのステップでどう思うのかを想像することが必要になってきます。そのため、われわれは右脳型の思考ができる人材を集めるようにしています」と、右脳型人材の必要性について触れます。
ソニー株式会社
TS事業部門副部門長
斉藤 博 氏
ソニー入社後デジタルカメラ事業やゲーム事業等多岐に渡る商品を手掛け、特にミラーレス一眼NEXシリーズやPlayStation® 4など、新規性の高い商品を立ち上げる。2013年に社長直下プロジェクトとして発足したTS事業準備室に社内起業家(イントラプレナー)として参画し、現在は組織を新たにしたTS事業部門の副部門長を務める。
基調講演:既存の枠組みを再定義する<br /> “エコシステム型イノベーション”の創出手法
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 プリンシパル
三ツ谷 翔太

三ツ谷翔太氏は京都大学工学部物理学科卒業後、同大学大学院工学研究科材料工学専攻修士課程を修了しました。アーサー・ディ・リトル(ADL)における主な担当領域は、製造業企業やサービス企業に対する新事業戦略やイノベーション戦略の立案、ならびに経済産業省などの官公庁に対する政策立案支援です。近年はスマートコミュニティや次世代モビリティなど、次世代の社会インフラ創出に向けたプロジェクトに数多く従事しており、今回はイノベーションの創出手法について、講演いただきました。
イノベーションを取り巻く構造的変化

冒頭、三ツ谷氏は「私たちは今、60年周期の産業変革と15年周期のICT変革の波が重なり合った、数百年に1度の大きな変革に遭遇しています」と現状を表現し、「イノベーションの起こし方そのものについて新しい視点が求められています」と語ります。破壊的イノベーションの拡大やイノベーションの連鎖構造の変化などによって、イノベーションを生み出すメカニズムが大きく変わってきているのです。さらに「従来の社会システムが様々な限界を変えつつある中、これまでのフレームワークの再定義に向けた技術が台頭し、社会システムの再設計が急速に進みつつあります」とも語ります。
こういった2つの動きが積み重なり、技術起点型イノベーション(新たな技術を起点としてイノベーションを起こす)や顧客起点型イノベーション(顧客に課題を提示してもらって共にイノベーションを起こす)は終わりを告げつつあると三ツ谷氏は感じています。そして、次に注目すべきイノベーションとして、「エコシステム型イノベーションというものが必要とされるようになってきました」と三ツ谷氏は語ります。エコシステム型イノベーションとは、「場づくりとしての新たなエコシステム形成を通じて、社会や産業の枠組みを再定義するイノベーション」であり、そこでは「さまざまなプレーヤーを巻き込んでいく関係性資源が、イノベーションの源泉になっていきます」と、三ツ谷氏は語ります。
事例から学ぶ“エコシステム型イノベーション”の要諦

ここで三ツ谷氏は、すでにエコシステム型イノベーションに取り組んでいる企業を、「自らの革新に挑むオペレータ」「産業革新を突きつけるスタートアップ」「試行錯誤しつつも革新に向かうサプライヤ」の3つの産業レイヤに分けて紹介しました。
まず、「自らの革新に挑むオペレータ」として紹介されたのが、ドイツの鉄道会社Deutsche Bahn(DB)です。DBは「ステーション・ツー・ステーションからドア・ツー・ドアへ」という、鉄道から先のモビリティに関するビジョンを打ち出しました。三ツ谷氏は「鉄道と競合しかねないモビリティーサービス事業にも手を出し、自らを否定するようなビジョンを打ち出したところに時代の転換を感じます」と語ります。同じくドイツの物流事業者DHLも、自らの提供価値を物流業界に閉じない形で再定義した例として触れました。
そして、「試行錯誤しつつも革新に向かうサプライヤ」では、ドイツの製造業SIEMENSの事例を取り上げました。SIEMENSは製造業を革新するため、大手IT企業のSAPなど、さまざまなプレーヤーを巻き込み、さらには政府をも巻き込んでインダストリー4.0という構想を打ち立てました。これによって、「ドイツ国内の製造機械メーカーや自動車メーカーなどを巻き込んで、新しいエコシステムを一気に作ってしまいました」と三ツ谷氏は紹介します。SIEMENSの事例の特徴は、外部への定期的なビジョン発信と、そのビジョンに基づいて国までをも巻き込んで新しいエコシステムを作ってしまったことであると三ツ谷氏は語ります。
エコシステム形成に向けた方法論

エコシステム型イノベーションを形成するためには、既存の産業構造の枠を超越する「課題を捉える視野」「枠組みの再定義」「経済圏の継続拡張」が必要であると三ツ谷氏は語ります。特に、「課題を捉える視野」を広げる例としてDBを挙げ、「もはや、鉄道会社だから鉄道のことだけを考えればいいという時代ではないのです。現業範囲だけでなく、エンドユーザーの体験全体、さらには社会の課題にまで検討の視野を広げることが重要です」と語ります。
多様なパートナーを集めた場を形成しながら、継続的に視野を拡大していくことが必要だと三ツ谷氏は語ります。「旅行者は鉄道による移動だけを考えるのではなく、事前にプランニングをしますし、目的地に着いた後にはラストワンマイルの移動もあります。また、鉄道事業者が貢献できる社会課題は移動に関する課題以外にも数多くありえるので、どうやってこの視野を広げていくのかが大きなポイントの一つになります」と三ツ谷氏。課題解決を鉄道のあり方だけではなく、交通全体や都市をも巻き込んで枠組みを自ら広げていかなければならないということです。このように課題解決の枠組みを広げると、結果的に他のプレーヤーも巻き込んでいくことになります。「そのように継続的に拡大される構造を自ら積極的に仕掛けていくのが、エコシステム型イノベーションの最大の特徴です」と三ツ谷氏はまとめます。
最後に、ADLがJR東日本と一緒に取り組んでいる「モビリティ変革コンソーシアム」についての紹介がありました。今後は日本の企業からも、次から次へと新しいエコシステムが出てくることを期待するとして、講演が締めくくられました。
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社
プリンシパル
三ツ谷 翔太
京都大学工学部物理工学科卒業。同大学大学院工学研究科材料工学専攻修士課程修了。主な担当領域は、製造業企業やサービス企業に対する新事業戦略/イノベーション戦略立案、ならびに、経済産業省などの官公庁に対する政策立案支援。近年はスマートコミュニティや次世代モビリティなど、次世代の社会インフラの創出に向けた官民のプロジェクトに数多く従事。また、日経エレクトロニクスなどにて連載多数。
ゲスト講演Ⅱ:デジタル時代の組織変革と新事業創出の取組み
株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 CDO(最高デジタル責任者)
岩野 和生 氏

岩野和生氏は東京大学理学部数学科を卒業後、日本アイ・ビー・エム株式会社に入社しました。同社で東京基礎研究所長を務めた後、米国ワトソン研究所においてオートノミック・コンピューティング担当ディレクター、先端事業担当などを歴任し、2012年より三菱商事株式会社ビジネスサービス部門顧問、国立研究開発法人 科学技術振興機構の上席フェローとなりました。その後、2017年より株式会社三菱ケミカルホールディングス執行役員、先端技術・事業開発室CDOに就任しています。IT企業から製造業に移られた岩野氏に、製造業におけるデジタル変革についてご講演いただきました。
化学産業におけるデジタル革命とは

岩野氏は冒頭、「CDOには“チーフ・デジタル・オフィサー”と“チーフ・データ・オフィサー”という2つの意味があります。本日はこの両方の立場で講演させていただきたいと思います」と自己紹介しました。その後、三菱ケミカルホールディングス(MCHC)について紹介します。「MCHCのスローガンは“KAITEKI実現”です。自分が心地よいだけでなく、地球全体もビジネス環境も含めて環境・社会的課題の解決に貢献し、持続可能な社会を築いていくことを目指しています」と語る岩野氏。10年後、20年後のKAITEKIをどう創造するのかというテーマに取り組んでいます。
MCHCが関わる化学産業は、1950年代に巨大投資してつくられた石油化学コンビナートを、60年以上、修理しながら使ってきました。岩野氏は、「当産業は、事故が起きると人の命に関わったり、大きな損害をもたらしたり、多くの川下産業に影響を与えるなどインパクトの大きな世界です。また、極端な川上産業なので、川上から川下に対してとても長いサプライチェーンが作られています」とMCHCが置かれている環境を紹介します。さらに岩野氏は、化学産業は自動車などの工業製品のようなコンポーネントを組み立てて最終製品を作る組み立て系製造業ではなく、プロセスによってものを生み出すプロセス産業でもあると説明します。以上のことから、コンポーネント産業で起きようとしている第4次産業革命の波が、化学産業やプロセス産業に同じように起こすことは、難しいが、挑戦に値するテーマだとみています。そのような中で、MCHCや化学業界にどのようにデジタルトランスフォーメーションを起こすのか、日々模索しています。
岩野氏は、「新しいビジネスモデルを考える時には、大きな流れを把握し予測しておかないと失敗すると思っています」と語りました。そして、「クラウド化やサービス化の動きがさらに進み、社会システムや社会サービスの方向に向かっている」「すべての企業や個人が、社会的に関与していないとサステナブルに活動できない社会になっていく」「価値の所在がモノからサービスに、サービスから関係性の中に位置づけられていく」「データとソフトウエアの重要性がますます大きくなっている。」「様々な境界が曖昧になっていっている。例えば、サイバーと物理的なものの協会、個人と組織、社会の協会、機会と人間の境界などです。」「個人や組織、専門家の社会的責任が大きく問われるようになってきている。」など、現状分析について触れました。
データとリアルな現場をもつMCHCのデジタル戦略

岩野氏は「1年半くらい前から、化学産業やプロセス業界でも、いよいよインダストリー4.0やインダストリー・インターネットといった流れが来るだろうと言われはじめたようです。昨年のワールドエコノミックフォーラム (通称、ダボス会議)では、いろいろな関連レポートが提出されました」と語ります。レポートは、「化学産業やプロセス産業におけるデジタル変革はどのようなものになるのか」「デジタルプラントの姿とはどのようなものか」などについて触れられていました。
岩野氏はCDOの立場から、組織におけるデジタル変革の課題について語りました。まず、”The Alchemy of Growth”(Mehrdad B, Steve Coley, David White)という2000年の本について触れました。そこでは、現業ビジネス (Horizon 1ビジネス) と新規事業 (Horizon 3 ビジネス) の取り組み方の違いを紹介しています。「もし、新規事業を現業ビジネスと同じグループで推進しようとすれば、たとえ、新規事業に優秀な人材や、資金を投入しても、現業が逼迫すればそういった人やお金は結局既存事業に引き戻されます。その繰り返しによって、新規事業がうまく育っていかないのがこれまでのパターンだと言われています」と岩野氏。そういったことを避けるためには、「既存事業と新規事業を確実に切り離すことが第一歩」とアドバイスします。その上で、もう一つ大切なこととして、「新規事業に関わる人材には、極めて優秀な人を当てるべきです。特にリーダーは、会社の中で実績があり尊敬されている人に任せること」との貴重なアドバイスがその本に紹介されているといいます。そうすると経営者の本気度が社内に伝わり、新規事業に求心力や説得力を生み出すのです。
一方で岩野氏は、「MCHCは実は宝の山を持っています」と語ります。製造業としてIT企業にはないデータとリアルな現場を持っているのです。さらに、MCHCには変革への意思があり、さまざまな事業の専門家もいます。それらがデジタル変革において大きな意味を持ってくると岩野氏は考えています。こういった宝を取り込んで新しい価値を創造するために、岩野氏はいくつかの目標を立てました。「環境やビジネスに対する破壊的な変化が確実に起きると考え、われわれ自身がその変革者になろうと思っています。そして、デジタル変革への指針や戦略に関わる水先案内人になります」と語り、岩野氏のチームがそのために外部から人材を集めてきたことを紹介します。各分野のエキスパートが集まるチームの3分の2は外部から入ってきています。一方で、デジタル変革をサステイナブルなものにするには、組織の風土が大事だと語ります。いわゆるデジタルネイティブな組織であることが必須になると考えています。そのために「今後は社内での教育や育成を積極的に考えます」と岩野氏は語ります。
デジタル変革をどのように実現させるか

MCHCにおけるデジタルトランスフォーメーションに大きく二つのアプローチをとっていると紹介されました。一つは、オペレーションの秀逸性の追求、二つ目は、新たなビジネスモデルの創造です。オペレーションの秀逸性には、プラントにおける故障予知、Predictive Maintenance、異物検知、知恵の継承を目指すナレッジマネージメントなどをあげました。新たなビジネスモデルは、インダストリー4.0やインダストリアルインターネットのプラットフォームの事例や、ロールスロイス社の航空機エンジンに対するPredictive Maintenanceと従量課金制の導入など にヒントがあると見ています。組み立て製造物ではないところで、上のような構造をどのように作り出すのかが現在の挑戦的課題です。しかし、化学業界にもモノ売りからサービスへという試みもみられているようです。その例として、ある化学会社が、お客様のペットボトルの製造工程における潤滑油の使用について、サービスのモデルを適用したことを紹介しました。新しい潤滑油の活用とセンサーの組み合わせです。
そして岩野氏は、最後に、組織と企業風土に関わる話題やコンピュータサイエンス的考え方 (Computational Thinking) の重要性について触れました。「デジタルによって、個人や企業の社会的責任を考えることが大切です」と語る岩野氏。さらに、イノベーションを起こすにはテクノロジーだけではなく、むしろ組織変革が大切で、MCHCでもデジタルを推進するためにコンピューターサイエンス的な考え方やリベラルアーツの側面も含めた教育なども視野に入れていることを紹介し、講演を終えました。
株式会社三菱ケミカルホールディングス
執行役員 CDO(最高デジタル責任者)
岩野 和生 氏
1975年 東京大学理学部数学科卒業、同年日本アイ・ビー・エム株式会社入社、1987年 米国プリンストン大学Computer Science学科よりPh. D.取得。東京基礎研究所所長、米国ワトソン研究所Autonomic Computing担当ディレクター、先進事業担当等を歴任。2012年より三菱商事株式会社 ビジネスサービス部門顧問、科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー、東京工業大学客員教授。2017年1月より株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員、先端技術・事業開発室 Chief Digital Officer。IEEE、ACM、SIAM会員。
クロージング
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 マネージングパートナー・日本代表
クロージングでは、アーサー・ディ・リトル・ジャパンの原田裕介氏がゲスト講演について振り返りました。まず、自己否定から新しいプロジェクトが始まったというソニーの斉藤博氏の講演のポイントは、「本質思考」と「進め方のパラダイムシフト」の2つであったと語ります。「本質思考」については、「“家の本来の役割”まで立ち戻った上で、“家電に求められている本質”を掘り下げ、自分たちが提供すべき最も大きなビジョンにたどり着いたこと」及び、「“アイデアが潰れる理由“まで立ち戻った上で、”イノベーション創造に求められる本質“を掘り下げ、独立性・小さいチーム・裁量・短期的成果求めずという組織要件にたどり着いた」と紹介しました。また、「最小のリソースと外部連携による組織力の担保」という「進め方のパラダイムシフト」があったことを述べました。次に、原田氏は「最小リソースで外部連携で大きなイノベーションを生み出す方法論」について触れ、米国DARPA(国防高等研究計画局 )の事例を参考に紹介しました。
次に、MCHC(三菱ケミカル)にはいろいろな財産があることが分かったという岩野氏の講演に触れ、特に、「デジタルトランスフォーメーションの本質は、“思想と風土”である」こと、および、「Horizon1から3への展開に必要なのは、“尊敬されるリーダーを置く”ことが変革の肝」であることを述べ、ソニーとMCHCとで共通する要素がいろいろとあることに気が付いたと語ります。原田氏は、参考になる事例として、「状況を好転させなければならないJ.ウェルチの時代」は、“もっと速く”。「大きな成果を上げ、より高いレベルを目指すJ.イメルトの時代」は“もっと早く”など、GE社のリーダーが、時代とともに変わる事業環境によって、異なる組織行動規範を植え付けようとしたメッセージをいくつか紹介しました。 最後に原田氏は、両社の取り組みやエコシステムを創造することが、これまでのパラダイムを覆す取り組みであることから、1943年にIBMの会長が「世界でコンピュータの需要は5台くらいだと思う」と語った発言や、1977年にDECの社長が「個人がコンピュータを持つ理由など見当たらない」と語ったことに触れ、「専門家であればあるほどパラダイムにはまってしまうことに留意するべきだ」と語り、第2回の全講演を締めくくりました。

