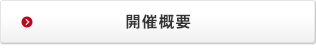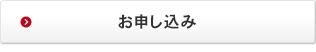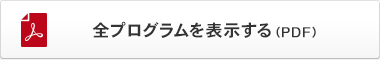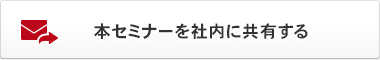New Business Creation Forum 2018 3rd
イノベーション闘争時代の新事業創出
~戦略的“つながり”と“組織”のあり方から問う、その真価~
![]()
2018 年 3 月 20 日 (火) 9:50~17:40 (受付 9:20~)
![]()
経営者、役員、経営企画、新規事業開発、事業戦略、研究・技術開発、
人財・組織開発、投資関連業務ほか、各事業部門の管理職の方々
豪華ゲスト登壇者

パナソニック株式会社
馬場 渉 氏

三井化学株式会社
福田 伸 氏

株式会社rimOnO
伊藤 慎介 氏

横河電機株式会社
阿部 剛士 氏

Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley Inc.
西城 洋志 氏

Honda R&D Innovations, Inc.
杉本 直樹 氏

株式会社ジャパンディスプレイ
伊藤 嘉明 氏

一橋大学イノベーション研究センター
米倉 誠一郎 氏
09:50~10:00 オープニング (10分間)
10:00~11:10 特別ゲスト講演Ⅰ【変革する組織の新事業戦略】
パナソニックにおける「大改革」
~イノベーションを“量産”し続ける組織へ~
- パナソニックが挑む新事業と「量産化技術開発」の取り組み
- 社内横断組織による、スピーディーな事業創出へ向けた仕組みづくり
- 新事業を生み出す組織、人づくりへの挑戦
 パナソニック株式会社
パナソニック株式会社
ビジネスイノベーション本部長
コーポレートイノベーション担当
パナソニック ノースアメリカ株式会社 副社長
馬場 渉 氏
2017年4⽉パナソニック株式会社⼊社。ビジネスイノベーション本部副本部⻑コーポレートイノベーション担当として全社イノベーション推進を担う。⽶シリコンバレーに拠点を置き、パナソニックノースアメリカ株式会社副社⻑を兼務。パナソニック⼊社前はSAP本社カスタマーエクスペリエンス担当バイスプレジデントとしてシリコンバレー・パロアルトに籍を置き、外部の⼤規模組織に対しデザインシンキングと最新テクノロジーによりイノベーション⽂化と実⾏能⼒を経営戦略として取り込むハンズオン型アドバイザリーに従事。公益社団法⼈⽇本プロサッカーリーグ(Jリーグ)特任理事。
![]()
今年で創業100年を迎えるパナソニック。既存ビジネスモデルに対する危機感から、2017年4月より大規模な組織改革と新たなイノベーション戦略に舵を切っている。IoTやAI技術を柱とした新事業創出と成長モデルの構築を目指し、全社横断的な専門組織を設置。「タテパナ」から「ヨコパナ」への変革、スピード重視のプロトタイピング、イノベーションの量産化へ向けた仕組みづくりを行う。その旗振り役となる馬場氏は、シリコンバレーにて新組織「Panasonic β」を立ち上げ、既存の家電製品、住宅などの枠を越えた新たな住空間サービスの提案に向けた「HomeX」プロジェクトを進めている。 当社の“世界一奪還“に向けた大改革を牽引されている馬場氏を招き、イノベーションを生み出し続けるための仕組みづくりと組織改革についてお話いただきます。
11:10~12:00 特別協賛講演 【新事業創出のための俯瞰解析】
俯瞰解析による未来予測×新事業戦略
~技術、市場、社会を分野横断的につなぐには?~
- 既存概念を打破した商品・サービスづくりの秘訣とは?
- 新たなビジネスチャンスやアライアンス先の探索、スタートアップの発掘など目的に応じたソリューションを解説
- 2050年までの未来へとつながる、戦略的なストーリーの描き方

代表取締役CEO
中村 達生 氏
埼玉県出身。1991年、早稲田大学大学院理工学研究科機械工学分野を修了後、三菱総合研究所に入社。コンサルティングに従事。可視化アルゴリズムや俯瞰解析ソフトウェアを開発し、知財調査・ビッグデータ・予測分析分野にてソリューションを展開。1994年から1998年まで東京大学工学部助手として勤務。三菱総研に復職後、2005年に工学博士を取得。2006年に膨大な情報を解析的に取り扱うことの必要性と意義を訴えてVALUENEX株式会社を設立、代表取締役CEOに就任(現任)。2014年2月米国カリフォルニア州メンロパークに現地法人を設立、CEOに就任(現任)。1年のうち約半分を海外にて活動。現在、早稲田大学理工学術院非常勤講師も務める。
![]()
産業、社会のあらゆる情報が横断的につながり、さらに、そこで営まれる様々な活動や行動が張り巡らされたセンサーにより集積される近未来の社会。ここでは、必要な情報を正しく適切につなぎ読み解くことが、クロスボーダーであり異業種間の激しい競争を勝ち抜く条件となります。研究、技術、製品・サービス、社会ニーズ、金融のそれぞれを代表する情報をつなぎ、正確に解析したビッグデータを俯瞰的に読み解くと、自社の置かれているポジション、次のビジネスチャンスとなる空白領域、トレンドに合わせた新事業領域、適切なアライアンス先を浮かび上がらせることが可能です。俯瞰解析手法による未来予測の実践を実例とともに紹介いたします。
12:00~13:00 Networking Lunch
※ ご昼食(ビュッフェ形式)と併せて、参加者同士の交流の場をご用意しております。是非ご参加くださいませ。
13:00~14:00 特別対談セッション 【大手企業×スタートアップの戦略的連携】
三井化学 × rimOnO の連携が起こすイノベーション
~戦略的連携を実現する、仕組みづくり~
|
三井化学株式会社
常務執行役員 研究開発本部長 福田 伸 氏 1986年北海道大学工学研究科原子工学博士課程修了後、同研究科にて助手として勤務。その後、日産自動車株式会社宇宙航空事業部勤務を経て、1992年三井化学株式会社(当時三井東圧化学)に入社。マテリアルサイエンス研究所GL、複合技術開発部長、新材料研究センター長を歴任。2012年より新規事業創出を担当する環境・エネルギー事業推進室長、次世代事業開発室長を経て、2017年より常務執行役員・研究開発本部長。 |
× |
株式会社rimOnO
代表取締役社長 (元経済産業省 官僚) 伊藤 慎介 氏 1999年に通商産業省(現 経済産業省)に入省。自動車課では次世代自動車用蓄電池の技術開発プロジェクト設立、情報経済課ではスマートハウス、日本版スマートグリッドの国家プロジェクト設立、航空機武器宇宙産業課では国産ジェット機の国家プロジェクトに従事するなどの経験を経て、2014年7月に経済産業省を退官。同年9月に株式会社rimOnOを設立。2016年5月に布製ボディの超小型電気自動車”rimOnO Prototype 01”を発表。現在もオープンイノベーション型で開発を進めている。 |
◆三井化学◆ 講演のポイント<大手企業側の視点>
- 連携の目的とゴール、マイルストーンの設定
- 連携を活かす、社内仕組みづくり ~チャレンジを促す組織設計と評価手法~
- 外部企業、スタートアップとの連携におけるポイント
阪大発ベンチャー マイクロ波化学株式会社やドローンベンチャー等、様々な企業との連携を通じたオープンイノベーション活動の取り組みを進めている三井化学。2017年10月には、ワンタッチでレンズの焦点距離が切り替わる電子メガネ「タッチフォーカス」を発表するなど、今後の新事業・新製品開発活動にも注目される。
◆rimOnO◆ 講演のポイント<スタートアップ側の視点>
- 大手各社を巻き込む、超小型モビリティ「rimOnO」の開発背景
- 連携先とWin-Winの関係性を生むポイント
- 「rimOnO」にみる、コラボレーションとものづくりの可能性と課題
経産省出身の伊藤氏とトヨタ自動車出身の工業デザイナー(znug design代表)の根津孝太 氏が2014年に設立したベンチャー企業。三井化学株式会社の他、帝人フロンティア株式会社、ローランド株式会社など大手企業各社を巻き込み、“乗り物からNoをなくす”という全く新しいコンセプトの布製超小型モビリティ「rimOnO」の開発に取り組んでいる。
14:00~14:10 Short Break
14:10~15:10 特別ゲスト講演Ⅱ 【新事業を生む組織体制】
横河電機における戦略的イノベーション活動と組織体制づくり
- 新事業創出のための組織設計 ~R&D、オープンイノベーション、M&A、特許・知財などを含む横断的組織づくり
- イノベーションを活性化させる組織マネジメントと評価手法
- 「イノベーション創出サイクル」における、戦略的外部連携
 横河電機株式会社
横河電機株式会社
執行役員 マーケティング本部長阿部 剛士 氏
1985年、インテルジャパン株式会社(現インテル株式会社)に入社、2005年、同社マーケティング本部長に就任、2007年、芝浦工業大学専門職大学院 技術経営/MOT卒業、2009年、同大学地域環境システム専攻博士課程修了、2011年、同社取締役副社長 兼 技術開発・製造技術本部長に就任、2016年、横河電機株式会社に入社、現在に至る。
![]()
計測、制御、情報をコアとしてグローバルにソリューションを展開し、今年で創業103年を迎える横河電機。事業部ごとのマーケティングとは異なり、グループ全体における中長期視点のマーケティング・経営戦略を担う組織である「マーケティング本部」を設ける。同組織は、R&D、オープンイノベーション、M&A、特許・知的財産、市場調査、工業デザインなど、イノベーション創出に必要なアセットを全方位的に網羅しており、阿部氏がその統括を担う。今後の新たなターゲット領域として、バイオ、エネルギー、マテリアル分野に注力。横断的組織からの革新的価値づくりに挑む阿部氏を招き、同社のユニークな組織体制づくりやイノベーションを支える様々な戦略的取り組みについてお話いただきます。
15:10~15:50 協賛講演 【新事業創出実践のための人材・組織戦略】
新事業創出を牽引できる人材、新事業が創出される組織文化
~人材開発・組織開発からみた事業創出のポイント~
- 出現率が低い事業創出人材の発掘
- 事業アイディアを潰す文化、引き出す文化
- 研究開発者と市場をつなぐ「マーケットダイブ」
 株式会社インヴィニオ
株式会社インヴィニオ
代表取締役土井 哲 氏
東京大学卒業後、東京銀行に入行。MITスローン経営大学院にてMSを取得。マッキンゼーを経て、ベンチャー企業の経営者を支援するコンサルティング会社を設立。97年にインヴィニオを立ち上げ、リーダー育成・組織文化変革を通じて組織能力を高めるパフォーマンスディベロップメント事業を展開。大企業の新規事業開発プロジェクトに関わる。
![]()
機関投資家の資金が脱炭素社会の実現にむけて大きく流れを変える中、既存事業を変革する、事業ポートフォリオを変える、自社のもつ脱炭素化に資する技術を事業化する絶好のチャンスが訪れています。一方で、大企業に就職する人の大半は安定性を求めており、事業創出の機会を求めて入社する学生はほとんどいません。そのような集団の中で事業を立ち上げ成功させるには、資質ある人材の発掘と意図的な組織文化醸成が不可欠です。事業創造に向いている資質とは何か、そのような人材をどのように発掘できるか、事業創向きの組織文化に変えることは可能か、20年近く新事業開発の支援をしてきた経験から見えてきたKFSや事例を共有します。
15:50~16:10 Coffee Break
16:10~17:40 特別パネルディスカッション 【新事業戦略と組織の未来】
日本企業におけるイノベーションの“妙薬“はあるか!?
- 新事業の成否を分けるカギ ~戦略的「つながり」と「組織」の実践事例から~
- イノベーションを生み出し続ける土壌、組織、人づくりとは
- これからの新事業戦略 ~乗り越えるべき壁(課題)と展望~
 Yamaha Motor Ventures & Laboratory
Yamaha Motor Ventures & Laboratory
Silicon Valley Inc.
CEO and Managing Director
(ヤマハ発動機株式会社)西城 洋志 氏
九州大学工学部卒業後、ヤマハ発動機株式会社に入社。約20年に渡り表面実装技術とロボット事業においてソフトウェア開発、ソリューション開発および新事業開発に従事。2014年5月よりYamaha Motor Corporation, USA のNew Venture Business Developmentの部長となり、その時期にシリコンバレーのエコシステムを活用した新事業開発の企画・戦略立案を行う。2015年7月にYamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley Inc.設立し、ベンチャー企業への投資を含めた新事業開発活動を行っている。
 Honda R&D Innovations, Inc.
Honda R&D Innovations, Inc.
CEO
株式会社本田技術研究所 執行役員杉本 直樹 氏
リクルートにて人事採用、営業担当などを経て、インターネットメディアの立ち上げに参画。1994年にUC Berkeley留学し、在学中に立ち上げたオンラインコミュニティを社内ベンチャー化。リクルート退職後は、シリコンバレーにてベンチャー投資コンサルタント等の後、2005年にホンダのCVCに参加。2011年にCVCをオープンイノベーションラボに改編し、コラボレーションを通じた新商品・新事業提案を推進。2017年、Honda R&D Innovations, Inc.を設立しCEO(兼 本田技術研究所 執行役員)に就任。シリコンバレー在住23年。東京大学工学部卒業。UC Berkeley MBA修了。

執行役員 CSO 兼 CMO
伊藤 嘉明 氏
日本コカコーラ、デル、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント(SPE)、ハイアール グループなどのグローバル企業にて、経営陣としてブランド認知度の向上、業績回復、シェア拡大、売り上げ新記録樹立等、事業再生を手がける。 2016年にはX-TANKコンサルティング株式会社を設立し、現在も代表取締役社長を務め、また2017年よりジャパンディスプレイに参画し、CSO兼CMOとして経営再建に携わる。

代表取締役CEO
中村 達生 氏

法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
米倉 誠一郎 氏
イノベーションを中心とした経営戦略と組織の史的研究が専門。『一橋ビジネスレビュー』編集委員長、およびアカデミーヒルズの日本元気塾塾長でもある。ハーバード大学歴史学博士号取得(Ph.D.)。2012年よりプレトリア大学日本研究センター所長・顧問を兼任。著書は、『オープン・イノベーションのマネジメント』(有斐閣)、『創発的破壊 未来をつくるイノベーション』(ミシマ社)、『2枚目の名刺』(講談社+α新書)、『経営革命の構造』(岩波新書)の他、近著に『イノベーターたちの日本史:近代日本の創造的対応』(東洋経済新報社)がある。
※プログラム内容や時間は急遽変更になる場合がございます。